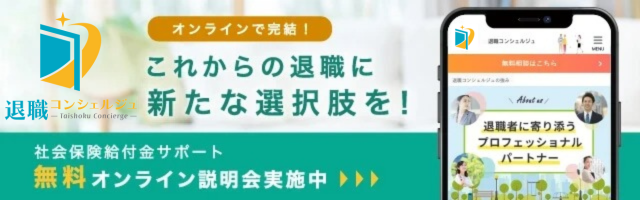仕事のストレスで限界を感じやすい人の特徴

同じ環境で同じ仕事をしていても、物事の考え方や感受性が違うように、人それぞれストレスの感じ方も異なります。特に、次の特徴に当てはまる人はストレスを抱えやすいことがあります。
- 真面目で責任感が強い
- 周囲に気を使いすぎてしまう
- 我慢して自分の意見を言えない
- 完璧主義
- 競争心が強い
真面目で責任感が強い人
例えば、仕事量が多くて期限内に終わらない場合でも、真面目で責任感が強い人は自分一人で解決しようと無理しがちです。
責任感の強さから他人に頼ることが苦手で、多少の体調不良では仕事を休めず出勤するなど、無理をしてしまう傾向にあります。さらに、自分が担当する仕事だけでなく、他人をサポートしようと業務過多に陥るなど、すべて自分で背負い込みやすいことも特徴です。
真面目で責任感が強い人は、ミスや他人に頼ることにより自分を過剰に責めてしまい、自己肯定感が下がってストレスを感じるケースがあります。
周囲に気を使いすぎてしまう人
気を使いすぎてしまう人は、常に他人の目を気にして自分の言動を制限する傾向にあるため、人よりストレスを受けやすくなることがあります。ついつい周囲の人の一挙一動に反応してしまうなど、他人からの評価に過敏になりがちです。
自分では気付かないうちに気を使ってしまう場合もあり、家に帰ってどっと疲れることも多いことが特徴です。
競争心が強い人
常に他者からの評価を気にして行動する競争心が強い人は、精神的な負担が大きくなることがあります。他者への嫉妬心により、ネガティブな感情を抱きやすいことも原因の一つです。
競争心が強い人は努力家でもあるため、評価をあげようと仕事を頑張りすぎて、心身に影響を与えているケースもあります。
いつも我慢してしまう人
日常的に我慢しすぎてしまう人は、身体的・精神的にストレスを感じても我慢することでやり過ごす傾向にあり、限界になるまで溜め込んでしまうことがあります。
自分が我慢すれば円滑に物事が進むと思い込みやすく、言いたいことが言えずモヤモヤした気持ちを溜め込みがちになることも原因です。いつも我慢してしまう人は、周囲に相談するのが苦手でストレス発散をうまくできないこともあり、負のスパイラルに陥ってしまう人もいます。
完璧主義の人
何事も完璧にこなさなければ気が済まない完璧主義の人は、ちょっとしたトラブルやミスが許せずストレスを感じることがあります。
また、自分自身だけでなく、チームメイトのミスにも敏感になることもストレスの原因です。自分で完遂させることにこだわってしまうなど他人を頼ることが苦手で、業務過多でも助けを求められない人もいます。
ストレスを感じやすい会社の特徴
仕事のストレスが限界だと感じる原因は、本人だけでなく本人だけでなく会社に原因があるのかもしれません。ストレスになりやすい職場環境の特徴は、主に以下のとおりです。
- 人材不足で業務量が多い
- 非現実的なノルマが設定されている
- コミュニケーションが不足している
- 人材の流動が激しい
- 評価体制が整っていない
- ハラスメントが常態化している
人材不足で業務量が多い
業務量に対して従業員の数が不足している場合や、必要なスキルを持った人材が不足している場合は、一人ひとりにかかる負担量が大きくなりストレスを感じやすくなります。
人材不足が深刻化し、残業や休日出勤が多い会社はストレス解消に必要な時間を確保しにくく、さらに不満を溜め込んでしまう結果につながります。長時間労働は身体的な負担もかかりやすく、集中力が低下して生産性も落ち、仕事が溜まるという負のループに陥りやすいことが特徴です。
非現実的なノルマが設定されている
仕事には業務の目標やノルマが設定されており、目標に向かって努力することが求められます。しかし、実現の可能性が低い厳しいノルマを与える会社では、従業員は過度なプレッシャーを感じやすい傾向にあります。
ノルマを達成できない場合は評価が下がって給与にも影響を与えるため、不安からストレスを感じやすくなることがある点に注意が必要です。チームや部署に課せられたノルマが非現実的なものである場合、職場全体の雰囲気が悪くなることによってストレスがかかるケースもあります。
コミュニケーションが不足している
職場でのコミュニケーションが不足している場合、孤立感や不安感が増すことでストレスを感じやすくなります。上司からの指示が一方的であったり、不明点を同僚に聞けない雰囲気だったりする場合も、不満が溜まりストレスがかかる原因です。
コミュニケーション不足の職場では、周囲に相談しにくい環境であることが多く、ストレスを溜め込みがちになる悪循環に陥りやすいことがあります。
人材の流動が激しい
従業員がすぐに辞めて新しい人材が入ってくるなど、人が頻繁に入れ替わる仕事もストレスの原因です。
人材の流動が激しいと業務の引き継ぎがうまくできないケースも多々あり、フラストレーションが溜まってしまいます。先輩社員が積極的にサポートしない体質の職場では、精神的な疲弊も大きく、ストレスが重なって限界だと感じてしまう原因になります。
評価体制が整っていない
仕事に対する評価が適切でない場合もストレスを抱えてしまう原因になるため、会社の評価体制も重要な要素です。
評価体制が整っていない職場では、仕事の成果を正当に評価してもらえず、頑張っても評価されないからとモチベーションが下がりやすくなります。職場全体のモチベーションが下がった状態だと、積極的な業務活動が行われず、やる気のある従業員にとってはストレスになることもあります。
評価基準があったとしても、曖昧だったり不公平だったりする場合もストレスが溜まりやすくなる原因です。
ハラスメントが常態化している
パワハラやセクハラ、モラハラなどのハラスメントが常態化している会社では、ストレスを受けやすくなります。
自分がハラスメントの当事者でなくても、上司や同僚が被害を受けているのを見ることも、被害者と同様に辛い気持ちを抱えてしまう原因です。また、被害を見て見ぬふりをすることで自分を責めてしまうことがあるかもしれません。
ハラスメントを受けたり、常態化している職場に勤務したりすることで、精神的・身体的な健康被害に発展する可能性があります。
自分ではストレスの限界に気付けない理由
第三者から見ると、明らかに健康を害している状態にもかかわらず、当事者は限界だと気付けないことがあります。心身の健康を守るためにも、まずはストレスに気付くことが重要です。
責任感が強く頑張りすぎてしまう
責任感が強く仕事を頑張りすぎてしまうことで、ストレスよりも「与えられた役目を果たす」ことに集中してしまい、限界に気付かないことがあります。
ストレスを感じていたとしても、「他人に迷惑をかけるから」「もう少しで成果が出るから」と自分を犠牲にして頑張りすぎてしまうことも限界に達してしまう理由の一つです。
ストレスに慣れてしまっている
ストレスを感じることに慣れている場合は、置かれた環境が当たり前になってしまい、ストレスの限界がわからなくなってしまいます。
急に大きなストレスに晒されたときより、徐々に小さなストレスが積み重なっていった場合はストレスに慣れているため、感覚が麻痺して限界に気付きにくいことがあります。
自分の感情や体調に鈍感になっている
自分の感情や体調の変化に鈍感になっている場合も、ストレスの限界に気付けない理由の一つです。慢性的にストレスを感じていると、感情や体調の変化に気付きにくくなり、「まだ大丈夫」と思い込みやすくなります。
自覚はなくても心身の健康は徐々に限界に近づき、そのままストレスが積み重なると体調不良を起こす結果につながります。限界を超えて大きく体調を崩して初めて、限界を超えたと自覚することもあるため注意が必要です。
周囲と比較してしまう
ストレスの感じ方は人それぞれのため、同じ環境で仕事をしていても、心身ともに健康に働ける人もいます。そのため、周りは問題なく仕事ができている状況で、自分は弱音を吐けないとストレスを溜め込むことがあります。
同じ環境で同じ仕事量をこなしていても、周囲が頑張っていると当たり前のことと認識してしまい、限界を超えやすくなることを理解することが重要です。
仕事のストレスで限界が近いときのサイン
仕事によるストレスで限界を超えてしまっている、もしくは限界が近い場合は心身にさまざまな影響を及ぼすことがあります。別の要因による症状だと思っていたのに、実はストレスが原因だったということもあるため、深刻な症状を引き起こす前にサインに気付くことが重要です。
ストレスが表れやすい体・精神・行動について、それぞれのサインを紹介します。
体に表れるストレスサイン
ストレスが積み重なると、疲れやすさや食欲不振、眠れないなど体の症状として表れやすくなります。
動悸、頭痛、便秘、下痢、肩こりなどの具体的な症状として表れるサインだけでなく、なんとなく風邪を引きやすくなった、眠りが浅くなったなど見逃しやすいものにも注意が必要です。食欲が落ちたり、眠れなくなったりするイメージがあるかもしれませんが、実は食べすぎてしまう人や寝すぎてしまう人もいます。
自覚がない場合でも、体重の増減が気付くきっかけになることもあるため、以前と大きく変化していないかチェックすることも大切です。特に体に表れる症状には病気が隠れている可能性もあるため、ストレスが原因と決めつけず、医療機関の受診も検討しましょう。
感情や考え方に表れるストレスサイン
サインには、精神的な落ち込みや集中力の低下、孤独感など精神的なサインも含まれます。
例えば、「悪い結果ばかりを考えるなどネガティブな思考に陥りやすい」「趣味が楽しめなくなった」「無気力で休みの日は横になってばかりいる」なども、精神的なサインの一つです。気分の落ちこみだけでなく、人によっては常にイライラして怒りっぽくなることもあります。
ストレスから精神的な疾患を発症している可能性もあるため、必要に応じて医療機関を受診しましょう。
行動に表れるストレスサイン
過度なストレスは心身に表れるだけでなく、行動にも影響を与えることがあります。例えば、以下のような行動はストレスサインかもしれません。
- ミスが増える
- コミュニケーションを取るのが億劫になる
- 身だしなみに気を使えなくなる
- 自宅の掃除ができず汚れたままになる
- 飲酒量や喫煙量が増える
- 浪費が増える
周囲の人は異常に気付いているのに、本人は自覚がないケースもあります。また、食事に興味がなくなり、同じものを食べ続けたり食事を抜いたりすることもストレスサインになりえます。
ストレス管理で心がけたいポイント
仕事のストレスを溜め込みすぎると、限界を超えて心身に大きな影響を与えることがあるため、できるだけ早く対処が必要です。すぐにでも改善できる以下のポイントを解説します。
- 食事
- 運動
- 休養
食事を見直す
規則正しく、バランスの良い食事を3食摂ることで、ストレスの影響を受けにくい体づくりを目指すことが大切です。ストレスを受けているときに不足しがちな栄養素を食事で補うことで、体の栄養バランスを整えられます。
ストレスを抱えている状態は、細胞の酸化を防いでダメージを抑える抗酸化機能が低下することで、ビタミンCやビタミンEなどの栄養素が不足しがちになります。玄米や豚肉、果物、ナッツ類などに多く含まれるビタミンB群やビタミンCの摂取を心がけましょう。
適度な運動を取り入れる
定期的に軽い運動をして体力の増加や健康増進を図り、疲れにくくストレスに強い体づくりを心がけることもポイントです。
体を動かしてストレス発散したり、日光に当たったりすることで精神的な健康増進にもつながります。
きちんと休養を取る
ストレスや疲れを感じているときは十分な睡眠時間を確保し、リフレッシュできる時間を作るなど休養をとることが重要です。
ストレスを感じると睡眠に影響が出るだけでなく、満足に眠れないことがさらなるストレスにつながり負のサイクルに陥ることもあります。また、睡眠不足は集中力の低下を招く原因にもなるため、十分な睡眠が取れる環境づくりが大切です。
真面目で責任感が強い人ほど、休みの日を返上して仕事をしてしまうことがあるかもしれません。休日は仕事から離れて、しっかり休養を取ることでストレス解消しやすくなります。
仕事のストレスで限界を感じているときに避けたいこと
仕事でストレスを感じているときは、以下の行動はできるだけ避けましょう。
- 無理をする
- 悩みを一人で抱える
- 自分を責める
- 不摂生な生活をする
- 衝動的に退職を決断する
なぜ上記の行動を避けるべきか、詳しく解説します。
無理をする
仕事のストレスが限界に達していても、自覚症状が少なく「もう少し頑張れる」と無理をすると、心身に悪影響をあたえかねません。
無理を重ねるとより深刻な結果につながる恐れもあるため、ストレスによる症状が表れている場合は無理しないことが大切です。前述のストレスサインを意識し、日頃から少しずつストレスを解消するよう心がけましょう。
悩みを一人で抱え込む
仕事の悩みを一人で抱え込むと、誰にも相談できない不安によってさらにストレスが溜まり悪循環に陥るリスクがあります。
周囲の人に話せる環境があれば、悩みを聞いてもらうだけでも気持ちが軽くなります。周りに話せる人がいない場合は相談窓口や専門家のサポートを利用するなど、抱え込まない工夫が必要です。
自分を責める
ネガティブな思考や集中力が低下したことによるミスなど、仕事のストレスが原因で起こる出来事を自分のせいにして責めるのは避けましょう。
自分のことを「弱い」「甘え」などと責めると、自己肯定感が下がる原因になります。自己肯定感の低下はさらなる精神的負荷につながるため、必要以上に自分を責めないことが大切です。
「自分の心身の健康が最優先」という考え方で、取り組みやすいストレス解消法を探しましょう。
不摂生な生活をする
過剰なストレスを感じると、食事の偏りや運動したくない気持ちになるかもしれません。過度な喫煙や飲酒、睡眠不足など不摂生な生活を続けると、心身の健康を損なう可能性が高まり、さらなるストレスの原因になるため注意が必要です。
ストレスを強く感じている状況では、無意識のうちに不摂生な生活になってしまうこともあるため、普段から意識的に健康的な生活を心がけることも重要です。
衝動的に退職を決断する
ストレスが限界に達していると、仕事を辞めてしまいたいという考えに至るかもしれません。確かに、仕事を辞めれば一時的にストレスの原因はなくなりますが、収入が途絶えて生活が不安定になるリスクがある点を理解しておきましょう。
収入がなくなることで新たなストレスが発生する可能性もあるため、後先を考えない衝動的な退職の決断は冷静に考える必要があります。心身に支障をきたしている場合は、すぐに退職するのではなく、休職して一度冷静になって考えてみる時間を確保しましょう。
ストレス解消のためにできる対処法
仕事のストレスは、限界を迎える前に解消することが大切です。ここでは、ストレス解消のために、すぐにできる対処法を紹介します。
ストレスの原因を洗い出す
ストレスだと感じる事柄を洗い出し、原因を突き止めることで、適切な対策が見えてきます。例えば、特定の人と接することがストレスに感じる場合、対策として別の部署への異動希望が可能か人事部に相談するなど、実現可能な対策を検討できるようになります。
また、紙に書き出すだけでも、すっきりとした気持ちになることもあるため、まずは原因の洗い出しから始めます。自分で改善できる部分は対策を考えて実行し、外的要因である場合は上司や同僚に相談するなど、改善の糸口へとつなげましょう。
信頼できる人に相談する
身近に信頼できる人がいる場合は、話を聞いてもらうことで不安や怒りといった気持ちが落ち着くことがあります。自分では気付きにくい部分もあるため、他者の視点から客観的に見てもらうことで客観的な状況を把握しやすくなることも、信頼できる人に相談するメリットです。
職場に信頼できる人がいるなら、アドバイスをもらったり、仕事を手伝ってもらったりすることで解決できるかもしれません。
プライベートを充実させる
仕事で感じているストレスのもとを改善できない場合は、プライベートの時間を充実させることでストレス解消を図る方法もあります。根本的な解決にはなりませんが、プライベートで仕事のことを考える時間を減らし、さらなるストレスにつながるのを避けられます。
運動や映画鑑賞、音楽鑑賞など、好きなことに集中できる環境を作るのがおすすめです。旅行や普段行かない場所・やらないことに挑戦するなど、非日常を感じられる時間を作ると、仕事を忘れてプライベートの時間に集中しやすくなります。
長期休暇を取る
仕事で強いストレスを感じているのであれば、限界を迎える前に長期休暇を取って休養するのも一つの対処法です。体を休めるだけでなく、仕事から離れる時間が増えることで精神的負担も緩和されます。
基本的に休暇中は仕事のことを考えず、体と心を休めることを優先しましょう。長期休暇で心身を休め、仕事に戻ってから今後の対策を検討することで、冷静な判断ができるようになります。
ストレス解消で解決しない場合の対処法
前述のストレス解消法で解決しない場合は、根本的な問題解決を図る必要があります。
社内の相談窓口を利用する
上司や同僚はストレスの原因である当事者だったり、問題に深く関わっていたりすることもあるため、専門の部署であれば打ち明けやすいこともあります。自分でできるストレス解消法を試してみても状況が好転しない場合は、会社の相談窓口で相談することも選択肢の一つです。
相談窓口で話した内容は他の人に漏れる心配がないため、安心して悩みを話せることもメリットです。当事者や関係者に近しい人に相談するのとは異なり、客観的なアドバイスも期待できます。相談を通して、今後どうすればいいのか答えが見つかる可能性もあります。
異動が可能か検討する
現在の職場環境にストレスの原因がある場合は、別の部署や支社に異動できないか検討する方法もあります。今の会社や仕事内容が好きで転職は避けたいときなどは、社内で環境を変える方法を模索してみましょう。
例えば、ストレスの原因になっている上司や同僚がいる場合や、部署全体に原因がある場合は環境を変えると改善することがあります。
ただし、会社の人事制度によって異動希望の伝え方が異なるため、就業規則を確認しておくことが重要です。会社によっては部署を移動する部署移動のほか、職種を変更する職種変更、勤務地を変更する転勤、関係他社へ部署移動する出向など、さまざまな選択肢があります。
公的な相談窓口を利用する
社内の相談窓口で相談しにくい場合や、自社の相談窓口が設けられていない場合は、外部の相談窓口も利用できます。具体的には自治体やハローワーク、労働局など公的な相談窓口のほか、弁護士やカウンセラーなど外部期間の専門家が挙げられます。
パワハラを受けているときなど、専門的な知識がないと対処できない状況に置かれている場合は専門家を頼ることも大切です。
医療機関を受診する
仕事のストレスで心身に影響が出ている場合は、医療機関の受診も検討しましょう。特に精神的な症状は自分では気付きにくく、自覚症状が少ないこともあります。客観的に判断してもらうことで、限界に達する前に気付けるきっかけになります。
精神的な不調が生じると回復するのに時間がかかるため、症状に気付いたら早めに受診することが重要です。
転職を検討する
相談窓口で相談しても人間関係や職場環境の問題が解決せず、異動希望が通らないなど環境を変えることもできない場合は、転職を検討するのも対処法の一つです。部署が変わっても改善しない場合や、会社の体質自体がストレスの原因になっている場合も、より自分に合った会社への転職で解決できるかもしれません。
ただし、転職後も同じようにストレスを抱えてしまうリスクを避けるため、転職先選びには慎重になる必要があります。
休職も視野に入れる
異動や転職は今後の人生が変わる大きな決断となるため、すぐに判断しにくいと感じるときは、まずは休職して一時的に仕事から離れる方法もあります。仕事から離れて心身の療養に努めることで、今後のことを冷静に考える時間ができ、衝動的な判断を避けやすくなります。
有給休暇が足りない場合は、労災の給付金や傷病手当金などの制度を利用できるケースもあるので、自分が受給条件に該当するか確認してみましょう。
ストレスで仕事を休む・辞めるのが甘えではない理由
仕事のストレスで限界を感じて休んだり、退職したりすることに対して「甘えではないか」と考えて無理してしまう人もいるかもしれません。
しかし、心身に影響が出ている場合は、自分自身を守る意味でも仕事に集中する意味でも休むことは重要です。ストレスを抱えたまま仕事を続けても、いずれは体調不良で仕事を休まざるをえない状況になることもあります。ストレスで仕事を休むことで「他人に迷惑をかける」と考えるのではなく、まずは自分の健康を優先しましょう。
また、できるだけ早い段階で、自分を休ませてあげることも大切なポイントです。ストレスサインが軽い段階で休めればより早い回復が見込めますが、無理して仕事を続けてダメージが大きくなると、回復するのに時間がかかる可能性もあります。長期の休みでなくても、休養により集中力が上がって仕事に集中しやすくなります。
仕事のストレスが原因で傷病が発生した際に利用できる制度
仕事のストレスが原因で病気になったと判断された場合、条件を満たすと労災保険を利用できることがあります。
労災保険(労働災害補償保険)とは
労災保険とは、労働者が仕事や通勤が原因で負傷したり病気になったりしたときに給付金が支給される制度です。基本的に、仕事のストレスで病気になった場合は健康保険ではなく労災保険が適用されます。
労災保険には、医療機関の診察や処置にかかる費用を補償する「療養補償給付」、療養による休業中の収入を補償する「休業補償給付」などいくつかの種類があります。
労災保険の給付条件
労災保険の補償を受けるためには、労働保険に加入していることが条件です。労働保険は労災保険と雇用保険の総称で、原則として1人以上の労働者を雇っている事業主に加入が義務付けられています。労働保険料は全額事業主負担で労働者の負担はなく、事業主に雇われている場合は労働保険に加入していることがほとんどです。
万が一ストレスにより傷病を負った場合、その発病が仕事による強いストレスのものと判断できる場合に限り労災認定されます。ただし、仕事だけが原因ではなく、私生活で抱えているストレスの影響も考慮されると労災認定されません。
仕事のストレスが原因で医療機関にかかる場合は、「労災による受診」と伝えたうえで、診察を受ける必要があります。労災指定の医療機関を受診する場合の医療費は、原則無料です。健康保険で受診した場合や、指定病院以外に行った場合は一時的に医療費の負担が必要ですが、手続きにより治療費は全額返還されます。
労災保険の必要書類と申請方法
仕事のストレスによる傷病で労災保険の給付を受ける場合は、労災保険給付の請求書を労働基準監督署長に提出して審査を受けます。
請求書は厚生労働省のホームページや労働基準監督署で入手でき、会社を通じて提出するか、自分で提出します。書類の受理後、労働基準監督署による調査が行われ、事実関係を確認したうえで労災認定される流れです。
労災以外で休職時に利用できる給付金
仕事のストレスで限界を感じ、休職する場合は会社からの給与がなくなるため、生活が困難になる可能性があります。条件を満たす場合は「傷病手当金」の給付を受けられることがあり、仕事を休んでいる間の収入源として期待できます。
傷病手当金とは
傷病手当金とは、健康保険の被保険者が病気やケガで働けず、会社を休んだときに支給される給付金です。仕事が原因の傷病は労災保険の対象ですが、労災認定されない場合は傷病手当金を利用できることがあります。
ストレスで心身に何らかの影響が出て、医師に「休養が必要」と診断された場合に申請することで、休んだ日数に応じた給付金を受け取れます。うつ病や適応障害など、精神的な病気で休む場合も対象です。
傷病手当金は、「支給開始日以前12か月間の標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2」で1日分を計算し、休んだ日の分が支給されます。支給期間の限度は連続した3日間の待期期間後、支給を開始された日から通算1年6か月です。3日間の待期期間中に傷病手当金は支給されないため、支給は4日以上連続して休む場合に限られます。
一度、傷病手当金を受給した後、支給期間が残っている場合は一時的に出勤したとしても、その後再び休職したときに残りの期間を受給できます。
傷病手当金の受給条件
傷病手当金を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 業務外の病気やケガのための休業であること
- 仕事に就けないと判断されていること
- 連続する3日間を含む4日以上仕事に就けなかったこと
- 休んだ日に給与の支払いがないこと
傷病手当金は会社の社会保険に加入している人が対象で、国民健康保険に加入している人や任意継続被保険者の場合は受給対象外です。
また、以下の条件を満たせば、退職後も継続して傷病手当金を受け取れます。
- 退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること
- 退職日の前日までに連続して3日以上出勤せず、退職日も出勤していないこと
- 退職日に傷病手当金を受給していた傷病で引き続き就労不能なこと
傷病手当金の必要書類と申請方法
傷病手当金を受給する際は、「傷病手当支給申請書」を加入している健康保険組合に提出します。在職中であれば、書類作成後に会社の担当部署を通じて申請するのが一般的です。
申請に医師の診断書は必要ありませんが、申請書に医師記入欄があるため、医療機関に依頼して作成してもらう必要があります。
給付金は休んだ日について支給されるため、休業が長期になる場合は1か月単位などある程度まとめて申請すると、書類提出が1か月ごとで済みます。短期間の休業の場合は、復帰後にまとめて申請しても問題ありません。
傷病手当金の申請方法については以下記事もご確認ください。
参考:傷病手当金をもらえないケースとは?会社が嫌がる理由や対処法・申請方法も紹介
ストレスにより退職する場合に利用できる給付金

雇用保険に加入していれば、仕事のストレスで退職したときに失業保険などの給付金を受給できる場合があります。ただし、条件によって受給できる給付金の種類は異なります。
失業保険とは
失業保険とは雇用保険の基本手当のことで、失業により収入が途絶えた人が求職活動に集中できるよう、生活を安定させるために支給される給付金です。仕事のストレスで限界を感じて退職した場合でも、一定の条件を満たせば受給できます。
給付日数や受給開始日は、退職理由が会社都合と自己都合で大きく異なり、会社都合の場合は雇用保険の被保険者期間によって最大で330日分が支給されます。自己都合による退職は、最大でも150日分です。
会社都合や正当な理由があって退職した人は、支給開始の時期が自己都合退職の人より早くなります。例えば、パワハラやセクハラなどのハラスメントや、職種転換の際に必要な配慮がされなかったなど、仕事のストレスで退職した場合は会社都合と認められることもあります。
心身の障害や疾病など健康上の理由で離職した人は、特定理由離職者と認められることがあり、失業保険の支給開始が自己都合退職の人より1か月早くなることが特徴です。ストレスで体を壊してしまったことを理由に退職する場合も、早期受給が可能な条件に該当する可能性があります。
失業保険の支給条件
失業保険を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上ある
- 就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力を持つが失業状態にある
会社都合や正当な理由があり退職した人は、離職日以前の1年間に雇用保険の被保険者期間が通算6か月以上あれば受給対象です。
失業保険をもらうためには、すぐにでも就職できる状態である必要があり、仕事のストレスによる体調不良ですぐには働けない場合は対象外となります。退職後も継続して傷病手当金を受け取る場合は、失業保険の延長申請が必要です。
失業保険の必要書類と申請方法
失業保険を受給する際は、主に以下の書類を準備します。
- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険被保険者離職票
- 個人番号確認書類
- 本人確認書類
- 写真2枚
- 本人名義の預金口座またはキャッシュカード
上記の書類を持って、住所地を管轄するハローワークの窓口で求職申込みを行うと、受給資格が決定されます。
失業保険以外に利用できる給付金
退職後にもらえる給付金は、失業保険だけではありません。雇用保険に入っていない人や被保険者期間が足りない人など、失業保険がもらえない人が対象になる支援制度もあります。
失業保険以外で退職後に利用できる主な給付金は、以下のとおりです。
| 給付金の種類 | 対象者 |
| 高年齢求職者給付金 | 雇用保険に一定期間加入していた65歳以上の失業者 |
| 特例一時金 | 短期特例被保険者に該当する失業者 |
| 日雇労働求職者給付金 | 日雇労働被保険者に該当する失業者 |
| 教育訓練給付金 | 雇用保険被保険者のうち一定条件を満たしたうえで、教育訓練を修了した人 |
| 職業訓練受講給付金 | 失業保険の対象外になり、一定条件を満たして職業訓練を受けた人 |
| 再就職手当 | 失業保険の受給中に一定の条件を満たして再就職した人 |
| 住居確保給付金 | 収入の減少で住居の確保が困難で、一定の条件を満たした人 |
まとめ
仕事のストレスから心身を壊してしまうと、回復までに長い期間かかってしまうことがあります。そのため、限界までストレスを抱え込んでしまう前に、サインに気付いて対処したり身近な人に相談したりすることが重要です。
自分ひとりではどうにもならないと感じたときは、休職や退職といった選択肢も視野に入れ、自分の健康を最優先に考えましょう。給付金制度を利用すれば、休職・退職後の経済的な不安を軽減することも可能です。
給付金の手続きに不安がある方には、「社会保険給付金サポート」の利用がおすすめです。専門スタッフが申請を丁寧にサポートするため、安心して生活の立て直し、新たな一歩を踏み出すことができます。

 給付金がいくらもらえるか
知りたい方
給付金がいくらもらえるか
知りたい方 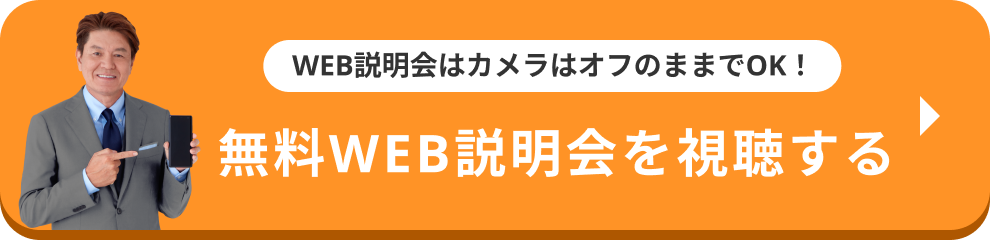
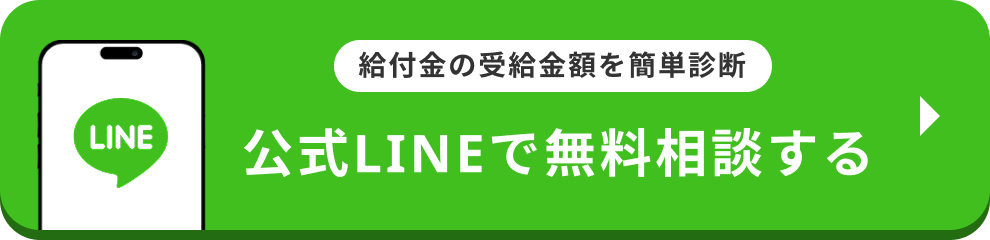
 給付金サポートを
ご検討中の方
給付金サポートを
ご検討中の方  評判・口コミ
評判・口コミ  給付金がもらえる
転職支援を活用する方
給付金がもらえる
転職支援を活用する方  その他退職について
ご不安がある方
その他退職について
ご不安がある方  もらえる給付金ラボ
もらえる給付金ラボ  退職コンシェルジュについて
退職コンシェルジュについて