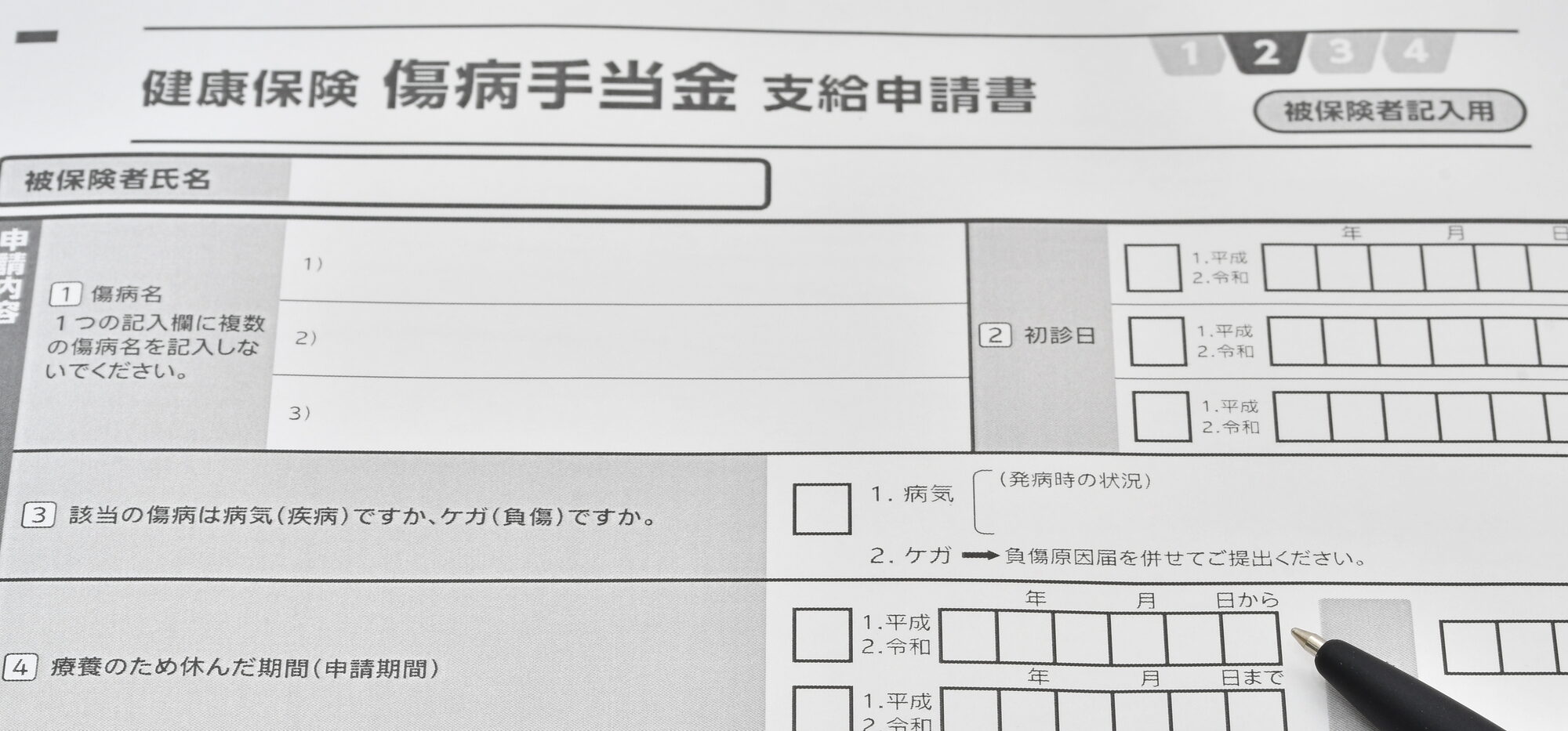2025.08.19
退職について
テーマ:
仕事を辞める前にするべきこと10選|辞める際の流れや手続きを解説

退職を考えているものの、「何から手をつけるべきかわからない」と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。仕事を辞める際には、保険や年金の切り替え、税金の支払い方法、失業手当など、多くの手続きが発生します。必要な準備を怠ると、思わぬ金銭的損失や社会保険の未加入期間が発生し、生活基盤が不安定になる恐れがあります。
本記事では、退職前に確認すべき手続きや必要書類、退職後に活用できる公的制度について解説します。スムーズな退職と次のキャリアを見据えて行動したい方は、ぜひ参考にしてください。
仕事を辞める前にするべきこと10選

退職後のトラブルや不安を避け、円滑に次のステップへ進むためには、事前の準備が欠かせません。ここでは、仕事を辞める前にするべきこと10選を紹介します。
就業規則を確認して退職ルールを把握する
スムーズな退職を実現するには、就業規則を確認し、自社の退職ルールを正しく把握しましょう。企業ごとに退職申告の期限や書類の提出方法、有給休暇の取り扱いが異なるため、曖昧な理解のまま手続きを進めると、引き継ぎや退職日調整などの社内手続きに支障をきたす恐れがあります。
例えば「退職の1ヶ月前までに申し出る」と定められている場合、その期限を過ぎると希望する退職日に間に合わない可能性があります。また、有給休暇の事前申請が必要な会社では、適切なスケジュールを立てておかないと、有給を消化できずに損をする結果になりかねません。
円満退職のために退職タイミングを見極める
会社への負担を最小限に抑えるためには、退職のタイミングを慎重に選ぶ必要があります。業務が立て込んでいる時期や人手不足の時期に退職を申し出ると、周囲の反発を招き、引き継ぎもスムーズに進まなくなるからです。
例えば、年末調整が行われる12月〜1月や、決算期にあたる3月〜5月などは、総務や経理を中心に多忙になる企業が多く見られます。一方、プロジェクトの完了直後や人事異動の直後は業務が一段落しており、退職の申し出に適したタイミングです。
会社の年間スケジュールや自部署の業務の波をあらかじめ把握し、適切な時期を選んで退職を申し出ましょう。
退職後の見通しを立てておく
退職の意思を固めたら、今後の生活設計とキャリアの見通しを立てておきましょう。退職後の方向性が不明確なままでは、精神的にも経済的にも不安が大きくなりがちです。
具体的には、転職先の内定状況や面接予定を整理し、キャリアの方向性と希望条件を明確にしましょう。また、次の就職まで一定の期間が空く場合は、生活費の確保や社会保険の切り替えなど、金銭面の計画も立てておく必要があります。
なお、在職中に転職活動を終えるべきか、退職後に活動を始めるべきかは、別見出しで詳しく解説します。
退職理由を整理しておく
円満退職を目指すためには、退職理由をあらかじめ整理し、冷静かつ前向きに説明できるよう準備しておきましょう。伝え方次第で、引き止めの可能性を減らし、上司の理解を得やすくなります。
例えば、「キャリアアップのため」や「家庭の事情による転居」など、論理的かつ具体的な理由を示すと、感情的な印象を与えずに済みます。また、すでに内定を得ている場合はその事実を明確に伝えると、上司の説得を避けやすいでしょう。
説明に自信が持てない場合は、あらかじめ話す内容をシミュレーションし、上司との面談に備えると安心です。
スムーズな退職を目指すために引き継ぎ資料を整備する
円滑に業務を引き継ぐためには、退職前に自分の業務を整理し、後任者が迷わず対応できるよう資料を整備しましょう。引き継ぎが不十分だと社内で混乱が起き、退職者への印象も悪くなりかねません。
具体的には、日々の業務手順に加えて、自分の担当業務の進捗や後任者に必要な情報をリスト化し、関係者の連絡先も含めて文書としてまとめておきます。また、対面での引き継ぎ時間も確保し、不明点が出た場合の連絡手段についても伝えておくと親切です。
社内の貸与物・備品を事前に確認して返却準備をする
退職前には、会社から借りている備品をすべてリストアップし、忘れず返却できるよう準備を進めておきましょう。備品の返却が遅れると、後日出社や郵送対応を求められるケースがあり、手間がかかります。
例えば、パソコンやスマートフォン、社員証、制服などが該当します。貸与されたデバイスに保存された業務データはバックアップを取り、個人情報や私物データは削除しましょう。あわせて、社外に渡した業務資料や名刺の回収も必要であれば対応します。
クレジットカードや賃貸契約など、社会的信用が必要な手続きを済ませる
退職後の生活を安定させるためには、在職中に社会的信用を要する手続きをあらかじめ済ませましょう。例えば、新しくクレジットカードを作成する場合や、住宅の賃貸契約・更新を行う場合には、在職中のほうが審査に有利です。
退職後は無職扱いとなり、審査に落ちる可能性が高くなります。カードを持っていない方や転居予定がある方は、退職前の手続きで生活の不安要素を減らしておきましょう。
引っ越し予定がある場合は在職中に済ませておく
転居の予定がある場合は、退職前に引っ越しを完了させておくと安心です。在職中のほうが収入と信用があるため、賃貸契約などの審査に通りやすいからです。会社の寮や社宅に住んでいる場合は、退職に伴って退去が必要となるため、早めの準備が求められます。
無職になると収入証明が難しくなり、審査が通らないケースもあります。生活基盤が安定していれば、退職後の転職活動や生活設計も落ち着いて進められるでしょう。
貯金を確保して退職後の生活費を備える
退職前には、収入の空白期間に備えて生活費を確保しておきましょう。退職後は給料が入らず支出だけが続くため、経済的に不安定になりがちです。
転職活動には交通費や書類作成費、面接用の服の準備などで出費が発生します。さらに、健康保険や年金、住民税の支払いが全額自己負担となるため、金額負担も増えます。生活費の目安を月単位で見積もり、3ヶ月〜6ヶ月分を目標に貯蓄するのが理想です。
あわせて、万が一の事態に備えて緊急用資金を別口座に分けて確保しておくと安心です。日頃から無駄遣いを避け、計画的に貯金を進める姿勢が求められます。
退職後の保険・失業手当など公的サポートを調べておく
退職後の手続きや支援制度について事前に調べておくと、退職後の生活設計がしやすくなります。具体的には、以下のような制度があります。
- 健康保険の任意継続制度
- 国民健康保険への加入手続き
- 失業保険の受給条件や申請方法
- 国民年金の納付方法
制度の適用には期限や条件があるため、事前の把握が必要です。退職後の手続きや手当については、別見出しで詳しく解説します。
仕事を辞める理由や辞めた方が良い職場の特徴
仕事を辞めるべきか悩んでいるときは、辞めたいと感じる自分の感覚に理由があるかどうかを見極めることが大切です。ここでは、退職を検討する際に判断材料となる職場の特徴を5つ紹介します。
心身に支障が出るほどの長時間労働や残業が多い職場
長時間労働や過度な残業が常態化している職場は、早めに見切りをつけるべきでしょう。身体的にも精神的にも疲弊し、健康を損なうリスクが高まります。
例えば、毎日2〜3時間以上の残業が当たり前で、休日にも業務対応を求められる職場では、プライベートの時間が確保できず、慢性的な疲労とストレスに悩まされます。
また、残業代が支払われないケースや、有給休暇の取得が事実上困難な職場も同様に注意が必要です。健康を犠牲にしてまで働き続けることにメリットはないため、心身に異変を感じた時点で職場環境の見直しを検討しましょう。
人間関係や職場の雰囲気が悪くストレスが大きい職場
職場の人間関係に強いストレスを感じている場合も、退職を視野に入れるべきです。人間関係は業務の効率や精神的な安定に直結するため、悪化すると働き続けること自体が苦痛になります。例えば、以下のような職場ではストレスが溜まりやすいでしょう。
- 上司や同僚との会話がほとんどなく孤立している
- パワハラやセクハラがあっても改善されない
- 感情的な指導が日常的にある
チームの雰囲気が悪く、責任を押し付け合うような環境も危険です。人間関係に悩み続けることは心身に悪影響を及ぼすため、信頼できる環境で働ける場所を探しましょう。
正当な評価をされずにキャリアが停滞する職場
努力や成果が評価されない職場に長く留まると、自分の成長機会を逃すことになります。不当な評価はモチベーションを奪い、キャリアの停滞を招きます。例えば、以下のような職場では自分の努力が無意味に感じられるでしょう。
- 上司の主観や社歴によって昇進が決まる
- 何年働いても立場が変わらない
- 成果を他人に横取りされる
また、フィードバックがなく、自分の課題や伸ばすべき点がわからない職場ではスキルアップも困難です。キャリアを前に進めたいなら、適切に評価される環境への転職を検討しましょう。
会社の将来性が見えない職場
会社の経営基盤や将来性に不安を感じる場合は、早めに行動を起こす必要があります。今後の方針が不透明な企業では、昇進や収入の見通しが立たず、長期的なキャリア設計が困難です。例えば、以下のような状況にある職場では今後のキャリア形成に支障が出ます。
- リストラや異動が頻繁にある
- 業界全体が縮小傾向にあるのに会社が対策を講じていない
- 事業方針が何度も変更されて現場が混乱している
優秀な社員が次々と辞め、残るのは消極的な人材ばかりというケースも危険です。安定した将来のためには、信頼できる経営方針とビジョンを持つ会社を選択しましょう。
仕事内容が自分に合っておらず成長も感じられない職場
日々の業務にやりがいや成長を感じられない場合も、転職を考えるタイミングです。自分に合わない仕事を続けていても、スキルが伸びずキャリアアップに結びつきません。以下のような状況では、仕事への意欲も下がっていきます。
- 毎日単純作業の繰り返しで達成感が得られない
- 自分の適性を無視した業務ばかり任されている
- 配属変更の希望も出せず今後の展望が見えない
将来のキャリアを充実させるためには、自分の強みを活かし、成長できる環境に移ることが重要です。
仕事を辞める際の流れ
退職を決断したあとも、段取りを誤るとトラブルになる可能性があります。ここでは、円満に仕事を辞めるための基本的な流れを5つのステップに分けて解説します。
上司に退職の意思を伝え、退職日を決定する
退職が決まったら、まずは直属の上司に退職の意思を伝え、退職日を調整してください。職場の業務状況に配慮しながら相談すると、信頼関係を損なわずに手続きを進められます。理想は、退職の1〜3ヶ月前にアポイントを取り、口頭で丁寧に相談する形で伝えることです。
繁忙期を避け、退職理由も簡潔かつ前向きに伝えましょう。引き止めに備えて、退職の意思が固いことも明確にしておく必要があります。退職日が確定すれば、引き継ぎや有給取得の計画も立てやすくなります。
退職願・退職届を提出して正式に退職手続きを行う
退職の意思を伝えたあとは、会社の指示に従い、退職願または退職届を提出して正式な手続きを進めます。退職願と退職届には以下の違いがあります。
|
退職願 |
退職届 |
|
|
意味 |
退職の意思を申し出る文書 |
退職の意思が確定した後に提出する文書 |
|
撤回可能か |
可能 |
不可 |
|
提出タイミング |
退職前の相談段階 |
退職が決定した後 (退職日の14日前まで) |
提出は直属の上司または人事部に行い、封筒に入れて手渡しするのが基本です。社内に規定がある場合は、内容やフォーマットに従って準備しましょう。受理されたあとは、退職日や引き継ぎ内容を再確認し、必要に応じて記録をメールなどで残すことが望ましいです。
引き継ぎ業務・社外挨拶・返却物の対応を行う
円滑な退職のためには、後任者が業務を問題なく引き継げる状態に整えてください。引き継ぎが不十分だと、社内外に迷惑をかけ、信頼を損ねるリスクがあります。業務マニュアルやタスク一覧を作成し、進行中の案件や対応中の顧客情報などを文書化しておきましょう。
また、社外の取引先には退職の連絡を行い、後任者の情報も伝えるようにします。連絡方法は関係性に応じてメール・電話・訪問などを使い分けることが望ましいです。加えて、パソコン・スマートフォン・社員証・名刺・制服などの社用備品は最終出社日までにすべて返却しましょう。
有給休暇を消化する
残っている有給休暇は、退職日までに計画的に取得しましょう。まずは人事部や上司に相談し、保有している有給休暇日数を確認します。給与明細や人事システムでも確認できる場合があります。
引き継ぎスケジュールと調整しながら、業務に支障を与えない範囲で休暇の計画を立ててください。取得が困難な場合は、会社規定に基づいて有給買取が可能かどうかも確認しましょう。有給の買取制度は法的義務ではありませんが、会社によっては認めているケースもあります。
保険・書類関連の手続きを忘れずに行う
退職後は、健康保険と年金の切り替え手続きを速やかに行ってください。手続きが遅れると保険や年金に未加入の期間が発生します。健康保険については、任意継続か国民健康保険のいずれかを選択します。任意継続する場合は、退職の翌日から20日以内、国民健康保険に加入する場合は退職の翌日から14日以内に手続きが必要です。
年金は国民年金に切り替わるため、退職後14日以内に市区町村の役所で手続きを行ってください。各種の手続きについては別見出しで詳しく解説します。
仕事を辞める際に会社からもらっておくべき書類
退職後は、各種の公的手続きや転職準備に関わる重要書類を確実に揃える必要があります。ここでは、退職後に必要となる代表的な書類の目的や取得方法を解説します。
退職証明書
退職証明書は、在職期間や職務内容などを証明する書類です。会社には発行義務がないため、必要な場合は会社に発行を依頼します。
退職証明書は、転職先から退職証明書の提出を求められた場合や、国民健康保険・国民年金の加入手続きで離職票の代わりに提出する場面があります。発行には退職後2年以内という期限があるため、必要になりそうな場合は早めに依頼しましょう。
離職票
離職票は、失業手当を受給する際に必要な書類です。転職先が決まっていない場合は必ず受け取りましょう。離職票をハローワークに提出すると、失業保険の給付申請ができます。
通常は退職から10〜14日後に会社から郵送されますが、会社によっては申請がない限り発行しない場合もあるため確認が必要です。万が一、退職後1ヶ月を過ぎても届かない場合は会社へ問い合わせ、それでも対応が得られなければハローワークへ相談すると会社へ対応を促してもらえます。
源泉徴収票
源泉徴収票は、所得税の納税状況や年間の給与を証明する税務書類です。年末調整や確定申告に必要です。退職後に転職する場合は、新しい勤務先に提出して年末調整を受けるために使用します。自営業や転職せずに年末を迎える場合は、自分で確定申告に用いることになります。
源泉徴収票は年末または退職後に発行されるため、退職前にいつ、どのように受け取れるかを会社に確認しておくと安心です。
雇用保険被保険証
雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していたことを証明する書類で、被保険者番号が記載されています。転職先や失業手当の手続きで必要になるので、必ず受け取りましょう。万が一、退職しても届かない場合は、ハローワークで再発行が可能です。
基礎年金番号通知書
基礎年金番号通知書は、公的年金制度に加入していることを証明する書類で、転職時や年金関連手続きに必要です。2022年以降は年金手帳から通知書へ切り替わっており、年金手帳を所持している方はそのまま使用できます。
会社に預けている場合は、退職時に返却されるため確認してください。年金手帳または通知書を紛失している場合は、最寄りの年金事務所で再発行の手続きが可能です。
健康保険資格喪失証明書
健康保険資格喪失証明書は、退職によって会社の社会保険資格を失ったことを証明する書類で、国民健康保険や国民年金の加入手続きに必須です。会社が資格喪失の手続きを行った後、通常は退職日の翌日から1週間程度で郵送されます。
国民健康保険の加入手続きには、退職日の翌日から14日以内の提出が求められるため、早めの受け取りと手続きが求められます。届かなかった場合は、健康保険組合または年金事務所で再発行が可能です。
手続きの遅れによる保険未加入期間を防ぐためにも、退職前に発行時期と送付方法を会社に確認しておきましょう。
【事前知識】仕事を辞めたあとにやるべき手続き
退職後は、健康保険や年金、税金など多くの公的手続きを自分で行う必要があります。ここでは、退職後に必要となる主な手続きと方法について解説します。
年金の切り替え手続き
退職後は厚生年金の資格を失うため、国民年金への切り替え手続きが必要です。以下の表に、必要な対応の概要をまとめます。
|
手続きの期限 |
退職の翌日から14日以内 |
|
提出先 |
市区町村の役所 |
|
提出物 |
・退職日が証明できる書類(退職証明書・離職票・資格喪失証明書など) ・基礎年金番号通知書または年金手帳 ・本人確認書類 |
転職先が未定であれば、自分で役所に出向いて国民年金の加入手続きを行う必要があります。期限を過ぎると未納扱いとなり、将来の年金額が減少する可能性があるため、速やかに対応してください。
また、配偶者が会社員や公務員として社会保険に加入している場合は、扶養に入ると「第3号被保険者」として保険料の支払いが免除されます。
年金の切り替えは将来の受給額に直結する重要な手続きなので、期限内に確実に対応しましょう。
参考:(厚生労働省【国民年金】加入・喪失・変更 必要書類リスト)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000084061.pdf
参考:(日本年金機構 国民年金に加入するための手続き)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04.html
健康保険の切り替え手続き
退職により会社の健康保険の資格を失うため、新たに健康保険への加入手続きを行う必要があります。以下の表に対応方法をまとめます。
|
国民健康保険に加入 |
任意継続被保険者制度を利用 |
|
|
手続きの期限 |
退職の翌日から14日以内 |
退職の翌日から20日以内 |
|
提出先 |
住所地の市区町村役所 |
元の健康保険組合 または協会けんぽ |
|
提出物 |
・健康保険資格喪失証明書 健康保険 ・厚生年金保険資格取得 ・資格喪失等確認請求書 ・身分証明書 |
・任意継続被保険者資格取得申出書 ・被扶養者届(該当時) ・収入証明書など(必要時) |
国民健康保険は市区町村が運営する制度で、保障内容は限定されますが、退職後の一般的な選択肢として利用されます。
一方、任意継続制度を選ぶと、会社で加入していた健康保険を最大2年間そのまま継続可能です。保険料は全額自己負担ですが、扶養家族が多い場合は負担が軽くなる可能性があります。
参考:(厚生労働省 国民健康保険の保険料・保険税について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21517.html
参考:(日本年金機構 国民健康保険等へ切り替えるときの手続き)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha2/20120803-05.html
参考:(全国健康保険協会 協会けんぽ 任意継続の加入手続きについて)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r316/
住民税の手続き
退職後は給与天引き(特別徴収)がなくなるため、自分で住民税を支払う「普通徴収」へ切り替わるケースがあります。支払い方法を把握し、納付漏れがないように注意が必要です。以下に住民税の支払い方法別に必要な手続き情報をまとめます。
|
普通徴収に切り替え |
特別徴収を継続 |
|
|
手続きの期限 |
なし(会社が処理) |
入社後すぐ |
|
提出先 |
なし(納付書が届く) |
転職先の人事担当 |
|
提出物 |
なし(市区町村から納付書が送付される) |
給与所得者異動届出書(転職先が提出) |
普通徴収になると、退職後に自宅へ届く納付書を使って、各自で金融機関やコンビニで支払うことになります。一方、すぐに転職する場合は、転職先の会社に依頼すれば特別徴収(給与天引き)の継続が可能です。
所得税の手続き
年の途中で退職し年末までに再就職しなかった場合は年末調整が行われていないため、自分で確定申告を行う必要があります。確定申告を怠ると、払いすぎた税金の還付を受けられなかったり、必要な控除が適用されなかったりする可能性があります。以下の表に、確定申告に関する概要をまとめます。
|
手続きの期限 |
翌年2月16日〜3月15日 |
|
提出先 |
納税地を管轄する税務署(またはe-Tax) |
|
提出物 |
・確定申告書 ・本人確認書類 ・源泉徴収票 ・医療費控除や保険料控除の証明書など |
確定申告では、年間の所得や控除額を正確に申告すると、払いすぎた税金が戻ってくることがあります。申告書は国税庁のWebサイトや税務署で入手でき、e-Taxを使えば自宅から申請も可能です。申告漏れを防ぐためにも、必要書類をあらかじめ整理しておきましょう。
参考:(国税庁 No.2020確定申告)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm
参考:(国税庁 〔令和5年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き〕申告書に添付・提示する書類)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/04/4_01.htm
転職は仕事を辞める前にするべき?
転職活動は、仕事を辞める前と後のどちらで行うかによって状況が変わります。ここでは、退職前と退職後、それぞれのタイミングで転職活動を行うメリットとデメリットを解説します。
仕事を辞める前に転職活動をするメリット・デメリット
仕事を辞める前に転職活動を行うと、生活基盤を維持しながら冷静に判断しやすくなります。収入を得ながら活動できるため、焦らずに転職先を選べる点が利点です。
仕事を辞める前に転職活動をするメリットは以下のとおりです。
- 収入が継続するため、経済的な不安が少なく落ち着いて活動できる
- 現職と内定先を比較しながら、ミスマッチの少ない転職先を選びやすい
- 内定を得た状態で退職交渉できるため、引き留めを受けにくくスムーズに辞めやすい
- 転職活動がうまくいかなくても、現職にとどまるという選択肢が残されている
一方で、現職と転職活動を同時に進めることには負担もあります。仕事を辞める前に転職活動をするデメリットは以下のとおりです。
- 業務と並行するため、時間や体力の確保が難しい
- 有給や休日を使って面接に行く必要があり、スケジュール管理が煩雑
- 多忙な職場では十分な準備ができず、納得のいく活動がしにくいこともある
- 転職活動に集中できず、選考が長引いたり機会を逃す恐れがある
以上を踏まえると、安定した生活を保ちながら次の職場を慎重に選びたい方は、仕事を辞める前に転職活動を進めるとよいでしょう。
仕事を辞めた後に転職活動をするメリット・デメリット
仕事を辞めた後に転職活動を行うと、スケジュールに余裕がある状態で取り組めるため、準備や選考に集中しやすくなります。精神的なゆとりが生まれ、キャリアの見直しや自己分析にも時間をかけることが可能です。
仕事を辞めた後に転職活動をするメリットは以下のとおりです。
- 面接や企業研究のスケジュール調整がしやすく、準備に集中できる
- 書類作成・面接対策・情報収集などに時間を割けるため、完成度の高い応募ができる
- 「すぐに入社可能な人材」として企業に好印象を与える場合がある
- 一度立ち止まって自分の働き方やキャリアを見直す機会になる
一方で、退職後の転職活動には経済的・心理的な不安もつきまといます。仕事を辞めた後に転職活動をするデメリットは以下のとおりです。
- 活動が長引くと空白期間ができ、選考で不利になる可能性がある
- 収入が途絶えることで生活費に困り、焦って就職先を決めてしまう恐れがある
- 「なぜ退職前に転職先を決めなかったのか」と企業側に不信感を持たれる可能性がある
- 規則正しい生活が崩れ、活動意欲が下がるリスクがある
以上を踏まえると、時間をかけて丁寧に転職活動を進めたい方にとっては退職後の活動が適しています。ただし、金銭面の備えや明確なスケジュールを立てた上で取り組むことが重要です。
仕事を辞める際の注意点
仕事を辞める際は、退職の時期や理由の伝え方、周囲への対応次第でその後の人間関係やキャリアにも影響が及びます。ここでは、円満に退職するための注意点を3つ解説します。
繁忙期を避けて円滑な退職を心がける
退職時期は、会社やチームの繁忙期を避けることが円滑な退職の基本です。業務が集中するタイミングで辞めると、引き継ぎが十分にできず、職場に混乱や不満を残すリスクがあります。
例えば、年度末の決算業務や繁忙月など、人手が必要な時期に退職を申し出ると、同僚の負担が増え、人間関係が悪化する可能性があります。繁忙期を外して相談すれば、上司との話し合いも前向きに進みやすく、スムーズな引き継ぎ計画も立てやすいでしょう。
退職理由はネガティブにならないよう前向きに伝える
退職理由は、前向きな内容にまとめると職場との良好な関係を維持しやすくなります。「不満があるから辞める」と思われると円満に退職するのは難しいでしょう。
例えば、「スキルを活かせる職場に挑戦したい」「新しい分野に挑戦したい」など、キャリアアップや成長意欲を軸にした理由であれば、相手にも納得されやすくなります。
退職理由に正直さは必要ですが、伝え方には戦略が求められます。感情的にならず、前向きな表現で退職の意思を伝えましょう。
お世話になった人には直接感謝の挨拶をする
退職時には、感謝の気持ちを直接伝えることが礼儀であり、信頼関係の維持にもつながります。口頭での挨拶はメールやメッセージよりも誠意が伝わりやすいため、できる限り対面で行うのが望ましいです。
同じプロジェクトを担当したメンバーや、日常的にサポートを受けた他部署の同僚などには、丁寧に感謝を伝えることが将来的な人脈の維持につながります。また、取引先への挨拶も信用を失わないために必要です。
退職後の生活を支える公的制度

退職後の生活に不安を感じる場合は、公的な支援制度を活用しましょう。各制度は条件を満たせば誰でも利用でき、収入が途絶えた期間の生活費や再就職活動の支援に役立ちます。さまざまな制度がありますが、ここでは代表的なものを3つ紹介します。
失業手当
失業手当は、生活資金を確保しながら求職活動を続けるために支給される給付金です。ハローワークで求職申込みを行い、定期的に就職活動の報告をすると、原則として退職理由に関係なく7日間の待期期間が設定されます。
その後、自己都合退職の場合はさらに1ヶ月間の「給付制限」があり、その後に給付が開始される仕組みです。給付額は退職前の平均賃金や年齢、被保険者期間によって決まります。
受給には「雇用保険被保険者離職票」の提出が必要で、再就職が決まった場合は支給が終了します。
再就職手当
再就職手当は、失業手当の受給資格を持つ方が早期に安定した就職を果たした場合に支給される一時金です。早期の就職を促進するために設けられており、一定の条件を満たせば基本手当の一部をまとめて受け取れます。
例えば、所定給付日数の3分の2以上を残して再就職した場合には、残日数の70%が支給され、3分の1以上を残している場合には60%が支給されます。再就職先が1年以上の雇用見込みがあることや、就職先がハローワークなどの紹介以外でも問題ないことなど、複数の要件が必要です。
職業訓練給付制度
職業訓練給付制度は、再就職に必要なスキルを身につけるための学習を支援する制度です。訓練を受けることで就職の選択肢が広がるため、スキルや資格が不足している方にとって重要な手段となります。
「公共職業訓練(ハロートレーニング)」や「求職者支援訓練」では、受講料の無料化に加え、条件を満たす場合には生活支援金の給付も受けられます。対象講座はIT・介護・営業事務など幅広く、再就職に直結する内容が中心です。
申し込みはハローワークで行い、訓練内容や給付条件について個別に確認を受ける必要があります。
まとめ
仕事を辞める前には、転職活動の準備や公的制度の確認、職場への伝え方など、計画的に取り組むべきことが多くあります。事前に適切な対応をしておくと退職後のトラブルや不安を減らし、スムーズに次のステップへ進むことが可能です。
この記事で紹介した内容を参考に、仕事を辞める前にやるべきことをひとつずつ実行し、安心して退職日を迎えられるよう備えてください。
退職後に受け取れる社会保険金の手続きに不安がある方は、「社会保険給付金サポート」の利用をご検討ください。専門家の支援を受けながら、確実な受給とスムーズな手続きが可能になります。まずはLINEから気軽にお問い合わせください。
この記事の監修者

杉山 雅浩
東京弁護士会所属。
池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。
NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、
詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。
YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!
おすすめの関連記事
ピックアップ
- CATEGORY
- 給付金について
- 転職・再就職について
- 就労について
- 社会保険について
- 精神疾患について
- サービスについて
- 傷病手当金について
- 失業保険について
- 退職について
- 障害年金について
- ピックアップ
- 人気記事
-
退職代行サービスの利用方法、実際の流れと体験談を紹介
-
今の会社に3年後もいる自信はありますか?
-
退職代行を利用した時の有給消化の仕組みとその対応方法
-
退職代行サービスを使うメリット・デメリットは?
-
ブラック企業を判定する方法と実際のチェックポイント
-
障害年金を知ろう
-
会社を“円満に退職する”方法は?
-
退職時の引き継ぎは義務?スムーズな業務引き継ぎの必須ポイント
-
パワハラ、モラハラ、セクハラとは?
-
辞めさせてくれない!そんな時こそ「退職代行サービス」
テーマ
- 転職サイト
- 不支給
- 引っ越し
- 雇用契約
- 退職代行
- 職務経歴書
- 等級
- 社宅
- 内定
- 退職代行サービス
- 人間関係
- 離職票
- 障害者手帳
- 就労移行支援
- ブラック企業
- スタートアップ
- 労務不能
- 精神保険福祉手帳
- 業務委託
- ハラスメント
- 転職
- 傷病手当金
- 労災
- 社会保険
- 引き継ぎ
- 違法派遣
- 障害者控除
- 産休
- 福利厚生
- 給与
- 派遣契約
- 退職届
- 解雇
- 就職困難者
- 残業代
- 障害厚生年金
- 面接
- 中小企業
- 再就職手当
- 退職金
- 失業保険
- 障害手当金
- ベンチャー企業
- 社会保険給付金
- 会社都合退職
- 資格取得
- 新型コロナウイルス
- 退職勧奨
- 職業訓練受講給付金
- 自己都合退職
- うつ病
- 有給消化
- 自己PR
- 退職給付金
- クレジットカード
- 統合失調症
- 休職
- 確定申告
- ハローワーク
- アルバイト
- 契約社員
- 免除申請
- 保険料
- 傷病手当
- 雇用保険
- 弁護士
- 適応障害
- 社会保障
- 退職コンシェルジュ
- 健康保険
- 公的貸付制度
- 住宅確保給付
- 就職
- インフルエンザ
- 年金
- 生活福祉資金貸付制度
- 職業訓練
- 労働基準法
- ストレス
新着記事
-
2026.01.06
退職して国民健康保険に切り替えたあとも傷病手当金はもらえる?注意点も解説
-
2025.12.27
インフルエンザで仕事を休むと「傷病手当金」はもらえる?条件・日数・申請方法まで解説
-
2025.12.26
傷病手当金と副業の関係をわかりやすく解説
-
2025.12.17
傷病手当金の不正と調査|どこからがNG?就労・外出・求職活動の正しい判断基準を解説
-
2025.12.16
【徹底比較】退職給付金サポート おすすめランキング
-
2025.12.09
傷病手当金をもらいながら働く方法はある?アルバイトならOK?収入を得る方法や注意点を解説
-
2025.12.09
社会保険給付金と失業保険の違いは?受給要件やメリット・デメリット解説
-
2025.12.08
産休・育休後そのまま退職はマナー違反?退職時のポイントと注意点
-
2025.12.07
会社を辞めさせられた場合は失業保険は受け取れる?条件や注意点を解説
-
2025.12.04
傷病手当金は退職後もらえない?受給できる条件と不支給になる理由を徹底解説





 サービス詳細
サービス詳細