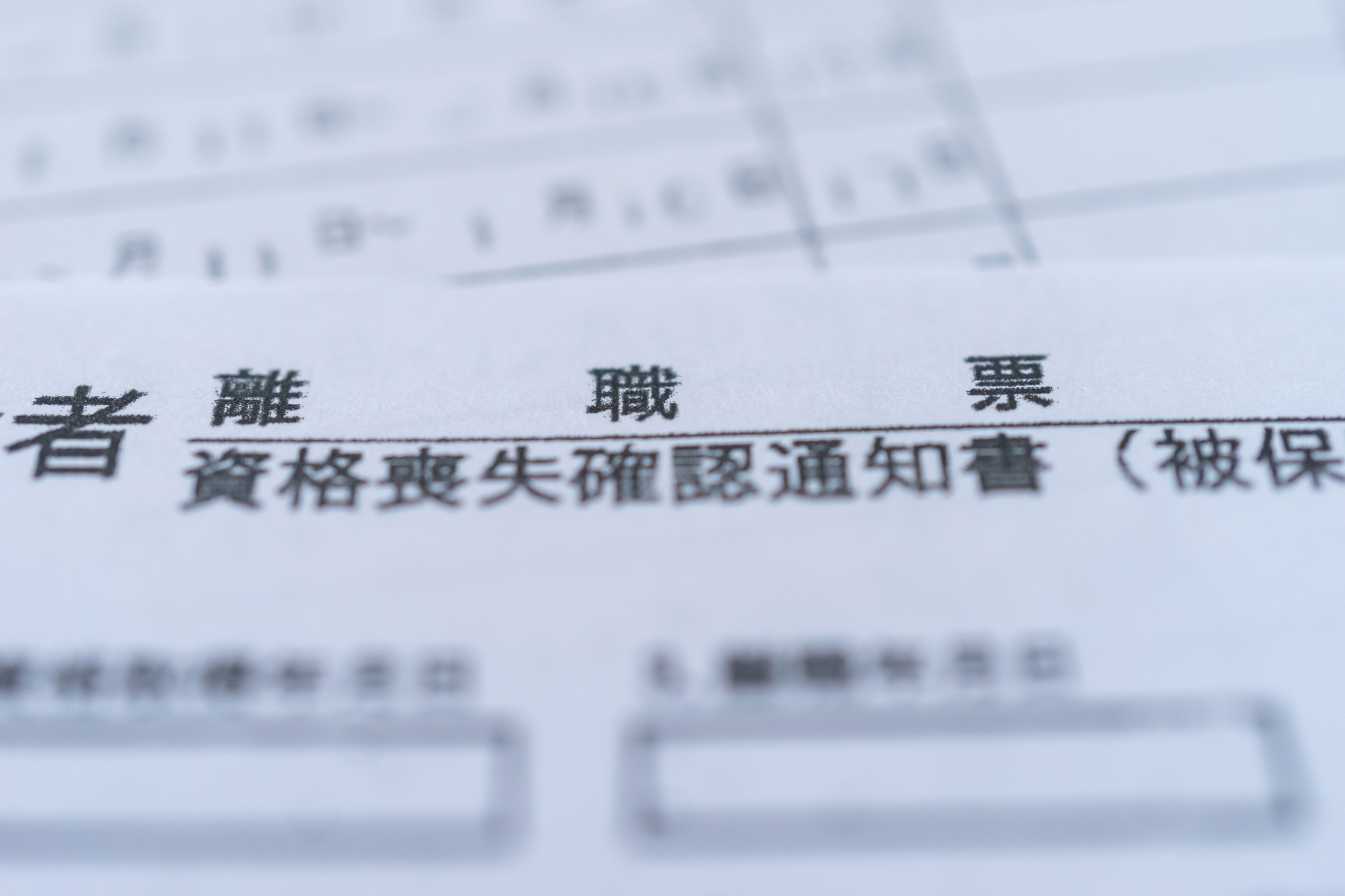2025.08.12
失業保険について
失業保険で損をしないためのポイントは?概要や受給する際の注意点も解説

失業保険を受け取りたいと考えていても、「自分は対象になるのか分からない」「損をしないためにはどうすればいいのか」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。失業保険には受給条件や手続きのルールがあり、退職理由や申請のタイミングによって、受け取れる金額や開始時期が大きく変わります。正しい知識がないまま手続きを進めると、本来もらえるはずの給付を受け損ねてしまう可能性もあります。
本記事では、失業保険で損をしないために知っておきたい制度の基本、申請方法、退職理由による違い、活用できる支援制度まで丁寧に解説します。
失業保険で損をしないためのポイント
 失業保険(正式には「基本手当」)は、働く意思と能力があるにも関わらず、職を失った人が、再就職までの生活を安定させるために支給される公的制度です。しかし制度の仕組みを正しく理解しないまま手続きを進めると、「本来もらえたはずの金額を受け取れなかった」「手続きが遅れて損をした」といった事態にもなりかねません。
失業保険(正式には「基本手当」)は、働く意思と能力があるにも関わらず、職を失った人が、再就職までの生活を安定させるために支給される公的制度です。しかし制度の仕組みを正しく理解しないまま手続きを進めると、「本来もらえたはずの金額を受け取れなかった」「手続きが遅れて損をした」といった事態にもなりかねません。
失業保険で損をしないために押さえておきたい基本的なポイントを解説します。
失業保険の制度を正しく理解しておく
失業保険の制度は一律ではなく、個人の状況によって受給条件(雇用保険の加入期間や離職理由)、給付日数、給付金額、給付制限の有無などが異なります。たとえば、会社都合退職か自己都合退職かで、受給開始時期や給付日数に大きな差が出るため、自分がどのケースに該当するかをしっかり確認することが大切です。
また、制度に関する知識が不十分なまま申請を行うと、不正受給とみなされて支給停止や返還請求を受けるリスクもあります。最新情報は厚生労働省やハローワークの公式サイトを確認し、不明点があればハローワークで相談するのが安心です。
なお、失業保険の詳細については後述の見出しで説明します。
雇用保険の加入期間を正確に把握しておく
失業保険を受給するには、原則として離職前2年間に「12カ月以上」雇用保険に加入している必要があります(自己都合退職の場合)。ただし、会社都合退職や契約満了など特定の条件に該当する場合は、「6カ月以上」の加入でも受給が可能です。
転職を繰り返していても、1年以内の空白期間の場合、被保険者期間として前職と通算されます。また、パートやアルバイトでも、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合には雇用保険の対象となり、受給資格を得られる可能性があります。
自分に合った制度や給付金の併用を検討する
失業手当以外にも、状況に応じて活用できる制度や給付金があります。たとえば、公共職業訓練を受講すれば、失業手当の給付期間が延長されるほか、交通費などの支援を受けられることもあります。また、早期に再就職が決まった場合には「再就職手当」が支給されるため、結果として受け取れる金額が増えるケースも少なくありません。
さらに、「教育訓練給付金」を利用すれば、指定講座の修了によって受講費の一部が戻ってくる仕組みです。病気や出産、介護などで一時的に働けない場合も、「受給期間延長制度」によって将来的に失業保険を受け取れる可能性が残されます。
併用できる制度もあるため、損をしないためにも、積極的な情報収集を行いましょう。
離職前6ヶ月の給与を意識的に調整する
失業手当の支給額は、離職前6ヶ月間の賃金日額(1日あたりの平均賃金)に基づいて計算されます。そのため、この期間に欠勤や時短勤務などがあると、受給額が下がるおそれがあります。
離職票にはこの6ヶ月の賃金情報が記載され、支給額の算定基準となるため、退職前に給与が下がらないよう意識しておくことが重要です。可能であれば、有給休暇を使って休むなど、計画的に収入を安定させる工夫をしておくとよいでしょう。
ハローワークで早めに相談や手続きを行う
失業保険は、自動的に給付されるものではなく、本人がハローワークに出向いて手続きを行う必要があります。申請が遅れると、その分受給開始も遅れ、結果的に損をしてしまう可能性があります。
また、自己都合退職であっても、退職理由や状況によってはハローワークの判断で「会社都合」扱いになる場合もあります。たとえば、過度な残業やパワハラ、賃金未払いなどが理由での退職は、特定受給資格者とみなされる可能性があり、給付制限なしで受給できることも想定されます。早めに相談して正しい情報を伝え、より有利な受給につなげましょう。
失業保険を受給するメリット・デメリット
失業保険は、経済的な不安を抱える退職後の期間を支える重要な制度です。再就職活動に集中できるメリットがある一方で、制度上の注意点も存在します。
失業保険を受給することで得られるメリットとデメリットをを整理して紹介します。
失業保険を受給するメリット
失業保険の最大のメリットは、生活資金を確保しながら安心して再就職活動に取り組める点です。具体的なメリットは、下記のとおりです。
・生活資金の補助
定期的な給付金により生活費の不安を軽減し、焦らずに次の転職先が探せます。
・再就職手当や職業訓練との併用
早期に再就職が決まった場合は「再就職手当」が支給される場合があり、実質的に手当総額が増えることがあります。職業訓練を受けた場合は「職業訓練受講給付金」などが追加で支給されることもあります。
・優遇措置が受けられる可能性
病気や介護、契約満了などやむを得ない理由で退職した「特定理由離職者」に該当すれば、自己都合退職でも給付制限なしで早期に受給が開始される可能性があります。
失業保険を受給するデメリット
一方で、失業保険を受給することによるデメリットも存在します。以下のような点には注意が必要です。
・雇用保険の加入期間がリセットされる
一度受給を開始すると、次回の失業時には再び一定期間の加入が必要です。継続的な支給を受けることはできません。
・年金との併給制限
60歳以上で老齢厚生年金を受給している場合、失業保険の受給により年金の一部または全額が支給停止になるケースがあります。
・就職活動が長引くリスク
給付金による収入が得られる安心感から、就職への意欲が薄れ、結果として転職活動が長引いてしまうこともあります。
これらのメリット・デメリットを正しく理解し、自分の状況に合わせた活用を心がけることが大切です。
失業保険の受給条件
失業保険を受け取るには、制度上の一定の要件を満たしている必要があります。基本的な3つの受給条件について確認しておきましょう。
雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
雇用保険は、労働者が失業した際に生活の安定を図るための公的保険制度です。「雇用保険」に加入していることが前提となるため、勤務先が雇用保険の適用事業所であるかどうかを確認することが大切です。
雇用保険の適用を受けるためには、以下の2つの条件を満たす必要があります:
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・31日以上の雇用見込みがあること
これらの条件を満たす労働者であれば、正社員はもちろん、パートやアルバイトでも雇用保険の対象となります。
離職前2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間があること
失業保険を受給するためには、離職前2年間に通算して12カ月以上の「被保険者期間」が必要です。
この「被保険者期間」とは、以下のいずれかを満たす月が1カ月としてカウントされます:
・賃金支払基礎日数が11日以上ある月
・労働時間が80時間以上ある月
なお、会社都合による退職や契約満了、病気・介護などやむを得ない事情がある場合は、「特定受給資格者」や「特定理由離職者」として認められ、離職前の1年間に6カ月以上の被保険者期間があれば受給資格を得ることができます。
就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること
失業保険は、再就職を目指して活動する人を支援する制度です。そのため、受給者には「就労の意志と能力」があることが求められます。
この条件を満たすには、次のような求職活動が必要です。
- ハローワークに「求職の申し込み」を行う
- 求人への応募や面接を受ける
- ハローワークで職業相談を受ける
- 再就職支援のセミナーやイベントに参加する
これらの活動実績は、失業認定の際に報告する必要があるため、日々の活動を記録しておくとスムーズです。
失業保険の給付条件は退職理由で異なる
失業保険の給付条件は、退職理由によって大きく異なります。「自己都合退職」と「会社都合退職」では、給付開始までの期間や給付日数に差があるため、自分の退職理由がどちらに該当するのかを正確に把握することが重要です。
それぞれのケースでの給付内容について詳しく解説します。
自己都合退職のときの失業保険
自己都合退職とは、自らの意思で退職を決めた場合を指します。たとえば、転職や家庭の事情、体調不良などがこれに該当します。
原則として、退職後7日間の待期期間に加え、1カ月間の「給付制限期間」があります。つまり、申請してから実際に失業保険が支給されるまで、約1カ月以上かかることになります。ただし、2025年4月以降、給付制限は1カ月に短縮されています。
自己都合退職の場合の給付日数は90日〜150日が基本で、会社都合退職より短く設定されています。
ただし、病気や介護、契約満了などやむを得ない事情がある場合、自己都合でも「特定理由離職者」として給付制限がなくなることがあります。
会社都合退職のときの失業保険
会社都合退職とは、労働者本人の意思に関係なく、会社の都合で退職を余儀なくされた場合を指します。主に以下のようなケースが該当します。
- 会社の倒産や事業所の閉鎖
- 経営不振による人員整理
- 一方的な解雇や雇い止め
- パワハラや過重労働などによるやむを得ない退職(ハローワークの判断による)
会社都合退職の場合、7日間の待期期間を過ぎれば、すぐに失業保険の支給が始まります。給付制限期間はありません。
給付日数は、年齢や被保険者期間に応じて90日〜330日まで設定されており、自己都合よりも手厚くなっています。再就職手当の支給要件を満たせば、給付日数が多い分だけ再就職手当の金額も増えやすくなります。
退職理由が「自己都合」か「会社都合」かによって、失業保険の内容に大きな差が出るため、手続きをする前にハローワークに相談し、自分のケースを確認することをおすすめします。
自己都合退職の場合でも失業保険をすぐに受け取れる場合がある
原則として、自己都合退職の場合には給付制限が設けられ、一定期間を経ないと失業保険を受け取ることができません。しかし、「特定受給資格者」や「特定理由離職者」として認定されることで、例外的に早期受給が可能になるケースもあります。
具体的な条件や手続き方法について紹介します。
「特定受給資格者」とは
「特定受給資格者」とは、主に以下のような理由で再就職の準備をする余裕もなく離職を余儀なくされた人を指します。
- 勤務先の倒産や事業の廃止
- 解雇、雇い止めなど、会社都合による一方的な退職
- 長時間労働やハラスメント、賃金未払いといった過酷な労働環境からの離職
このような事情がある場合、自己都合であっても「特定受給資格者」として給付制限なしで失業保険をすぐに受け取ることが可能になります。
「特定理由離職者」とは
「特定理由離職者」とは、「特定受給資格者」には当たらないものの、やむを得ない事情で離職した人を指します。主に以下のようなケースが該当します。
- 契約期間満了による退職
- 家族の介護や配偶者の転勤による離職
- 病気やけが、妊娠・出産による退職
自己都合での退職ではあるものの、一定の要件を満たせば「特定理由離職者」として扱われるため、給付制限がなくなる場合があります。
「特定受給資格者」と「特定理由離職者」の優遇
特定受給資格者や特定理由離職者に該当すると、失業保険の受給において次のような優遇措置を受けることができます。
・給付制限の免除
1カ月間の給付制限がなくなり、待期期間終了後すぐに支給が開始されます。
・受給要件の緩和
通常、失業保険を受け取るには12カ月以上の雇用保険加入が必要です。しかし、特定受給資格者・特定理由離職者の場合は「11日以上働いた月が6カ月」あれば受給資格を得られます。
自己都合であっても状況によっては大きな支援を受けられる可能性があるため、自分の退職理由を確認しておくことが大切です。
「特定受給資格者・特定理由退職者の手続き」とは
これらの認定を受けるには、ハローワークでの審査が必要です。自己申告だけではなく、客観的な証拠書類の提出が求められる場合もあります。
たとえば、病気で退職した場合には医師の診断書、介護の場合には介護認定の通知書、パワハラや長時間労働が理由の場合には勤務記録や上司とのやり取りの記録などが必要になることがあります。
早期に失業保険を受け取りたい場合は、離職票の提出と同時に必要な証拠書類を整えておき、ハローワークで「特定理由離職者」としての認定を受けられるよう相談することが重要です。
失業保険の申請方法
失業保険を受給するには、ハローワークでの求職申し込みから始まり、いくつかのステップを順に踏んでいく必要があります。申請が遅れると受給開始も遅れるため、スムーズに手続きを進めることが大切です。
失業保険を申請するための具体的な流れを説明します。
必要書類を揃える
ハローワークで求職申し込みを行う前に、以下の書類を準備しておきましょう。
- 雇用保険被保険者離職票-1・2
- 雇用保険被保険者証
- 証明写真(たて3cm×よこ2.4cm、正面上半身)×2枚
- 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載された住民票のいずれか1つ)
あらかじめ準備しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。
ハローワークで求職を申し込む
必要書類が揃ったら、最寄りのハローワークに出向いて求職の申し込みを行います。
- 求職申込書に記入する
- 必要書類を提出し、職業相談を受ける
- 雇用保険説明会の日時案内を受け取る
離職票などを基に受給資格の審査が行われ、条件を満たしていれば「失業等給付受給資格者のしおり」が渡されます。また、雇用保険説明会の日程は、申し込み日から7日後以降に設定されることが一般的です。忘れないように日時をメモしておきましょう。
待期期間を過ごす
求職申し込みを済ませると、7日間の待期期間に入ります。この期間は、ハローワークが失業状態を確認するためのものです。
短時間のアルバイトや内職も就労とみなされ、支給対象外になるおそれがあります。この7日間は、一切の就労をしないように努めましょう。
また、待期期間中に再就職が決定してしまうと、再就職手当の支給対象外になる場合があるため、注意が必要です。
雇用保険説明会に参加する
指定された日程の雇用保険受給説明会に参加します。説明会では、以下の内容について説明が行われます。
- 失業保険制度の概要と仕組み
- 受給までの流れと手続きの注意点
- 求職活動の方法と報告方法
説明会に参加する際の持ち物は、以下です。
- 雇用保険受給資格者のしおり
- 印鑑
- 筆記用具
説明会終了後には、「雇用保険受給資格者証」および「失業認定申告書」が交付され、初回の「失業認定日」が案内されます。
失業認定日にハローワークを訪れる
失業認定日は、ハローワークが実際に失業の状態であることを確認する日です。原則として4週間に1回設定されます。
失業認定申告書を提出し、就職活動の実績(求人への応募や面接、セミナー参加など)を報告する日です。
初回の失業認定日は、離職票提出日から約3週間後に設定されることが一般的です。認定を受けることで、ようやく失業保険の支給が開始されます。
失業保険の申請には段階的なステップがありますが、準備を整えていれば複雑な手続きではありません。早めの行動と正しい情報の把握が、受給までの最短ルートになります。
失業保険を受給する際の注意点

失業保険は再就職までの生活を支える制度ですが、正しく利用しないと不正受給や損失のリスクが伴います。特に副業や家業の手伝い、再就職手当の申請タイミング、扶養制度との関係などには注意が必要です。
失業保険を受給する際によくある注意点をまとめました。
家業の手伝いや副業は不正受給になるリスクがある
失業手当は「就労できない状態」にある人に支給されるため、家業の手伝いや副業があると「就業している」と見なされる可能性があります。
家事手伝いや農業・商業など家業への従事も、報酬の有無にかかわらず「就業」と判断されるケースがあります。申告せずに失業手当を受給すると、不正受給とされ、返還命令や加算金、最悪の場合は刑事罰の対象となる可能性もあります。
少しでも不明点や疑問点がある場合は、事前にハローワークで確認し、必ず申告することが大切です。
再就職手当の金額が減る可能性がある
再就職手当は、「失業手当の支給残日数が3分の1以上ある状態で早期に再就職した人」に対して支給される制度です。
そのため、失業手当を長く受け取ってから再就職すると、支給残日数が少ないと、再就職手当の金額が減額されるか、支給されない可能性があることに注意しましょう。また、「就業促進定着手当」も、早期再就職を前提とした制度のため、支給条件に影響が出る可能性があります。
再就職の目処がある場合は、できるだけ早いタイミングでの申請・行動が、支給額の最大化につながります。
扶養に入る方がお得になる場合もある
失業手当の受給額が少ない場合、配偶者などの扶養に入ることで、以下のようなメリットを得られることがあります。
・健康保険料の負担が減る:扶養に入ることで、保険料を自分で支払う必要がなくなります
・住民税の負担軽減:所得が一定以下であれば、住民税が非課税になるケースがあります
・年金負担の軽減:第3号被保険者として、国民年金保険料の支払いが免除される可能性があります
ただし、扶養に入れるかどうかの基準は「基本手当の日額」で決まり、日額が3,612円以下であれば扶養に入ることが可能です。これを超えると、受給期間中は扶養から外れる必要があります。
まとめ
失業保険は、退職後の生活を支える重要な制度です。ただし、受給には条件や手続きがあり、退職理由や申請のタイミングによっても支給内容が大きく変わるため、損をしないためにも制度の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。
「自分は失業保険を受け取れるのかどうか分からない」「手続きが不安」という方は、専門のサポートを活用するのもひとつの方法です。社会保険給付金サポートは、専門家が複雑な手続きをサポートするサービスであり、安心して制度を活用できるようになります。正しい情報と準備をもとに、損をしない選択をしていきましょう。
この記事の監修者

杉山雅浩
スピネル法律事務所 弁護士
東京弁護士会所属。
池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。
NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、
詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。
YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、テ日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!
おすすめの関連記事
ピックアップ
- CATEGORY
- 給付金について
- 転職・再就職について
- 就労について
- 社会保険について
- 精神疾患について
- サービスについて
- 失業保険について
- 再就職手当
- 雇用保険について
- 退職について
- 障害年金について
- ピックアップ
- 人気記事
-
退職代行サービスの利用方法、実際の流れと体験談を紹介
-
今の会社に3年後もいる自信はありますか?
-
退職代行を利用した時の有給消化の仕組みとその対応方法
-
退職代行サービスを使うメリット・デメリットは?
-
ブラック企業を判定する方法と実際のチェックポイント
-
障害年金を知ろう
-
会社を“円満に退職する”方法は?
-
退職時の引き継ぎは義務?スムーズな業務引き継ぎの必須ポイント
-
パワハラ、モラハラ、セクハラとは?
-
辞めさせてくれない!そんな時こそ「退職代行サービス」
テーマ
- クレジットカード
- 資格取得
- 退職届
- 引っ越し
- 労働基準法
- 退職コンシェルジュ
- 退職代行
- アルバイト
- 精神疾患
- 面接
- 社宅
- 雇用契約
- ストレス
- 退職代行サービス
- 雇用保険
- うつ病
- 障害手当金
- 障害者手帳
- 内定
- ブラック企業
- 健康保険
- 統合失調症
- 自己都合
- 精神保険福祉手帳
- 就労移行支援
- ハラスメント
- 年金
- 契約社員
- 会社都合
- 労災
- 業務委託
- パワハラ
- 転職活動
- 弁護士
- 失業給付
- 産休
- 社会保険
- モラハラ
- 転職サイト
- 公的貸付制度
- 新型コロナウイルス
- 解雇
- 福利厚生
- セクハラ
- 職務経歴書
- 生活福祉資金貸付制度
- 有給消化
- 中小企業
- 失業手当
- 障害年金
- 人間関係
- 不支給
- 休職
- ベンチャー企業
- 就職困難者
- 引き継ぎ
- スタートアップ
- 等級
- 免除申請
- 会社倒産
- 再就職手当
- 給与
- 転職
- 離職票
- 適応障害
- 退職勧奨
- 社会保険給付金
- 残業代
- 違法派遣
- 労務不能
- 住宅確保給付
- 自己PR
- 職業訓練受講給付金
- 退職金
- 派遣契約
- 傷病手当金
- 給付金
- 確定申告
- 退職給付金
- 会社都合退職
- 障害厚生年金
- 年末調整
- 職業訓練
- 保険料
- ハローワーク
- 自己都合退職
- 失業保険
- 障害者控除
- 再就職
- 社会保障
- 就業手当
- 退職
- ブランク期間
- 退職願
- 職業訓練受講手当
- 就職
- 傷病手当
新着記事
-
2025.10.07
年金と失業保険を同時にもらう方法はある?年齢別の受給方法を解説
-
2025.10.07
ハローワークの認定日の時間に遅刻したら失業保険は受けられない?欠席した場合も解説
-
2025.10.03
失業保険はいつ振り込まれる?支給日の目安と早くもらう方法を解説
-
2025.10.03
個人事業主も失業保険をもらえる?受給できるケースとできないケース
-
2025.10.03
離職票が届くまでにできることとは?届くのが遅い場合の原因や対処法を徹底解説
-
2025.09.19
退職サポーターズは怪しい?口コミ・評判を徹底調査!
-
2025.09.09
仕事を辞めるタイミングとは?適切な伝え方や注意点を解説
-
2025.09.04
仕事のストレスで限界を感じたときの対処法は?退職する前に知っておきたいポイント
-
2025.09.04
再就職手当はいつもらえるの?受給条件や支給額、申請手順を解説
-
2025.09.04
特定理由離職者になるにはどんな手続きが必要?判断基準や必要書類を解説





 サービス詳細
サービス詳細