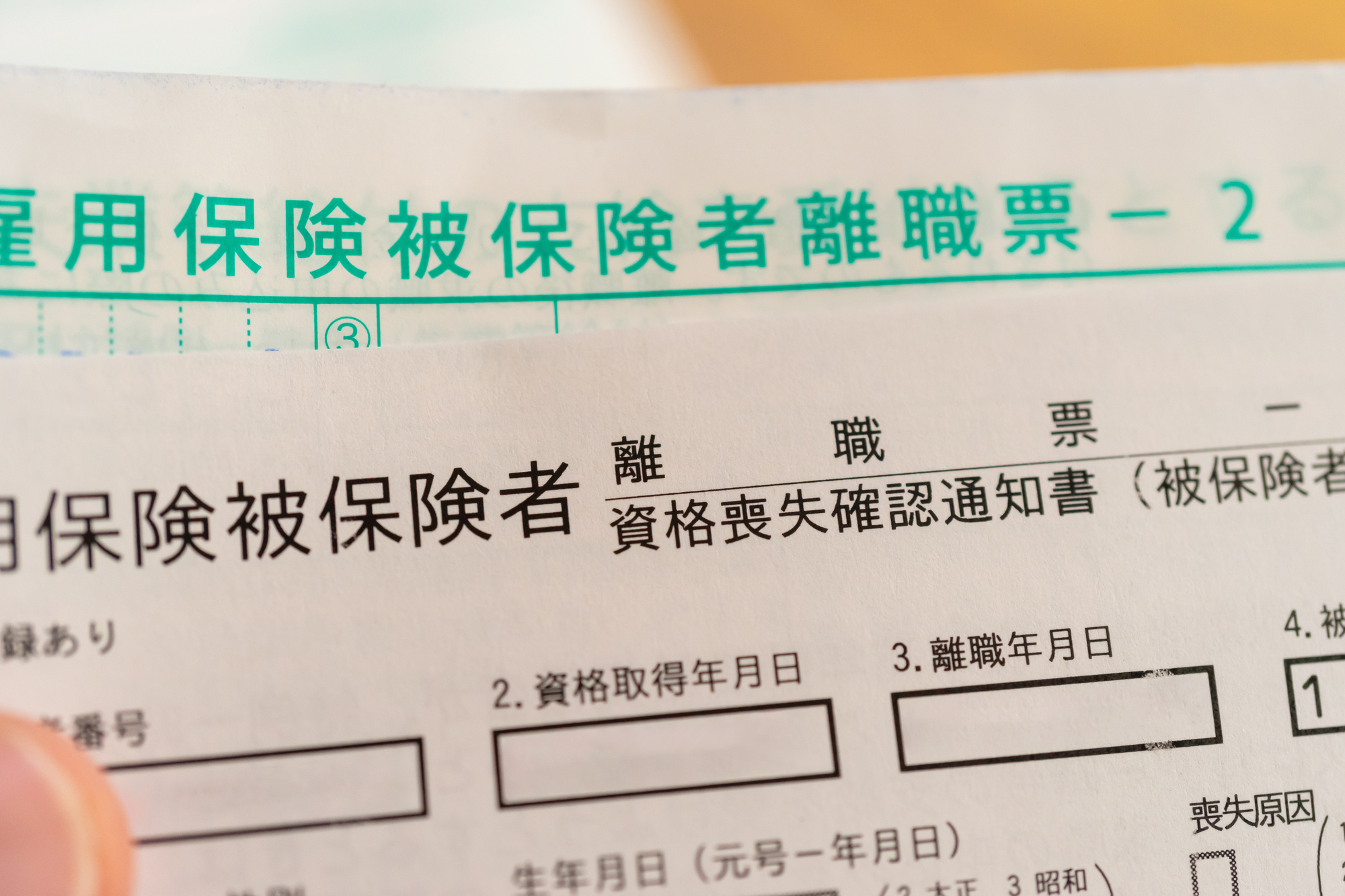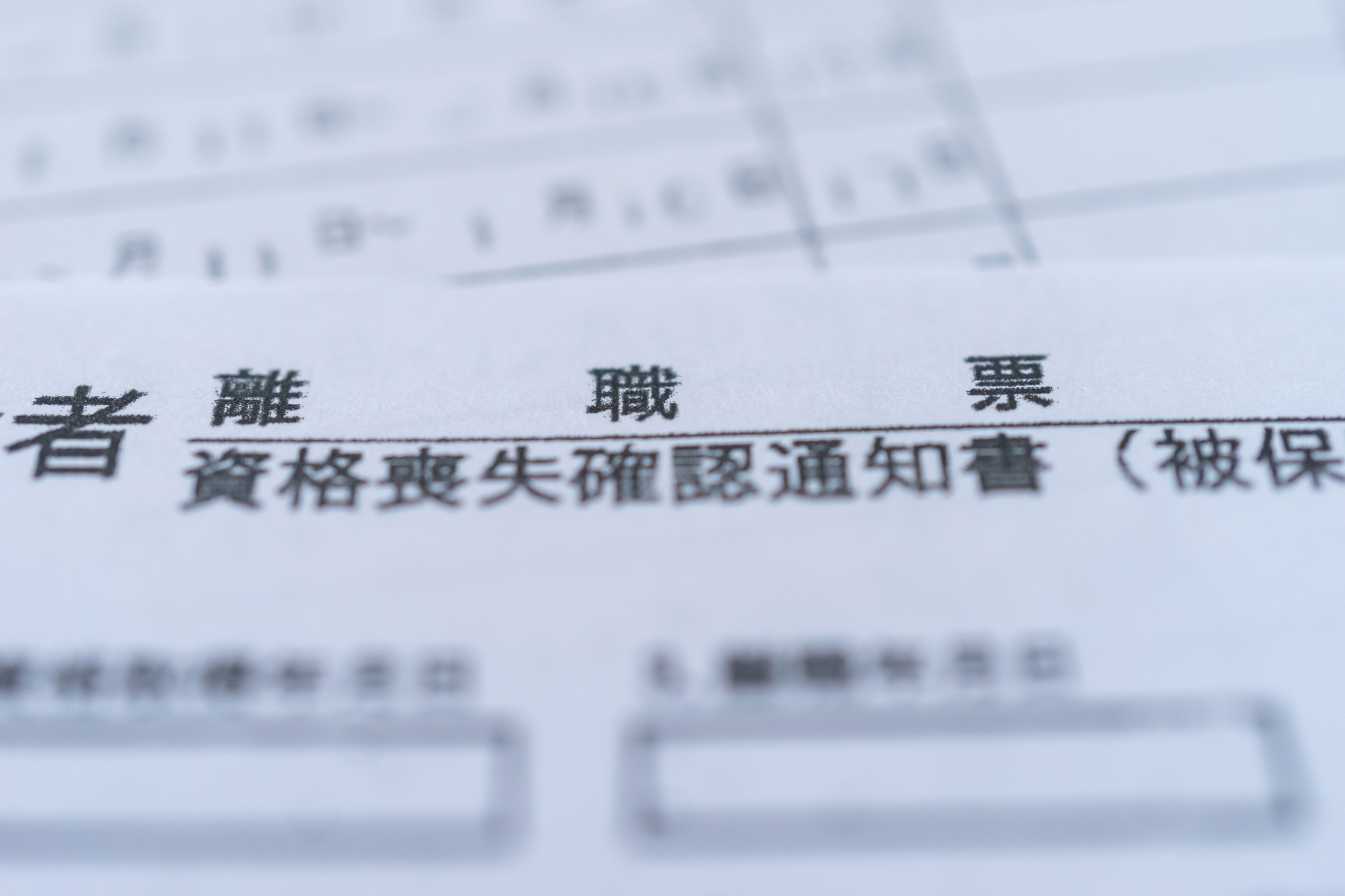2025.07.18
退職について
ストレスで仕事を辞める場合は診断書が必要?活用できる制度も解説
 ストレスが原因で仕事を辞めたいと考えたとき、「診断書は必要?」「退職後に使える制度は?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。退職は自分の意思で可能ですが、診断書があると手続きを円滑に進めやすくなり、失業保険や支援制度の利用にもつながります。
ストレスが原因で仕事を辞めたいと考えたとき、「診断書は必要?」「退職後に使える制度は?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。退職は自分の意思で可能ですが、診断書があると手続きを円滑に進めやすくなり、失業保険や支援制度の利用にもつながります。
本記事では、ストレスによる退職時に診断書を取得するメリットや、活用できる制度、再就職に向けた準備のポイントまで、わかりやすく解説します。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
ストレスで仕事を辞める場合は診断書が必要?

結論から言いますと、診断書がなくても退職することは可能です。労働者には、原則として退職の自由が認められており、たとえ体調不良が理由であっても、会社に対して理由を詳しく説明する義務はありません。
しかし、診断書があると、会社側に対し退職理由を客観的に示すことができるため、退職までの手続きがスムーズに進む可能性があります。就業規則などで「退職時には診断書の提出が必要」と定められている場合もあるため、事前に会社の規定を確認しておくことが重要です。
また、会社側が就業規則に診断書提出の義務を定めていない場合でも、退職の申し出を受けた会社には、従業員を引き止める法的権利はありません。あくまで、労働者の意思が尊重されるべきであるという点を理解しておくと安心です。
ストレスで仕事を辞める場合に診断書をもらうメリット
ストレスでの退職に際し、医師から診断書をもらうことには、以下のようなメリットがあります。
- 会社にスムーズに退職の意思を伝えられる
- 失業保険の受給条件が緩和される可能性がある
- 公的支援や再就職支援などの制度を利用しやすくなる
診断書は病名や労務不能の状態を客観的に証明した内容が記載されており、体調不良を理由に退職する場合、会社側にも納得してもらいやすくなります。
また、ストレスによる退職であっても、診断書があることで「特定理由離職者」と認定される可能性があります。これにより、失業保険の受給要件が緩和され、給付までの期間が短縮されるなどのメリットがあります。
さらに、適応障害やうつ病、自律神経失調症といった病名が医師からついた場合、公的機関による支援や就労支援サービス、生活支援制度などが受けられることもあります。こうした制度の多くは、診断書の提出を前提としているため、適切なサポートを受けるためにも診断書の取得は有効といえるでしょう。
ストレスで仕事を辞める時の診断書について
ストレスが限界に達しても体調の不調は目に見えにくいものです。しかし、医師の診断書があれば、会社に状況をうまく伝えられない場合にも役立ちます。
ここでは診断書の取得方法や内容、費用、有効期限について詳しく解説します。
診断書のもらい方
診断書をもらうには、適切な診療科にかかることが大切です。ストレスが原因の不調であれば、心療内科や精神科の受診が基本となります。内科などでは診断書の発行を断られることがあるため、症状に合った専門科を選びましょう。
初診では、病状の経過や背景が医師に十分に伝わりにくく、その場で診断書が出ないこともあります。体調の変化を時系列で説明できるよう、事前にメモを準備しておくとスムーズです。
また、診断書を退職のために使用したい場合は、目的を医師にしっかりと伝えることが重要です。診断書は用途によって記載内容が変わるため、「会社に提出する」「労務が困難であることを示したい」といった希望があれば、具体的に伝えておきましょう。
診断書に記載される内容
診断書には、以下のような内容が記載されます。
- 病名(例:適応障害、うつ病など)
- 現在の症状
- 治療の方針や内容
- 労務不能の理由(働けない医学的根拠)
- 療養の必要期間
- 医師の署名・押印
会社に提出する場合は、「労働が困難である医学的な理由」が明記されていることがポイントになります。なお、記載内容は医師の判断に基づいて作成されますが、「退職を希望している」など、希望がある場合は事前に伝えておくと、より目的に合った診断書になることがあります。
医師の署名・押印は、診断書としての正当性を示します。提出先に対し、原本(正本)が必要か、コピーで良いかの確認も忘れずに行いましょう。
診断書の費用
診断書の発行は保険適用外(自由診療)のため、全額自己負担となります。一般的な診断書の費用は、3,000円〜10,000円前後ですが、病院によって金額に差があるため、あらかじめ費用を確認しておくと安心です。
また、診断書が必要な提出先(会社、ハローワークなど)により、指定様式があるケースもあり、よく確認してから医師に依頼するようにしましょう。
診断書の有効期限
診断書には法律上の明確な有効期限はありませんが、一般的には1〜3ヶ月以内に発行されたものが望ましいとされています。古い診断書は、会社によっては「無効」と判断されてしまう場合もあるため、提出時期に合わせて取得することが大切です。
診断書の作成には通常、数日から1週間程度かかります。急ぎで必要な場合は、当日発行が可能かどうか、事前に医療機関へ確認しておきましょう。
ストレスで仕事を辞める時の具体的な流れ
ストレスによる体調不良で退職を決めた場合、やるべきことがいくつかあります。ここでは、診断書の取得から退職届の提出までの流れをわかりやすく解説します。
医師の診断を受けて診断書をもらう
まずは、心療内科や精神科などの専門機関を受診しましょう。ストレスによる体調不良の場合、適応障害やうつ病といった診断名が付くケースが多く、診断名は退職の理由としての説得力を高めます。
診断書には、「労務不能であること」や「一定期間の療養が必要であること」が記載されます。医学的な裏付けがあることで、会社側も状況を理解しやすくなり、退職までの手続きもスムーズに進めやすくなります。
診断書の提出期限が決まっている場合は、早めの受診を心がけることが大切です。必要書類の準備にも時間がかかることがあるため、余裕を持って動き出しましょう。
退職の意思を伝える
診断書を取得したら、次は退職の意思を会社に伝えます。一般的には、直属の上司や人事担当者に口頭と文書(退職届)で伝えるのが基本です。口頭だけでなく文書でも提出することで、トラブルを防ぎやすくなります。
法律上は、退職の申し出から2週間後には退職が可能ですが、業務の引き継ぎや有給消化などを考慮し、1ヶ月前を目安に伝えると安心です。
体調が悪く出社が難しい場合は、電話で連絡したうえで、診断書と退職届を郵送するという方法もあります。その際は、配達記録が残るレターパックや簡易書留などを利用すると確実です。
引き継ぎや有給休暇を消化する
退職が決まった後は、業務の引き継ぎを進めます。体調に無理のない範囲で、できるだけ引き継ぎを行うと印象が良くなります。出社が難しい場合は、業務の流れをまとめた簡単な資料を作成しておきましょう。誠意を見せることが重要です。
有給休暇が残っている場合は、退職日までに計画的に消化することができます。退職の意思を伝える際に、あわせて有給休暇の取得希望も伝えておくと手続きがスムーズです。体調が優れず、引き継ぎの負担が大きい場合は、上司や同僚に相談することも選択肢のひとつです。
退職届を出して退職する
退職届には、「一身上の都合により退職いたします」といった一般的な表現を使用します。病名や理由の詳細は記載不要です。
退職届には退職日を明記し、会社のルールに従って書面で提出します。基本は上司への直接手渡しですが、体調や出社状況によっては郵送でも問題ありません。
退職後には、社会保険の切り替えや雇用保険(失業手当)の手続きが必要になるため、あらかじめ必要書類や手続きの流れを確認しておくとより安心です。
ストレスで仕事を辞める際の注意点
ストレスを理由とした退職は、心身の健康を守るために必要な選択です。しかし、進め方を誤ると損をしてしまうこともあります。トラブルを避け、安心して次の一歩を踏み出すために、事前に知っておきたいポイントを整理しておきましょう。
無断欠勤はしないようにする
退職前に無断欠勤をしてしまうと、退職金や有給休暇の消化といった制度が利用できなくなる恐れがあります。また、会社に損害を与えたと判断された場合、懲戒解雇とされる可能性もあるため注意が必要です。
体調が悪くて出社できない場合でも、「体調不良が原因である」ことを伝えれば問題ありません。心の不調は見えづらいものですが、正当性のある理由です。必要以上に引け目を感じる必要はありません。
どうしても会社に連絡をするのが精神的に難しいときは、退職代行サービスを利用する方法もあります。専門業者が間に入り、会社とのやりとりを代行してくれるため、本人の負担を軽減できます。
退職後の生活も見据えておく
ストレスを抱えたまま、限界まで我慢して働き続ける必要はありません。しかし、退職後の生活を想定しておくことで「辞めなければよかった」と後悔するリスクが減らせます。
無理にすぐ働く必要はありませんが、収入がなくなり生活の不安がストレスの原因になってしまっては、元も子もありません。失業保険や傷病手当金など、活用できる制度を事前に調べておくことが大切です。
また、ストレスの原因について整理しておくと、今後の就職先選びや再発防止にもつながります。「人間関係がつらかった」「業務量が多すぎた」など、自分がストレスを感じやすいポイントを振り返り、理解を深めることで次に活かしやすくなります。
休職も検討する
退職を決断する前に、まずは「休職」という選択肢も検討してみましょう。体調が原因であれば、一定期間仕事を休み、その間に心身の回復を図ることができます。
また、ストレスの原因が職場の人間関係や環境にある場合、部署異動などで改善される可能性もあります。信頼できる上司や人事担当に相談してみましょう。
健康保険に加入していれば、休職中に「傷病手当金」を受け取れる場合があります。給与の代わりに支給される給付金で、一定の条件を満たせば退職後も受給を継続できる点は、心強いポイントです。
ストレスで仕事を辞める際に活用できる失業保険
ストレスを理由に退職した場合でも、一定の条件を満たせば失業保険(雇用保険の給付)を受け取ることができます。ここでは「失業手当」や「傷病手当」の内容や受給条件などを紹介します。
失業手当とは
失業手当は、雇用保険に加入していた労働者がやむを得ず仕事を辞めた場合や、再就職が困難になった場合に生活を支えるために支給される給付金です。
失業手当を受給するための主な条件は以下のとおりです。
- 雇用保険に加入し、保険料を支払っていたこと
- 離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があること(特定受給資格者・特定理由離職者は、1年間に6ヶ月以上で可)
- 働く意思と能力があり、求職活動をしていること
一方、以下に該当する場合は受給対象外となります。
- 妊娠・出産・育児のためすぐに働けない
- 病気・ケガ・障害などで就労できない状態
- 働く意思がない(再就職の意思がない)
- 家事や学業に専念している
- 会社の役員になっている
- 自営業で雇用保険に加入していなかった
「働ける状態であること」は、失業手当受給の前提条件です。
傷病手当とは
退職後すぐに働けない場合には、失業手当ではなく「傷病手当」を受け取れる可能性があります。傷病手当は、雇用保険の給付制度のひとつで、病気やケガなどで15日以上就労が難しい場合に対象となります。
傷病手当の受給条件は以下のとおりです。
- 基本手当(失業手当)の受給資格を満たしている
- 病気やケガなどにより15日以上、または30日以上就労できない
- 病気やケガの発生が「求職の申込み後」である
手続きを進めたい場合、病気やケガが治ったあとの最初の失業認定日までに、ハローワークにて傷病手当支給申請書や受給資格者証などの必要書類を提出します。申請書は、ハローワーク窓口での受け取りまたはハローワークインターネットサービスサイトからのダウンロードで入手可能です。
失業手当と傷病手当は同時には受給できない
失業手当は、就労の意思と能力があり、求職活動をしている人を対象とした制度であり、傷病手当は病気やケガにより働くことができない状態の人が対象の制度です。つまり、同時受給はできません。
たとえば、退職後すぐに療養が必要な場合は、まず傷病手当を受け取り、体調が回復してから失業手当に切り替えるという流れになります。退職後29日以内にケガや病気が改善した場合は、一般的な失業保険の申請方法とほぼ同じです。
受給の流れは、次のとおりです。
- 必要書類を用意してハローワークで求職申し込み
- 7日間の待期期間を経て説明会に参加
- 給付制限がある場合(自己都合退職など)はさらに期間を置いて支給開始
退職から30日以上経っても体調が回復しない場合は、失業手当の「給付期間延長」の手続きを行いましょう。給付期間が経過してしまうことを防ぐための制度で、事前申請が必要です。
ストレスの退職は特定理由離職者になる可能性がある
ストレスを理由に退職する場合、一般的には「自己都合退職」に分類されるケースが多いものの、一定の条件を満たせば「特定理由離職者」として扱われることがあります。
特にうつ病や適応障害といった精神的な疾患を原因として退職する場合、「正当な理由のある自己都合退職」と認められると、「特定理由離職者」としての扱いになります。
特定理由離職者に該当すると、以下のようなメリットがあります。
- 受給要件の緩和(被保険者期間6ヶ月以上で可)
- 給付制限なし(すぐに支給開始)
ただし、特定理由離職者として認定されるには、医師の診断書が必要です。「労務不能」であることや、「療養が必要」といった内容が記載されていることが望ましく、ハローワークでの提出が求められます。以下の記事にて詳しく説明しているので、 ぜひ参考にしてください。
うつ病で退職しても失業保険はもらえる?受給条件や受給方法を紹介
失業保険における特定理由離職者のメリット
ストレスなどの正当な理由によって自己都合退職をした場合、「特定理由離職者」に該当すると、通常の自己都合退職者と比べて失業保険の面で有利な取り扱いを受けられることがあります。
具体的なメリットについて解説します。
失業手当の受給要件が緩和されている
特定理由離職者は、再就職が困難な事情を抱えているとみなされるため、受給要件が緩和されています。
- 一般の離職者:離職日以前の2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要
- 特定理由離職者:過去1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給可能
比較的短い勤務期間でも失業手当の対象となる点は、大きな特徴です。
失業保険の支給が早い
特定理由離職者には、給付制限期間が設けられていません。そのため、以下のようなスケジュールで支給が開始されます。
- ハローワークでの手続き後、7日間の待期期間が発生
- 雇用保険説明会への参加
- 初回認定日(おおむね1ヶ月程度で初回の支給開始)
一方、通常の自己都合退職者や懲戒解雇の場合は、待期期間の後にさらに1ヶ月の給付制限期間が発生します。比較的早いタイミングで失業手当を受け取れる点は、特定理由離職者の大きなメリットです。
ストレスで仕事を辞めた人が再就職する際に活用できるサービス
ストレスが原因で退職した場合、再就職してもストレスに悩まされる可能性を考え、不安になる方も多いことでしょう。無理のないペースで再スタートを切るために活用できる、具体的サービスを紹介します。
ハローワーク
ハローワークでは、誰でも無料で利用できる支援が用意されています。とくに障害者専門の窓口が設けられており、精神的な不調を抱える方への配慮もなされている点が特徴です。
求人の紹介をはじめ、職業訓練の案内や、履歴書作成・面接に関するアドバイス、企業とのマッチングやインターンに関する相談まで、幅広いサポートが提供されています。雇用保険に関する各種手続きも一括して行えるため、これらの支援を一箇所で受けられるという利便性の高さは、ハローワークの大きな魅力と言えるでしょう。
就労移行支援センター
就労移行支援センターは、うつ病や適応障害などの精神疾患を抱える方に対して、再就職に向けた準備をサポートするための施設です。たとえば、ビジネスマナーやパソコンスキルを学べるほか、履歴書の作成支援や模擬面接の練習なども行われています。
生活リズムを整えるための支援も受けられるため、就労に向けた土台作りに役立ちます。一定の条件を満たせば、国の助成によって無料または低額で利用できるため、無理なく働く準備を進めたい方にとっては、非常に心強い存在といえるでしょう。
障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターは、「働くこと」と「暮らすこと」の両方を支える支援機関です。たとえば、生活リズムを整えるためのアドバイスや金銭管理のサポートに加え、健康面や家庭環境に関する相談にも応じてくれます。
医療機関や福祉サービス、ハローワークなど、関係機関との連携も行っており、必要に応じた支援体制が整えられています。ストレスの影響が長引いていたり、生活面にも不安を抱えている方にとっては、包括的な支援を受けられる貴重な存在です。
ストレスで仕事を辞めた場合の転職活動のポイント

ストレスが原因で退職した場合、転職活動を始めるタイミングや職場選びには慎重さが求められます。同じようなストレスを繰り返さないためには、事前の準備と情報収集が重要です。
職場環境をしっかり確認する
次の職場を探すときは、給与や勤務条件だけでなく、職場の雰囲気や人間関係も重視しましょう。特にストレスの原因が「人間関係」や「労働時間の長さ」など明確であれば、同じような環境を避けるためにも、事前に情報を得ておくことが重要です。
面接では、「職場の雰囲気」や「働き方」について具体的に質問することで、自分に合うかどうかを判断しやすくなります。「残業の状況」や「チームの雰囲気」などについて掘り下げたり、可能であれば職場見学を依頼したりすることで、職場の実態が見えてきます。
体調が回復してから転職活動を始める
退職後すぐに無理して働こうとするのではなく、まずは心身の回復を最優先にしましょう。十分に休養を取り、日常生活のリズムが整ってから転職活動を始めることが理想的です。
不調の度合いや回復の目安については、医師やカウンセラーと相談し、客観的に判断することが勧められます。いくら「もう復帰して働けそう」と思っても、焦って再発してしまっては本末転倒です。
転職エージェントを活用する
一人での転職活動に不安がある場合は、転職エージェントを活用する方法も効果的です。キャリアアドバイザーが希望条件をヒアリングし、適した求人を紹介してくれるほか、面接対策や書類添削などをサポートしてくれます。
また、職場や環境面での相性は自分では気づきにくいものです。プロの視点でアドバイスが受けられるため、安心して次のステップへ進むことができます。
ストレスで仕事を辞める際によくある質問
ストレスによる退職は決して珍しいことではありませんが、初めての手続きや制度利用には疑問や不安もつきものです。ここでは、よくある質問と答えについてわかりやすく紹介します。
失業保険の申請方法は?
失業保険の申請は、以下の流れで行います。
- 必要書類を揃える
- ハローワークで求職を申し込む
- 7日間の待期期間を過ごす
- 雇用保険説明会に参加する
- 失業認定日にハローワークを訪れる
必要な書類は以下です。
- 雇用保険被保険者離職票(1・2)
- 雇用保険被保険者証
- 証明写真(縦3cm×横2.4cm、正面上半身)×2枚
- 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか)
うつ病や適応障害の場合に他に活用できる制度はある?
状態に応じて、以下の制度が活用できる可能性があります。
- 自立支援医療制度:精神科の通院費が軽減される制度
- 障害年金:長期的な就労困難が認められる場合に支給
- 障害者手帳:再就職支援や交通費の割引、福祉サービスの利用などが可能
- 生活保護:収入がなく生活に困窮している場合に支給される最低限の生活保障
自治体や医療機関を通じて申請可能です。
ストレスで仕事を辞める際には自己都合退職か会社都合退職のどっち?
退職の理由によって、扱いが異なります。
- 自己都合退職:自ら退職の意思を伝えて辞めた場合
- 会社都合退職:会社からの解雇やハラスメントなど、退職せざるを得ない事情がある場合
ストレスの原因がパワハラやいじめなど会社側にある場合、証拠があれば会社都合退職(特定受給資格者)として認められることもあります。
なお、自己都合と会社都合では、失業保険の支給時期や期間に違いが出るため、ハローワークでの相談時には事情を詳しく説明することが大切です。
ストレスで仕事を辞めた際に履歴書にはどのように書く?
履歴書の退職理由欄には、基本的には「一身上の都合により退職」と記載して問題ありません。詳細な理由を記載する義務はなく、伝えなくても虚偽とはなりません。
ただし、面接で空白期間について質問されることはあるため、「療養のために一定期間休んでいた」など、事前に自分なりの説明を考えておくと安心です。伝え方に迷った場合は、転職エージェントなどに相談する方法もあります。
まとめ
ストレスが原因で仕事を辞めることは、決して珍しいことではなく、心身の健康を守るための大切な選択です。診断書の有無にかかわらず退職は可能ですが、診断書を用意することで手続きがスムーズになり、失業保険や傷病手当金といった制度の利用にもつながりやすくなります。
退職後の不安を軽減するためには、制度を正しく理解し、状況に応じて「特定理由離職者」などの認定を受けることも重要です。支援サービスの活用や転職準備の進め方にも工夫をすることで、無理のない再スタートが可能になります。
しかし「傷病手当金」や「失業手当」などの社会保険給付金は、制度が複雑なため、個人での申請が難しいと感じる方も少なくありません。自分が給付金の対象になるか知りたい方や、申請に不安がある方は「社会保険給付金サポート」の活用がおすすめです。専門スタッフが手続きの流れや対象制度の確認など、丁寧にサポートを行います。まずはお気軽にご相談ください。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
この記事の監修者

杉山 雅浩
東京弁護士会所属。
池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。
NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、
詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。
YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!
おすすめの関連記事
ピックアップ
- CATEGORY
- 給付金について
- 転職・再就職について
- 就労について
- 社会保険について
- 精神疾患について
- サービスについて
- 傷病手当金について
- 失業保険について
- 退職について
- 障害年金について
- ピックアップ
- 人気記事
-
退職代行サービスの利用方法、実際の流れと体験談を紹介
-
今の会社に3年後もいる自信はありますか?
-
退職代行を利用した時の有給消化の仕組みとその対応方法
-
退職代行サービスを使うメリット・デメリットは?
-
ブラック企業を判定する方法と実際のチェックポイント
-
障害年金を知ろう
-
会社を“円満に退職する”方法は?
-
退職時の引き継ぎは義務?スムーズな業務引き継ぎの必須ポイント
-
パワハラ、モラハラ、セクハラとは?
-
辞めさせてくれない!そんな時こそ「退職代行サービス」
テーマ
- 転職サイト
- 不支給
- 引っ越し
- 雇用契約
- 退職代行
- 職務経歴書
- 等級
- 社宅
- 内定
- 退職代行サービス
- 人間関係
- 離職票
- 障害者手帳
- 就労移行支援
- ブラック企業
- スタートアップ
- 労務不能
- 精神保険福祉手帳
- 業務委託
- ハラスメント
- 転職
- 傷病手当金
- 労災
- 社会保険
- 引き継ぎ
- 違法派遣
- 障害者控除
- 産休
- 福利厚生
- 給与
- 派遣契約
- 退職届
- 解雇
- 就職困難者
- 残業代
- 障害厚生年金
- 面接
- 中小企業
- 再就職手当
- 退職金
- 失業保険
- 障害手当金
- ベンチャー企業
- 社会保険給付金
- 会社都合退職
- 資格取得
- 新型コロナウイルス
- 退職勧奨
- 職業訓練受講給付金
- 自己都合退職
- うつ病
- 有給消化
- 自己PR
- 退職給付金
- クレジットカード
- 統合失調症
- 休職
- 確定申告
- ハローワーク
- アルバイト
- 契約社員
- 免除申請
- 保険料
- 傷病手当
- 雇用保険
- 弁護士
- 適応障害
- 社会保障
- 退職コンシェルジュ
- 健康保険
- 公的貸付制度
- 住宅確保給付
- 就職
- インフルエンザ
- 年金
- 生活福祉資金貸付制度
- 職業訓練
- 労働基準法
- ストレス
新着記事
-
2026.01.06
退職して国民健康保険に切り替えたあとも傷病手当金はもらえる?注意点も解説
-
2025.12.27
インフルエンザで仕事を休むと「傷病手当金」はもらえる?条件・日数・申請方法まで解説
-
2025.12.26
傷病手当金と副業の関係をわかりやすく解説
-
2025.12.17
傷病手当金の不正と調査|どこからがNG?就労・外出・求職活動の正しい判断基準を解説
-
2025.12.16
【徹底比較】退職給付金サポート おすすめランキング
-
2025.12.09
傷病手当金をもらいながら働く方法はある?アルバイトならOK?収入を得る方法や注意点を解説
-
2025.12.09
社会保険給付金と失業保険の違いは?受給要件やメリット・デメリット解説
-
2025.12.08
産休・育休後そのまま退職はマナー違反?退職時のポイントと注意点
-
2025.12.07
会社を辞めさせられた場合は失業保険は受け取れる?条件や注意点を解説
-
2025.12.04
傷病手当金は退職後もらえない?受給できる条件と不支給になる理由を徹底解説





 サービス詳細
サービス詳細