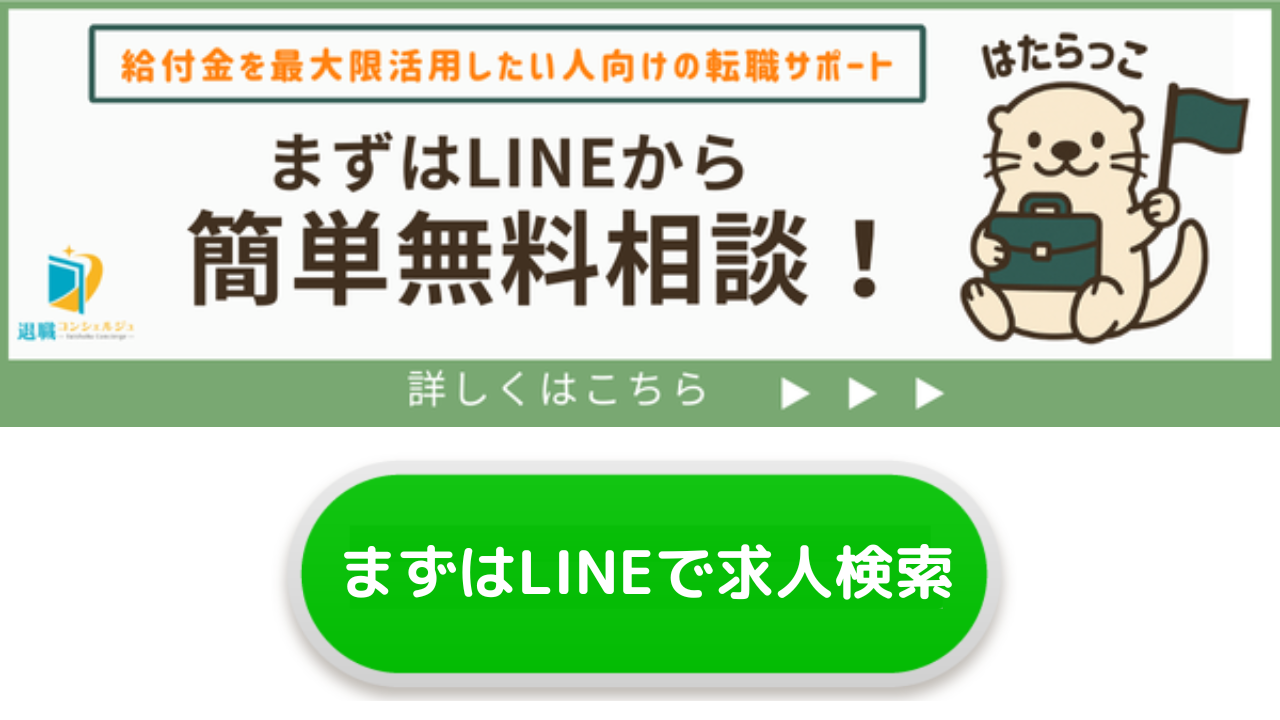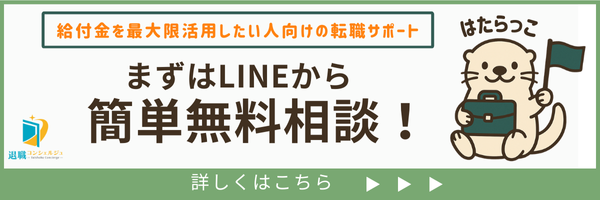2025.05.19
給付金について
失業保険は何年働いたらもらえる?半年・1年・2年のケースで解説

失業保険を受け取るには、原則として離職日以前に12ヶ月(1年)以上就労している必要がありますが、倒産をはじめとする会社都合で退職する場合は、1年未満でも受給可能です。しかし、自分に置き換えると、何年働いたら受け取れるのかわからない方もいるでしょう。
そこで今回は、失業保険を受け取るために何年働いたら良いのかを、半年、1年、2年の期間や退職理由ごとに分けて解説します。失業保険を一度受け取った後、再度受け取るための経過年数や、具体的な手続きの流れ、失業保険に関連する手当についても解説しますので、退職を検討中の方は参考にしてください。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
【期間別】失業保険は何年働いたらもらえる?

そもそも、失業保険とは、雇用保険に基づいて支給される基本手当のことで、失業手当や失業給付金と呼ばれる場合もあります。何年働いたら失業保険をもらえるかは、失業保険の受給要件で定められており、具体的には以下の2つの要件を満たさなければなりません。
- 本人に就業の意思と能力があり、求職活動を行っていること
- 直近の2年間で雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上あること
この要件に基づくと、退職前の2年間に就業して雇用保険に加入していた期間が12ヶ月、つまり1年以上である必要があります。このとき、1ヶ月の労働日数が11日以上、もしくは賃金支払いの元となった労働時間が80時間以上であることを満たさなければなりません。
しかし、特定の条件を満たす場合は、加入期間が1年未満であっても失業保険を受給できます。ここからは、半年働いた場合、1年働いた場合、2年働いた場合の3つのケースに分けて、失業保険を受給するために必要な条件を詳しく解説します。
半年働いた場合
離職理由が「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する場合は、離職日以前の1年間における被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば、失業保険を受給することが可能です。
特定受給資格者とは、倒産や解雇によって再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた人を指します。また、特定理由離職者とは、特定受給資格者以外の人で、期間の定めのある労働契約が更新されないなど、やむを得ない理由により離職した人のことです。
これらに該当する場合は、自分に退職の原因はないため、雇用保険の被保険者期間が離職日以前の1年間に6ヶ月以上あれば支給要件を満たせば、失業保険を受給できます。
1年働いた場合
自己都合で離職した場合は、離職日以前の2年間における被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要です。したがって、1ヶ月の労働日数が11日以上、賃金支払いのもととなった労働時間が80時間以上の要件を満たしたうえで1年間(12ヶ月)働いた場合は、自己都合退職でも失業保険の受給資格を満たします。
ただし、自己都合退職の場合は、1ヶ月の給付制限期間が設けられる点に注意が必要です。
2年働いた場合
被保険者期間が2年間ある場合は、自己都合退職や特定受給資格者、特定理由離職者のいずれの場合でも受給資格を満たすため、失業保険を受給できます。
【退職理由別】失業保険は何年働いたらもらえる?
何年働いたら失業保険をもらえるかは、前述のとおり退職理由によっても変わります。ここでは、自己都合退職と特定理由離職者、特定受給資格者の3つのケースに分けて解説します。
自己都合退職のケース
自己都合退職とは、自身の都合や希望によって退職する場合を指します。例えば、キャリアアップを目指して転職活動を行うために退職するケースや家庭の事情によるケースなどが該当します。
前述のとおり、自己都合で退職する場合に失業保険を受給するには、離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要です。また、給付開始までに、7日間の待期期間に加えて1ヶ月の給付制限期間が設けられます。
特定理由離職者のケース
特定理由離職者とは、やむを得ない事情で退職せざるを得なかった人を指します。
具体的には、以下の例があげられます。
- 労働契約の更新がなかった場合
- 健康上の理由で離職した場合
- 家庭の事情で離職した場合
- 通勤困難な状況になった場合
これらに該当する場合は、離職日以前の1年間において被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば、失業保険を受給可能です。さらに、 給付制限期間もありません。労働契約の更新がなかった場合は、所定給付日数の延長も可能です。
特定受給資格者のケース
特定受給資格者とは、会社側の都合で退職した人を指します。
具体的には、以下の例があげられます。
- 倒産や事業所の廃止
- 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)
特定受給資格者に該当する場合は、特定理由離職者と同じく、1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば、失業保険を受給できます。
失業保険を一度受給したら次は何年後?
前回離職した際に失業保険を受給していた場合、再度の受給は何年後に可能なのでしょうか。新たに必要な経過年数について、会社都合退職と自己都合退職の2つの場合に分けて解説し、失業保険の受給条件や受給期間をあわせてご紹介します。
会社都合退職の場合
基本的には、前回どのような退職理由で失業手当を受け取ったかは、次に受給する際の雇用保険加入期間の算出に影響することはありません。失業保険を受けると、雇用保険の加入期間がリセットされるためです。
そのため、前回の受給後に再就職して会社都合退職で失業保険を受けるには、新たに半年間の加入が必要です。例えば、一度失業保険を利用した後に次の会社を会社都合で退職した場合でも、雇用保険に半年間加入していれば再度失業保険を受けられます。
自己都合退職の場合
自己都合退職も同様で、前回どのような退職理由で失業手当を受け取ったかは、次に受給する際の雇用保険加入期間の算出に影響することはありません。
ただし、新たに失業保険を受ける際の退職理由が自己都合の場合に、失業保険を受けるには雇用保険に1年以上加入している必要があります。
会社都合退職に比べて自己都合退職では、雇用保険への加入期間が長くなる点に注意が必要です。
失業保険の受給条件
失業手当を受け取るためには、次の条件を満たす必要があります。
- 雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
- 離職前2年間に12ヶ月以上の雇用保険の被保険者期間があること(特定受給資格者の場合は1年間に6ヶ月以上)
- 就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること
つまり、雇用保険への一定以上の加入期間と再就職に向けた求職活動を行うことが重要です。
なお、給付額は失業前の給与額と年齢によって変動します。また、自己都合退職の場合は給付制限期間が設けられる場合があるなど、給付開始までの期間は退職理由によって異なる点に注意が必要です。
失業保険の受給期間
失業保険の受給期間は、原則として、離職日の翌日から1年間(所定給付日数が330日の場合は1年と30日、360日の場合は1年と60日)です。
病気やけが、妊娠、出産、育児等が理由で30日以上働けない場合は、その働けない期間の分だけ受給期間を延長できます。ただし、延長できる期間は最長で3年間です。
失業保険の受給金額
失業手当の受給額は「給付日数 × 基本手当日額」の計算式で算出されます。一般的な相場では、受給額は離職前の賃金の5〜8割程度です。ここからは、賃金日額、基本手当日額、基本手当総額の計算方法をご紹介します。
賃金日額を計算する
賃金日額とは、離職前の直近6ヶ月間に支払われた賃金の総額を、180で割った金額のことで、失業保険の受給金額を計算するベースになります。賃金日額における賃金には、基本給や残業代、住宅手当や通勤手当といった各種手当が含まれます。ただし、臨時的に支払われる賞与や退職金、祝い金などは、含まれません
基本手当日額を計算する
続いて、基本手当日額を計算します。基本手当日額は、賃金日額に50%〜80%の給付率を掛け合わせて算出します。
なお、給付率は、具体的な給付率は厚生労働省の基準に基づいて決定され、賃金日額が低いほど高く設定されています。
基本手当総額を計算する
最後に基本手当総額を計算します。基本手当日額に所定給付日数を掛け合わせることで、総受給額が算出されます。
所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢などによって異なります。例えば、自己都合退職の場合、被保険者期間が1年以上5年未満であれば所定給付日数は90日です。
具体的な例として、離職前6ヶ月間の賃金総額が180万円で給付率が60%、所定給付日数が90日の場合を検討してみましょう。
まず、賃金日額は180万円÷180日=1万円、基本手当日額は1万円×60%=6,000円となります。さらに、所定給付日数が90日の場合の総受給額は6,000円×90日=54万円です。
なお、基本手当日額には上限額と下限額が設定されています。自身の所定給付日数がわからない場合は管轄のハローワークに問い合わせましょう。
失業保険の申請方法
失業保険を受給するには、ハローワークで申請手続きを行う必要があります。具体的な流れは以下のとおりです。
- 必要書類を整える
- ハローワークで求職を申し込む
- 待期期間を過ごす
- 雇用保険説明会に参加する
- 失業認定日にハローワークを訪れる
ここからは、各流れを具体的に解説します。
必要書類を揃える
失業保険の受給には、前提として求職の申し込みが必要です。事前に以下の必要書類を準備しましょう。
- 雇用保険被保険者離職票-1・2
- 雇用保険被保険者証
- 証明写真(たて3cm×よこ2.4cm、正面上半身)×2
- 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
- 住所・氏名・年齢が確認できる本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1つ)
また、令和2年12月25日より、雇用保険関係の手続きを行う際の押印は原則として不要となりましたが、一部の書類では、必要となるため印鑑(認印は可、スタンプ印は不可)を持参することをおすすめします。
ハローワークで求職を申し込む
ハローワークで必要書類を提示して求職の申し込みを行います。具体的な流れは次のとおりです。
- 求職申込書に記入する
- 必要書類の提出、職業相談を行う
- 雇用保険説明会の日時が決定する
失業保険を受給するには、求職の意思と能力があり、求職活動を行わなければなりません。ハローワーク窓口で、求職活動を目指している旨を伝えて、離職票の提出と求職の申し込みを行いましょう。
申し込み手続きが完了して受給資格が決定すると、窓口より「失業等給付受給資格者のしおり」が渡されます。
また、受給には、「雇用保険説明会」への参加が原則として必要です。開催は申請日から7日後以降になるため、忘れずに開催日時をメモしておきましょう。
待機期間を過ごす
ハローワークで求職の申し込みをして失業保険の受給資格を得ると、7日間の待機期間が設けられます。求職申し込みをした日から失業期間が7日に満たない場合は、失業保険は給付されない点に注意しましょう。
7日の待期期間は、どの求職申請者にも共通して設定され、この期間中にハローワークは求職申請者の失業状況を調査します。この期間中は、たとえ短時間でも勤務やアルバイトをすると就労とみなされるため、一切の就労をしないようにしましょう。
また、失業保険の受給中に再就職すると、再就職手当が給付されます。しかし、7日間の待期期間中に入社日を迎える場合は再就職手当を受け取れないため、再就職手当の受給を目指している場合は日程の重複に注意してください。
雇用保険説明会に参加する
失業保険を受給するにあたっては、求職の申し込み時に案内された雇用保険受給説明会に原則として参加しなければなりません。雇用保険受給説明会は、失業保険の仕組み、受給の仕方、求職活動の進め方などが詳しく説明される重要な機会なので、しっかり聞いて理解を深めてください。
なお、雇用保険説明会に参加する場合は、求職の申し込み時に渡された「雇用保険受給資格者のしおり」と印鑑(認印は可、スタンプ印は不可)、筆記用具を忘れずに持参してください。
雇用保険説明会が終了した後は、会場で「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が配られます。また、初回の失業認定日が案内されるため、必ずメモを取っておきましょう。
失業認定日にハローワークを訪れる
失業保険を継続して受給するには、指定された失業認定日にハローワークを訪れて所定の手続きを行います。
「失業認定日」とは、ハローワークが前回から当日までの間の失業の事実を認定する日です。窓口に失業認定申告書を提出して、就職活動の実績を報告しなければなりません。
通常は、4週間ごとに1日、平日のうちの指定された日が失業認定日に設定されます。ただし、初回の失業認定日に限っては、求職申し込みを行うために離職票を提出した日から約3週間後に設定されるので、必ず確認しておきましょう。
失業保険をもらう際のアルバイトについて
失業保険の受給額だけでは生活費を賄えない場合、アルバイトをする人もいるでしょう。しかし、受給中にアルバイトをする場合はいくつか注意しておくことがあります。ここでは、特に注意したい3つのケースを解説します。
待機期間中のアルバイト
失業保険をもらうに際してアルバイトを行う場合、特に気をつけたいのが待期期間です。失業保険の受給手続き後、最初の7日間は「待機期間」となります。
この期間中にアルバイトを行うと就業しているとみなされるため、待機期間がその分延長されてしまうため注意が必要です。例えば、待機期間中に2日間アルバイトをした場合は、通常の7日間にその2日分が加算され、待期期間は合計で9日間となります。
給付制限期間中のアルバイト
自己都合退職の場合は、待機期間終了後に1ヶ月間の給付制限期間が設けられます。この期間中は、待期期間中とは異なりアルバイトが可能です。
ただし、週の所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以上の雇用見込みがある場合は、雇用保険の加入対象となるため、「就職」とみなされる可能性があります。就労とみなされた場合は、失業保険の受給資格が失われることも考えられるため、給付制限期間中にアルバイトをする際の労働時間や雇用日数には気をつけましょう。
失業保険受給中のアルバイト
失業保険の受給開始後は、一定条件下でアルバイトを行うことが可能です。ただし、1日4時間以上の労働を行った日は、その日数分の失業手当の支給が先送りされてしまいます。
一方で、1日あたり4時間未満の労働であれば、収入額によっては手当が減額されるケースがあり、特に、受け取り給与額には注意が必要です。具体的には、1日の収入と失業手当の合計が「退職直前の6ヶ月に受け取った給与総額÷180」の80%を超える場合は、手当が減額または支給停止となることがあります。
また、給付制限期間中のアルバイトと同様に、週20時間以上の労働や31日以上の雇用見込みがあるケースでは、雇用保険の加入対象となります。このケースでは、就労しており失業状態ではないとみなされる可能性があるため注意が必要です。
再就職が決まるともらえる「再就職手当」について

失業保険の受給に際して7日間の待期期間経過後に、一定の受給日数が残っている場合、再就職手当を受給できる可能性があります。ここでは、再就職手当の概要と受給条件、受給金額の目安、申請方法を解説します。
再就職手当とは
再就職手当は、雇用保険の「就職促進給付就業促進手当」の1つにあたり、失業認定を受けた人が再就職した際に支給される手当のことです。早期の再就職を促すための手当であり、再就職までの期間が短いほど手当金の額が大きくなるように設計されています。
再就職手当は、再就職先が正社員ではなく派遣社員でも支給されます。ただし、給付を受けるには条件があり、誰にでも支給されるわけではない点に注意が必要です。
再就職手当の受給条件
再就職手当を受給するための条件は、以下のとおりです。
- 待期期間7日間の終了後に就職または事業を開始していること
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- 前の事業主と資本・取引面で密接な関係がない事業主に就職していること
- 1年以上勤務する見込みがあること
- 雇用保険の被保険者になっていること
- 過去3年以内に再就職手当を受けていないこと
- 受給資格決定前に採用が決定していないこと
- 離職理由による給付制限期間満了後、ハローワークや職業紹介事業者の紹介で就職していること(※待期期間満了後1か月の期間内に再就職した場合のみ)
前述した派遣社員として再就職するケースでも、上記の条件を満たせば再就職手当を受給できます。
また、より確実な再就職手当の受給を目指す場合は、転職エージェントの活用もおすすめです。
退職コンシェルジュの運営するエージェントでは、給付金のプロ相手に再就職手当などの相談も可能です。まずはLINEで気軽にご相談ください!
再就職手当の受給金額
再就職手当の具体的な受給金額は、人によって変わります。基本手当の支給残日数によって給付率が異なるためです。
具体的な給付率の違いは、以下のとおりです。
- 支給日数を所定給付日数の3分の2以上残して早期に再就職した場合:基本手当の支給残日数の70%の額
- 3分の1以上残して早期に再就職した場合:基本手当の支給残日数の60%の額
再就職手当の申請方法
再就職手当を受けるには、再就職が決定した後速やかにハローワークに申請して失業保険の支給停止手続きを行い、さらに再就職手当の申請を行います。
具体的な申請の流れは、以下のとおりです。
- 採用証明書を受け取りハローワークに提出する
- ハローワークの窓口で再就職手当支給申請書を出してもらう
- 申請書を新しい就職先に提出して記入してもらい受け取る
- 再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格証をハローワークの窓口に提出する
失業保険に関するよくある質問と回答
ここからは、失業保険の受給や受給期間中の就労に関するよくある質問と回答をご紹介します。
離職理由の判断は誰がするの?
離職理由の判断は、主にハローワークの所長や地方運輸局長が行います。
会社から発行される離職票には、会社側が記載した離職理由が示されます。しかし、労働者がその内容に納得できない場合は、ハローワークに異議を申し立てることが可能です。
この際、ハローワークは客観的な資料や証拠に基づいて、離職理由の確認と判断を行います。そのため、離職前に会社と労働者双方で離職理由を確認したうえで、認識の違いを解消しておくことが重要です。
病気や妊娠などですぐに働けない場合は?
病気や妊娠などですぐに働けない場合、失業保険を受け取ることはできませんが、受給期間を延長できます。
失業保険を受給するには、就職の意思と能力があり、積極的に求職活動を行わなければなりません。そのため、病気やけが、妊娠、出産、育児などの理由で直ちに働けない場合は、基本手当を受給することができないためです。
しかし、上記の理由で30日以上働けない場合は、受給期間の延長申請が可能です。最大で3年間にわたって、受給期間を延長することができます。
失業保険をもらいながら働くことはできる?
失業保険を受給中にアルバイトやパートなどで働くことは可能ですが、一定の条件を満たす必要があります。
まず、1日の労働時間が4時間以上のケースでは、その日は「就労日」とみなされるため、基本手当は支給されません。一方、1日の労働時間が4時間未満のケースでは、その日は「内職・手伝い」として扱われ、基本手当は支給されるものの収入に応じて減額されます。
まとめ
失業保険を受給するには、原則として離職日以前に12カ月以上就労していることが条件となります。しかし、倒産や解雇などの特定受給資格者に該当する場合や、契約更新がされずに特定理由離職者となった場合には、離職日以前の1年間において被保険者期間が通算で6ヶ月以上あれば失業保険を受給可能です。
また、一度失業保険を受給した後に再び失業保険を受給する場合、前回の退職理由が次の加入期間の算出に影響することはありません。そのため、新たに失業保険を受給可能かどうかは再就職先での加入期間と退職理由によって判断します。自身のケースが受給条件を満たすには何年働いたら良いのかは、ハローワークに確認することをおすすめします。
失業保険の受給を申請するには、本記事でご紹介したように手続きが複雑なケースもあります。申請方法がわからない方は、ぜひ退職コンシェルジュが提供する「社会保険給付金サポート」をご利用ください。専任スタッフが申請手続きをサポートいたします。不安な点をご相談いただける個別相談会も実施しておりますので、合わせてご活用ください。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
この記事の監修者

杉山雅浩
スピネル法律事務所 弁護士
東京弁護士会所属。
池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。
NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、
詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。
YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、テ日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!
おすすめの関連記事
ピックアップ
- CATEGORY
- 給付金について
- 転職・再就職について
- 就労について
- 社会保険について
- 精神疾患について
- サービスについて
- 失業保険について
- 再就職手当
- 雇用保険について
- 退職について
- 障害年金について
- ピックアップ
- 人気記事
-
退職代行サービスの利用方法、実際の流れと体験談を紹介
-
今の会社に3年後もいる自信はありますか?
-
退職代行を利用した時の有給消化の仕組みとその対応方法
-
退職代行サービスを使うメリット・デメリットは?
-
障害年金を知ろう
-
ブラック企業を判定する方法と実際のチェックポイント
-
会社を“円満に退職する”方法は?
-
退職時の引き継ぎは義務?スムーズな業務引き継ぎの必須ポイント
-
辞めさせてくれない!そんな時こそ「退職代行サービス」
-
パワハラ、モラハラ、セクハラとは?
テーマ
- クレジットカード
- 資格取得
- 退職届
- 引っ越し
- 労働基準法
- 退職コンシェルジュ
- 退職代行
- アルバイト
- 精神疾患
- 面接
- 社宅
- 雇用契約
- ストレス
- 退職代行サービス
- 雇用保険
- うつ病
- 障害手当金
- 障害者手帳
- 内定
- ブラック企業
- 健康保険
- 統合失調症
- 自己都合
- 精神保険福祉手帳
- 就労移行支援
- ハラスメント
- 年金
- 契約社員
- 会社都合
- 労災
- 業務委託
- パワハラ
- 転職活動
- 弁護士
- 失業給付
- 産休
- 社会保険
- モラハラ
- 転職サイト
- 公的貸付制度
- 新型コロナウイルス
- 解雇
- 福利厚生
- セクハラ
- 職務経歴書
- 生活福祉資金貸付制度
- 有給消化
- 中小企業
- 失業手当
- 障害年金
- 人間関係
- 不支給
- 休職
- ベンチャー企業
- 就職困難者
- 引き継ぎ
- スタートアップ
- 等級
- 免除申請
- 会社倒産
- 再就職手当
- 給与
- 転職
- 離職票
- 適応障害
- 退職勧奨
- 社会保険給付金
- 残業代
- 違法派遣
- 労務不能
- 住宅確保給付
- 自己PR
- 職業訓練受講給付金
- 退職金
- 派遣契約
- 傷病手当金
- 給付金
- 確定申告
- 退職給付金
- 会社都合退職
- 障害厚生年金
- 年末調整
- 職業訓練
- 保険料
- ハローワーク
- 自己都合退職
- 失業保険
- 障害者控除
- 再就職
- 社会保障
- 就業手当
- 退職
- ブランク期間
- 退職願
- 職業訓練受講手当
- 就職
- 傷病手当
新着記事
-
2025.10.15
仕事を辞めるタイミングとは?適切な伝え方や注意点を解説
-
2025.10.09
失業手当の手続きで提出する必要書類は?離職票再発行や延長申請の流れも解説
-
2025.10.08
個人事業主が再就職手当をもらえるケースと手続き方法、注意点を解説
-
2025.10.08
アルバイトを4時間ピッタリすると失業手当はどうなる?支給条件や注意点も解説
-
2025.10.08
いつが得?損しない退職日の決め方とパターン別おすすめの退職日
-
2025.10.08
失業認定日までに就職が決まったらどうする?必要な手続きの手順を解説
-
2025.10.08
確実に退職できる理由はある?退職理由で嘘をつくメリット・デメリット
-
2025.10.08
引き止められない退職理由の具体例|円満退社するコツと引き止められたときの対策
-
2025.10.07
年金と失業保険を同時にもらう方法はある?年齢別の受給方法を解説
-
2025.10.07
ハローワークの認定日の時間に遅刻したら失業保険は受けられない?欠席した場合も解説





 サービス詳細
サービス詳細