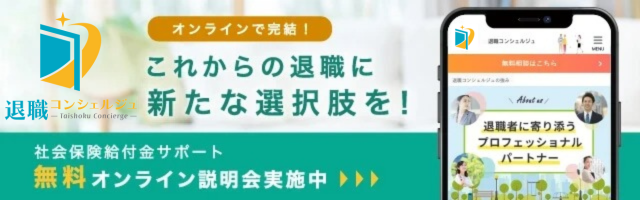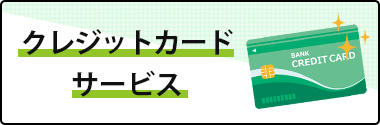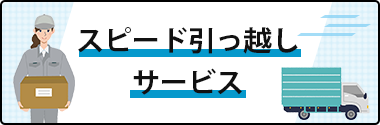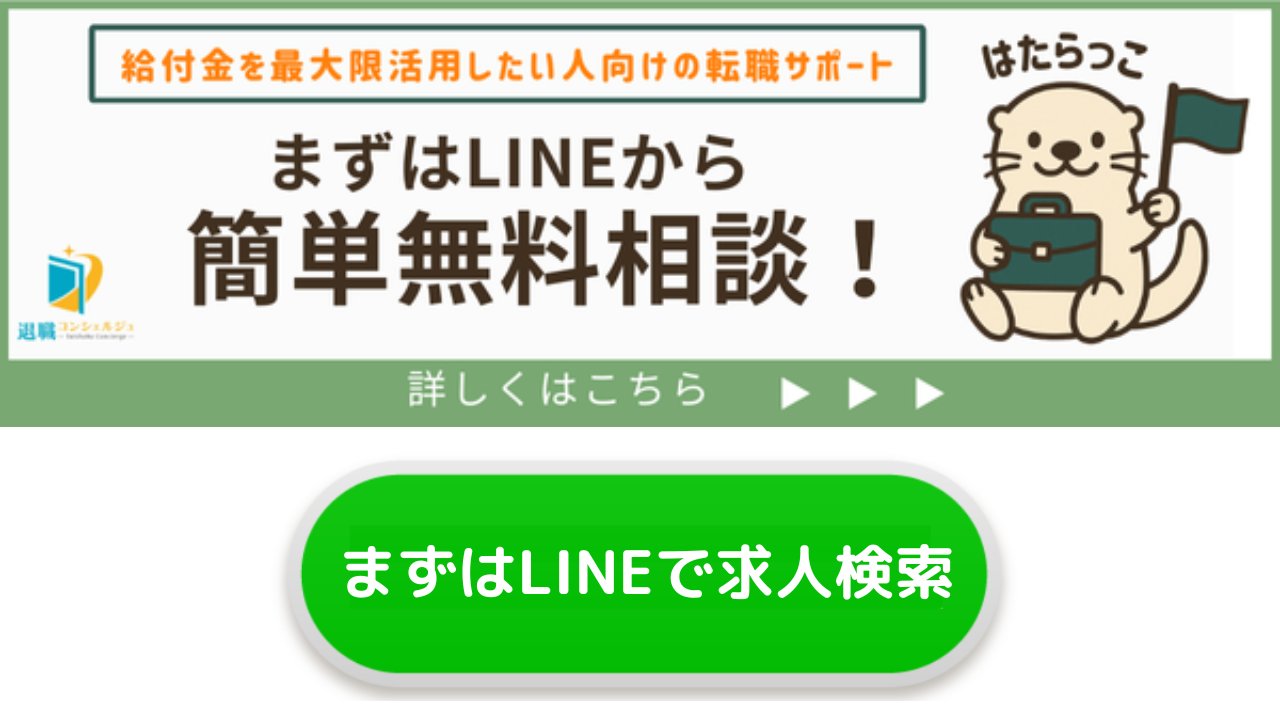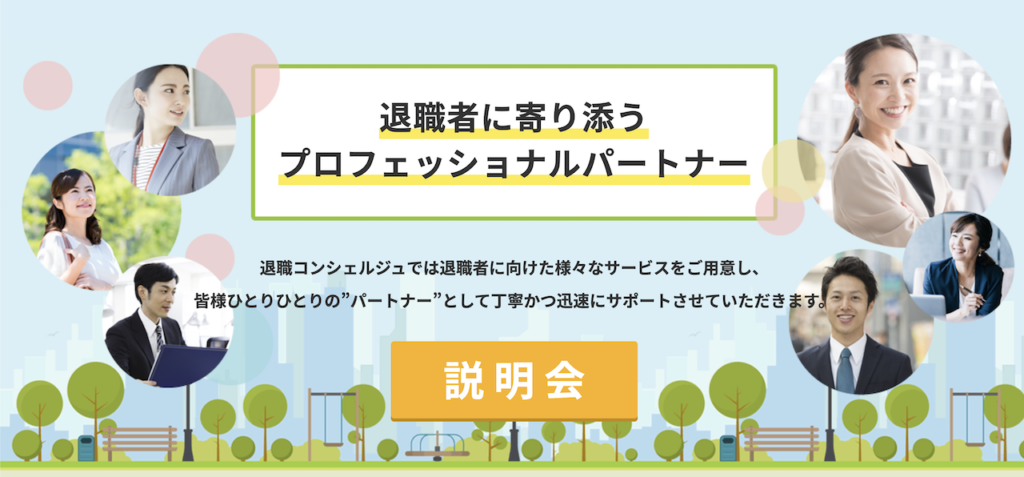退職手続きの流れ
まずは退職までのスケジュールについて流れに沿って解説していきます。
業務の引継ぎなどに追われ退職の手続きが大変になってしまわないよう、あらかじめ流れを把握しておくと計画的に手続きを進めることができるでしょう。
退職の意思表示(退職の1~3カ月前)
まず最初に自分の直属の上司へ退職の意思を伝えましょう。
民法上では正社員をはじめとした雇用契約に期間の定めがない雇用形態の場合は2週間前までに退職の意思を伝えれば問題ありませんが、就業規則に定めがある場合はそれに従った期限で伝える方が無難です。
急な退職は引継ぎや後任の採用、手配などが間に合わない場合があり、その影響で円満退社が難しくなってしまう可能性があります。
会社側への負担も考え、可能な限り早めに退職の意思を伝えることが大切です。
退職願を提出(退職の1カ月前)
退職願については提出しなくても民法上は問題ありませんが、会社によっては提出が求められる場合があります。不安な場合は上司へ退職願の提出有無について確認するのがよいでしょう。
会社都合での退職の場合は提出をしないケースがほとんどですが、会社によっては提出が定められている場合もあります。その場合は退職理由を「一身上の都合により」とはせずに「退職勧奨のため」や「事業部門の縮小のため」など具体的に記載しましょう。
「一身上の都合により」としてしまうと自己都合退職とみなされ失業保険の給付が遅くなる恐れがあるため注意が必要です。
業務の引き継ぎ(退職の1~3カ月前)
業務の引継ぎについても退職日予定日から考えて余裕のあるスケジュールとなるよう計画的に進めていきましょう。
引継ぎ完了の予定日は余裕をもって退職日の3日前としておくことを推奨します。
業務を中途半端な状態で引き継がないようにすることが基本ですが、どうしても難しい場合はここまでの内容とこれから行うべきことについて社内へきちんと共有しておきましょう。後任者がすでにいる場合は引継ぎと並行して業務を教えることになると思いますが、その際は引継ぎ内容を資料にまとめておくとより会社側の管理も楽になります。
取引先へのあいさつ(退職の2~3週間前)
社外の取引先へ退職する旨を伝えるためのあいさつは一般的に退職の2~3週間前に行うとされています。ただし中には退職日まで退職の旨は内密にしておくことが決まりとなっている会社もあるため、念のため上司へあいさつの有無について確認しておきましょう。
直接会ってあいさつすることが理想ですが、難しい場合はメールで伝えても問題ありません。その際は一斉送信は避け、個別に送ると印象が良いでしょう。
退職を取引先のお客様に伝えるタイミングはいつ?失礼のない伝え方について!
有休の消化やデスクの整理整頓
まだ有給が残っていれば退職日までにすべて消化することができます。その場合引継ぎや取引先へのあいさつは有給消化日数も考慮したスケジュールで進めましょう。
また、最終出勤日にはデスク周りの清掃や整理整頓も忘れずに行ってください。
退職(最終出社)当日
最終出勤日までに引継ぎ等が問題なく完了していればその日は事務手続きや社内へのあいさつ等がほとんどになります。支給品や貸与物の返却、事務手続き等を進めながらあいさつも済ませていきましょう。
退職時に会社に提出・返却するもの
退職に伴い退職届の提出や貸与物の返却など事務的な手続きが多く必要となります。どういったことが必要なのか前もって把握しておくことが大切です。
退職届
退職届は、退職の意思が確定したことの証明として提出する書類です。会社指定のフォーマットがあればそちらを使用しますが、特にない場合は自分で用意をする必要があります。
退職願と同様に会社都合退職の場合は提出不要ですが、もし提出を求められたら自己都合退職と誤って認識されないよう退職理由を具体的なもので記載しましょう。
会社から支給されたもの
会社から支給、貸し出されているものはすべて返却が必要です。
保険証をはじめ、制服、携帯電話やパソコンが挙げられますが、会社で用意、購入したものはたとえ名刺1枚であっても返却が必要です。
なお、保険証は最終出勤日ではなく、退職日の当日まで利用ができます。最終出勤日を超えて使用する場合は退職日の翌日以降に、扶養家族がいる場合はその家族の分も含めすべて郵送で返却しましょう。
業務資料やマニュアル
社外秘や機密情報が載った書類やデバイス等も確実に返却します。昨今は情報漏洩を厳しく取り締まっている会社も非常に多いため、トラブルを避けるためにも速やかに返却しましょう。
退職時に会社から受け取るもの
退職時は返却だけでなく、受け取るべきものもあります。
漏れがないように確認しすべて受け取れるようにしましょう。
雇用保険被保険者証
従業員が雇用保険へ加入していることを証明する書類です。
雇用保険への加入手続きは会社が行い、そのまま被保険者証も会社が保管することが一般的なため、受け取っておくようにしましょう。
年金手帳
厚生年金への加入を証明する書類で年金番号が記載されています。年金手帳自体は2022年に廃止となったため、それ以降に入社した場合は会社への提出は不要な書類ですが、会社へすでに提出済みかつ会社が保管している場合はこちらも忘れず受け取りましょう。
源泉徴収票
年末調整や確定申告の際に必要となる書類です。
年内途中で退職し転職する場合は年末調整後の最終的な給与額が確定していません。そのため源泉徴収票を転職先へ提出し、転職先で年末調整を行います。
年をまたいでの転職となる場合は自分で確定申告を行いますが、その際にも源泉徴収票が必要となります。受け取り後は忘れずに保管しておきましょう。
離職票
失業手当(いわゆる失業保険)の申請の際に必要となります。
発効までに時間がかかるため、失業手当の受給予定がある方は退職前に早めに会社へ申し出ておくことがよいでしょう。
すでに転職先が決まっている場合や失業手当を受け取れない場合は必ずしも必要ではありません。
退職証明書
その名の通りその会社を退職したことを証明する書類です。
離職票とは違い公的な書類ではなく社内で発行される書類のためすぐに受け取ることが可能です。
こちらも必ずしも必要な書類ではありませんが、離職票が届くまでの期間は退職証明書を代用して失業手当の仮申請を行うことができます。離職票の到着まで待つことが難しい場合は会社へ発行を依頼するようにしておきましょう。
生活面で退職前にしておくべき3つのこと
仕事を辞めて、すぐに新しい仕事を始めないという場合には無職の期間が続くことになります。
そうすると、就職している時には当たり前だと思っていたことが通用しなくなることで生活に不便が出てしまうようなこともあります。
そこで、実際に退職する前に生活面においてやっておくべき3つのことを紹介します。
クレジットカードを作成しておく
クレジットカードを作成するには、クレジットカード会社の審査に通らなければなりません。
クレジットカード会社の審査では、安定した収入や信用が必要になります。
もちろんカード会社によって審査基準は異なりますが、年収や勤続年数が長いほど信頼があると判断されて審査に有利になります。
無職であれば審査に落ちてしまう可能性が高いですし、すぐに就職したとしても勤務年数が1年以下では収入が安定しているとは判断されない可能性もあります。
そのため、クレジットカードを1枚も持っていない場合や、新しいクレジットカードの作成を迷っているような場合には、退職前に新しいカードを作成しておきましょう。
引っ越しの予定があるならば引っ越ししておく
もし引っ越しをする予定があるのなら、退職する前に引っ越しすることをおすすめします。
会社の社宅や寮に住んでいるのであれば、退職によって必ず引っ越しが必要になります。
不動産でもクレジットカードと同様に審査があり、収入や信頼が必要になります。
家を購入するにしても賃貸にしても、審査が通らなければ住む場所が確保できません。
もちろん、無職では絶対に引っ越しできないというわけではありません。預貯金の残高審査や親に代理契約してもらうなどの手段などを使えば引っ越しできるケースもあります。
しかし、必ず審査に通るというわけではないので、やはり就職している間に引っ越ししておくべきと言えるでしょう。
多少の貯金を準備しておく
退職後1ヵ月は給料が入りますが、その後は給料が入ってこなくなってしまいます。
しかし、転職活動や今後の生活にはお金が必要です。
その日暮らしの生活ではお金が尽きてしまう可能性もあるので、退職前には多少の貯金をしておくべきでしょう。
転職活動にも面接に行くための交通費や履歴書の作成に掛かる費用、スーツがなければスーツも必要になります。
また、すぐに就職しないのであれば健康保険や年金、住民税などは自身で支払う必要があります。
健康保険や年金はこれまで会社が半額負担してくれていたので、退職すれば全額自己負担になるので支払いが高額に感じられるでしょう。
支払いが滞ってしまわないように、貯金で賄えるように準備しておくべきと言えます。
退職してから休む場合に知っておきたいこと
退職後に生活で困ってしまわないように、ある程度の準備は退職前にしておくべきです。
退職してから少しの間は休むという場合であれば、なおさらしっかりと準備しておきたいものです。
そこで、退職してから少しの間休むためにも知っておきたいことは次のものが挙げられます。
失業手当について
会社を退職すれば、失業手当(失業保険、失業給付金)を受け取ることができます。
この失業手当は、雇用保険に加入していることが条件にあります。
会社に勤めていれば雇用保険には加入していることから、失業手当を受け取る資格があるのです。
ただし、雇用保険に加入している期間が退職前の2年の間に12カ月以上であることが条件になります。
ただし、退職理由が会社都合の場合には、退職前の1年間に6カ月以上加入していれば受給資格を得られます。
しかも、自己都合退職は失業手当の給付まで3カ月ほど必要になりますが、会社都合であれば7日後から支給されます。
そのため、退職理由には注意したいものです。
退職後の健康保険について
退職した後にも健康保険に加入しなければ医療費が高額になってしまいます。
すぐに就職しないのであれば、特に健康保険についてはどうすべきか予め考えておくべきでしょう。
方法としては3つ挙げられます。
国民健康保険への加入、もしくは配偶者や親族の健康保険の被扶養者になることが一般的には多いかもしれません。
また、退職時に加入している健康保険の任意継続被保険者になるという方法もあります。
退職してから転職する場合に知っておきたいこと
退職してからすぐに転職したいという人も多いでしょう。
しかし、仕事を続けながら転職活動をすることは難しいですし、仕事を辞めてから転職活動を行うにしてもなかなか転職活動が上手くいかないことも多いものです。
そこで、退職してから転職する場合に知っておきたいことを紹介します。
転職サポートを利用してみる
転職するのであれば給与や福利厚生なども大切ですが、「自分のやりたい仕事内容ができるのか」「スキルアップに繋がるのか」といったことも気になるものです。
次に就職する会社には長く勤めたいと考えるのが当然ですし、本当に自分に合った会社に勤めたいと誰でも考えているでしょう。
そこで、転職活動をスムーズかつ納得できる会社選びをするためにも転職サポートを利用するということを検討してみてはいかがでしょうか。
自分に合った求人を紹介してもらえたり、書類審査が通りやすいようにアドバイスをもらえたりするなど、手厚いサポートを受けられます。
退職コンシェルジュの運営する転職エージェントでは、給付金のプロ相手に再就職手当などの相談も可能です。まずはLINEで気軽にご相談ください!
転職&給付金の相談はこちら▼
まとめ
働いている間は仕事で忙しいからと全てを退職後にしようと考えていると、生活面で不便になってしまう可能性があります。
退職前にはクレジットカードや引っ越しについて準備しておき、退職後のビジョンについても考えておきましょう。
退職コンシェルジュでは、クレジットカードサービスや引っ越しサービス、転職サポートなど退職の際に必要となるサービスを提供しています。
退職前後にお困りのことがあれば、是非お気軽にご相談ください。
▼社会保険給付金無料セミナー実施中!(自由参加)
アクセス先ページの下部からご希望の日程をお選びいただき、ご参加いただけます。(画像をクリック!)
※WEBセミナーのためご自宅で視聴が可能です。
※完全自由参加型のため会話等はできません。ご了承ください。(お客様の映像や音声は映りませんのでご安心ください。)
[各種サービス]
退職コンシェルジュとは

『退職者に寄り添うプロフェッショナルパートナー』
退職コンシェルジュでは退職者に向けた様々なサービスをご用意し、皆様ひとりひとりの”パートナー”として丁寧かつ迅速にサポートをさせていただきます。 退職する際の社会保険給付金、退職代行、引越し等なんでもご相談ください。ご相談は無料で行っております。

退職者に寄り添う
プロフェッショナルパートナー
退職コンシェルジュでは退職者に向けた様々なサービスをご用意し、皆様ひとりひとりの”パートナー”として丁寧かつ迅速にサポートをさせていただきます。 退職する際の社会保険給付金、退職代行、引越し等なんでもご相談ください。ご相談は無料で行っております。

 給付金がいくらもらえるか
知りたい方
給付金がいくらもらえるか
知りたい方 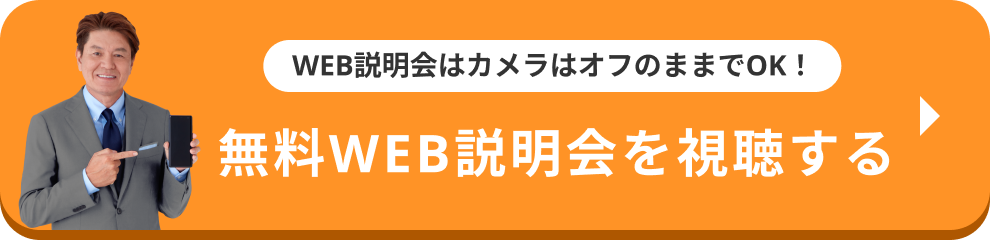
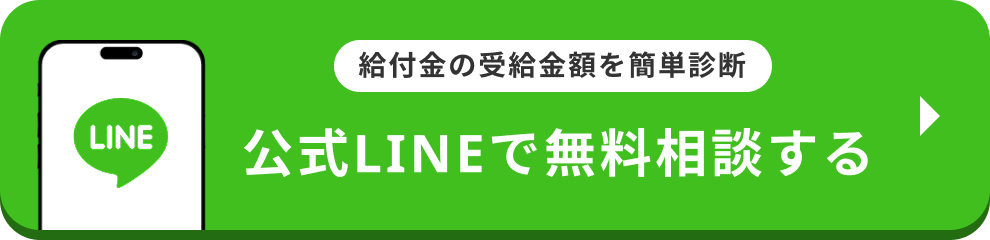
 給付金サポートを
ご検討中の方
給付金サポートを
ご検討中の方  評判・口コミ
評判・口コミ  給付金がもらえる
転職支援を活用する方
給付金がもらえる
転職支援を活用する方  その他退職について
ご不安がある方
その他退職について
ご不安がある方  もらえる給付金ラボ
もらえる給付金ラボ  退職コンシェルジュについて
退職コンシェルジュについて