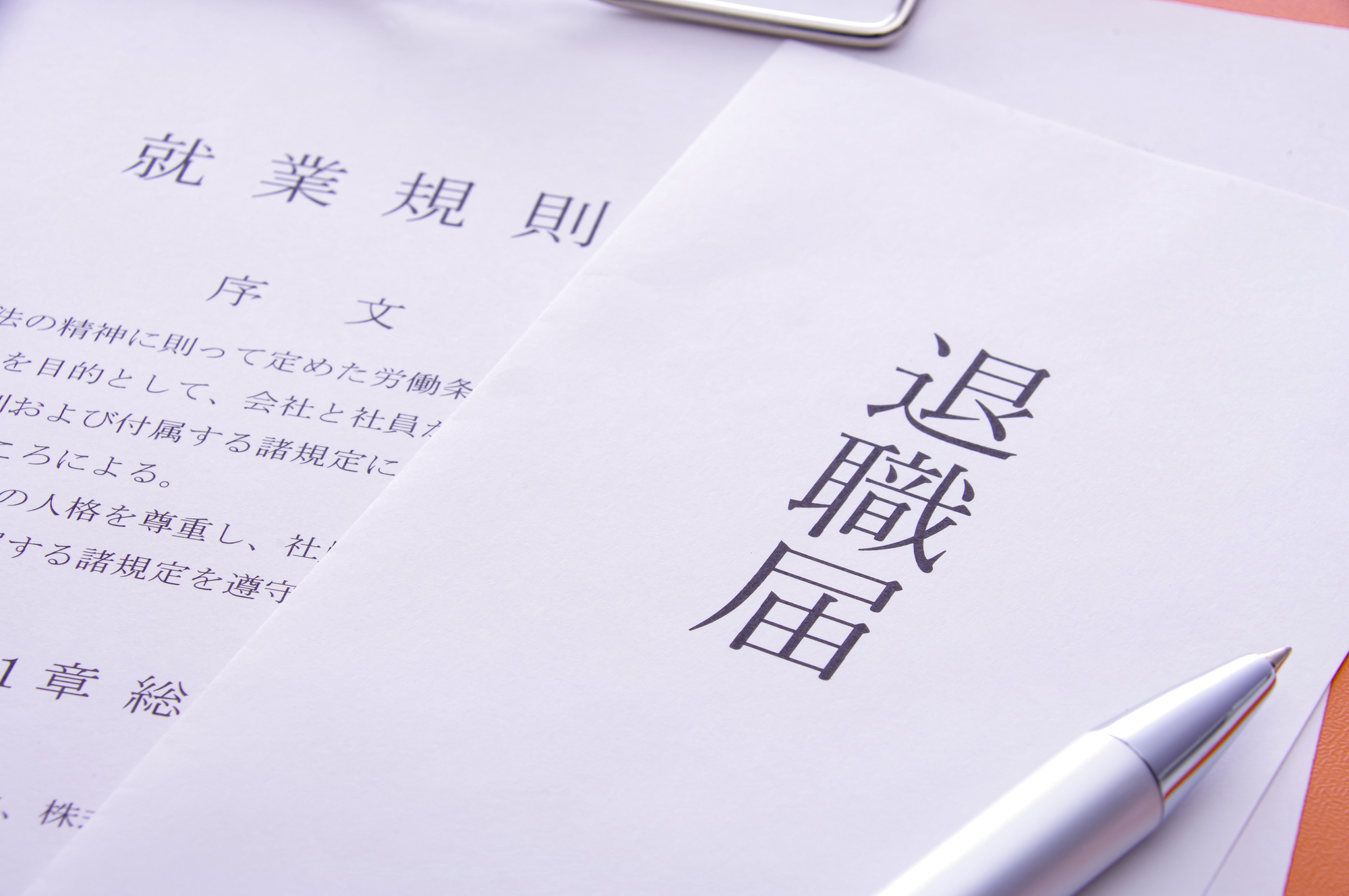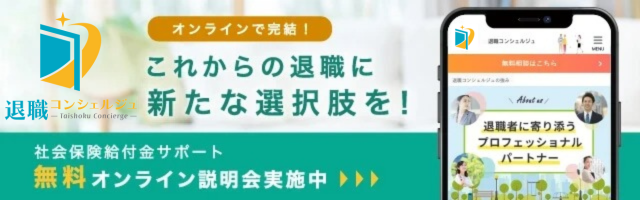退職日は月末にしない方がいい理由
退職日を月末にしない方がいい理由は、社会保険料の負担が増える可能性があるからです。
退職時は、資格喪失日が属する月の前月までの社会保険料を支払います。会社で加入している社会保険は、退職日の翌日が資格喪失日です。そのため、退職日を月末にすると翌月1日が資格喪失日となり、前月分までの社会保険料を納める必要があります。例えば、3月31日に退職した場合は4月1日が資格喪失日となり、3月分までの社会保険料を退職前の会社を通じて支払うことになります。
一方、月の途中で退職すると、会社では前月分までの社会保険料を納めることになり、当月分の負担が減ることが特徴です。例えば、3月30日に退職すると3月31日が資格喪失日となり、2月分までの社会保険料を支払います。
ただし、退職してすぐに再就職しない場合は、退職日の翌日以降は国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。退職後は1日の空白期間もなく、健康保険や年金に加入しなければならないことに注意しましょう。
退職日によって切り替えが必要な社会保険

転職する場合でも、退職日から入社日まで1日でも空白期間があるときは、社会保険の切り替え手続きが必要です。退職後に切り替えが必要な社会保険には、以下の2つがあります。
- 健康保険
- 年金保険
ここでは、健康保険と年金保険の種類や切り替え手続きの基礎知識について解説します。
健康保険
日本は国民皆保険制度を採用しており、何らかの健康保険に加入する必要があります。健康保険の3つの区分と主な種類は、加入対象者を以下の表にまとめました。
| 健康保険の区分 | 健康保険の種類 | 加入対象者 |
| 被用者保険 | 健康保険組合 | 主に大企業の従業員やその家族 |
| 全国健康保険協会(協会けんぽ) | 主に中小企業の従業員やその家族 | |
| 共済組合 | 公務員とその家族 | |
| 国民健康保険 | 自営業者など会社に所属しない人 | |
| 後期高齢者医療制度 | 主に75歳以上の高齢者 |
健康保険組合・協会けんぽ・共済組合は、会社員として働いているときに加入できる健康保険で、退職後は原則として資格喪失となります。
そのため、再就職まで1日でも空く場合は、国民健康保険への切り替え手続きが必要です。手続きは、住所地を管轄する市区町村役場で行います。保険料は後日送られてくる納付書に従い、自ら支払う必要があります。
退職日の翌日が入社日の場合は、就職先の健康保険に加入することになるため、労働者自ら手続きしたり保険料を支払ったりする必要はありません。
年金保険
日本の公的年金制度により、20歳以上60歳未満のすべての人は国民年金(基礎年金)への加入が必要です。会社員の場合は、基礎年金に加えて厚生年金にも加入します。
国民年金には、以下の3つの種別があります。
- 第1号被保険者:自営業者・学生・無職の人
- 第2号被保険者:会社員・公務員
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者
会社員として働いている場合、国民年金の第2号被保険者としてだけでなく、厚生年金の被保険者として保険料を納めていることになります。退職後、1日以上無職の期間がある場合は、国民年金の第1号被保険者への切り替え手続きが必要です。
【退職日別】社会保険料への影響
退職日をいつにするかは、退職後に受け取る手取り額に直結する重要な問題です。
退職日が「月末」「月の途中」「月末前日」か、それぞれを比較すると社会保険料の支払いに大きな違いが生まれます。社会保険料の負担の違いは、社会保険(健康保険・厚生年金)の資格を失う日(資格喪失日)が月をまたぐかどうかです。
ここでは、退職日によって退職月分の社会保険料の負担がどのように変わるかを解説します。
退職日を月末にした場合
退職日を月末にした場合、社会保険の資格喪失日は翌月1日となるため、退職した月の分まで保険料を支払うことになります。翌月1日以降、再就職するまでの期間は国民年金と国民健康保険に加入し続ける必要があります。
具体的には、退職日が11月30日とすると資格喪失日は12月1日となり、11月分の保険料を支払い、12月1日からは国民年金と国民健康保険に加入して保険料を納める流れです。
注意したいのは、給与の支給日が退職当月の場合、前月と当月の2か月分の保険料が天引きされる可能性があるため、手取り額が少なくなることがあります。
国民健康保険料は、前年の所得や家族構成、地域によって異なるため、条件によって変動します。国民年金保険料は、令和7年度実績で1か月17,510円です。
退職日が月途中の場合
月末ではなく月の途中で退職日した場合は、社会保険料は前月分までが支払い対象です。
例えば、11月15日に退職したとすると、資格喪失日は11月16日です。この場合は、会社で払う社会保険料は10月分までですが、退職日までの11月分は免除されます。
すぐに再就職しない場合は、11月16日から国民健康保険と国民年金に加入し、資格喪失日から保険料を支払うことになります。つまり、11月1日から11月15日までの社会保険料の支払いが免除となるため、月末で退職するより得することがメリットです。
退職日を月末前日にした場合
退職日を月末の前日にした場合は、月末が社会保険の資格喪失日となり、保険料の負担は前月分までのため当月分は免除されます。再就職まで期間が空く場合は、資格喪失日の月末から国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
例えば、退職日が11月29日のときは、資格喪失日は11月30日です。11月分の保険料は免除され、11月30日から国民健康保険と国民年金の支払いがスタートします。
月の途中で退職するより、月末前日を退職日にする方が免除される期間が長いことから、一般的には月末の前日に退職すると社会保険料の負担が減らせるとされています。しかし、ベストな退職日は個々の事情によって異なるため、一概に「月末前日を退職日にするのが良い」とは言えません。
退職日は月末にしない方が得するケース
個々の事情により、退職日をいつにするのが良いかは異なります。同様に、いつにすると損するかも人によって異なるため、自分のケースに当てはめて考えることが重要です。
ここでは、退職後の計画に応じて、退職日を月末にしない方が得するケースを「退職後すぐに就職しない場合」と「家族の扶養に入る場合」に分けて、具体的に解説します。
退職後すぐに就職しないケース
退職後すぐに就職しない場合は、退職日を月末にすると社会保険料の負担が大きくなることがあります。
例えば、11月30日に退職した場合、11月分の社会保険料を支払うことになり、12月1日からは国民健康保険と国民年金の支払いが始まります。つまり、社会保険料の免除が受けられません。
一方で、11月29日に退職した場合、11月1日から11月29日までの社会保険料は免除され、資格喪失日の11月30日から国保と国民年金を支払います。このケースでは、29日分の保険料を支払う必要がなくなり、月末に退職するより負担を減らせるメリットがあります。
退職後に家族の扶養に入るケース
退職後、すぐに家族の扶養に入る場合は、扶養に入った時点で社会保険料の負担はなくなることに留意して退職日を決めましょう。
例えば、11月30日に退職すると、11月分まで社会保険料を支払う必要があります。資格喪失日は12月1日のため、12月1日から扶養に入ると12月以降の保険料負担はなくなります。
一方で、11月15日に退職して翌日から扶養に入った場合は、11月分からの保険料負担がなくなるため、月末で退職するより1か月分の負担が減ることがメリットです。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
退職日を月末にした方が得するケース
社会保険料の負担だけを考えると「月末以外」の退職が得するように見えますが、退職後の計画によっては「月末」を退職日とした方が、総合的なメリットが大きくなるケースもあります。特に、「転職のスケジュール」や「会社の給与・休暇制度」を考慮することが重要です。
ここでは、退職日の翌日に就職する場合や、ボーナス・有給休暇が退職に影響する場合に、月末退職を選ぶことで得られる金銭的・手続き的なメリットを解説します。
翌日1日に就職するケース
翌月1日に入社することが決まっている場合は、月末に退職すると社会保険の切れ目なく転職できます。
退職日から入社日まで1日でも空くと、その期間は国民健康保険や国民年金への切り替えが必要です。退職日の翌日に入社日を迎えることで、切り替え手続きが不要になり、切り替え手続きや保険料支払いの手間がかかるのを避けられます。
ボーナスの支給日が月末のケース
退職時期とボーナスのタイミングが重なっているときは、ボーナス支給日も考慮に入れて退職日を決めると、金銭的に得することがあります。
ボーナスの支給条件は会社ごとに異なりますが、「支給日に在籍していること」が条件になっているのが一般的です。そのため、支給日が月末の場合は、退職日がたった1日違うだけでボーナスが受け取れなくなる可能性があることを考慮して慎重に決める必要があります。
社会保険料の負担額との兼ね合いにもよりますが、ボーナスを受け取ってから退職した方が得する人は、月末の支給日に在籍している状態になるよう、退職日を設定しましょう。
有給休暇が残っているケース
有給休暇が残っている場合は、残りの日数をすべて消化するために、退職日を月末にするのも選択肢の一つです。
月末での退職を無理に回避しようとした結果、有給休暇を消化しきれないまま退職日を迎えてしまうと、損した気持ちになることがあります。月末退職を選ぶことで、残っている有給休暇を使い切れるのであれば、社会保険料のメリットにこだわりすぎる必要はありません。
「有休消化」と「保険料負担の軽減」のどちらが自分にとって利益になるかを考えて、退職日を決めるのがおすすめです。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
退職日までの一般的な流れ
いつ退職するかを決めたら、以下の流れで退職日まで準備を進めます。
- 上司に退職の意思を伝える
- 期限までに退職届を提出する
- 業務の引き継ぎを行う
- 取引先や同僚に挨拶する
- 退職に関する書類を受け取る
ここでは、退職日までのステップについてそれぞれ詳しくみていきましょう。
上司に退職の意思を伝える
退職することを決めたら、直属の上司に退職の意思を伝えます。
退職の意思を伝える際に退職理由を聞かれることがあるため、円満退職しやすくなるような理由を準備しておきましょう。退職理由として、待遇や仕事内容への不満、人間関係などを挙げると心証がよくないだけでなく、退職を引き止められることがあります。
円満退社を目指すなら、「スキルアップのため」「新しい分野で一から頑張りたい」など、ポジティブな退職理由を伝えるのがおすすめです。前向きな理由であれば、面談の雰囲気が明るくなり、退社日の希望も伝えやすくなります。
期限までに退職届を提出する
退職の意思を口頭で伝えただけでは証拠が残らないため、あとから「言った」「言わない」のトラブルに発展する可能性があります。そのため、退職の意思を伝えた上で、後日改めて退職届も提出しましょう。
退職の申し出は、会社の就業規則に記載された期限までに提出するのが一般的です。民法上は、退職日の2週間前までに申し出れば問題ありませんが、就業規則通りに進める方がトラブルになりにくいでしょう。
業務の引き継ぎを行う
退職日までに業務の引き継ぎを行い、スムーズに退職できるよう準備を進めていきます。
引き継ぐ担当者がまだ決まっていない場合は、あらかじめ引き継ぎ書を作っておくと安心です。退職日ぎりぎりになって、引き継ぎ作業が終わらず慌ててしまうことなく退職できます。
取引先や同僚に挨拶する
退職日の数週間前から、取引先に挨拶回りをして退職することを伝えます。
挨拶回りのタイミングや内容は、上司と相談して決めるとトラブルが起こりにくいでしょう。直接挨拶できない場合は、メールや手紙で伝えても問題ありません。
当日の退勤時間までに、同僚や他部署の上司にも挨拶しておきます。業務時間内に挨拶回りをするときは、上司に許可をとっておくことが大切です。
退職に関する書類を受け取る
退職後の計画によっては、会社から書類をもらう必要があります。例えば、失業保険の受給に必要な雇用保険被保険者証や離職票、年金の切り替え手続きに必要な年金手帳などです。
ただし、被保険者証は労働者本人が管理している場合もあるため、まずは手元にないか確認しましょう。退職後に必要な手続きを把握し、それぞれの必要書類を集めて準備することが重要です。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
退職後すぐに就職しない場合に必要な手続き

退職日から再就職まで空白の期間が生じる場合は、主に以下の手続きが必要です。
- 失業保険の申請
- 年金保険の切り替え手続き
- 健康保険の切り替え手続き
ここでは、退職後すぐに就職しない場合に必要な手続きをそれぞれ解説します。
失業保険の申請
退職後、すぐに就職せず失業保険を受け取る場合は、原則として退職日の翌日から1年以内に失業保険の受給申請を行う必要があります。
会社から雇用保険被保険者証と離職票を受け取ったら、速やかにハローワークにて手続きしましょう。雇用保険被保険者証は自分で管理している場合もあるので、手元に準備しておくと手続きをスムーズに進められます。
離職票は、退職後1週間〜2週間程度で会社から郵送または手渡しされるのが一般的です。
年金保険の切り替え手続き
退職後、就職するまで1日でも期間が空く場合は、国民年金への切り替えが必要です。退職日の翌日から14日以内に、住所地を管轄する市区町村役場で手続きする必要があります。
手続きの持ち物は、年金手帳や基礎年金番号通知書などの基礎年金番号がわかる書類です。年金とマイナンバーを紐づけている場合は、マイナンバーカードなど個人番号がわかる書類があれば手続きできます。
健康保険の切り替え手続き
年金保険と同様に、再就職まで期間がある場合は国民健康保険への切り替え手続きも必要です。退職日の翌日から14日以内に、住所地の市区町村役場で切り替える手続きを行います。
離職前の健康保険は資格喪失日から使えなくなるので、退職後は速やかに手続きしましょう。手続きの際は、健康保険資格喪失証明書やマイナンバーカードなどの持参が必要です。
まとめ
退職日は月末にしない方がいい理由は、社会保険料の負担額が増えるケースがあるためです。一方で、月途中や月末前日に退職すれば、資格喪失日の設定上の理由により、退職月分の社会保険料が免除されるためお得感があります。
しかし、退職日をいつにすると得するかは退職後の状況や残っている有給休暇の日数、ボーナスの支給日などの都合で変化します。
自分の場合はいつ退職すれば、退職後の金銭的負担を減らせるのか知りたい方は、「社会保険給付金サポート」の活用がおすすめです。専任スタッフが利用できる給付金制度の手続きを全力でサポートし、退職後の生活を安定させるお手伝いいたします。相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼

 給付金がいくらもらえるか
知りたい方
給付金がいくらもらえるか
知りたい方 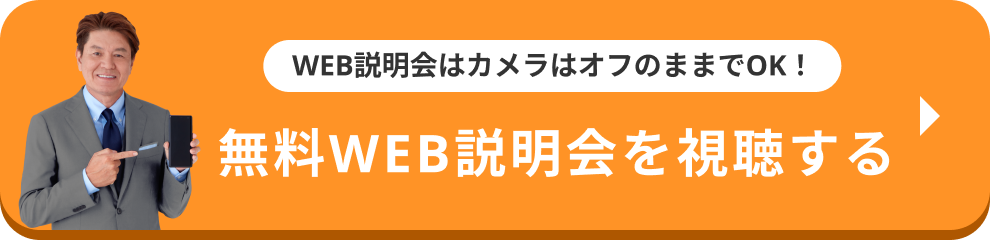
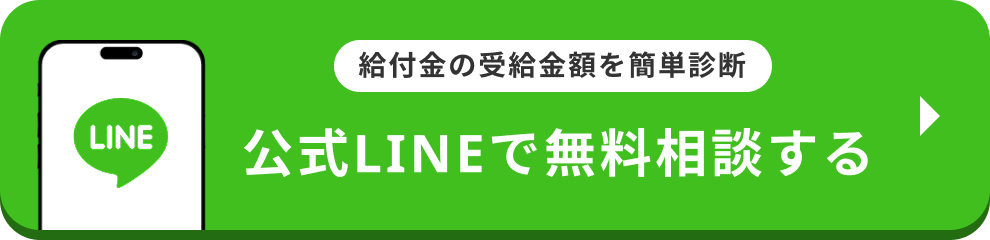
 給付金サポートを
ご検討中の方
給付金サポートを
ご検討中の方  評判・口コミ
評判・口コミ  給付金がもらえる
転職支援を活用する方
給付金がもらえる
転職支援を活用する方  その他退職について
ご不安がある方
その他退職について
ご不安がある方  もらえる給付金ラボ
もらえる給付金ラボ  退職コンシェルジュについて
退職コンシェルジュについて