2025.11.04
退職について
テーマ:
失業保険はいつからもらえる?1日でも早くもらえる方法や注意点を解説

退職後に失業保険を受け取るまでには、いくつかのステップが必要です。離職票の入手から申請、失業認定など順序を理解して準備しておくことでスムーズに受給を始められます。
本記事では、退職から実際に失業保険が振り込まれるまでの流れや、受給開始時期が変わる要因を解説します。いつからもらえるのか知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
失業保険をもらうまでの基本の流れ
原則として、失業保険は退職して失業保険をもらうための手続きを終えてから、7日間の待期期間が経過後に支給されます。
退職日からぴったり7日後に受け取れるわけではないため、誤解しないように注意が必要です。離職理由や過去の受給状況、待期期間中のアルバイトなどさまざまな条件によっていつからもらえるかは異なります。
まずは、退職から失業保険の受け取りまで基本の流れを解説します。
STEP1:退職後に離職票を入手する
退職したら、まずは以下の必要書類を準備します。
- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険被保険者離職票-1、-2
- 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
- 本人確認書類
- 顔写真2枚
- 本人名義の預金通帳やキャッシュカード
上記のうち、「雇用保険被保険者証」を会社が管理している場合は、退職時に会社から受け取れます。自分で保管している場合は、あらかじめ準備しておきましょう。
離職票は、退職日から10日内に会社がハローワークに書類を提出すると発行されます。そのため、手元に届くのは早くても1週間前後、遅いと2週間ほどかかる可能性があることに留意しましょう。
離職票の発行は労働者本人が会社に依頼しないと発行してもらえないため、退職前に担当者に手続きを依頼しておく必要があります。
STEP2:ハローワークで「求職の申込み」を行う
必要書類を準備したら、ハローワークに行って「求職の申込み」を行います。
ハローワークは基本的に土日祝日、年末年始を除く平日の8時30分から17時15分が開庁日時となっていますが、地域によって異なる場合があります。土日や夜間に開庁している地域もありますが、失業保険の受給申請はできないケースが多いため、いつ行けばよいかを確認しておくことが大切です。
受給資格が決定するともらえる「受給者のしおり」は、受給中に必要な情報が載っているため、大切に保管しておきましょう。
STEP3:7日間の待期期間を過ごす
求職の申込みが完了したら、担当者の指示に従って7日間の待期期間を過ごすことになります。
待期期間とは、受給資格が決定した日から失業状態の日が通算7日間経過するまでの期間です。原則、待期期間が終了した日の翌日から失業保険が支給されます。
ただし、離職理由などにより給付制限がかかる人は、待期期間が過ぎても支給は開始されません。
STEP4:雇用保険初回説明会に参加する
求職の申込みでもらった「受給者のしおり」を持って、ハローワークが指定した日時の雇用保険初回説明会に参加します。説明会では失業保険に関する説明があるため、必要なことはメモしましょう。
説明会では、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡されます。これらは失業保険の受給に欠かせない書類のため、大切に保管しておく必要があります。
STEP5:求職活動の実績を積む
初回失業認定日までに、求職活動を1回以上行う必要があります。詳しくは後述しますが、具体的な求職活動として、求人への応募や職業相談、再就職のための各種試験や検定の受験などが挙げられます。
民間の求人サイトに登録しただけ、求人情報を閲覧しただけでは実績にはならないので注意が必要です。「就職相談後に職業紹介を受けた」など、2回以上の実績とみなされるケースもあるため、不明点は説明会や窓口などで解消しておくとよいでしょう。
STEP6:失業認定を受ける
雇用保険初回説明会で伝えられた失業認定日にハローワークへ行き、失業認定を受けます。失業認定を受けるときは、「雇用保険受給資格者証」と求職活動実績などを記載した「失業認定申告書」を持参しましょう。
無事に認定されると、給付金の支給手続きが行われます。不認定になると、今回分の給付金は支給されません。不認定で支給が先送りになったとしても、次回の認定日に認定されれば受給が開始されます。
STEP7:失業保険が振り込まれる
認定日に認定を受けて給付金の支給が決定されると、求職の申込みで指定した銀行口座に失業保険が振り込まれます。
実際に振り込まれるのは、支給決定から約1週間後です。手続きの不備や金融機関の営業日によって前後するため、1週間ピッタリに入金されるわけではありません。
求職の申込みで指定した銀行口座の口座番号が間違っていたり、申込み後に氏名などを変更したりすると振り込まれないことがあります。口座番号にミスがないか確認するのはもちろん、申込み後に銀行口座の情報に変更があった場合は、速やかにハローワークで変更手続きをしましょう。
失業保険をもらえる時期が変わる6つの原因
失業保険の支給が開始される時期は、主に以下の6つの原因に左右されます。
- 申請時期
- 失業の状態
- 離職理由
- 過去の受給歴
- 教育訓練の受講状況
- 申請後の就労状況
それぞれの原因が、どのように失業保険の受給に影響するかを解説します。
失業保険の申請時期
前述のとおり、失業保険をもらうためには、ハローワークで「求職の申込み」と呼ばれる手続きが必要です。手続き開始が遅れると、その分給付金が入金されるのも遅くなります。
失業保険の手続きは退職の翌日から開始できるため、早くもらいたい場合は速やかに申請しましょう。
ただし、手続きに必要な「離職票」は退職後1週間〜2週間ほどで会社から送られてくるため、実際には退職してから1週間後くらいに手続きすることになります。
なかには、離職票の到着が遅れてなかなか手続きを始められず、受給が遅れてしまうこともあるかもしれません。その際は、「仮手続き」しておくと、離職票が届くまでの間に手続きを進められます。
失業の状態
失業保険を受給するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 原則、離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12か月以上あること
- 失業の状態であること
失業の状態とは、以下をすべて満たす人のことを指します。
- ハローワークで求職の申し込みを行う
- 就職しようとする積極的な意思がある
- いつでも就職できる能力があるのに職業がつく事ができない
つまり、就職の意思がない人や就職する能力がない人は、今の状況では失業保険をもらえません。「就職する能力がない人」には、具体的に次のような人が該当します。
- 病気やケガですぐに働けない
- 妊娠・出産・育児によりすぐに働けない
- 退職後にしばらく休養しようと考えている
- 家事に専念するため今は働く意思がない
「失業の状態にない」と判断される人はすぐに受給できませんが、再び失業中と認定されれば受給可能です。やむを得ない事情ですぐに求職活動を開始できない人は、失業保険の受給期間を延長申請できます。
離職理由
失業保険の支給開始時期を左右する給付制限には、離職理由が大きく関係しています。受給に関する離職理由は、以下の3つに区分されます。
|
離職理由の区分 |
具体的な理由 |
|
特定資格受給者 |
倒産や解雇など会社都合で離職した人 |
|
特定理由離職者 |
有期雇用契約の期間満了後に更新されずに離職した人、正当な理由があり自己都合退職した人 |
|
一般の離職者 |
転職など自己都合で退職した人 |
参考:ハローワークインターネットサービス|特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
上記のうち、特定受給資格者と特定理由離職者には給付制限がかからないため、一般の離職者と比べて受給開始が早まります。
一方、一般の離職者は原則1か月の給付制限が設けられており、その後に受給開始となります。また、重責解雇された人の給付制限は3か月です。
過去の失業保険受給歴
給付制限の期間は、離職理由のほかに過去の受給状況も影響します。退職日からさかのぼって5年間に2回以上、正当な理由がなく自己都合退職し、失業保険の受給決定を受けていると給付制限は3か月です。
受給決定を受けた回数で判断されるため、実際に失業保険を受け取ったか、どのくらいの期間を受け取ったかは関係ありません。
教育訓練等の受講状況
2025年4月以降、給付制限のある人が教育訓練等を受けると、制限が解除されるようになりました。給付制限の期間に関係なく、受講開始から制限が解除されて支給が始まります。
退職後に受講する場合だけでなく、退職日以前の1年以内に受講した場合も対象です。ただし、途中で退行した人は対象外になります。
失業保険申請後の就労状況
待期期間や給付制限期間の間に働いてしまうと、条件によっては受給が先送りされることがあります。アルバイトやパート、フードデリバリーなど、雇用形態にかかわらず制限の対象になる可能性があることに注意しましょう。
待期期間に働いてしまった場合は、働いた日数分が延長されます。例えば、7日間の待期期間中に2日間働くと合計9日間になり、受給開始が遅れることになります。
給付制限期間に働いた場合は、労働時間や賃金によって減額や先送りとなる仕組みです。労働時間により、受給にどのような影響を与えるかを以下の表にまとめました。
|
給付制限中の労働時間 |
受給への影響 |
|
1日4時間未満 |
賃金によって減額される |
|
1日4時間以上 |
働いた日は不支給になり先送りされる |
参考:厚生労働省|はろカフェ
【具体例】失業保険はいつからもらえるか?
前述のとおり、失業保険がいつからもらえるかは申請時期や失業状態、離職理由などによって異なります。ここでは、ケースごとの受給開始時期について具体例を出しながら解説します。
会社都合で退職したケース
会社都合で退職して失業保険をもらう場合は、初回認定日が最短の受給日です。具体的には、受給申請から7日間の待期期間後、初回認定日の前日までの給付金が認定日の約1週間後に振り込まれます。
認定日は求職の申込みをした日から4週間ごとに設定されるため、会社都合の場合は申請日から1か月程度でもらえます。例えば、10月1日に求職の申込みを行なった場合、10月7日までが待期期間となり、10月8日から認定日前日28日までの分が10月29日で認定され、その約1週間後に入金される流れです。
「一般の離職者」に該当するケース
給付制限が1か月の一般の離職者に該当し、教育訓練を受講していないケースでは、最短で7日間の待期期間と1か月の給付制限が経過した後から受給開始となります。実際に銀行口座に振り込まれるのは、給付制限後の失業認定日から約1週間後です。
例えば、10月1日に求職の申込みをした場合、待期期間が明けるのが10月8日、1か月の給付制限は11月7日までとなります。つまり、11月8日から次回の認定日の前日11月25日までの受給分が11月26日に認定され、その約1週間後に振り込まれる流れです。
ただし、上記はあくまで計算上の話であり、実際にはハローワークや金融機関の営業日などで変わることがあります。
給付制限中に教育訓練等を受講したケース
退職後に教育訓練等を受講すると、受講した日から給付制限がかからなくなります。
原則、給付制限が3か月の人が10月1日に求職の申込みを行ったとすると、受給開始となるのは翌年1月初旬です。
しかし、給付制限中、例えば10月15日から教育訓練を受講した場合で考えてみましょう。
この場合、初回失業認定日の10月29日に支給決定され、その約1週間後に10月15日から初回認定日の前日までの分が支給される流れです。給付制限が解除されない場合と比べ、早く受給できるようになります。
ただし、受講の申し出のタイミングによっては、手続きが遅れて受講開始日から解除されないことがあります。
受給延長申請後に求職活動を再開するケース
失業保険はすぐにでも働ける人を対象にしているため、何らかの事情がありすぐに働けない人はその事情が解消するまでもらえません。
失業保険の受給期間は1年間で、その期間中に求職活動を再開できる場合は、受給申請して通常通り待期期間や給付制限後から支給されます。やむを得ない事情で30日以上働けない場合は、受給機関を退職日から最長4年間の延長が可能です。
例えば、6か月間にわたり就労できない状況が続いた場合は、延長申請で当初の受給期間が6か月間延長され、結果として受給期間は1年6か月間になります。
ただし、延長後に失業保険を受給するためには、働けなかった事情が解消されたという証明書の提出が必要です。
失業保険は退職後からいつまでもらえる?
そもそも、失業保険は退職後に申請してからいつまでもらえるのでしょうか。ここでは、給付金をいつまでもらえるか、受給の際に注意したいポイントを解説します。
申請期限は原則として1年間
失業保険の申請期限は「受給期間」と呼ばれ、原則として退職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると求職の申込みができなくなるため、自分の受給期間を把握しておきましょう。
また、受給期間を過ぎると失業保険の申請ができなくなるだけでなく、受給中の失業保険も受け取れなくなります。
例えば、90日分受け取れる場合に、受給期間が経過する2か月前に手続きすると、約1か月分は受け取れなくなる仕組みです。給付制限がある場合、申請のタイミングによってはほとんど受け取れない可能性もあるため、待期期間や給付制限期間を考慮して早めに手続きを開始しましょう。
実際に給付金を受け取れる日数は所定給付日数
失業保険を受け取れる期間は、所定給付日数によって異なります。
所定給付日数とは、失業保険(基本手当)を受け取れる日数のことです。離職理由や雇用保険の加入期間、離職時の年齢によって以下のように設定されています。
・特定受給資格者及び一部の特定理由離職者
|
離職時の年齢 |
雇用保険の被保険者期間 |
||||
|
1年未満 |
1年以上5年未満 |
5年以上10年未満 |
10年以上20年未満 |
20年以上 |
|
|
30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
– |
|
30歳以上35歳未満 |
120日 |
180日 |
210日 |
240日 |
|
|
35歳以上45歳未満 |
150日 |
180日 |
240日 |
270日 |
|
|
45歳以上60歳未満 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
|
|
60歳以上65歳未満 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
|
参考:ハローワークインターネットサービス|基本手当の所定給付日数
・一般の離職者
|
雇用保険の被保険者期間 |
所定給付日数 |
|
10年未満 |
90日 |
|
10年以上20年未満 |
120日 |
|
20年以上 |
150日 |
参考:ハローワークインターネットサービス|基本手当の所定給付日数
・就職困難者
|
離職時の年齢 |
雇用保険の被保険者期間 |
|
|
1年未満 |
1年以上 |
|
|
45歳未満 |
150日 |
300日 |
|
45歳以上65歳未満 |
150日 |
360日 |
参考:ハローワークインターネットサービス|基本手当の所定給付日数
失業保険はいつ振り込まれる?
失業保険の支給は、待期期間や給付制限が明けてから始まりますが、実際に受け取れるのは失業認定日から約1週間後です。
初回の受給額は、待期期間・給付制限が経過後から認定日の前日までの給付金が指定した銀行口座に振り込まれます。2回目以降は、前回の認定日から今回の認定日前日までの分が入金されます。
ただし、指定した金融機関の営業日や営業時間によって、振込日は多少前後することに留意しましょう。
また、給付金を受け取るためには失業認定を受けなくてはいけません。失業認定日にハローワークに来所し、失業認定申告書を提出する手続きが必要です。
申告書には、期間中に行った求職活動を記入します。認定には一定以上の求職活動実績が求められ、認定日に書類を提出しても実績が足りないなど不備があると不認定となり、今回分は支給されません。
失業保険を遅滞なく受け取るポイント
退職後の生活を安定させるためにも、できるだけ早く失業保険を受け取りたいものです。離職理由や失業の状態は自分で変えられない条件ですが、申請時期や就労状況など、ポイントを押さえておくとスムーズに受給しやすくなります。
退職後するに手続きを開始する
失業保険を遅延なく受け取りたい場合は、退職後速やかに手続きを開始することが重要です。手続きが遅れると、その分受給開始も遅くなってしまいます。
また、受給期間を過ぎてしまうと受け取れなくなったり、受け取れる金額が減ったりすることがあるため、できるだけ早く手続きしましょう。
失業保険の受給申請が遅れる原因として、退職後に離職票が手元に届くのが遅れることが挙げられます。離職票が届かない場合は、退職日の翌日から12日目以降であれば「仮手続き」が可能です。仮手続きを進めておけば、待つ時間を無駄にすることなくスムーズに受給開始しやすくなります。
認定日に失業認定を受ける
失業保険を受け取るためには、受給申請だけでなく失業認定の手続きも必要です。
失業認定とは、失業状態で求職活動していることを証明するため、ハローワークが決めた日時に来所して行う手続きです。失業認定日には、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書の提出を求められます。
指定の時間に遅れても問題ありませんが、指定された日中に来所できないと、次回の失業認定日まで給付金がもらえなくなります。
ただし、給付金は先送りされるだけで支給総額が減るわけではありません。受給が遅れる原因になるため、早くもらいたい場合は失業認定を必ず受けましょう。
決められた回数以上の求職活動を行う
失業認定では、期間中に行った求職活動の実績を報告します。失業状態と認定されるためには、積極的に求職活動を行っている必要があり、ハローワークが定める回数以上の実績が求められます。
初回の失業認定日では、雇用保険初回説明会が1回として加算されるため、そのほかに1回以上、2回目以降の認定日は前回の認定日から2回以上の実績が必要です。
求職活動とは、求人への応募やハローワークが実施する職業相談、許可を受けた民間事業者が実施するセミナー、各種国家試験・検定などです。実績によっては、認定に証明書などが必要なこともあります。
待期期間や給付制限期間にアルバイトをしない
待期期間にアルバイトなどをしてしまうと支給が先送りになることがあるため、早く受給したいのであれば、期間中は求職活動に集中するほうが無難です。
給付制限中のアルバイトは可能ですが、1日4時間以上の労働は受給が先送りになります。また、4時間未満でも減額されることがあるため、早くもらいたい人や満額もらいたい人はアルバイトの影響も考慮しましょう。
失業保険を1日でも早く受け取りたいなら教育訓練の受講がおすすめ
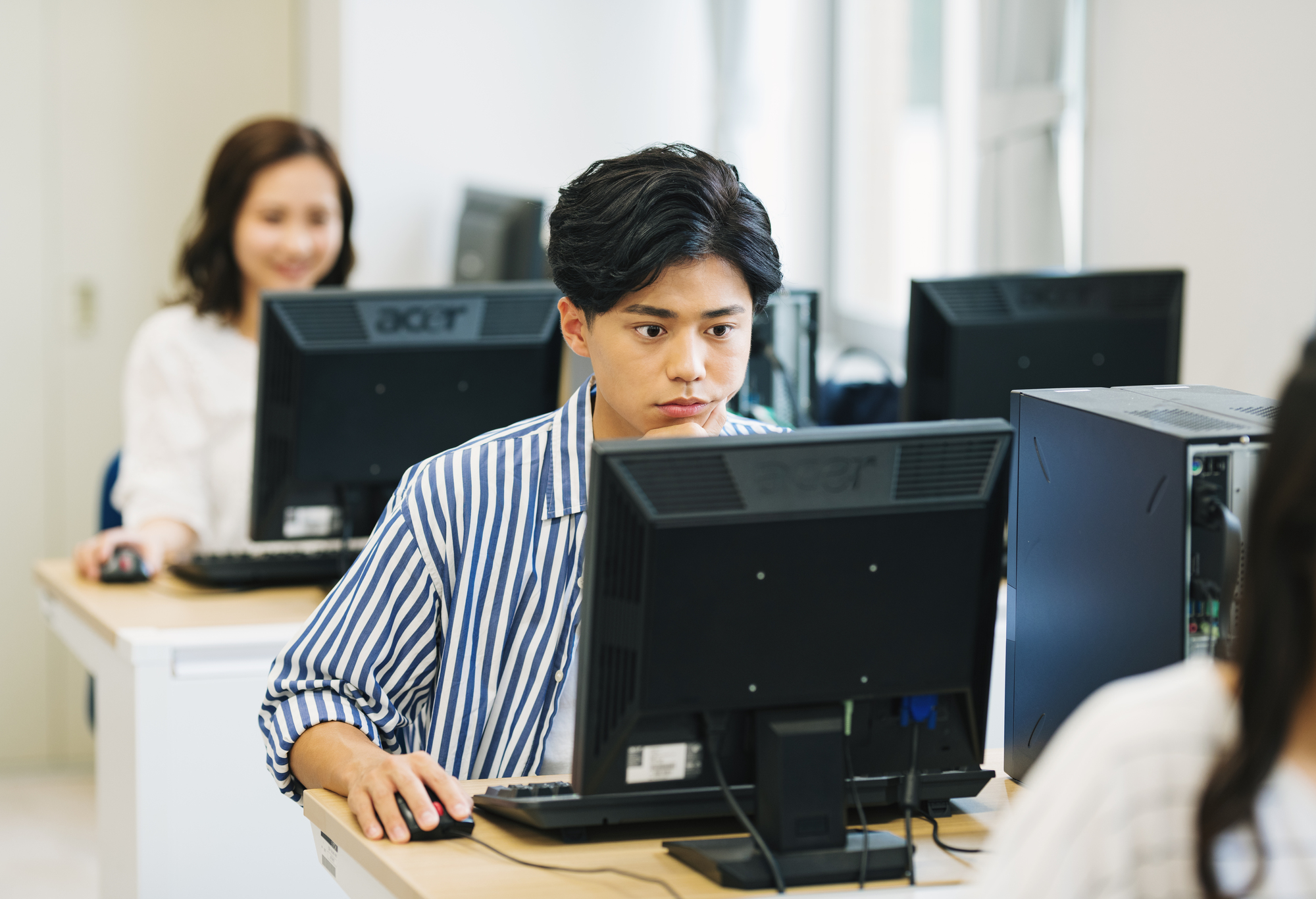
給付制限がかかる人は、待期期間だけの人と比べて受給開始の時期が遅くなります。しかし、教育訓練等の受講は、給付制限を解除して受給までの期間を早められることがメリットです。
ここでは、教育訓練を受講する際に知っておきたいポイントを解説します。
給付制限の解除対象となる教育訓練等とは
給付制限の解除対象となる教育訓練等は、主に以下が該当します。
- 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
- 公共職業訓練等
- 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
- 上記に準ずると職業安定局長が定める訓練
教育訓練給付金とは、労働者のスキルアップを目指して厚生労働大臣が指定した教育訓練を修了すると費用の一部が支給される制度です。約1万7,000講座が対象で、なかにはオンライン受講が可能な講座や夜間・土日に受講できる講座もあります。
公共職業訓練とは、国や都道府県が実施する原則無料の職業訓練制度「ハロートレーニング」のことです。ハローワークの職業指導で1か月未満の教育訓練を受けて修了したときに、支払った教育訓練経費の一部が支給されます。自治体により、訓練の内容や期間はさまざまです。
教育訓練給付金は、条件を満たせば在職者も受講可能です。一方、公共職業訓練は原則有料で在職者も受講できます。
教育訓練等の受講で失業保険を早く受け取れるようになる人の特徴
職業訓練等を受講することで、失業保険の受給が早くなる人の特徴は以下のとおりです。
給付制限がかかっている
2025年4月1日以降かつ離職日前1年以内に受講した、または離職日以降に受講した
ただし、重責解雇された人は対象外のため、該当の教育訓練を受けても給付制限は解除されません。重責解雇とは、労働者の故意または重い過失により会社に重大な損失を与えるなどの理由で解雇されることです。
在職中の受講でも退職後の給付制限が解除される
在職中に職業訓練等を受講していた場合も、給付制限解除の対象です。
ただし、前述のとおり退職した日以前の1年間に受けた教育訓練が対象になります。例えば、2024年8月31日に職業訓練を受講し、2025年10月1日に退職した場合は対象外です。
職業訓練によっては受講に条件があり、回数が制限されることがあります。以前に制度を利用している場合は、今回受講できないケースがあるので注意しましょう。
給付制限解除の手続き方法
職業訓練等を受けて給付制限を解除する際は、以下の書類を持ってハローワークの窓口で手続きします。
|
訓練の受講時期 |
必要書類 |
|
失業保険の受給資格決定以降、または決定時に受講中 |
・訓練開始日が記載された領収書 ・訓練実施施設による訓練開始日の証明書 |
|
失業保険の受給資格決定前に修了 |
・訓練修了日が記載された修了証明書 ・訓練実施施設による訓練修了日の証明書 |
参考:厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
教育訓練給付金の受給手続きをした場合など、ハローワーク側が教育訓練の受講事実を確認済みであれば、上記の書類が不要なケースもあります。
給付制限が2か月以上の人は申し出の期限に注意
給付制限が2か月以上あり、職業訓練等の受講制限を解除したい場合は、申し出の期限に注意しましょう。
教育訓練の受講開始日が、失業保険の初回認定日以降で次の認定日の相当日前の場合、受講開始日直後の失業認定日の相当日までの申し出が必要です。受講開始日が認定日の相当日以降かつ給付制限期間満了後の失業認定日前の場合は、給付制限期間の満了後にくる失業認定日までに申し出します。
期限までに申し出していない場合、受講開始日から認定日までの失業保険はもらえません。
例えば、給付制限が3か月で10月1日に受給資格が決定した人は初回認定日が10月29日、2回目の認定日は11月26日です。11月15日に教育訓練の受講を開始した場合、11月26日までに申し出をすれば、11月15日から受給開始となります。
この例では、11月26日までに申し出しなかった場合、11月15日から11月26日までの失業保険は受け取れません。
まとめ
失業保険が支給されるのは、認定日から約1週間後です。認定日は失業保険の申請日をもとに設定されるため、退職後速やかに手続きしましょう。
また、給付制限期間が長い人は初回の振り込みまで数か月かかります。できるだけ早く受け取りたいのであれば、教育訓練等を受講するなどの工夫が必要です。
失業保険がいつからもらえるか不安な人や、遅延なく受け取りたい人は「社会保険給付金サポート」の活用がおすすめです。社会保険給付金サポートでは、スムーズに受給できるように実績豊富な担当者が丁寧にサポートします。相談は無料なので、まずはお気軽にお問い合わせください。
この記事の監修者

杉山 雅浩
東京弁護士会所属。
池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。
NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、
詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。
YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!
おすすめの関連記事
ピックアップ
- CATEGORY
- 給付金について
- 転職・再就職について
- 就労について
- 社会保険について
- 精神疾患について
- サービスについて
- 傷病手当金について
- 失業保険について
- 退職について
- 障害年金について
- ピックアップ
- 人気記事
-
退職代行サービスの利用方法、実際の流れと体験談を紹介
-
今の会社に3年後もいる自信はありますか?
-
退職代行を利用した時の有給消化の仕組みとその対応方法
-
退職代行サービスを使うメリット・デメリットは?
-
ブラック企業を判定する方法と実際のチェックポイント
-
障害年金を知ろう
-
会社を“円満に退職する”方法は?
-
退職時の引き継ぎは義務?スムーズな業務引き継ぎの必須ポイント
-
パワハラ、モラハラ、セクハラとは?
-
辞めさせてくれない!そんな時こそ「退職代行サービス」
テーマ
- 転職サイト
- 不支給
- 引っ越し
- 雇用契約
- 退職代行
- 職務経歴書
- 等級
- 社宅
- 内定
- 退職代行サービス
- 人間関係
- 離職票
- 障害者手帳
- 就労移行支援
- ブラック企業
- スタートアップ
- 労務不能
- 精神保険福祉手帳
- 業務委託
- ハラスメント
- 転職
- 傷病手当金
- 労災
- 社会保険
- 引き継ぎ
- 違法派遣
- 障害者控除
- 産休
- 福利厚生
- 給与
- 派遣契約
- 退職届
- 解雇
- 就職困難者
- 残業代
- 障害厚生年金
- 面接
- 中小企業
- 再就職手当
- 退職金
- 失業保険
- 障害手当金
- ベンチャー企業
- 社会保険給付金
- 会社都合退職
- 資格取得
- 新型コロナウイルス
- 退職勧奨
- 職業訓練受講給付金
- 自己都合退職
- うつ病
- 有給消化
- 自己PR
- 退職給付金
- クレジットカード
- 統合失調症
- 休職
- 確定申告
- ハローワーク
- アルバイト
- 契約社員
- 免除申請
- 保険料
- 傷病手当
- 雇用保険
- 弁護士
- 適応障害
- 社会保障
- 退職コンシェルジュ
- 健康保険
- 公的貸付制度
- 住宅確保給付
- 就職
- ストレス
- 年金
- 生活福祉資金貸付制度
- 職業訓練
- 労働基準法
新着記事
-
2025.12.17
傷病手当金の不正と調査|どこからがNG?就労・外出・求職活動の正しい判断基準を解説
-
2025.12.16
【徹底比較】退職給付金サポート おすすめランキング
-
2025.12.09
傷病手当金をもらいながら働く方法はある?アルバイトならOK?収入を得る方法や注意点を解説
-
2025.12.09
社会保険給付金と失業保険の違いは?受給要件やメリット・デメリット解説
-
2025.12.08
産休・育休後そのまま退職はマナー違反?退職時のポイントと注意点
-
2025.12.07
会社を辞めさせられた場合は失業保険は受け取れる?条件や注意点を解説
-
2025.12.04
傷病手当金は退職後もらえない?受給できる条件と不支給になる理由を徹底解説
-
2025.12.01
休職でも傷病手当金はもらえる?休職手当との違いや支給額を解説
-
2025.12.01
うつ病は傷病手当がもらえない?活用できる制度も併せて紹介
-
2025.12.01
適応障害で傷病手当金はもらえる?受給するメリット・デメリットと申請方法





 サービス詳細
サービス詳細














