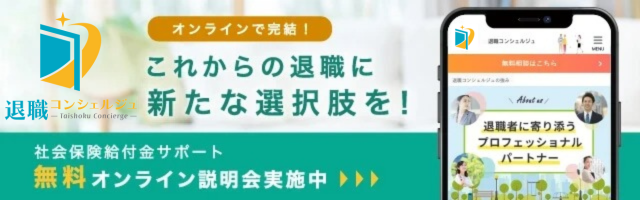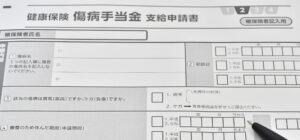確実に退職できる退職理由はある?

どのような退職理由であっても、人手不足など会社の都合で引き止められることはあります。そのため、確実に退職できる理由を見つけるのは難しいのが事実です。
しかし、会社が退職を引き止めにくい退職理由もあるため、確実に退職したい場合は引き止められにくい理由を伝えることが重要です。
確実に退職するために嘘の退職理由を伝えても問題ない?
「確実に退職したい」と考えているのであれば、できるだけ会社が引き止めにくい退職理由を伝えるのが得策です。しかし、嘘の退職理由で退職するのは法的に問題ないのか気になる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、嘘の退職理由を伝えるとどうなるのかを解説します。
嘘の退職理由で退職しても法律上は問題ない
雇用期間に定めがない雇用形態の場合、法律上は嘘の退職理由で退職しても罰則などはありません。
退職に関する法律は民法第627条で定められており、労働関係の終了に関する項目では退職理由に言及していないため、理由の内容に限らず退職できます。
理由にかかわらず会社は退職を拒否できない
会社は労働者から退職の届出があった場合、拒否することはできません。民法627条第1項において、以下のとおり定められているためです。
”当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。”
民法627条により、理由に関わらず退職を拒否できない期間の定めがない雇用契約の場合は、退職の意思を伝えた日から2週間経過後に法律上は退職可能です。
契約社員など、期間の定めのある雇用契約において雇用期間中に退職する場合は、以下の条件を満たせば、理由にかかわらず会社は退職の申し出を拒否できません。
- 期間の定めのある雇用契約で働いている
- 雇用期間が5年を超えている、または終期が不確定である
- 5年を経過して働いている
必ずしも本当の退職理由を伝えないほう良いケースもある
退職理由で嘘をつくことは、会社の引き止めを避けられるだけではありません。本当の退職理由を伝えてしまうと、トラブルに発展する可能性が考えられる場合など、必ずしも本当のことを伝えることが良いとは限らないためです。
例えば、上司と相性が合わなくて退職する場合、上司に直接「あなたと合わないから辞めます」と伝えてしまうと、職場の雰囲気が悪くなり周囲の人にまで影響を与えてしまう結果になることもあります。
確実に退職するために嘘をつくメリット
確実に退職するために嘘をつくメリットには、主に以下が挙げられます。
- 引き止められずにスムーズに退職しやすい
- 職場の雰囲気が悪くなりにくい
- 退職後も会社関係者と良好な関係を保ちやすくなる
- 知られたくない本音を隠せる
それぞれのメリットを詳しく解説します。
引き止められずスムーズに退職しやすい
嘘の退職理由により会社に退職を引き止められにくくなり、スムーズな退職が実現できる可能性があります。特に、確実に退職したいと考えている場合に、本当の退職理由を伝えると会社に退職を引き止められる可能性があるケースに有効です。
一方、例えば「なんとなく仕事が合わないから辞めたい」など、これといった退職理由がない場合も、もっともらしい理由をつけることで円満退社しやすくなるでしょう。
職場の雰囲気が悪くなりにくい
本当の退職理由が、会社や上司、同僚への不満など職場環境に関する場合、そのまま伝えてしまうと退職まで職場の雰囲気が悪くなることがあります。一般的には退職日から2週間以上前に退職の申し出をする必要があり、退職理由によっては退職日まで気まずい雰囲気で仕事をすることになってしまうかもしれません。
無理に嘘をつく必要はありませんが、誰も傷つけない、不快にさせない嘘の理由を伝えることで、退職日まで職場の雰囲気が悪くなることなく働けるようになります。
退職後も会社関係者と良好な関係を保ちやすくなる
納得してもらいやすい退職理由を伝えることで、退職後も会社関係者と良好な関係を継続しやすくなることもメリットです。
退職理由によっては、そのまま伝えると会社との間に亀裂を生む原因になることがあります。特に、同じ業界や職種に転職する予定がある場合は、退職後も付き合いが続くかもしれません。本当の退職理由を伝えないほうがよいと判断し、嘘を付くのも将来的なリスクを減らす方法の一つです。
知られたくない本音を隠せる
退職理由を正直に話した場合、理由を深掘りされ、教えたくない本音を聞き出される可能性があります。特にプライベートな理由や会社に関する不満など、本音や事情を隠したまま退職できることがメリットです。
退職理由で嘘をつくデメリット
本当の退職理由を伝えないメリットは多くありますが、嘘をつくデメリットに注意が必要です。後先考えず嘘をついてしまうことのないよう、ここで紹介するデメリットを把握しておきましょう。
嘘をつくことでストレスを感じることがある
お世話になった会社に対して嘘の退職理由を伝えることは、罪悪感の原因になりストレスを感じる人もいます。特に、親しい同僚にも本当のことを話せず退職するのは心苦しいと感じ、退職後も引きずってしまうこともあるかもしれません。
嘘をつくことにストレスを感じやすい人の場合、退職理由を明確にせず、「詳しくは話せない」「一身上の都合」と伝えるほうが精神的負担が少ないこともあります。「話せない」と最初に伝えれば相手も深掘りしにくいので、「詳しくは聞かないでほしい」というスタンスで退職まで過ごすのが無難です。
嘘がバレると気まずいまま退職することになる
嘘の退職理由を伝えて退職の申し出をした場合、退職日までに嘘がバレてしまうと、関係者と気まずい雰囲気になることがあります。退職するまで気まずいままになるため、早々に嘘がバレてしまうと職場に居づらいと感じることになるかもしれません。
例えば、上司や同僚など同じ部署やチームの人が原因で辞める場合、嘘がバレて本人に伝わってしまうと退職日までの業務に支障をきたす結果になる可能性があります。
退職まで辻褄合わせを続ける必要がある
退職することが周囲に広まると、退職理由を詳しく聞かれることも少なくありません。
人によっては、「どこの会社に転職するのか」「転職後の引越し先は決まっているのか」など、プライベートな内容に踏み込んで質問してくることもあるため、嘘がバレないように退職日まで辻褄わせをする必要があります。
その場しのぎで回答していると、嘘に嘘が重なって矛盾が生じたり、話した内容を忘れてしまったりと綻びが出やすいため注意しましょう。複雑な嘘は避け、詳細を聞かれても深くは話さないことが重要です。
退職後の行動に影響を与えることもある
嘘の退職理由の内容によっては、退職後の仕事や生活に影響を与えることがあります。
例えば、「配偶者の転勤についていくために退職する」と伝えたのに、退職後も転居しない場合、周辺で会社関係者に会ってしまう可能性が考えられます。「引っ越したはずなのに、なぜここにいるの?」と思われ、社内で噂になる可能性も否定できません。
「退職後はもう関係ない」と割り切ることもできますが、同じ業界や職種に転職する場合など、仕事や生活に悪い影響を与えてしまうことに注意が必要です。
確実に退職したいときの退職理由の具体例
ここからは、会社に引き止められにくい退職理由の具体例を紹介します。
違う業界や職種に挑戦したい
「これまでとは異なる業界や職種に挑戦したい」など、今の会社では達成できない目標や夢ができて退職することは前向きな気持ちによる退職のため、会社や上司も引き止めにくい退職理由です。
働いているうちに、異業種に挑戦したい気持ちが出てくるのは珍しいことではありません。「前々からやりたいと思っていたことに挑戦できるのは若いうちだけ」と今挑戦すべき根拠を用意しておくと、納得してもらいやすいでしょう。
転職先がすでに決まっている
本当に転職先が決まっているかどうかにかかわらず、転職先が決まっていると伝えることも、スムーズに退職しやすい理由の一つです。すでに転職先が決まっている場合、入社日までには退職しないとトラブルに発展する可能性があるためです。
転職先の会社名など詳細を聞かれることがあるかもしれませんが、詳しく話す必要はありません。
ただし、「転職先が決まっている」と嘘をついて退職し、その後に失業保険をもらう予定のときは、「離職票」の発行依頼を忘れないようにする必要があります。
資格取得などスキルアップしたい
資格取得や語学留学など、「スキルアップのために勉強時間を確保したい」という退職理由も、ポジティブな退職理由のためスムーズに退職しやすいでしょう。
退職後、専門学校や大学、大学院など各種学校に入学予定の場合は、「入学試験に合格した」と伝えると会社は引き止めにくいためです。本来の退職理由を隠して嘘をつく場合も、本当に試験勉強しているか会社側は事実確認できないため、詳細を話さなければバレにくい理由の一つです。
起業・独立する
退職後、自分で会社を立ち上げたり個人事業主として開業したりする場合も、会社にとって引き止めにくい退職理由です。一般的には退職後実際に起業したかまでは追及されることはないので、本当の退職理由を隠しやすいでしょう。
ただし、同じ業界で起業・独立する場合、会社や上司との関係性によっては歓迎されないこともあるため、当たり障りのない別の退職理由を伝えるのがよいケースもあります。
結婚に伴い転居する
結婚による転居など、ライフスタイルの変化による退職は会社が引き止めにくく、確実に退職しやすい理由です。さらに、具体的な転居日を伝えることで、その日までに確実に退職せざるを得ない状況を作ると会社にも納得してもらいやすくなります。
ただし、退職理由が転居だからといって、就業規則や民法上の申し出期限を過ぎてから退職を伝えるとトラブルになることがあるので注意しましょう。退職理由にかかわらず、期限までに伝えることが重要です。
家族の都合で退職せざるを得ない
配偶者や両親、親戚などと暮らすために転居が必要になった場合も、会社は引き止めにくい退職理由です。プライベートな事情が含まれるため、詳しい質問をされにくい傾向にあります。
例えば、配偶者の転勤についていく場合や、両親の介護などが挙げられます。特に家族の病気は緊急性が高く、速やかに退職しやすい理由の一つです。
一身上の都合
退職理由を深く聞かれない場合や、嘘をつきたくない場合は「一身上の都合」で貫く方法もあります。そもそも退職理由を詳しく伝える法的義務はなく、一般的に自己都合で退職する際は「退職願」に「一身上の都合」と書くので矛盾もありません。
ただし、退職願に「一身上の都合」と書いても、上司に退職を申し出たときに詳しい理由を聞かれる可能性は否定できません。ある程度具体的な理由を話さないと、退職日まで気まずい雰囲気で過ごさなければいけなくなる可能性があることに注意しましょう。
上司に聞かれたときは、「転職する」「実家に帰る」など具体的な退職理由を簡潔に伝えるのが無難です。
確実に退職したいときに避けたい退職理由
ここでは、確実に退職したいと考えているなら、避けたほうがよい退職理由を紹介します。
給与など待遇への不満
「給与が少ない」「住宅手当がない」など、給与や福利厚生に関する不満は確実に退職したいときの退職理由として避けたほうがよいでしょう。待遇は会社側で改善できてしまうため、「改善するから残ってほしい」と引き止められやすいためです。
待遇への不満を理由にすると引き止められやすいだけでなく、現状に不満があることがバレてしまうため、会社や上司と気まずい雰囲気のなか退職することになる可能性もあります。実際には不満がある場合でも、確実に退職したい場合は退職理由として正直に伝えるのはおすすめしません。
人間関係に関する不満
「〇〇さんと合わないから」など、上司や同僚に対する不満も確実に退職したい場合の退職理由には向きません。待遇面と同様に、職場環境も会社側で改善しやすく、異動などの改善策を提示されて退職を引き止められることがあるためです。
退職理由が人間関係に関する不満だと、本人の耳に入った場合に気まずい雰囲気になったり、トラブルに発展したりすることも考慮しなくてはいけません。そのため、待遇への不満と同様に、人間関係を退職理由にするのもスムーズに退職したいときは避けたい退職理由です。
会社の方針に対する批判
会社の経営方針に対する批判や不満は、会社や上司に悪い印象を与えかねません。
場合によっては会社と対立することになり、円満退社が難しくなることもあります。スムーズに退職したい人は本当の理由を隠し、「転職するから」など別の理由をつけるのが無難です。
仕事内容に関する不満
「自分に合っていない」「やりがいがない」など、仕事内容に関する不満も、確実に退職したいときは避けたい退職理由です。部署異動など、職場環境を変えると改善する理由であれば、会社や上司に引き止められる可能性があります。
仕事内容に意義を見出せない場合、正直に伝えてしまうと印象が悪いまま退職することになってしまい、退職後に影響することもおすすめできない理由の一つです。
体調不良
「体調が悪いから」と嘘をついて退職しようとすると、休職を勧められることがあるため、確実に退職したい場合は避けたほうがよいでしょう。
実際に体調不良で仕事を続ける選択肢もある場合は、休職後の復帰を待ってくれることもあるため、正直に現状を伝えることも大切です。
一方、嘘をついて体調不良を理由にする場合、周囲の人から心配されることがあるため、退職日まで辻褄合わせをすることになり罪悪感やストレスを感じやすいかもしれません。
嘘の退職理由でスムーズに退職する際のポイント
確実に退職するために嘘の退職理由を伝える際は、いくつかのポイントを押さえる必要があります。
ポジティブな理由を伝える
本当の退職理由を話したくない、話さないほうが良いと判断した場合は、できるだけポジティブな理由を伝えると会社から引き止められにくいでしょう。
例えば、「新たな業界に挑戦するため」「スキルアップするため」など、周囲も納得しやすく円満退社を実現できる理由がおすすめです。
詳細は極力話さない
嘘の退職理由を伝えるときは、できるだけ詳細を話すのを避けると嘘だとバレにくくなります。
退職理由を詳しく聞かれると、「聞かれた分だけ答えなければいけない」とさらに嘘を重ねてしまい、辻褄が合わなくなって嘘がバレてしまうことがあります。退職理由は簡潔に伝えるだけにとどめ、詳細を聞かれても「家庭の事情で」「まだ全然決まっていなくて」など濁すと相手も踏み込みにくいでしょう。
仲の良い同僚にも本当の理由は話さない
会社や上司に嘘の退職理由を伝えた場合、周囲の人にも本来の退職理由を隠しておくと、不要なトラブルを避けやすくなります。
仲の良い同僚には本当の理由を話したくなるかもしれませんが、どこから情報が漏れて嘘がバレるかわからないので、誰にも話さないほうがスムーズに退職できます。同僚に深入りされて嘘がバレるリスクを減らすため、嘘の退職理由も極力伝えないほうが無難な選択です。
話に一貫性を持たせる
嘘の理由で退職する際は、嘘の内容に一貫性を持たせることが重要です。その場しのぎで嘘を重ねると、矛盾が生じて嘘がバレる可能性があります。
例えば、上司には「家族の介護のために転居する」と伝えたのに、同僚には「配偶者の転勤についていく」と別の理由を伝えてしまうなど、内容が異なったり矛盾が生じてしまったりすると不信感を持たれてしまいます。
嘘をつく場合は誰に対しても同じ嘘の理由を伝えるようにして、矛盾が生じないように注意しましょう。
退職後のことも考慮した理由にする
通常であれば、退職してしまえば会社に退職理由を詮索されることはありませんが、生活圏で会社の関係者に会う可能性がある場合は注意が必要です。例えば、近所に同僚が住んでいる状況で転居を理由にする場合、退職後に同じ場所に住み続けていると再開したときに不審に思われる可能性があります。
特に転居を伴う嘘の退職理由を伝えるときは、同じ業界や職種で転職後に会社の関係者と再開する機会が出てくる可能性があり、嘘がバレる原因になります。退職後に嘘の退職理由だったとバレたとしても法律上の問題はありませんが、仕事で付き合いが続くときは悪い印象を与えかねません。
確実に退職したいときの注意点
確実に退職したいときは、退職を伝えるタイミングや退職日、退職までのマナーなど注意したいポイントが多数あります。なかでも、スムーズに退職するために押さえておきたい注意点を取り上げて解説します。
就業規則で定められた申告期限にしたがって退職を伝える
雇用期間の定めがない場合や、雇用期間が5年を経過して雇用されているときなど、民法上は退職日の2週間前までに申し出れば退職できます。
しかし、実際は会社ごとに就業規則で退職を申し出る期限が決まっていることが多いのが実情です。法律上2週間前でもペナルティはないが、トラブルなく確実に退社したいなら就業規則に従うのがよいでしょう。
繁忙期と重ならないようにする
法律上、労働者は条件を満たせば自由に退職できるため、退職日を会社の都合に合わせる必要はありません。しかし、繁忙期と重なってしまうと繁忙期が終わるまで会社に残って欲しいと引き止められる可能性があります。
確実に退職したい人のなかでも、退職時期にこだわりがない場合は、会社の繁忙期や年度末、年度始めなど人の入れ替わりが激しい時期を避けると、スムーズに退職しやすくなります。
引き継ぎや退職の挨拶をきちんと済ませる
本音では会社や上司に不満があったとしても、引き継ぎや挨拶をきちんと済ませてから退職することが重要です。特にお世話になっている人やチームメンバーなどには、直接退職を報告するようにしましょう。
業務や挨拶が中途半端なまま退職してしまうと、「無責任」「マナーがない」といった印象を与えてしまう可能性があります。もう会うことはないと思っていても、退職後に再会したり仕事で付き合いができたりすることがあるため、引き継ぎや挨拶はきちんと済ませてから退職しましょう。
会社や上司への不満は言わない
本当の退職理由が会社や上司に対する不満でも、退職する際に上司や同僚など周囲の人に言うのは避けましょう。
不満を伝えたことで事実とは異なる噂が流れたり、問題が大きくなったりする可能性もあるため、確実に退職したいなら会社の不満は口にしないのが無難です。
退職後も同じ業界内で転職する際は嘘をつきすぎない
退職理由で嘘をついても法的なペナルティはありませんが、嘘の内容によっては再就職後に悪影響が出る可能性も理解しておきましょう。
特に、同じ業界や職種で転職活動をする場合は再就職後の会社が取引相手になるなど、退職後も関係が続くことがあります。嘘をつきすぎると、後々辻褄わせができなくなって自分が困ることになるため、ほどほどにしておきましょう。
退職を決めてから退職後の手続きまでの流れ

ここからは、退職を決意してから退職後までにやることの流れを解説します。
ステップ1:退職を伝える準備をする
退職を決めたら、まずは退職を申し出るタイミングを決めます。
民法上は退職日の2週間前までに申し出が必要ですが、会社によっては就業規則で申し出の時期が決められていることがあります。就業規則に法的な拘束力はないが、円満退社するには就業規則に沿って申し出のタイミングを決めましょう。
退職を伝えるときに併せて退職願を提出する場合は、書類の準備も進めておきます。
ステップ2:退職を申し出る
退職の意思を伝える順番は、最初に直属の上司、次はさらに上の役職の上司や人事部など必要に応じて報告していきます。退職を伝えるときは、口頭あるいはメールなどであらかじめ直属の上司にアポイントメントを取ったうえで伝えましょう。
法的な決まりはありませんが、自己都合退職の場合は退職願を持っていくと確実に退職する意思を伝えやすくなります。また、就業規則で退職願の提出が決められていることもあるため、事前に確認しておくと確実です。
ステップ3:退職日までに業務の引き継ぎを行う
退職日までに業務の引き継ぎが必要な場合は、後任の人や同じチームの人などに業務手順や進捗状況を伝える作業を行います。
具体的な後任者がなかなか決まらない場合は、書面でまとめておくと直前になってばたつくことなくスムーズに退職しやすいでしょう。中途半端なまま退職することがないよう、スケジュールに余裕を持って引き継ぎ業務を進めることが大切です。
ステップ4:最後の出社日に挨拶する
無事に最後の出社日を迎えたら、退勤時間までに上司や同僚に挨拶します。勤務時間中に部署を回って挨拶する場合は、事前に上司に相談して許可を取っておくとトラブルなく進められます。
取引先など社外の人へ挨拶するタイミングは、必ず上司と相談しましょう。直接会って挨拶できない場合は、メールなどで連絡することも可能です。
転職後に会うことになる可能性もあるので、退職の挨拶をしておくことで良い印象を残せるでしょう。
ステップ5:すぐに転職しない場合は退職後に会社から離職票を受け取る
退職後、再就職する予定だが転職先が決まっていない場合は、一定の条件を満たすと失業保険を受給できます。再就職までの生活を安定させるためにも、受給手続きを進めておくと安心です。
失業保険をもらうときは、退職後に会社から離職票を受け取る必要があります。会社に離職票の発行を依頼すると、退職日から1週間〜2週間程度で自宅に郵送されるてくるのが一般的です。
ステップ6:ハローワークで失業保険の受給手続きを行う
離職票が届いたら、以下の必要書類を持って速やかにハローワークで失業保険の受給手続きを行います。
- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険被保険者離職票-1、-2
- 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
- 本人確認書類(マイナンバーカードがない場合)
- 顔写真2枚
- 本人名義の預金通帳やキャッシュカード
ステップ7:失業保険を受給しながら求職活動を行う
失業保険の受給手続きが完了して受給が決定したら、決められた回数以上の求職活動を行います。ここで言う求職活動とは、求人への応募やハローワークが開催する各種講習の受講などです。
求職活動をしないと失業保険の受給が止まってしまうことがあるので、ハローワークの指示に従って活動しましょう。
ステップ8:再就職する
失業保険をもらいながら求職活動し、無事再就職が決まった場合は、再就職手当や就職促進定着手当などの就業促進給付を受けられる可能性があります。
まとめ
法律上は理由を問わず退職できますが、確実に退職したい場合は職場の雰囲気や今後の人間関係を考え、引き止められにくい理由を選ぶことが大切です。嘘の理由を伝えるときは、バレた際のリスクや精神的な負担も考慮しながら、ポジティブかつシンプルに伝えるのが無難でしょう。
また、「辞めること」だけでなく、「辞めた後の生活」を安心して送れるよう準備することも重要です。退職後は収入が途切れる不安もあるため、失業保険や各種給付金の制度を上手に活用しましょう。
もし複雑な手続きが不安な方は、受給をサポートしてくれる「社会保険給付金サポート」の利用もおすすめです。退職に関する不安や悩みを解消し、その後の手続きを丁寧にサポートします。相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼

 給付金がいくらもらえるか
知りたい方
給付金がいくらもらえるか
知りたい方 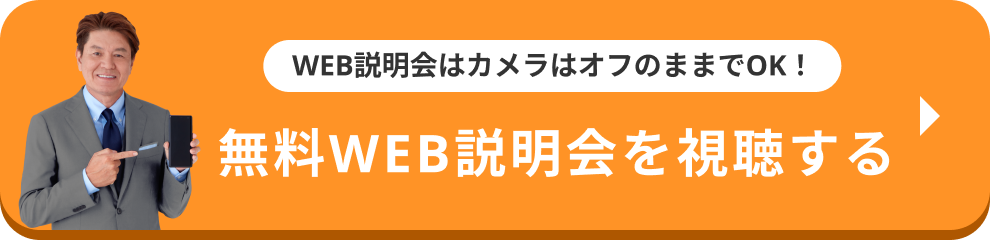
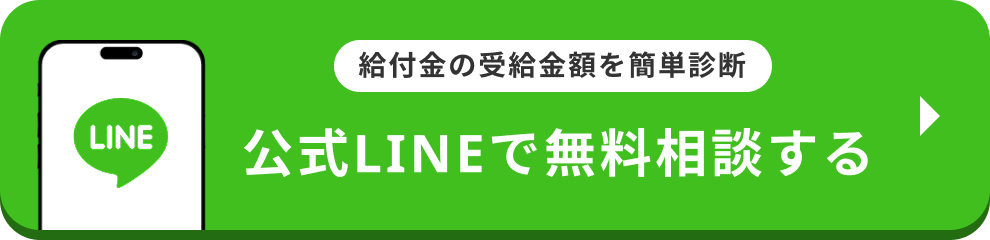
 給付金サポートを
ご検討中の方
給付金サポートを
ご検討中の方  評判・口コミ
評判・口コミ  給付金がもらえる
転職支援を活用する方
給付金がもらえる
転職支援を活用する方  その他退職について
ご不安がある方
その他退職について
ご不安がある方  もらえる給付金ラボ
もらえる給付金ラボ  退職コンシェルジュについて
退職コンシェルジュについて