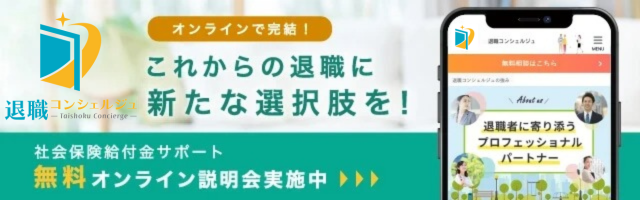退職後に必要になる書類
退職したらやることによって、用意する必要書類が異なります。書類の入手先もそれぞれ異なるため、事前にどこでもらえるか把握しておくことが重要です。
ここでは、退職後に必要になる書類を会社から受け取るものと、自分で用意するものに分けて解説します。
退職する会社から受け取る書類
退職後の手続きに必要な書類のうち、離職する際に会社からもらう書類は主に以下のとおりです。
| 書類の種類 | 入手可能な時期 | 必要となる手続き |
| 雇用保険被保険者証 | 退職前後 | 失業保険の手続き
再就職先への提出 |
| 健康保険資格喪失証明書 | 退職後1週間程度 | 健康保険の切り替え手続き
国民年金の切り替え手続き |
| 年金手帳または基礎年金番号通知書 | 退職前後 | 国民年金の切り替え手続き |
| 雇用保険被保険者離職票 | 退職後1週間〜2週間程度 | 失業保険の手続き |
| 源泉徴収票 | 退職後1か月程度 | 所得税の精算 |
雇用保険被保険者証と年金手帳は会社に預けている場合があり、手元にない場合は退職時に返却されたか確認が必要です。年金手帳は令和4年に廃止されているため、それ以降に年金に加入した人は基礎年金番号通知書が発行されています。
上記の書類以外に、再就職先から求められた場合は「退職証明書」も発行してもらう必要があります。退職証明書は依頼されない限り会社が自主的に発行することはないため、必要な場合は退職する会社へ依頼が必要です。
自分で用意する書類
退職後に必要な書類のうち、自分で用意するものは以下のとおりです。
- 本人確認書類
- マイナンバーカード、または個人番号通知書など個人番号がわかる書類
- 印鑑
- 預金通帳やキャッシュカード
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
前述のとおり、年金手帳や基礎年金番号通知書、雇用保険被保険者証は会社保管ではなく自分で保管している場合もあります。手元にある場合は、事前に準備しておくと退職後の手続きをスムーズに進めることが可能です。
なお、預金通帳やキャッシュカードは失業保険の受け取りや健康保険料の口座振替などで必要になることがあります。
【退職したらやること①】失業保険の申請
一定の条件を満たす場合、退職後に失業保険をもらえることがあります。
失業保険の申請期限は離職日の翌日から1年間が基本で、短期雇用特例被保険者は6か月間です。失業保険を申請する場合は、期限内に住所地を管轄するハローワークの窓口で求職申込みの手続きを行います。
失業保険は申請から支給が開始されるまでに時間がかかるため、できるだけ早く受給するには、前職の会社から離職票が届いたら速やかに手続きする必要があります。
失業保険の申請には、以下の書類が必要です。
- 雇用保険被保険者証
- 離職票
- マイナンバーカード(または個人番号が確認できる書類)
- 本人確認書類
- 写真(縦3.0cm×横2.4cm)2枚
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
退職後の再就職先が決まっている場合
退職後の就職先が決まっている場合は、失業保険を受け取れません。そのため、再就職先が決まっている人は失業保険の手続きは不要です。
退職時に再就職先が決まっていない場合
失業保険は失業手当とも呼ばれ、失業したときに求職活動する間の生活を安定させるために給付される「雇用保険の基本手当」を指します。
退職時に再就職先が決まっておらず、以下の条件を満たしている人は失業保険を受け取れる可能性があります。
- 原則として、退職前2年間に12か月以上雇用保険の被保険者になっていた期間があること
- 現在失業中であること
- 積極的に就職する意思があること
- いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること
ただし、会社の倒産や解雇など会社都合による退職の場合は、雇用保険の被保険者期間が離職前1年間に6か月以上が条件で、受給額や受給期間が自己都合退職と比べて緩和されます。
退職理由が会社都合の場合は、受給開始までの期間も優遇されており、受給資格の決定後7日間の待期期間を経て支給されます。
自己都合での退職でも失業保険はもらえますが、7日間の待期期間後に1か月の給付制限期間があるため、受給開始は会社都合の場合より遅くなる点に注意が必要です。
【退職したらやること②】国民年金の切り替え手続き
退職後、厚生年金から国民年金への切り替え手続きが必要になるケースがあります。
国民年金への切り替えが必要な場合は、年金手帳または基礎年金番号通知書を持って、退職日の翌日から14日以内に住所地の市区町村役場で手続きを完了させます。万が一遅れてしまった場合でも、速やかに役場で手続きしましょう。
国民年金は以下の3つに区分され、退職後すぐに再就職する場合と、再就職まで期間が空く場合で、必要な手続きが異なります。
| 区分 | 該当する人 |
| 第1号被保険者(国民年金) | 個人事業主・学生・主婦・無職の人など |
| 第2号被保険者(厚生年金) | 会社員・公務員 |
| 第3号被保険者 | 厚生年金加入者に扶養されている配偶者 |
退職後すぐ再就職する場合
退職後に離職期間なく再就職する場合は、厚生年金に加入し続けることになるため、切り替え手続きは不要です。
ただし、離職期間が1日以上ある場合は国民年金への加入手続きが必要になります。退職した月や翌月に再就職する場合でも、離職期間が1日でもあれば国民年金に加入する必要がある点に注意しましょう。
例えば、3月末に退職して翌月16日に再就職した場合、3月31日までは第2号(厚生年金)ですが、4月1日〜4月15日までは第1号(国民年金)、再就職した16日以降は第2号(厚生年金)となります。つまり、4月1日から14日以内に第1号(国民年金)へ切り替える必要があります。
再就職しない、あるいは再就職まで期間が空く場合
退職後に再就職しない場合や再就職まで期間が空く場合は、国民年金への切り替えが必要です。具体的には、退職後に無職になる人や学生、主婦などが該当します。退職後に個人事業主として開業する場合も、国民年金に加入する必要があります。
厚生年金に加入している配偶者の扶養に入る場合は、第1号(国民年金)ではなく第3号になるため、配偶者の会社で加入手続きをします。
退職後の再就職先が決まらず収入がなくなり、国民年金保険料の支払いが難しい場合は、必要に応じて一部免除または全額免除の手続きができます。前年度の所得金額によっては保険料納付猶予制度も活用できるため、支払いが難しい場合は条件を満たすか確認しましょう。
免除や納付猶予を利用しても10年以内であれば追納が認められているため、将来もらえる年金額を減らすことなく、失業中の負担を抑えることも可能です。
【退職したらやること③】健康保険の切り替え手続き
在職中に加入していた健康保険は退職日の翌日から使えなくなるため、退職後は新しい保険への切り替え手続きを行います。手続きは退職後に再就職するまでの期間や、どの健康保険に加入するかなど、個々の状況によって異なります。
健康保険を切り替えるときに必要な書類は、以下のとおりです。
- 健康保険資格喪失証明書
- マイナンバーカード(または個人番号がわかる書類)
- 本人確認書類
- キャッシュカードまたは通帳、印鑑
退職後すぐ再就職する場合
退職後、離職期間なしですぐに再就職する場合は、再就職先で健康保険に加入します。会社が保険の切り替え手続きを行ってくれるため、自分で手続きする必要はありません。
再就職先に入社後、前職を退職後にもらえる「健康保険資格喪失証明書」を提出すると会社が手続きを進めてくれます。
退職後に離職期間が発生する場合
退職後、すぐに再就職せず離職期間が発生する際の健康保険の手続きとして、次の3つのパターンが挙げられます。
- 国民健康保険に加入する
- 任意継続被保険者制度を利用する
- 家族の扶養に入る
再就職先が決まっていない場合や個人事業主として開業する場合は、基本的に国民健康保険への切り替えが必要です。退職日の翌日から14日以内に、市区町村役場で加入手続きを行います。
国民健康保険に切り替える以外に、退職後も前職の健康保険に加入し続ける「任意継続被保険者制度」の利用も可能です。
特に扶養家族がいる場合、国民健康保険は扶養家族分の保険料が必要になるため、退職前より負担が重くなるケースがあります。任意継続被保険者制度を利用すれば、退職前と同様に扶養家族の保険料がかからないことがメリットです。
ただし、退職前は事業所と保険料を折半していたのに対し、退職後は全額負担になります。任意継続被保険者制度を利用するときは、原則として退職日の翌日から20日以内に手続きが必要です。
退職後、家族の健康保険に扶養家族として入る場合は、原則5日以内に手続きします。扶養家族と認められるためには、同居の有無や収入などの条件を満たす必要がある点にも注意しましょう。
退職に伴い所得が減少し、健康保険料の支払いが困難と認められると減免してもらえる可能性があります。減免には手続きが必要なため、まずは市区町村役場の窓口で相談しましょう。
【退職したらやること④】住民税の支払い
退職や再就職のタイミング、納付方法の選択によっては、退職後の住民税を自分で納付する必要があります。住民税の納付方法は、以下の2種類です。
- 特別徴収
- 普通徴収
住民税の特別徴収とは、会社の給与から天引きにより納付する方法です。給与所得以外の収入がない会社員であれば、基本的には特別徴収で住民税を納めます。
一方、普通徴収とは自分で市区町村に納付する方法です。退職後に再就職が決まっていない人や確定申告している会社員、個人事業主などが対象となります。
退職後1か月以内に再就職する場合
退職した月や翌月中に再就職することが決まっている場合は、再就職先でも退職前と同様に給与から天引きしてもらえます。
ただし、前職の会社から再就職先に「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を送付してもらうか、自分で受け取って再就職先に提出する必要があります。届出しない場合は前職の会社により普通徴収へと切り替えられ、市区町村から住民税の納付書が送られてくるため、自分で納付することも可能です。
再就職まで1か月以上空く場合
退職後すぐに再就職しない場合は、退職のタイミングによって住民税の支払い方法が異なります。
| 退職の時期 | 支払いの対象となる期間 | 支払い方法 |
| 1月〜4月 | 退職月から5月分まで | 最後の給与・退職金から一括徴収で天引き |
| 5月 | 5月分 | 最後の給与・退職金から天引き |
| 6月〜12月 | 再就職するまで | 普通徴収 |
退職後は前職の会社が普通徴収への切り替え手続きを行うため、自分で切り替え手続きする必要がありません。普通徴収に変更後、市区町村から送られてきた納付書に従い住民税を納めます。
【退職したらやること⑤】所得税の精算
会社員は基本的に毎月の給与から概算の所得税が天引きされ、年末調整で払い過ぎや不足分を調整します。
しかし、退職後に年末調整の機会がない場合、自分で所得税を申告して納付する必要があります。
退職した年の年末までに再就職した場合
退職した年の年末までに再就職した場合は、再就職先で年末調整してもらえれば自分で申告する必要はありません。前職でもらった源泉徴収票を再就職先に提出すると、年末調整で精算してもらえます。退職する際にもらった源泉徴収票は、年末調整まで大切に保管しましょう。
退職後、しばらく経っても源泉徴収票が送付されてこないときは、前職の会社に確認が必要です。
再就職が翌年以降になる場合
退職した年の翌年以降に再就職する場合や個人事業主として開業した場合、再就職先で年末調整できなかった場合は確定申告で所得税を精算します。
確定申告の申告期限は、退職した年の翌年2月16日から3月15日の間です。所得税の納付が必要な場合、申告が遅れると延滞税が課せられることがあるため、事前に必要書類を準備して余裕を持って手続きを進めましょう。
退職したらやることをスムーズに進めるためのポイント

退職したらやるべきことは多岐にわたるため、ついつい手続きを忘れてしまうことがあるかもしれません。
万が一忘れてしまうと、税金に延滞税がかかったり失業保険の受給時期が遅れたりすることがあるため、スムーズに手続きを進めることが重要です。
退職前に必要書類を準備しておく
退職したらやることのなかには、退職前から準備できるものもあります。例えば、失業保険の申請に必要な顔写真や、年金の切り替えに必要な年金手帳の準備などです。事前にできるものから始めておくと、退職後に慌てず済みます。
特に「離職票」や「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」「退職証明書」など、会社に依頼しないともらえない書類は、退職前に必要かどうか確認しておきましょう。
事前準備には、自分に必要な書類がいつどこでもらえるかを把握し、余裕を持って準備しておくことが大切です。
手続きの期限を把握しておく
各手続きには期限が設けられているため、何をいつまでにやるかを決めておくことが重要です。期限を把握したうえで、優先順位を付けるとスムーズに手続きを進められます。
期限を過ぎてしまった場合でもそのままにせず、各手続きを管轄している機関の窓口に相談して速やかに対処しましょう。
退職サポートを活用する
退職後に必要な手続きの種類は多く、揃えなければならない書類や手続きの手順も複雑です。
自分で進めることが難しい場合は、退職サポートを利用するのも一つの方法です。専門知識を持つスタッフにサポートしてもらうことで、失業保険などの利用できる制度をもらさず確実に活用できるようになります。
まとめ
退職したらやることには、失業保険の申請や年金・健康保険の切り替え、税金の支払いなどがあります。手続きをスムーズに進めるためには、事前にどのような手続きが必要か把握しておくことが重要です。
ただし、退職のタイミングや再就職の有無によって、必要な手続きや提出書類が異なります。複数の手続きを並行して行う必要があるため、時間や労力がかかる点にも注意が必要です。
「どの手続きが自分に必要なのかわからない」「内容が複雑で不安」と感じる方は、「社会保険給付金サポート」の活用を検討してみてはいかがでしょうか。条件に応じて、失業保険や健康保険の給付金を受け取れる可能性があります。専門知識を持つ担当者が手続きを丁寧にサポートしますので、まずはお気軽にご相談ください。

 給付金がいくらもらえるか
知りたい方
給付金がいくらもらえるか
知りたい方 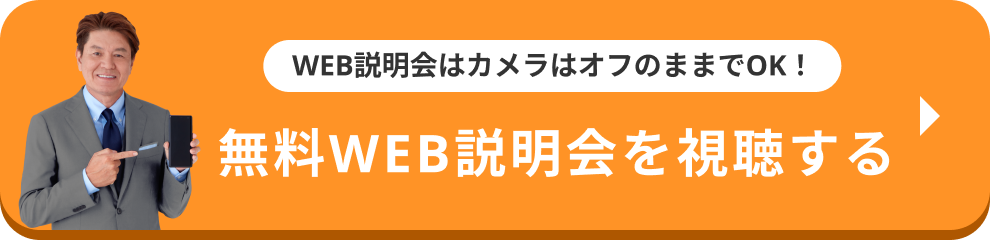
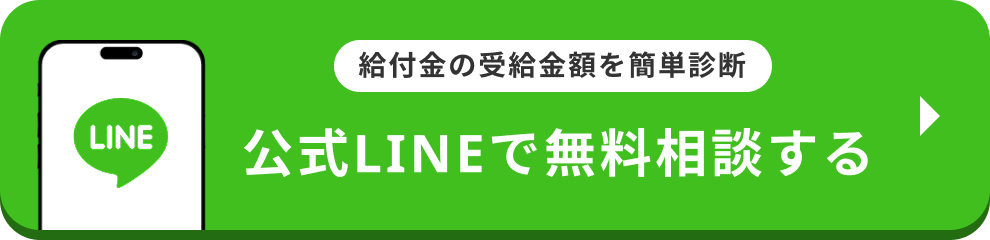
 給付金サポートを
ご検討中の方
給付金サポートを
ご検討中の方  評判・口コミ
評判・口コミ  給付金がもらえる
転職支援を活用する方
給付金がもらえる
転職支援を活用する方  その他退職について
ご不安がある方
その他退職について
ご不安がある方  もらえる給付金ラボ
もらえる給付金ラボ  退職コンシェルジュについて
退職コンシェルジュについて