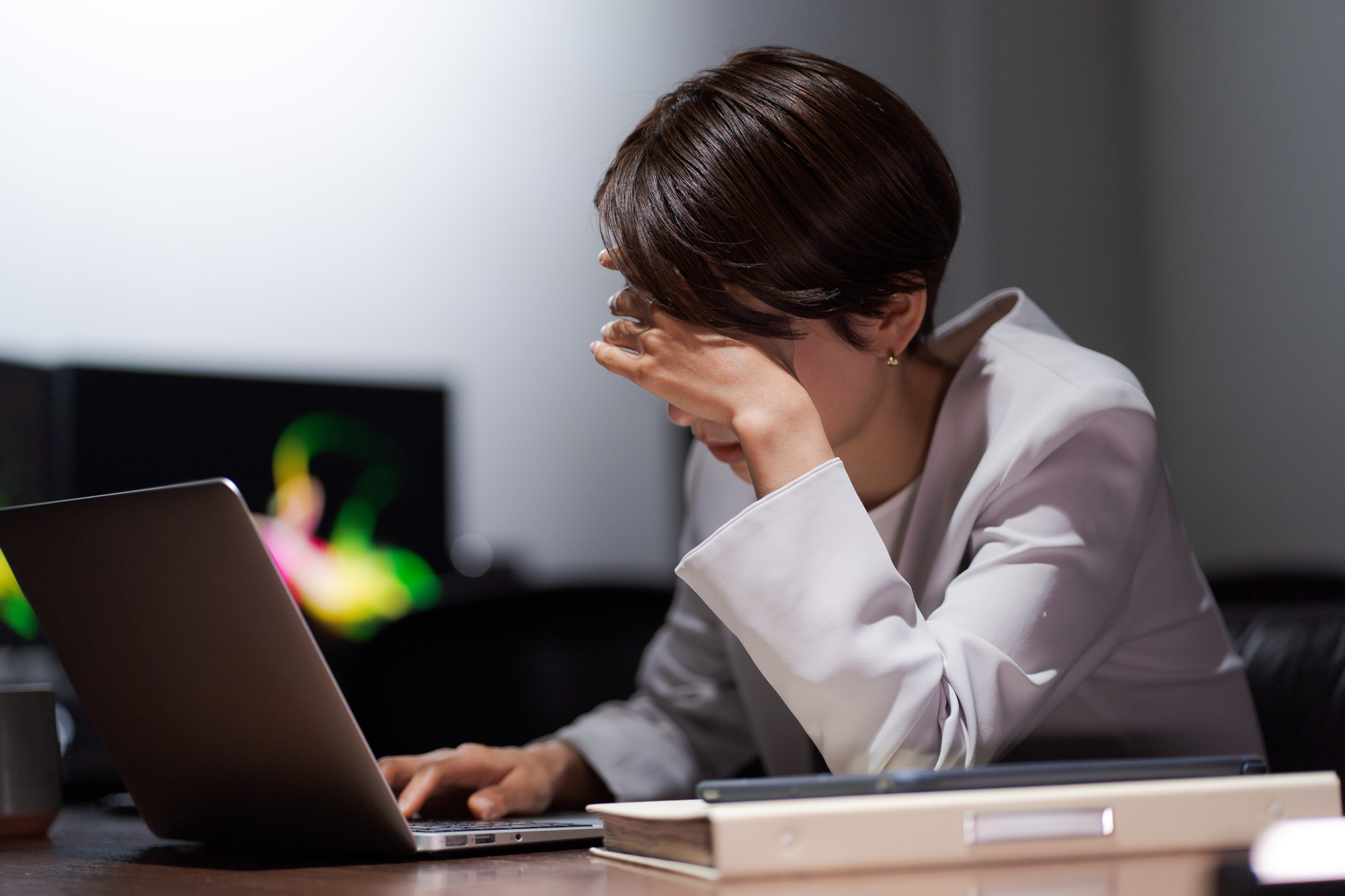2025.09.02
失業保険について
仕事を辞めてもらえるお金15種類!もらう際の注意点も解説

仕事を辞めてもらえるお金にはどのようなものがあるのか気になる方も多いでしょう。退職後に受け取れるお金は、失業保険をはじめ、職業訓練受講給付金や住居確保給付金など多岐にわたります。
ただし、制度ごとに申請先や期限、受給条件が異なるため、情報を整理しないと受け取り漏れが起こりかねません。
本記事では、雇用保険の加入有無や退職理由に応じて利用できる全15種類の給付制度を一覧で整理し、それぞれの特徴と申請ポイントをわかりやすく解説します。
仕事を辞めてもらえるお金とは

仕事を辞めた後にもらえるお金には、複数の種類と呼び名があります。なかには内容が似ていて混同されやすいものもあるため、それぞれの違いを正しく理解しておくことが大切です。ここでは、退職給付金の言葉の意味や、退職金・失業保険との違いについて解説します。
退職給付金について
退職給付金とは、従業員が退職した際に支給される金銭全般を指す言葉です。退職給付金の制度は企業ごとに内容が異なり、勤務年数や在籍中の役職、就業規則などによって支給の有無や金額に差があります。
退職給付金は、退職後の生活費や将来の備えとして役立つ資金です。退職前に自分が該当するかどうか、会社の制度を確認しておきましょう。
退職金や失業保険との違い
退職給付金は、企業が支給する退職時の金銭的給付全般を指し、退職金や失業保険とは目的や支給主体が異なります。
退職金は企業が独自に設ける制度で、長年勤めた社員への慰労金や功労金として支給されるのが一般的です。一方、失業保険は国の雇用保険制度に基づく給付金であり、離職後に就職活動をしている方に支給されます。
退職金と失業保険は目的と支給条件、申請先がすべて異なるため、それぞれを理解して適切に申請・受給しましょう。
仕事を辞めてもらえるお金の一覧
退職後に利用できる給付制度は、雇用保険に加入していたかどうかや、退職の理由・生活状況によって適用範囲が異なります。以下の表では、それぞれの制度が誰を対象にしているのか、どのような内容で支給されるのかを簡潔にまとめています。
|
雇用保険加入要否 |
支給対象 |
主な内容 |
|
|
失業保険(基本手当) |
必要 |
離職者 |
再就職までの生活支援 |
|
傷病手当 |
必要 |
病気やケガで求職困難な方 |
失業保険の代替として支給される手当 |
|
技能習得手当・寄宿手当 |
必要 |
職業訓練受講者 |
通所・宿泊に関する補助(1日500円〜) |
|
高年齢求職者給付金 |
必要 |
65歳以上の離職者 |
一時金(30日または50日分)として支給 |
|
特例一時金 |
必要 |
短期・季節労働の離職者 |
40日分の基本手当日額を一括支給 |
|
日雇労働求職者給付金 |
必要 |
日雇労働者 |
最大7,500円/日(印紙枚数により変動) |
|
教育訓練給付金 |
必要 |
教育訓練受講者 |
受講費の20〜80%(上限224万円※4年制の専門実践教育訓練を受講する場合)補助 |
|
広域求人活動費・移転費 |
必要 |
遠方で求職・転居する方 |
交通費・引越費用の一部補助 |
|
再就職手当 |
必要 |
早期就職した人 |
残支給日数の60〜70%を支給 |
|
職業訓練受講給付金 |
不要 |
雇用保険未加入者 |
月10万円+交通費や住居費を支給 |
|
求職者支援資金融資 |
不要 |
生活困難な訓練受講者 |
最大月10万円を無利子貸付(返済必要) |
|
住居確保給付金 |
不要 |
離職者・収入減者 |
市区町村ごとに定める額を上限に家賃を最大9か月まで支給 |
|
退職手当(退職金) |
不問 |
企業勤続者 |
勤続年数に応じた報酬(企業により異なる) |
|
傷病手当金 |
不問 |
健康保険加入者 |
就労不能時に標準報酬月額の2/3を支給 |
|
未払賃金立替払制度 |
不問 |
倒産企業の退職者 |
未払い賃金の80%(年齢別上限あり)を国が支給 |
仕事を辞めてもらえるお金9選【社会保険に加入していた人】
仕事を辞めたあとにもらえるお金には、さまざまな種類があります。それぞれ名称や制度内容が異なるため、混同しないように整理して理解することが大切です。ここでは、社会保険に加入していた方が退職後に受け取れる公的給付金を9種類紹介します。
失業保険(基本手当)
失業保険(基本手当)は、仕事を辞めた方が再就職するまでの生活を支えるための給付金です。
雇用保険に一定期間加入していたことが条件で、原則として離職前2年間に通算12ヶ月以上の被保険者期間が求められます。
申請はハローワークで行い、「求職の意思と能力があること」「就職活動をしていること」が支給の条件です。給付日数や金額は、離職理由・年齢・勤続年数・賃金によって異なります。
傷病手当
傷病手当は、病気やケガで就職活動ができない場合に、失業保険の代わりに支給される給付金です。対象者は、失業保険の受給資格がある方のうち、病気や負傷によって15日以上求職活動が困難となった方です。
手当の日額は、失業保険と同額が支給されます。また、30日以上継続して働けない場合は、受給期間を最大4年間まで延長可能です。申請はハローワークで行い、医師の診断書など必要書類を提出します。
体調不良が原因で職探しができない場合は早めにハローワークに相談し、手続きを進めましょう。
技能習得手当・寄宿手当
技能習得手当・寄宿手当は、職業訓練に参加する方が経済的に困らずに学べるよう支援する制度です。再就職を目指す方が新たなスキルを習得するための訓練を受ける際、その通所にかかる費用や生活費負担が障壁にならないよう補助されます。
対象となるのは、ハローワークにて求職申し込みを行い、公共職業訓練などの条件を満たして訓練を受講している方です。支給される手当は3種類に分かれており、それぞれの支給内容は以下のとおりです。
|
内容 |
上限額 |
|
|
受講手当 |
訓練を受けた日数に応じて支給 |
1日500円(最大20,000円) |
|
通所手当 |
訓練施設までの交通費 |
月額42,500円まで |
|
寄宿手当 |
自宅から通えない場合の宿泊費 |
月額10,700円 |
訓練期間中の生活を安定させ就職の選択肢を広げるためにも、条件に該当する方は技能習得手当・寄宿手当の利用を積極的に検討しましょう。
高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金は、65歳以上で離職した方が受け取れる一時金です。通常の失業保険(基本手当)は64歳までを対象としていますが、高齢者でも雇用保険の被保険者であれば一定の条件を満たすことでこの給付金を受け取れます。
高年齢求職者給付金の制度は、雇用保険に加入していた高齢者が離職後も自立した生活を送れるよう支援することが目的です。対象者には、離職時に雇用保険の被保険者であり、ハローワークに求職申し込みをしていることが求められます。
支給額は、通常の失業手当1日分にあたる基本手当日額に所定の給付日数(30日または50日)を掛けた金額です。所定給付日数は、被保険者であった期間が1年以上なら50日、6ヶ月以上1年未満なら30日となります。
特例一時金
特例一時金は、短期的または季節的に雇用される方が失業した場合に支給される給付金です。安定的な雇用に就くことが難しい労働者の生活を支援することを目的としています。
対象となるのは、短期特例被保険者として登録されており、離職日以前の1年間に通算6ヶ月以上の被保険者期間がある方です。農業や建設、スキー場など、季節的な仕事に従事していた方が該当します。支給額は、基本手当日額×40日分で、一括して支給されます。
特例一時金は、離職日の翌日から6ヶ月以内にハローワークで手続きを行わなければ受給できないため、早めの対応が必要です。
日雇労働求職者給付金
日雇労働求職者給付金は、日雇い労働者が失業したときに受け取れる給付金です。日々単発の仕事で生活を支えている方が対象で、一般的な雇用保険の仕組みとは別に設けられた制度です。
日雇労働求職者給付金の制度を利用するには、あらかじめ日雇労働被保険者手帳(日雇手帳)」の交付を受け、印紙付きの雇用保険料が所定枚数分貼付されている必要があります。具体的には、失業した月の前月と前々月の合計で26枚以上の印紙が必要です。
支給金額は、印紙保険料の納付状況に応じて、1日あたり4,100円〜7,500円となります。
教育訓練給付金
教育訓練給付金は、離職者や在職中の方がスキルアップや資格取得を目指す際に、受講費用の一部を国が補助する制度です。再就職を有利に進めたい方や、キャリアの幅を広げたい方を支援するために設けられています。
対象となるのは、雇用保険の被保険者期間が一定以上あり、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講・修了した方です。支給額は受講内容によって異なり、以下の3つの区分に分かれています。
|
支給割合(上限) |
例 |
|
|
一般教育訓練 |
受講費用の20%(上限10万円) |
簿記、TOEIC、宅建など |
|
特定一般教育訓練 |
上限25万円 |
医療事務、保育士など |
|
専門実践教育訓練 |
受講費用の50〜80%(上限最大224万円) |
看護師、介護福祉士など |
再就職や転職に役立つスキルを身につけたい方は、条件を確認のうえ、制度を積極的に活用しましょう。
広域求人活動費と移転費
広域求人活動費・移転費は、求職活動や就職のために遠方へ移動・転居する方を対象とした交通費・引越費用の補助制度です。地域や業種によって求人が限られるなか、職業選択の幅を広げるための支援を目的としています。
広域求人活動費は、複数の都道府県にまたがる求職活動を行う方へ実費の一部を支給する制度です。例えば、東京から大阪の企業に面接に行く場合、交通費や宿泊費の一部が支給されます。条件として、ハローワークに求職登録を行い、事前申請が必要です。
移転費は、就職のために転居を伴う場合に、引っ越しにかかる費用を補助する制度です。支給対象には、内定後に就業地近くへ移動する必要がある方が含まれます。支給額は引っ越しにかかる実費の範囲内で、上限は地域や世帯構成により異なります。
どちらの制度も手続きには見積書や移動履歴の提出が求められ、ハローワークの許可が必要です。
再就職手当
再就職手当は、失業保険の受給期間中に早期に再就職が決まった場合に支給される手当です。失業期間を短縮させ、早期の職場復帰を促進することが目的です。
対象となるのは、基本手当の支給日数が3分の1以上残っている状態で、安定した職業に就いた方です。さらに、過去3年以内に再就職手当を受給していないことなどの要件もあります。
支給額は、残っている支給日数に基本手当日額を掛けた金額の60%または70%です。支給率は、失業後の再就職までの日数や雇用形態によって変動します。
仕事を辞めてもらえるお金3選【社会保険に加入していなかった人】
社会保険に未加入だった方でも、条件を満たせば給付金や融資制度の対象になる可能性があります。ここでは、社会保険に加入していなかった方が利用できる代表的なお金を3つ紹介します。
職業訓練受講給付金
職業訓練受講給付金は、社会保険に未加入だった方でも月10万円の給付金と無料の職業訓練を受けられる制度です。
雇用保険に加入していない求職者や、自営業を廃業した方などを対象としており、収入・資産などが一定以下であれば在職中でも対象になることがあります。具体的には、本人の収入が月8万円以下、世帯収入が一定基準以下であること、かつ職業訓練の全日程に出席することが条件です。
給付金のほか、通所手当(交通費)や寄宿手当(住居費)などの支援も受けられるため、金銭的な不安を抱えずに学び直しやスキルアップを目指せます。
求職者支援資金融資
求職者支援資金融資は、職業訓練受講給付金だけでは生活が難しい方を対象に、最大月10万円を無利子で借りられる融資制度です。
給付金を受給していても生活が苦しい場合、この融資制度を活用すると訓練中の生活費を確保できます。無担保・保証人不要で、月5万円または10万円を上限として訓練期間中に借りることが可能です。
融資を受けるには、ハローワークから要件確認書を取得し、所定の手続きを行う必要があります。貸付利率は年3.0%で、返済義務がある点には注意が必要です。
住居確保給付金
住居確保給付金は、収入の減少によって住居を失うおそれがある方に家賃相当額を支給する制度です。
対象となるのは、主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内であるか、または給与等の収入がそれに準ずる程度まで減少している方です。支給期間は原則3か月(最大9か月まで延長可能)で、実際の家賃額のうち、自治体ごとに定められた上限額までを自治体から家主に直接支払います。
仕事を辞めてもらえるお金3選【その他】
雇用保険に加入していない場合や給付条件を満たさない場合でも、企業からの支給や特定の状況に応じて受け取れるお金があります。ここでは、退職後の生活資金に役立つ支援を3つ紹介します。
退職手当(退職金)
退職手当は、企業が従業員の勤労に対する報酬として支給する制度です。支給の有無や金額は企業によって異なり、勤続年数や退職理由によって決まります。
自己都合退職では金額が減るケースや、会社都合退職で上乗せされるケースもあり、内容は就業規則や雇用契約書で確認する必要があります。退職手当は制度の有無も含めて企業ごとの対応となるため、退職前に確認しておきましょう。
傷病手当金
傷病手当金は、健康保険の加入者が病気やケガで働けなくなったときに支給される制度です。
業務外の理由で就業不能となった場合、給与の代わりとして最大1年6か月間支給されます。受給には以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
- 業務外の病気・ケガによる療養であること
- 就労不能であること(医師の証明が必要)
- 連続する3日間の待機を含む4日以上仕事を休んでいること
- 休業中に給与の支払いがないこと
支給額は、支給開始日前の12ヶ月間の標準報酬月額をもとに算出され、1日あたり約3分の2が支給されます。
傷病手当金の申請方法については以下記事もご確認ください。
参考:傷病手当金をもらえないケースとは?会社が嫌がる理由や対処法・申請方法も紹介
未払賃金立替払制度
未払賃金立替払制度は、会社の倒産によって給与や退職金が未払いとなった従業員を救済するための制度です。労働基準法に基づき、国が一定の条件を満たす退職者に未払い分の最大80%を立て替えて支給します。
対象となるのは、以下の条件を満たす方です。
- 退職日の6ヶ月前から請求日前日までに支払期日が到来していた賃金が未払いであること
- 法的倒産または事実上の倒産状態の企業で、退職日が倒産認定日から2年以内であること
上限額は年齢によって異なります。
仕事を辞める際にもらっておくべき書類
退職後に必要な手続きの多くは、退職時に受け取る各種書類がそろっているかどうかで進行のスムーズさが変わります。再就職の準備や失業保険の申請、公的制度の利用など、重要な場面で必要となるため、必ず受け取りの確認をしましょう。
以下の表に、退職時に必ずもらっておくべき主要な書類と用途をまとめました。
|
主な用途 |
|
|
退職証明書 |
在職期間や退職理由などを証明。転職先からの提出依頼や、国民健康保険・年金の手続きに使用 |
|
源泉徴収票 |
年内の給与・所得税額が記載されており、年末調整や確定申告に必要。 |
|
雇用保険被保険者証 |
雇用保険に加入していた証明書。転職先の雇用保険手続きや、失業給付の申請時に必要 |
|
離職票(1・2) |
失業手当の申請に必須 |
|
健康保険資格喪失証明書 |
社会保険から脱退したことの証明書。国民健康保険への加入や、配偶者の扶養に入る際の手続きで必要 |
|
年金関係書類(年金手帳または基礎年金番号通知書) |
年金加入者番号が記載されている書類。国民年金への切り替えや、次の職場での厚生年金手続きに必要 |
上記の他にも、マイナンバーカードを各種手続きで使う場面があるため、あらかじめ準備しておくと安心です。
仕事を辞めてもらえるお金を受け取るメリット・デメリット
退職後に利用できる給付制度は、恩恵だけでなく注意すべき点もあるため、両面を理解したうえで活用を検討しましょう。ここでは、仕事を辞めてもらえるお金の主なメリットとデメリットを紹介します。
メリット
退職後の不安を軽減し、より良い再出発に集中できるのが給付制度の強みです。主なメリットは以下のとおりです。
- 収入がなくなる不安を軽減できる
- 転職活動やスキルアップに専念できる
- 再就職手当など追加の支援が受けられることもある
- 病気・介護などでも条件により支給対象になることがある
制度を活用すれば金銭的な余裕を確保しながら、落ち着いて将来の選択肢を広げられます。
デメリット
制度を利用するには条件や制約があるため注意が必要です。申請の手間や自由な働き方への制限など、以下のデメリットも理解しておきましょう。
- 失業保険は受給までに時間がかかる(自己都合の場合は原則として1ヶ月の給付制限)
- 失業保険の受給中は原則として働けない
- 申請手続きが複雑で、時間と労力がかかる
給付制度は便利ですが、手続きや運用には手間がかかるため活用前に内容を十分に確認し、自分に合った選択をしましょう。
仕事を辞めた後にお金をもらう際の注意点

退職後に給付金や手当を受け取る際には、制度の仕組みを正しく理解し、適切な手続きが必要です。条件や書類の不備によって支給されないケースや、不正とみなされて処罰の対象となるリスクもあります。
ここでは、仕事を辞めた後にお金をもらう際の注意点を3つ解説します。
給付金の申請条件や受給資格を正しく理解しておく
受給資格を満たしていなければ、申請しても給付金は支給されません。給付制度にはそれぞれ支給要件があり、退職理由や離職票の記載内容が重要な判断基準です。
例えば、自己都合退職であってもやむを得ない事情(契約満了、家族の介護など)があると特定理由離職者に該当する場合があります。
給付を確実に受け取るためには、自分の退職理由と制度の内容を照らし合わせ、事前に条件を確認しておく必要があります。
必要書類を正確にそろえて申請期限を守る
手続きに必要な書類が不備なく揃っていないと、給付申請は受理されません。給付金の申請では、離職票や雇用保険被保険者証、本人確認書類などの提出が必要です。
離職票は会社から発行されるまでに日数がかかるケースもあるため、退職後は早めに会社へ確認してください。また、ハローワークでの手続きは、退職日の翌日から可能です。期限内に申請を完了しなければ無効になる場合もあるため、スケジュールを明確にし、迅速に行動しましょう。
虚偽申告や不正受給は重い罰則の対象になる
不正な手段で給付金を受け取ると、重大な法的責任を問われます。申請内容に虚偽があったり、本来の条件を満たさないまま給付を受けたりした場合は、不正受給と見なされる対象です。
例えば、求職中と申告しながら実際には働いていた場合や、面接活動を装って虚偽報告をした場合、発覚すると給付金の全額返還に加え、最大3倍の追徴金が科されます。悪質な場合には詐欺罪として刑事罰(懲役や罰金)の対象になることもあります。
仕事を辞めたらもらえるお金に関するよくある質問
仕事を辞めたあとに受け取れる給付金や支援制度にはさまざまな種類があり、誤解されやすい点も少なくありません。ここでは、仕事を辞めたらもらえるお金に関するよくある質問を3つ紹介します。
自己都合退職でも失業手当はもらえる?
自己都合退職でも失業手当は受給可能です。受給条件は以下のとおりです。
- 雇用保険に12ヶ月以上加入していること
- 就職の意思と就労可能な健康状態であること
- 積極的に就職活動を行っていること
ただし、自己都合退職の場合は給付制限期間があり、退職後7日間の待期期間に加えて原則1ヶ月の給付制限が設けられています。給付開始までに一定の時間がかかる点に注意してください。
なお、病気や介護、ハラスメントなどのやむを得ない理由で退職した場合には、特定理由離職者として認定され、給付制限が免除されることもあります。
仕事を辞めた後ハローワークに行かないとどうなる?
ハローワークに行かない場合、失業手当を受給できません。職業訓練や就職支援など、ハローワークが提供するサポートも受けられなくなります。また、国民年金や健康保険の保険料を軽減するための制度はハローワークでの証明書が必要となるため、制度の活用が難しくなるケースもあります。
なお、ハローワークに行くのが困難な場合は、給付金の申請をサポートする外部サービスの利用を検討するとよいでしょう。手続きを怠ると受給の機会を失うため、退職後は速やかにハローワークへ相談してください。
仕事を辞めたら200万円もらえる制度はある?
仕事を辞めたら200万円もらえる制度は存在しません。しかし、失業手当や再就職手当、教育訓練給付金など複数の支援制度を組み合わせれば、結果的に200万円を超える支給を受け取れるケースはあります。
とはいえ、自分がどの制度に該当し、いくら受け取れるかを正確に把握するのは容易ではありません。不安がある場合は、ハローワークや給付金サポートサービスへ相談しましょう。
まとめ
仕事を辞めたあとに活用できる公的・私的な支援制度は、雇用保険の基本手当から住居確保給付金、退職金まで幅広く存在します。制度ごとに対象者や支給額、手続き期限が異なるため、自分が該当するかを早めに確認し、必要書類を整えて期限内に申請することが重要です。
なかでも、失業保険は待期期間や給付制限があり、自己都合退職では支給開始まで時間が空くほか、申請書類のミスや離職票の記載内容次第で給付額が減額されるリスクもあります。給付金を確実に、そして最大限に受け取るには、制度の仕組みを正しく理解しなければなりません。
「書類の書き方がわからない」「自分がいくら受け取れるのか不安」とお考えの方は、社会保険給付金サポートをご検討ください。受給要件の確認から申請書類の作成・提出まで専任コンシェルジュがマンツーマンでサポートし、受給漏れを防ぎます。
LINEから簡単に相談できるので、まずは気軽にお問い合わせください。
この記事の監修者

杉山雅浩
スピネル法律事務所 弁護士
東京弁護士会所属。
池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。
NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、
詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。
YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、テ日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!
おすすめの関連記事
ピックアップ
- CATEGORY
- 給付金について
- 転職・再就職について
- 就労について
- 社会保険について
- 精神疾患について
- サービスについて
- 失業保険について
- 再就職手当
- 雇用保険について
- 退職について
- 障害年金について
- ピックアップ
- 人気記事
-
退職代行サービスの利用方法、実際の流れと体験談を紹介
-
今の会社に3年後もいる自信はありますか?
-
退職代行を利用した時の有給消化の仕組みとその対応方法
-
退職代行サービスを使うメリット・デメリットは?
-
障害年金を知ろう
-
ブラック企業を判定する方法と実際のチェックポイント
-
会社を“円満に退職する”方法は?
-
退職時の引き継ぎは義務?スムーズな業務引き継ぎの必須ポイント
-
辞めさせてくれない!そんな時こそ「退職代行サービス」
-
パワハラ、モラハラ、セクハラとは?
テーマ
- クレジットカード
- 資格取得
- 退職届
- 引っ越し
- 労働基準法
- 退職コンシェルジュ
- 退職代行
- アルバイト
- 精神疾患
- 面接
- 社宅
- 雇用契約
- ストレス
- 退職代行サービス
- 雇用保険
- うつ病
- 障害手当金
- 障害者手帳
- 内定
- ブラック企業
- 健康保険
- 統合失調症
- 自己都合
- 精神保険福祉手帳
- 就労移行支援
- ハラスメント
- 年金
- 契約社員
- 会社都合
- 労災
- 業務委託
- パワハラ
- 転職活動
- 弁護士
- 失業給付
- 産休
- 社会保険
- モラハラ
- 転職サイト
- 公的貸付制度
- 新型コロナウイルス
- 解雇
- 福利厚生
- セクハラ
- 職務経歴書
- 生活福祉資金貸付制度
- 有給消化
- 中小企業
- 失業手当
- 障害年金
- 人間関係
- 不支給
- 休職
- ベンチャー企業
- 就職困難者
- 引き継ぎ
- スタートアップ
- 等級
- 免除申請
- 会社倒産
- 再就職手当
- 給与
- 転職
- 離職票
- 適応障害
- 退職勧奨
- 社会保険給付金
- 残業代
- 違法派遣
- 労務不能
- 住宅確保給付
- 自己PR
- 職業訓練受講給付金
- 退職金
- 派遣契約
- 傷病手当金
- 給付金
- 確定申告
- 退職給付金
- 会社都合退職
- 障害厚生年金
- 年末調整
- 職業訓練
- 保険料
- ハローワーク
- 自己都合退職
- 失業保険
- 障害者控除
- 再就職
- 社会保障
- 就業手当
- 退職
- ブランク期間
- 退職願
- 職業訓練受講手当
- 就職
- 傷病手当
新着記事
-
2025.10.17
退職バンクにはどんな口コミ・評判がある?怪しいと言われてしまう理由も解説!
-
2025.10.17
失業保険の初回支給はいくら?【2025年最新版】支給額と計算方法・少ない理由を徹底解説
-
2025.10.17
勤続1年未満でも失業保険はもらえる?勘違いしやすい条件を整理
-
2025.10.17
失業手当と扶養の関係を徹底解説(2025年版)|受給中に扶養に入れる?外れる?
-
2025.10.15
仕事を辞めるタイミングとは?適切な伝え方や注意点を解説
-
2025.10.09
失業手当の手続きで提出する必要書類は?離職票再発行や延長申請の流れも解説
-
2025.10.08
個人事業主が再就職手当をもらえるケースと手続き方法、注意点を解説
-
2025.10.08
アルバイトを4時間ピッタリすると失業手当はどうなる?支給条件や注意点も解説
-
2025.10.08
いつが得?損しない退職日の決め方とパターン別おすすめの退職日
-
2025.10.08
失業認定日までに就職が決まったらどうする?必要な手続きの手順を解説





 サービス詳細
サービス詳細