2025.07.08
退職について
テーマ:
賢い退職の仕方とは?知っておくべき手続きや制度などを解説
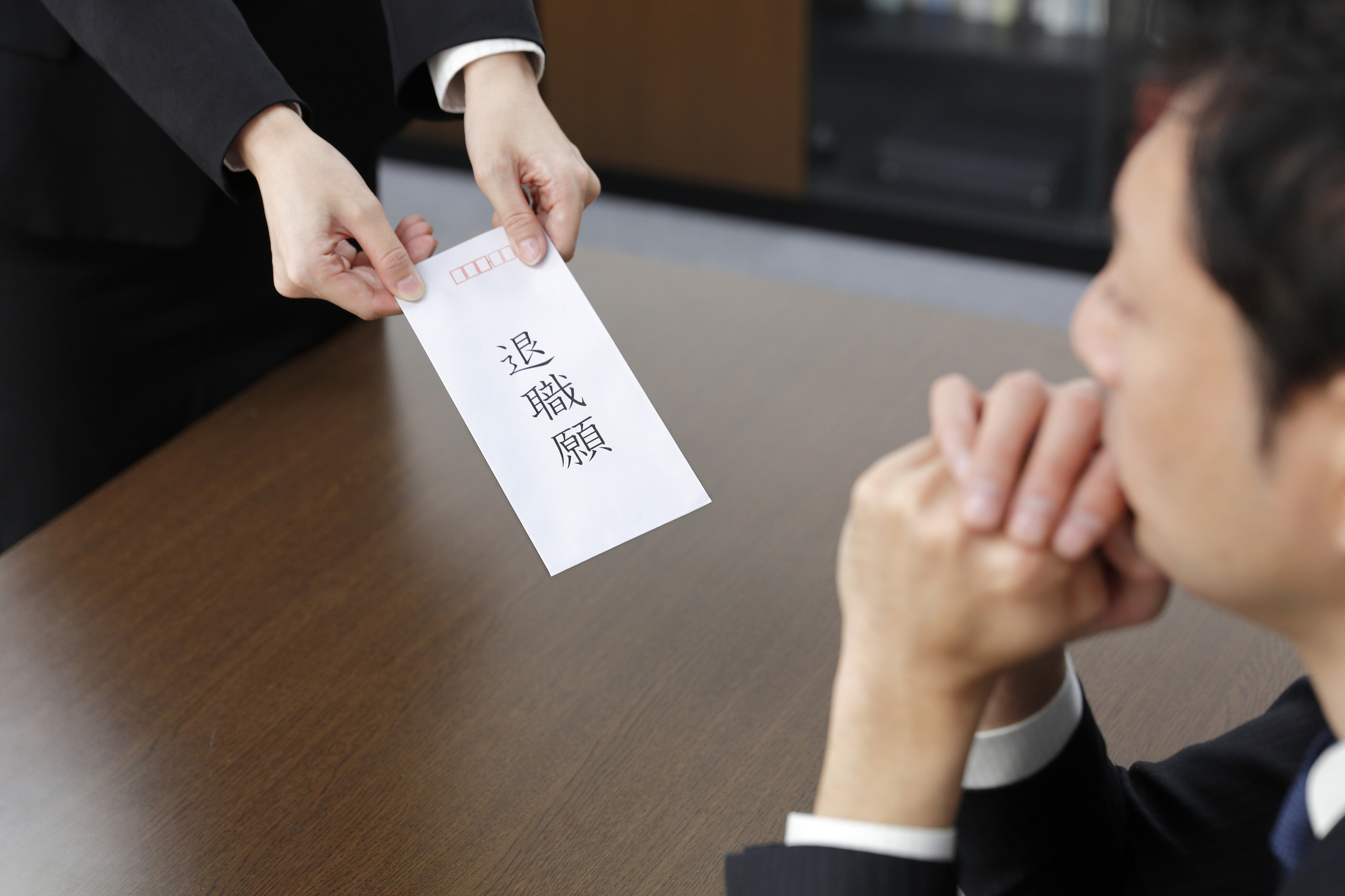
賢い退職とは、トラブルを防ぎ円満に退職することを意味します。退職は、新しい道を進むための大切な選択です。勢いや思いつきで進めると、あとで「こんなはずじゃなかった」と後悔することになりかねません。
本記事では円満退職、かつ自分が損をしないための「賢い退職の仕方」について、必要な準備や知っておきたい制度、手続きのポイントをわかりやすく解説します。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
賢い退職の仕方とは?
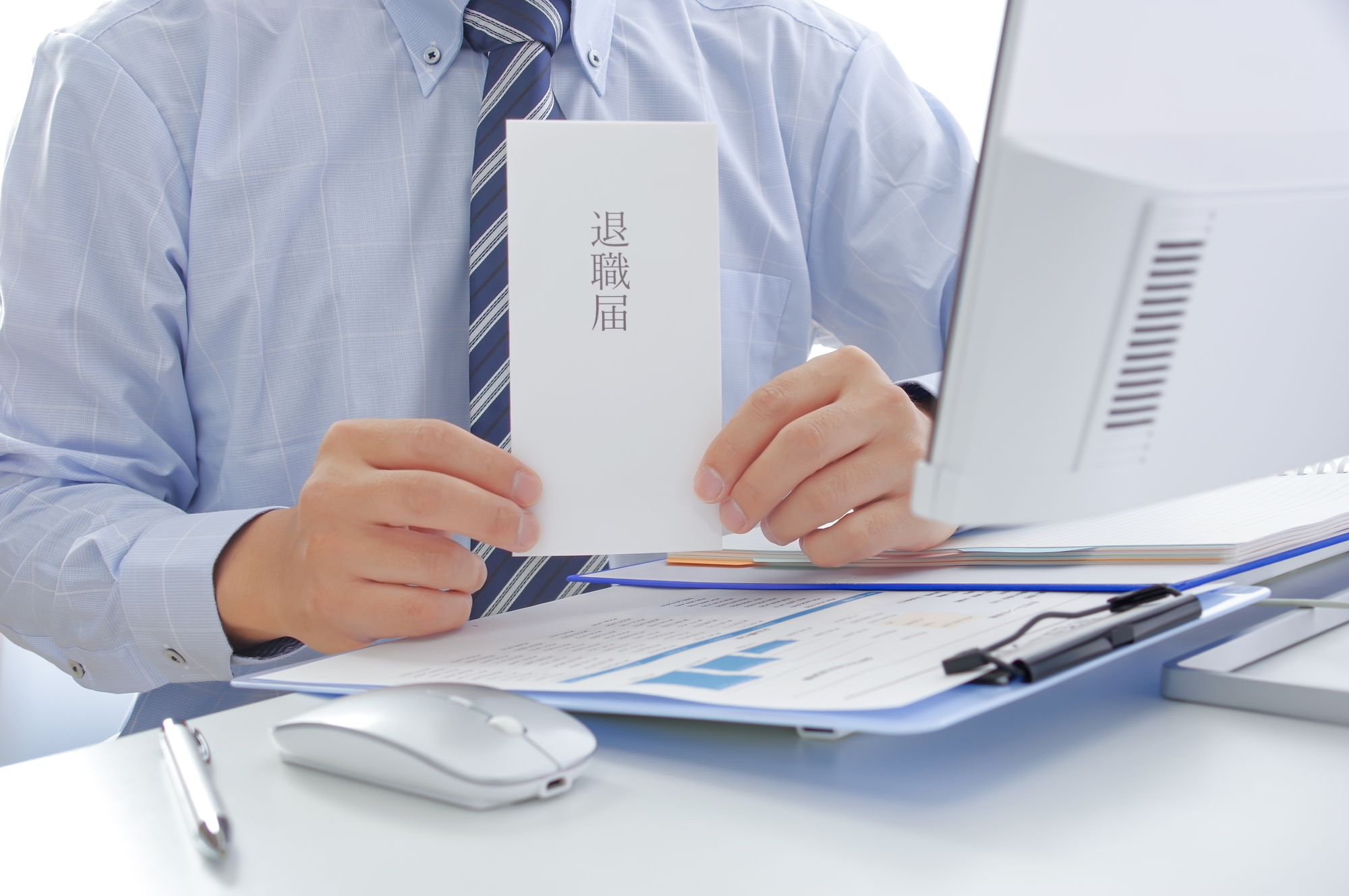
退職を考えたとき、勢いや感情だけで決断してしまうと、「もっと考えておけばよかった」と後悔することもあります。賢く退職するためには、事前の準備や、制度に関する正しい知識を持っておくことが大切です。
例えば、退職するタイミングや伝え方によって、職場との関係性や退職後の手続きのスムーズさが変わります。失業保険や健康保険などの制度を把握しておけば、経済的な損を防ぐことにもつながります。「辞めたい」と思ったその時から、少しずつ準備を始めることが大切です。
賢く退職するメリット
退職は人生の大きな節目であり、正しく準備し、賢く進めることで下記のようなメリットが得られます。
- 経済的な損を避けられる
- 人間関係を円満に保てる
- 次のステップにスムーズに繋げられる
退職時期の選び方や手続きのタイミングによって、社会保険料や税金の負担が変わることがあります。退職金や有給休暇の扱いなどの制度を知ることも、金銭面でのメリットにつながります。
退職の意思の伝え方や引き継ぎの進め方に気を配ることで、職場との関係を悪化させずに済みます。退職後も、必要に応じて前職に相談できる関係性が保てる可能性もあるでしょう。
転職活動や失業保険の申請など、退職後にやるべきことを把握しておけば、無駄な時間や出費を減らせます。心と体に余裕を持って次のキャリアに向き合えることも、賢く退職する大きなメリットです。
賢い退職をするために準備すべきこと
退職をスムーズに進めるためには、事前準備が欠かせません。伝え方やタイミングによっては職場との関係性が大きく左右されるほか、退職後の手続きや生活にも影響が出ることがあります。
ここでは、賢く退職するために押さえておきたい具体的な準備について紹介します。
退職の切り出し方を考える
退職を伝えるときは、タイミングを見て、最初に直属の上司に伝えるのが基本です。繁忙期や大きなプロジェクトの最中などは避け、1〜2カ月前を目安に余裕を持って相談するのが望ましいでしょう。
アポイントを取る際は、「少しご相談があるのですが」など、配慮のある言い回しを使いましょう。個室など、周囲に聞かれにくい場所で話すことも大切です。
退職の意思を伝える際は、あいまいな表現を避けます。はっきりと決意を示すことで、待遇交渉や引き止めを回避しやすくなります。「◯月末で退職したいと考えています」と具体的に伝えることがポイントです。
退職のタイミングを考える
退職の時期によっては、社会保険料や税金の負担に差が出ることがあります。たとえば、月途中で退職しても資格喪失日が月内であれば、その月の保険料は発生しません。一方、月末退職の場合は、月内の医療費が保障されるなどの安心感もあります。
退職日次第では、国民健康保険料、国民年金保険料の自己負担が発生するため、できるだけ無職期間を減らせるよう調整しましょう。
また、賞与や退職金の支給タイミングの確認も必要です。在籍する会社の就業規則を確認し、受け取れるものはきちんと受け取ってから退職することで、経済的損失が防げます。有給休暇が残っている場合は、退職前に計画的に消化することで、心身を整える時間も確保できます。
退職後の生活を考える
あらかじめ退職後の過ごし方をイメージしておくと、不安や迷いを減らすことができます。転職先を決めてから退職する、ゆっくり考える期間を取るなどを事前に決めておくと、次の行動がスムーズです。
もし、退職後に考えたい場合は、当面の生活費を確保しておくことが安心につながります。また、「なぜ辞めたいのか」という理由を明確にしておくと、転職活動や退職後の生活において自分の軸を持って動きやすくなります。
賢い退職をするために知っておくべき手続きや制度
退職後は、健康保険や年金、税金、失業保険など、さまざまな手続きが必要になります。知識がないまま手続きを後回しにしてしまうと、余分な出費が発生したり、必要な給付を受け損ねてしまったりする可能性がある点に注意が必要です。
ここでは、退職後に押さえておきたい主な制度や手続きについてわかりやすく紹介します。
健康保険や年金の手続き
退職後の健康保険は、「家族の扶養に入る」「国民健康保険に加入する」「任意継続被保険者になる」のいずれかを選びます。任意継続を希望する場合は、退職日の翌日から20日以内の申請が必要となり、早めの選択・加入が必要です。
年金については、市区町村の窓口に出向き、厚生年金から国民年金への切り替えを行います。目安は退職日の翌日から14日以内です。14日をすぎても手続きは可能ですが、未納期間を防ぐためにも、できるだけ早めに対応しましょう。
税金の手続き
退職後は、所得税・住民税・退職金に関する手続きが発生します。所得税については、年内に再就職すれば転職先で年末調整が可能ですが、再就職しない場合は自分で確定申告が必要になります。
住民税は退職時期によって納付方法が変わります。1〜5月に退職すると、一般的に残額が給与や退職金から一括で徴収されます。6月以降の退職であれば、自治体から届く納付書により、自分で支払う必要があります。普通徴収と呼ばれる支払い方法です。納付方法の希望がある場合は、事前に会社に伝えておくと安心です。
また、退職金を受け取る際には会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出します。退職所得控除の適用を受け、税負担の軽減が可能です。未提出の場合、退職金全額に対して一律20.42%の源泉徴収がされてしまうため、税負担を抑えるためにも必ず提出しましょう。
失業保険の制度
失業保険(雇用保険の基本手当)は、再就職までの生活を支える制度です。受給には雇用保険の加入期間などの条件があります。
自己都合退職の場合は、離職前2年間に通算12カ月以上の被保険者期間が必要です。会社都合退職や特定理由離職者は、直近1年間に6カ月以上あれば対象になります。
支給開始時期も退職理由で異なります。自己都合の場合は7日間の待期+1カ月の給付制限があり、会社都合なら7日後から支給が始まります。また、早期(給付日数の3分の1以上が残っている状態)に再就職すると「再就職手当」がもらえる可能性があることも覚えておきましょう。
円満退職するためのコツ

退職時の印象はその後の人間関係やキャリアに影響を与える可能性があります。ここでは、職場との関係を悪化させず、円満退職するために意識しておきたいポイントを紹介します。
引き止めにくい退職理由を伝える
退職理由は、前向きな内容を選ぶのが基本です。たとえば「キャリアアップのため」「新しい挑戦をしたい」といった理由は、相手も納得しやすく、感情的な対立を避けやすくなります。
待遇や人間関係への不満をそのまま伝えてしまうと、引き止めや言い争いに発展することもあるため避けましょう。正直にすべてを話す必要はありません。「家族の事情」「転居を伴う」など、会社側が引き止めにくい具体的な事情を挙げると、話がこじれにくくなります。
余裕を持った引き継ぎや挨拶を行う
円満退職には、引き継ぎと丁寧な挨拶が欠かせません。最低でも、退職の1カ月以上前に意思を伝え、スケジュールに余裕をもたせて引き継ぎの準備を始めましょう。
業務マニュアルの作成や、後任への口頭説明など、相手が困らないように配慮した対応を心がけることで、周囲からの信頼にもつながります。
また、お世話になった人たちには忘れずに挨拶をしましょう。社内外問わず、感謝を伝える一言だけで印象が大きく変わります。
不満は言わずに感謝の気持ちを持つ
退職が決まっても、最後まで誠実な姿勢を保つことが大切です。遅刻や業務の手抜きなどがあると、それまでの評価が覆ってしまうこともあります。最後に一言、「ありがとうございました」と感謝を伝え、美しい退職を心がけましょう。
また、退職したからといってSNSなどで会社の悪口を書くと、思わぬところで信用を損なう可能性があります。離れたあとも、自分の言動が見られているという意識を持っておくと安心です。
まとめ
退職は単なるゴールではなく、新しいスタートのための大切な節目です。勢いや不満だけで動いてしまうと、後悔することにもなりかねません。
賢く退職するには、正しい知識と準備が必要です。退職の伝え方、タイミング、手続き、そして退職後の生活までを見据えて行動することで、無駄なトラブルや損失を避け、気持ちよく次のステップへ進むことができます。
「制度が複雑で不安」など失業保険の申請に不安をお持ちの方は、退職コンシェルジュが提供する「社会保険給付金サポート」をご活用ください。サポート実績が豊富な専任スタッフによる専門サポートを受けることで、自分に適した方法を見つけることが可能です。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
この記事の監修者

杉山 雅浩
東京弁護士会所属。
池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。
NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、
詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。
YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!
おすすめの関連記事
ピックアップ
- CATEGORY
- 給付金について
- 転職・再就職について
- 就労について
- 社会保険について
- 精神疾患について
- サービスについて
- 傷病手当金について
- 失業保険について
- 退職について
- 障害年金について
- ピックアップ
- 人気記事
-
退職代行サービスの利用方法、実際の流れと体験談を紹介
-
今の会社に3年後もいる自信はありますか?
-
退職代行を利用した時の有給消化の仕組みとその対応方法
-
退職代行サービスを使うメリット・デメリットは?
-
ブラック企業を判定する方法と実際のチェックポイント
-
障害年金を知ろう
-
会社を“円満に退職する”方法は?
-
退職時の引き継ぎは義務?スムーズな業務引き継ぎの必須ポイント
-
パワハラ、モラハラ、セクハラとは?
-
辞めさせてくれない!そんな時こそ「退職代行サービス」
テーマ
- 転職サイト
- 不支給
- 引っ越し
- 雇用契約
- 退職代行
- 職務経歴書
- 等級
- 社宅
- 内定
- 退職代行サービス
- 人間関係
- 離職票
- 障害者手帳
- 就労移行支援
- ブラック企業
- スタートアップ
- 労務不能
- 精神保険福祉手帳
- 業務委託
- ハラスメント
- 転職
- 傷病手当金
- 労災
- 社会保険
- 引き継ぎ
- 違法派遣
- 障害者控除
- 産休
- 福利厚生
- 給与
- 派遣契約
- 退職届
- 解雇
- 就職困難者
- 残業代
- 障害厚生年金
- 面接
- 中小企業
- 再就職手当
- 退職金
- 失業保険
- 障害手当金
- ベンチャー企業
- 社会保険給付金
- 会社都合退職
- 資格取得
- 新型コロナウイルス
- 退職勧奨
- 職業訓練受講給付金
- 自己都合退職
- うつ病
- 有給消化
- 自己PR
- 退職給付金
- クレジットカード
- 統合失調症
- 休職
- 確定申告
- ハローワーク
- アルバイト
- 契約社員
- 免除申請
- 保険料
- 傷病手当
- 雇用保険
- 弁護士
- 適応障害
- 社会保障
- 退職コンシェルジュ
- 健康保険
- 公的貸付制度
- 住宅確保給付
- 就職
- インフルエンザ
- 年金
- 生活福祉資金貸付制度
- 職業訓練
- 労働基準法
- ストレス
新着記事
-
2026.01.06
退職して国民健康保険に切り替えたあとも傷病手当金はもらえる?注意点も解説
-
2025.12.27
インフルエンザで仕事を休むと「傷病手当金」はもらえる?条件・日数・申請方法まで解説
-
2025.12.26
傷病手当金と副業の関係をわかりやすく解説
-
2025.12.17
傷病手当金の不正と調査|どこからがNG?就労・外出・求職活動の正しい判断基準を解説
-
2025.12.16
【徹底比較】退職給付金サポート おすすめランキング
-
2025.12.09
傷病手当金をもらいながら働く方法はある?アルバイトならOK?収入を得る方法や注意点を解説
-
2025.12.09
社会保険給付金と失業保険の違いは?受給要件やメリット・デメリット解説
-
2025.12.08
産休・育休後そのまま退職はマナー違反?退職時のポイントと注意点
-
2025.12.07
会社を辞めさせられた場合は失業保険は受け取れる?条件や注意点を解説
-
2025.12.04
傷病手当金は退職後もらえない?受給できる条件と不支給になる理由を徹底解説





 サービス詳細
サービス詳細














