2025.05.13
退職について
テーマ:
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは?使い道や発行フローを紹介

退職時に発行される書類の一つに「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」があります。名前だけを見ると難しく感じますが、この書類は雇用保険の資格喪失を知らせるための通知です。
実際には、退職後の手続きで必ず必要になるとは限りません。しかし、転職先や社会保険の切り替え時などで求められる場合があるため、注意しておきましょう。本記事では、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」の基本的な使い道や発行までの流れ、注意点についてやさしく解説します。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」とは?
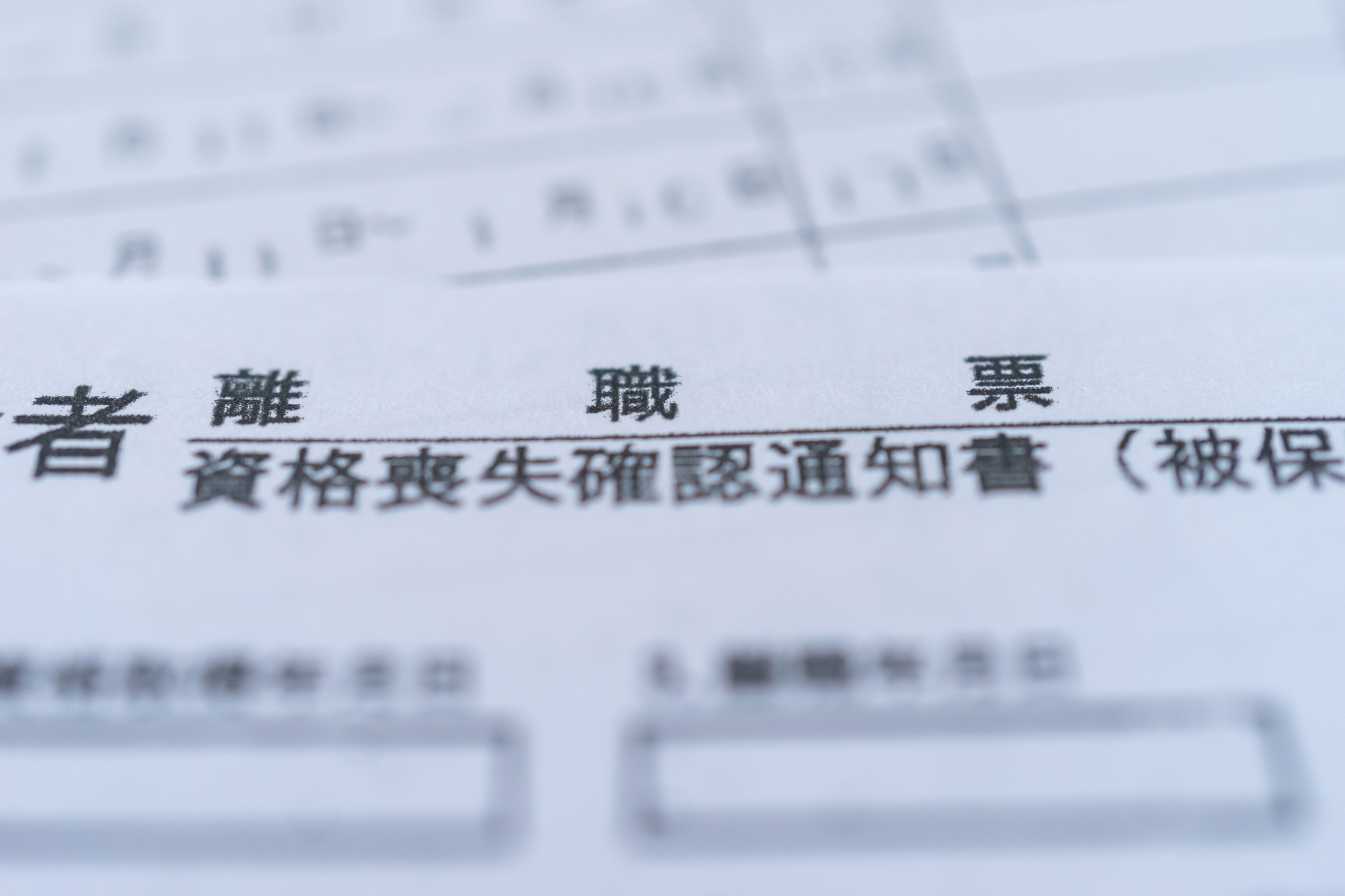
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」は、退職などにより雇用保険の被保険者資格を喪失したことを通知する書類です。雇用保険に加入していた人が、退職により資格を失ったことを本人に知らせる目的で交付されます。
この書類は、退職後の転職活動や失業手当の申請の手続きにおいては、必要になることがほとんどありません。失業手当を受け取る際に必要となるのは、別途交付される「離職票」です。
ただし、転職先によっては提出を求めるケースや、社会保険の切り替え時などに使用するケースがあります。届いた場合は、念のためすぐには処分せずしばらく保管しておくと安心です。
また、雇用保険に関する書類は個人・法人を問わず、原則4年間保管しておくことが雇用保険法施行規則第143条で定められています。実際に使用する機会は多くないものの、法律上も4年間は保管することが推奨されているため、大切に保管しておきましょう。
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」がもらえるタイミング
企業は、退職者が被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に、ハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出する義務があります。ハローワーク内の処理完了後、ハローワークは企業に「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を郵送し、その後、企業から退職者へ通知書が交付される流れです。
通常、退職から2週間程度で手元に届くことが多いですが、遅れることもあります。万が一、3週間以上経っても届かない場合は、退職した会社の人事担当者に確認してみましょう。
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」の発行フロー
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」は、以下の流れで発行されます。
1.在職中に雇用保険加入の有無を確認する
まずは、自身が雇用保険に加入しているかを確認しましょう。一般的に、週20時間以上の勤務があり、31日以上の雇用見込みがある場合は、雇用保険の加入対象となります。
2.退職時には会社に「離職票」の発行不要の旨を伝える
離職票が不要な場合は、退職手続きの際にその旨を会社に伝えます。離職票は失業手当の申請に必要な書類ですが、申請しない場合は発行を省略することが可能です。
なお、離職票を希望する場合には「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」は発行されません。これは、離職票-1が通知書の役割も兼ねているためです。
3.会社の担当者が雇用保険の資格喪失手続きを行う
退職後、会社は「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出します。原則として、資格喪失日(退職日の翌日)から10日以内に手続きを行う必要があります。
4.ハローワークが資格喪失確認通知書を発行し、会社へ送付
手続きが完了すると、ハローワークから会社宛に「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」(会社控え・本人控え)が交付されます。
5.会社から退職者に本人控えが送付される
企業は、本人控えをすみやかに退職者に送付します。多くの場合、退職後2週間ほどで届きますが、遅れることもあるため、届かない場合は早めに会社に確認しましょう。
雇用保険喪失手続きをしてくれない主な理由
本来、雇用保険の喪失手続きは退職後すみやかに行われるべきものですが、何らかの理由で進まないケースもあります。ここでは、手続きが遅れたり手続きが行われなかったりするときの主な原因について解説します。
そもそも雇用保険の加入手続きをおこなっていない
企業には、従業員が以下の3つの条件を満たす場合、雇用保険加入手続きをおこなう義務があります。
- 31日以上の雇用見込みがある
- 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
- 学生ではない(※一部例外あり)
しかし、実際には法令に違反して、従業員を雇用保険に加入させていない企業も存在します。このような場合、資格喪失手続きが進められません。
ただし、その場合も退職者が企業に「遅延理由書」を作成・提出してもらうことで、過去2年まで遡って雇用保険に加入する手続きは可能です。
ハローワークが混雑している
企業がいくら手続きを進めていても、ハローワークの窓口や事務処理が混雑している影響で、資格喪失手続きが予定より遅れてしまうことがあります。特に、3月や9月は多くの退職・転職者が手続きをおこなうため、混み合いやすい時期です。手続きが長引いていると感じた場合は、企業やハローワークに直接進捗状況を確認してみましょう。
悪意から会社が雇用保険喪失手続きをおこなっていない
残念ながら「退職を引き止めたい」「嫌がらせをしたい」などの理由で、意図的に喪失手続きをおこなわない企業も存在します。このような場合は、1人で抱え込まず、ハローワークに相談しましょう。ハローワークが企業に指導を行い、必要な手続きを進めてくれます。
雇用保険喪失手続きをしてくれない場合の対処法

もし、企業が雇用保険の喪失手続きを進めてくれない場合でも、適切に対処することで問題を解決できる可能性があります。あわてずに、次の方法を試してみましょう。
離職票が発行されないことをハローワークに相談する
通常、離職票は退職から2週間程度で届くことが一般的です。しかし、一定期間を過ぎても届かず、会社に何度も問い合わせても発行されないケースがあるため、その場合は、管轄のハローワークに相談しましょう。
窓口で「離職票が交付されない状況」であることを伝えると、ハローワークが会社に対して状況確認や発行の働きかけを行ってくれます。
ハローワークで失業給付の仮手続きを行うことができる
離職票が手元にない場合でも、退職日を証明できる書類(退職証明書や健康保険資格喪失証明書など)を準備すれば、ハローワークで失業給付の仮手続きができます。仮の受給資格者証を受け取ることで、離職票がなくても失業手当の申請手続きを進められます。なお、正式な手続きには、初回の失業認定日までに離職票を提出する必要があるため、後日準備しましょう。
ハローワークで離職票を発行してもらえるか相談する
離職票は、退職者が発行を希望した場合、企業側が必ず用意しなければならない書類です。しかし、悪質な企業では、発行義務があるにもかかわらず対応を拒み続けるケースもあります。
このような場合は、ハローワークに事情を説明し、今後の対応方法について相談しましょう。退職証明書や健康保険の資格喪失証明書などをもとに、離職票を直接発行してもらえるケースがあります。困ったときは、1人で抱え込まず、ハローワークの窓口で相談してみましょう。
まとめ
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」は、退職後に受け取る書類のひとつで、基本的には資格喪失を知らせるための通知です。手続きで必ずしも必要になるわけではありませんが、場合によっては転職先や社会保険の切り替えなどで提出を求められることもあります。手元に届いたら、大切に保管しておきましょう。また、会社が適切に手続きを行わない場合は、ハローワークに相談することで、状況に応じた対応が可能です。
雇用保険や退職後の手続きに不安を感じている方は、「社会保険給付金サポート」の活用もおすすめです。適切な給付を受けられるよう、専門家が丁寧に申請をサポートいたします。相談は無料です。まずは一度、お問い合わせください。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
この記事の監修者

杉山 雅浩
東京弁護士会所属。
池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。
NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、
詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。
YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!
おすすめの関連記事
ピックアップ
- CATEGORY
- 給付金について
- 転職・再就職について
- 就労について
- 社会保険について
- 精神疾患について
- サービスについて
- 傷病手当金について
- 失業保険について
- 退職について
- 障害年金について
- ピックアップ
- 人気記事
-
退職代行サービスの利用方法、実際の流れと体験談を紹介
-
今の会社に3年後もいる自信はありますか?
-
退職代行を利用した時の有給消化の仕組みとその対応方法
-
退職代行サービスを使うメリット・デメリットは?
-
ブラック企業を判定する方法と実際のチェックポイント
-
障害年金を知ろう
-
会社を“円満に退職する”方法は?
-
退職時の引き継ぎは義務?スムーズな業務引き継ぎの必須ポイント
-
パワハラ、モラハラ、セクハラとは?
-
辞めさせてくれない!そんな時こそ「退職代行サービス」
テーマ
- 転職サイト
- 不支給
- 引っ越し
- 雇用契約
- 退職代行
- 職務経歴書
- 等級
- 社宅
- 内定
- 退職代行サービス
- 人間関係
- 離職票
- 障害者手帳
- 就労移行支援
- ブラック企業
- スタートアップ
- 労務不能
- 精神保険福祉手帳
- 業務委託
- ハラスメント
- 転職
- 傷病手当金
- 労災
- 社会保険
- 引き継ぎ
- 違法派遣
- 障害者控除
- 産休
- 福利厚生
- 給与
- 派遣契約
- 退職届
- 解雇
- 就職困難者
- 残業代
- 障害厚生年金
- 面接
- 中小企業
- 再就職手当
- 退職金
- 失業保険
- 障害手当金
- ベンチャー企業
- 社会保険給付金
- 会社都合退職
- 資格取得
- 新型コロナウイルス
- 退職勧奨
- 職業訓練受講給付金
- 自己都合退職
- うつ病
- 有給消化
- 自己PR
- 退職給付金
- クレジットカード
- 統合失調症
- 休職
- 確定申告
- ハローワーク
- アルバイト
- 契約社員
- 免除申請
- 保険料
- 傷病手当
- 雇用保険
- 弁護士
- 適応障害
- 社会保障
- 退職コンシェルジュ
- 健康保険
- 公的貸付制度
- 住宅確保給付
- 就職
- インフルエンザ
- 年金
- 生活福祉資金貸付制度
- 職業訓練
- 労働基準法
- ストレス
新着記事
-
2026.01.06
退職して国民健康保険に切り替えたあとも傷病手当金はもらえる?注意点も解説
-
2025.12.27
インフルエンザで仕事を休むと「傷病手当金」はもらえる?条件・日数・申請方法まで解説
-
2025.12.26
傷病手当金と副業の関係をわかりやすく解説
-
2025.12.17
傷病手当金の不正と調査|どこからがNG?就労・外出・求職活動の正しい判断基準を解説
-
2025.12.16
【徹底比較】退職給付金サポート おすすめランキング
-
2025.12.09
傷病手当金をもらいながら働く方法はある?アルバイトならOK?収入を得る方法や注意点を解説
-
2025.12.09
社会保険給付金と失業保険の違いは?受給要件やメリット・デメリット解説
-
2025.12.08
産休・育休後そのまま退職はマナー違反?退職時のポイントと注意点
-
2025.12.07
会社を辞めさせられた場合は失業保険は受け取れる?条件や注意点を解説
-
2025.12.04
傷病手当金は退職後もらえない?受給できる条件と不支給になる理由を徹底解説





 サービス詳細
サービス詳細














