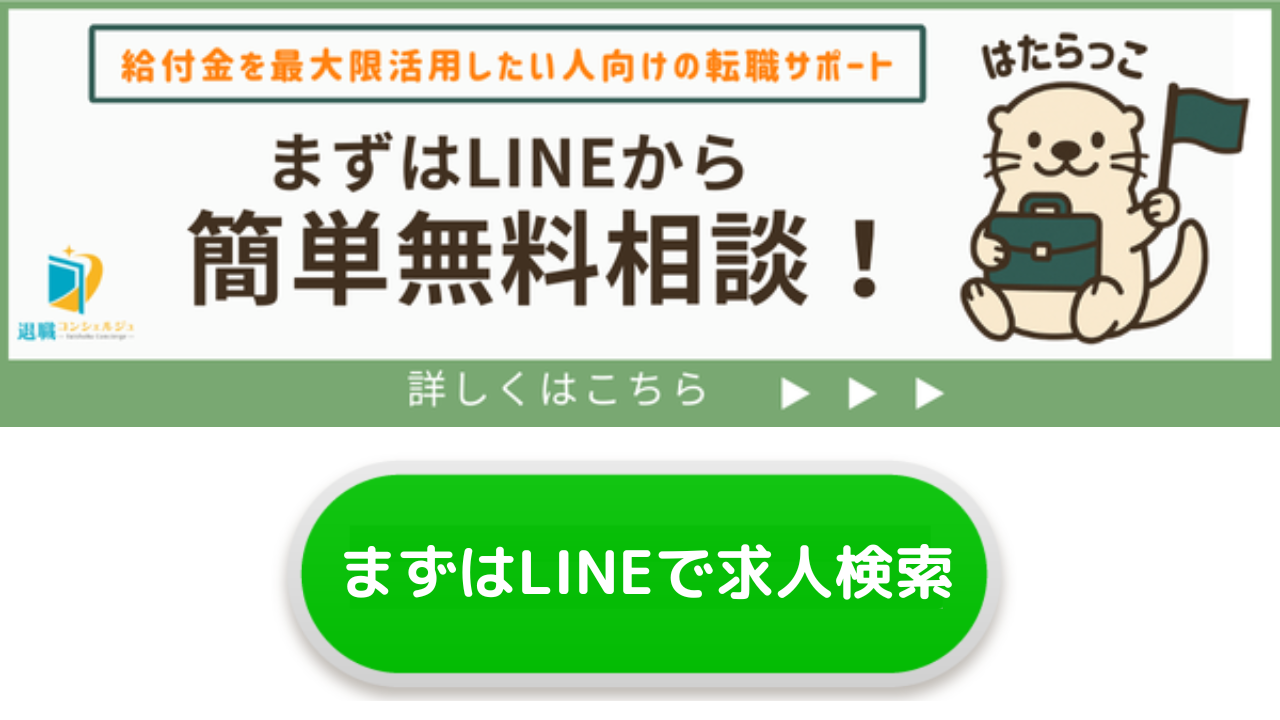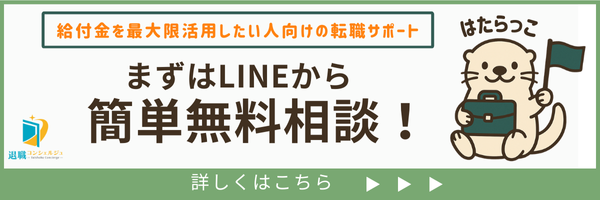2025.05.20
失業保険について
派遣社員は契約満了になっても失業保険がもらえる?条件や金額を解説

派遣社員として働いていたものの、労働契約で定められていた期間が経過して契約満了した場合も失業保険を受給することができます。しかし、次の仕事をどうするか、また、どのように失業保険を申請すれば良いのかわからずお悩みの方もいるでしょう。
そこで今回は、派遣契約における契約満了の概要と、契約社員や正社員との雇用形態の違い、失業保険の概要と申請方法を解説します。派遣で契約満了や雇止めになる主なケース例や、契約満了前に確認したいポイント、契約満了後に再就職を目指すコツもご紹介しますので、契約満了間近の方や契約満了後で失業保険の受給を検討中の方は参考にしてください。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
派遣の「契約満了」とは

派遣労働における「契約満了」とは、あらかじめ派遣契約で定められていた契約期間が終了することです。例えば、3月1日から5月31日までの契約であれば、5月31日が契約満了日です。
契約満了後に契約を更新しない場合、派遣先企業は契約満了の30日前までに派遣元に対してその旨を通知する義務があります。
また、契約満了による終了には、派遣社員自身の意思や派遣先企業の都合による場合があります。契約満了後、自己都合で終了する場合は派遣元に申し出なければなりません。また、企業都合で終了する場合は派遣元と協議して、雇用安定のための措置が取られます。
「派遣社員」「契約社員」と「正社員」の違い
契約満了により労働契約が終了するかどうかは、雇用期間が限定されているか否かで異なります。雇用期間は雇用形態によって異なるため、派遣社員、契約社員、正社員の違いを理解しておきましょう。
派遣社員とは
派遣社員とは、派遣元企業(派遣会社)と労働者が有期雇用契約を結んで、派遣先企業で業務を行う雇用形態です。
派遣契約の期間は、派遣先企業との契約内容に基づいて設定され、一般的には3カ月から6カ月程度が多くなっています。
また、派遣先企業との契約が更新される場合は、派遣社員の契約も更新されることがあります。ただし、派遣法によって、同一の組織単位での派遣期間はいわゆる3年ルールが適用され、原則として3年が上限です。
なお、派遣社員自身が契約更新を希望しない場合や、派遣先企業が契約を更新しない場合には、契約期間の満了(契約満了)をもって有期雇用契約が終了します。
契約社員とは
契約社員とは、企業と直接的な有期雇用契約を結んで、定められた期間内で業務を行う雇用形態です。
契約期間は企業や業務内容によって異なりますが、一般的には6カ月から1年程度が多いのが特徴です。
派遣社員は派遣元企業と契約する一方で、契約社員は企業と直接契約する点が異なります。
正社員とは
正社員とは、企業と期間の定めのない無期雇用契約を結んで、業務を行う雇用形態です。企業の正規の従業員として安定した雇用が保障されているのが特徴です。
派遣社員や契約社員の給与形態は、時給制や日給制、月給制など多様ですが、正社員は月給制が主で、賞与(ボーナス)や退職金の支給対象となります。
また、業務内容も異なり、派遣社員や契約社員は契約で定められた範囲の業務を行うため、正社員に比べて責任の重い業務に従事するケースは少なくなります。
失業保険とは
前述のとおり、派遣社員が契約満了で退職した場合も、失業保険を受給できます。ただし、受給には「雇用保険に加入していた」などの一定の条件を満たさなければなりません。
ここからは、失業保険の受給条件や受給金額などの概要を解説するので、失業保険を受け取るために理解を深めておきましょう。
失業保険の受給条件
そもそも、失業保険とは、雇用保険に基づく「基本手当」のことです。被保険者が離職した際に、再就職を早期に実現できるように支援するために支給されます。
失業手当を受け取るための条件は次のとおりです。
- 雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
- 離職前2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間があること(特定受給資格者と特定理由離職者の場合は1年間に6カ月以上)
- 就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること
失業手当の受給には、上記の3つの条件を満たす必要があります。そのため、以下のケースに当てはまる人は受給条件を満たさないため受給できません。
- 妊娠・出産・育児などのために、すぐに就労できない人(就労能力に欠ける)
- 病気・ケガ・障害などのために、すぐに就労できない人(就労能力に欠ける)
- 就職するつもりがない人(就労意思に欠ける)
- 家事に専念している人(就労意思に欠ける)
- 学業に専念している人(就労意思に欠ける)
- 会社などの役員に就任している人(求職活動を行っていない)
- 雇用保険に加入していなかった自営業の人(そもそも雇用保険料を支払っていない)
失業給付金の受給金額
失業手当の受給額は、次の計算式で決定します。
基本手当 = 給付日数 × 基本手当日額
一般的な受給額は、離職前に受け取っていた賃金の5〜8割程度が目安となります。
計算手順は次のとおりです。
- 賃金日額の計算方法:退職前6カ月の賃金合計 ÷ 180
- 基本手当日額の計算方法:賃金日額 × 給付率(50~80%)
- 基本手当総額の計算方法:基本手当日額 × 給付日数
「基本手当日額」とは、雇用保険に定められた、1日当たりに受給できる金額です。退職日以前の6カ月間の賃金(賞与を除く)を180で割った「賃金日額」に、50〜80%の給付率を掛けた金額が基本手当日額になります。
なお、給付率は、厚生労働省の基準に基づいて決定され、離職時の年齢や退職前の賃金により異なります。支給額のバランスを取るために、賃金日額が低いほど給付率が高くなる仕組みです。
また、雇用保険の賃金日額や基本手当日額には、下限額(2,295円)と年齢区分に応じた上限額が設けられています。自身の限度額については、管轄のハローワークに確認してください。
失業保険の申請方法
失業保険の申請は、以下の流れで進めます。
- 必要書類を揃える
- ハローワークで求職を申し込む
- 待機期間を過ごす
- 雇用保険説明会に参加する
- 失業認定日にハローワークを訪れる
必要書類を揃える
失業保険の申請には、ハローワークでの求職申し込みが必要です。求職申し込みにあたっては、以下の書類が必要ですので、準備しておきましょう。
- 雇用保険被保険者離職票-1・2
- 雇用保険被保険者証
- 証明写真(たて3cm×よこ2.4cm、正面上半身)×2
- 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
- 住所・氏名・年齢が確認できる本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1つ)
なお、令和2年より、雇用保険関係の手続きを行う際の押印が原則的に不要となりました。ただし、一部の書類は押印を必要とするため、念のために印鑑(認印は可、スタンプ印は不可)を持参しておくと良いでしょう。
ハローワークで求職を申し込む
必要書類が揃えば、ハローワークの窓口で求職の申し込みを行います。
具体的には次の流れで進めます。
- 求職申込書に記入する
- 必要書類の提出、職業相談を行う
- 雇用保険説明会の日時が決定する
前述のとおり、失業保険の受給には求職の意思と能力があり、求職活動を行う必要があります。そのため、ハローワーク窓口で、求職の意思を伝えたうえで、離職票の提出と求職の申し込むことが必要です。
求職の申し込みが完了して受給資格が決定すると、「失業等給付受給資格者のしおり」が窓口で渡されます。
また、原則として失業保険の受給にあたり、「雇用保険説明会」に参加して今後の流れなどの説明を受けなければなりません。参加すべき雇用保険説明会の日程は、求職申請日から7日後以降になります。求職申請時にハローワーク窓口で伝えられた日付を忘れずにメモしておき、必ず参加しましょう。
待機期間を過ごす
ハローワークでの求職申請が済んで受給資格を得ると、始めの支給までに7日間の待機期間が設けられます。この7日間は、ハローワークが求職者が失業状態にあることを調査する期間です。
そのため、待機期間中に就労すると失業状態にはないと判断され、求職申し込みをした日以降の失業期間が7日に満たない場合は給付されません。仮に、短時間の勤務やアルバイトをした場合は就労とみなされて支給日が後ろ倒しされるため、一切の就労をしないように気をつけましょう。
なお、失業保険の受給中に、給付日数を残して再就職する場合に一定の条件を満たすと、手続きを行うことで再就職手当を受給できます。しかし、待機期間中に入社日を迎えると、失業状態にはないと判断されて再就職手当を受け取ることができなくなります。再就職手当の受給を目指して求職活動を急ぐ場合は、注意してください。
雇用保険説明会に参加する
失業保険を受給するには、原則的には求職の申し込み時に案内された雇用保険受給説明会に参加しなければなりません。
雇用保険説明会では、失業保険の受給にあたって理解しておくべき仕組みや受給の流れ、再就職に向けた求職方法などが詳しく説明されるので、理解を深めることが重要です。
また、雇用保険説明会への参加時は、以下のものを持参してください。
- 雇用保険受給資格者のしおり(求職申請の際に受け取る)
- 印鑑(認印は可、スタンプ印は不可)
- 筆記用具(メモとペンなど)
雇用保険の説明会が終了すると、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡されます。また、初回の失業認定日が案内されるので確認しておきましょう。
失業認定日にハローワークを訪れる
前述の「失業認定日」とは、ハローワークが求職者に対して失業の事実を認定する日のことです。求職者は、ハローワーク窓口に失業認定申告書を提出して、就職活動をしている実績を報告することで、失業保険を受け取れます。
失業認定日は、通常は4週間ごとに1度、平日に設定されるもので、ハローワークから指定されます。ただし、初回の失業認定日は、離職票を提出して求職申請をした日から約3週間後に設定されるため、注意しましょう。
派遣で契約満了・終了・雇い止めになる主なケース
派遣社員として働く場合、契約満了とは別に、終了(契約解除)、雇い止めになることがあります。
終了とは、労働契約で定められた契約期間の途中に雇用契約が解除されることです。ただし、契約解除は派遣先企業、派遣元企業、労働者が一方的にできるものではなく、病気や違反行為などやむを得ない事情に限って認められます。
また、雇い止めとは、契約更新を繰り返して一定期間において雇用を継続していたにもかかわらず、期間満了のタイミングで契約更新をせずに退職させることです。契約期間が満了している以上、原則的には違法にはあたりません。しかし、従前は契約更新が繰り返されていたケースでは労働者には突然の負担となるため、法的な問題が生じる可能性があります。
ここからは、派遣勤務から契約満了・終了・雇い止めになる主な3つのケースについて解説します。
正社員として採用されるケース
契約満了や終了、雇い止めになる代表例に、有期契約で働く労働者が、その派遣先や契約先企業で正社員として採用されるケースがあげられます。この場合、従来の有期契約は終了して、新たに無期の正社員契約が締結されます。
ただし、派遣社員から正社員への移行に際して雇用元が変わり、労働条件や給与体系の変更が伴うことが多いため、労働者と企業間の双方での十分な協議が必要です。
企業の経営状況や業務内容の変化によるケース
企業の経営状況や業務内容の変化によって、契約の更新が見送られるケースも少なくありません。例えば、業績の悪化や事業縮小に伴って人員削減が必要となる場合、プロジェクトの終了によって特定の業務が不要となる場合などが該当します。
このようなケースでは、期間満了に伴って雇い止めの手段が取られます。しかし、従前は契約の更新が繰り返されている場合は、労働者が雇用の継続に対して合理的な期待を持っていることも多いでしょう。そのため、企業が一方的に契約を終了させることは、法的に問題となる可能性があります。
労働者に将来的な就労の機会を得させるためにも、企業は契約終了の前に、労働者に対して早めに通知し、適切な手続きを踏むことが求められます。
能力不足や勤務態度の不良が原因のケース
労働者の能力不足や勤務態度の不良が原因で、契約の更新が見送られるケースも、契約満了や終了、雇い止めにつながる代表例です。具体的には、業務遂行能力が不足して求められるレベルに達していない、無断欠勤が続く、職務命令違反を起こすケースなどが挙げられます。
ただし、これらの理由によって契約を更新しない場合は、企業はその正当性を明確に示さなければなりません。
派遣の「3年ルール」とは
前述の通り、派遣社員が働く際、派遣法によって同一の組織単位での派遣期間は3年が上限となる、「3年ルール」が存在します。ここでは、3年ルールの対象者と例外、3年を超えて働きたい場合の対処法を解説します。
対象者
「3年ルール」は、同一の派遣労働者が、同一の組織単位(課やグループなど)で3年を超えて働くことを制限する派遣法上の規定です。
3年以上同一の勤務先で働けない状況は、継続して働く機会が侵害されるようにも感じるかもしれません。しかし、実際は派遣社員を守るための重要な役割を果たします。3年ルールは、長期にわたり働き続けてきた派遣労働者の雇用の安定性を確保し、正社員との均等待遇を推進する目的で設けられているためです。
具体的には、同一の派遣労働者が同一の組織単位での就業期間が3年を超える場合は、派遣先企業はその労働者を直接雇用するか、もしくは他の組織単位に配置転換する必要があります。
ただし、次にご紹介するケースに該当する場合は、3年ルールの例外とされ、3年を超えて同一の組織単位でも就業することができます。
例外
3年ルールの例外に該当するのは、派遣先企業が労働組合の意見を聴取し、労使協定を締結した場合です。この場合は、派遣社員の雇用の安定が図られているため、同一の組織単位での派遣受け入れ期間を3年を超えて延長することが可能です。
さらに、60歳以上の派遣労働者や、産休・育休取得者の代替要員として派遣される場合なども、例外として扱われることがあります。
3年を超えて働き続けたい場合
3年ルールに該当するものの、同じ派遣先で3年を超えて働き続けたい場合には、次の2通りの対処法が考えられます。
- 派遣先企業に直接雇用を提案し、正社員や契約社員として採用されるケース
- 派遣先企業が労働組合との協議を経て、派遣受け入れ期間の延長を行うケース
このように、3年ルールに該当する場合でも、雇用形態を変更して派遣先と直接労働契約を結んだり、労働組合が協議を行ったりすれば、同一の職場で3年以上にわたって働くことが可能です。
契約満了する前に確認したいポイント
派遣社員が安定して働き続けるためには、契約満了前に以下の3つのポイントを確認しましょう。
契約期間の残り
契約満了前に必ず確認したいのが、残りの契約期間です。現在の契約期間がどれだけ残っているかを正確に把握することは、今後のキャリアプランを立てる上で非常に重要であるためです。
契約終了日を確認したうえで、退職までの期間にどのようなスキルを習得し、どのような実績を積むべきかを計画すると、次の就職活動を有利に進めることができるでしょう。また、契約期間中に達成すべき目標やプロジェクトを明確にして、それらを完遂すれば、自己評価や市場価値を高めることが可能です。
契約の更新
契約満了が近づいた際は、契約を更新するか否かを検討しましょう。自身のキャリア目標や職場環境、業務内容、待遇などを総合的に評価して、更新が自身の成長や満足度に寄与するかを判断してください。
更新を希望する場合は、早めに派遣元や派遣先と意思疎通を図り、条件交渉を行うことが望ましいでしょう。一方、新たなキャリアを模索する場合は、契約満了前から転職活動を開始して、スムーズな再就職を目指すことが重要です。
派遣先からの評価
派遣先からの評価は今後のキャリアに大きな影響を与える要素であるため、必ず確認しましょう。
定期的なフィードバックや評価面談を通じて、自身の業務遂行能力や職場での貢献度を確認することが大切です。
フィードバックの結果、高い評価を得ていることがわかれば、契約更新や直接雇用のオファーを受ける可能性が高まります。一方、改善点が指摘されている場合は、契約期間中にそれらを克服する努力を行い、評価の向上を目指すことが求められます。
契約満了の際の選択肢
契約満了の際は、派遣社員をしながらキャリアアップを目指すのか、それとも働き方自体を変えるのかを選択する良いタイミングです。ここでは、契約満了後の選択肢を3つご紹介します。
新しい派遣先を紹介してもらう
派遣会社は、登録スタッフのスキルや経験に基づき、適切な派遣先を提案する役割を担っており、契約満了の際は、新しい派遣先を紹介してもらえます。
別の派遣先を紹介してもらうメリットは、既に築かれた派遣会社との信頼関係や、これまでの業務経験を活かしやすい点です。ただし、希望する条件の派遣先がすぐに見つからない場合があるため、柔軟な対応が求められます。
違う派遣会社に登録する
現在の派遣会社で希望する条件の派遣先が見つからない場合は、新たな派遣会社への登録を視野に入れましょう。各派遣会社は異なる企業と取引関係を持っているため、複数の派遣会社に登録することで多様な求人へアクセスできる機会が増え、選択肢が広がります。
新しい派遣会社に登録するメリットは、自身のスキルやキャリアプランに合った派遣先を見つけやすくなる点です。ただし、新しい派遣会社との信頼関係を築きスキルを証明するために、登録時の面談やスキルチェックなどを再度行う必要があります。
正社員としての安定した雇用を目指す
契約満了を機に、正社員としての安定した雇用を目指すことも一つの選択肢です。正社員を目指すのであれば、ハローワークや求人サイトを活用して正社員の求人情報を収集し、積極的に応募しましょう。
正社員としての雇用は、雇用の安定性や福利厚生の充実など、多くのメリットがあります。ただし、即戦力としてのスキルや経験が求められることが多い点に注意が必要です。
また、転職活動には時間と労力が必要となるため、契約満了前から求人を探しておくなど、計画的に進めることが大切です。
【退職理由別】応募先企業に与えるイメージ
転職活動にあたっては、履歴書や職務経歴書の作成が必要です。その際、退職理由を書かなければならず、不安を感じる方もいるのではないでしょうか。ここからは、退職理由が契約満了、自己都合、会社都合の3つのケースに分けて、退職理由が応募先企業に与えるイメージについて解説します。
契約満了
契約社員や派遣社員として働いた後、契約期間の終了により退職した場合、応募先企業は悪い印象を持つことは基本的にはありません。反対に、安定した勤務を続けたことに対して評価する傾向があります。契約満了まで勤めたことは、最低限の業務遂行能力や責任感を持って働いていた証拠と捉えられやすいためです。
ただし、契約満了後の進路についての考えが問われることがあるため、説明できるように準備しておきましょう。
自己都合退職
自己都合退職の場合、応募先企業はその理由や背景を慎重に見極めようとします。例えば、キャリアチェンジやスキルアップを目的とした退職であれば、前向きな意欲を持つ人物として評価されやすいでしょう。
一方で、人間関係や労働環境への不満を理由に退職した場合は、ストレス耐性が低いと判断されることもあるため注意が必要です。また、短期間での転職を繰り返していると、長続きしない人物という印象を与えるリスクがともないます。
自己都合退職をした場合は、計画的なキャリア形成の一環であることを強調して、今後の目標や希望職種について具体的に伝えることが重要です。
会社都合退職
会社都合による退職は、経営悪化や事業縮小など企業側の事情によるものが多いため、応募先企業もその点を理解しやすい傾向があります。
特に、リストラや倒産など、本人の能力とは無関係に退職せざるを得なかった場合は、不当な評価を受けることは少ないでしょう。
ただし、会社都合退職の理由によっては、どのような状況だったのか詳しく説明を求められることがあります。例えば、業績不振による人員整理であれば問題視されることは少ない一方で、勤務態度や能力不足を理由に契約が打ち切られた場合は評価に影響する可能性があるでしょう。
契約満了から再就職を目指すポイント

契約満了から再就職を目指すには、契約満了前から準備をすることが大切です。ここからは、再就職を目指す際の3つのポイントを解説します。
契約満了が判明した時点で次の職を探し始める
契約満了後にスムーズに求職活動を進めるためには、契約満了が判明した時点で、次の職を探し始めることが重要です。契約期間が残っているにもかかわらず求人を確認することに全く問題はなく、反対に、早めの行動がスムーズな転職につながるためです。
在職中に転職活動を行う際は、履歴書の職歴欄には「在職中」と記載しましょう。また、面接時には退職予定日を伝えておくと、採用担当者も入社時期を調整しやすくなります。
次の職場に求める条件や待遇を明確にしておく
転職活動を始める前に、次の職場に求める条件や待遇を明確にしておくことも重要です。具体的には、給与、勤務時間、勤務地、福利厚生、職種、企業文化など、自分が重視する条件をリストアップして、優先順位をつけると良いでしょう。
希望条件をまとめておけば、求人情報を比較検討する際の指針が明確になり、ミスマッチを防ぐことができます。また、自身のスキルや経験を再確認して、それらがどのように新しい職場で活かせるかを考えると、自己PRの材料にもなります。
速やかに求人企業へのエントリーを開始する
契約満了後に更新を希望しないことを現職の企業に伝えた後は、速やかに求人企業へのエントリーを開始することが重要です。早めにエントリーすると、選考プロセスに余裕を持たせられ、採用側にも前向きな印象を与えられるためです。
早期に動き出すことで、複数の選択肢から最適な職場を選ぶことが可能となるでしょう。
より自分に合った職場を探す場合は、転職エージェントの活用もおすすめです。
退職コンシェルジュの運営するエージェントでは、給付金のプロ相手に再就職手当などの相談も可能です。まずはLINEで気軽にご相談ください!
まとめ
派遣社員における契約満了後に契約を更新しない場合、「雇用保険に加入して保険料を支払っている」「契約満了後に再就職を希望している」などの、一定の条件を満たせば失業保険を受給できます。一般的な契約満了には、派遣社員自身が更新を希望しない場合と、派遣先企業の都合による場合に分かれます。
自身で更新を希望しない場合は、契約満了がわかった時点で再就職先を探すのが良いでしょう。早めに行動することでさまざまな求人に触れることができ、最適な転職先を見つけやすくなるためです。
また、満足のいく求人が見つからない場合は生活を安定させるために、失業保険の受給も選択に入れましょう。失業保険の受給には、離職後に求職申し込みをしたうえで失業認定を受けるなどの手続きが必要です。
ただし、申請には必要書類が多く、どのように申請すれば良いかわからない方もいるでしょう。退職コンシェルジュが提供する「社会保険給付金サポート」では、支援実績が豊富な専任スタッフが、申請手続きを丁寧にサポートいたします。個別相談会や無料説明会も実施していますので、ぜひご参加ください。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
この記事の監修者

杉山 雅浩
東京弁護士会所属。
池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。
NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、
詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。
YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!
おすすめの関連記事
ピックアップ
- CATEGORY
- 給付金について
- 転職・再就職について
- 就労について
- 社会保険について
- 精神疾患について
- サービスについて
- 傷病手当金について
- 失業保険について
- 退職について
- 障害年金について
- ピックアップ
- 人気記事
-
退職代行サービスの利用方法、実際の流れと体験談を紹介
-
今の会社に3年後もいる自信はありますか?
-
退職代行を利用した時の有給消化の仕組みとその対応方法
-
退職代行サービスを使うメリット・デメリットは?
-
ブラック企業を判定する方法と実際のチェックポイント
-
障害年金を知ろう
-
会社を“円満に退職する”方法は?
-
退職時の引き継ぎは義務?スムーズな業務引き継ぎの必須ポイント
-
パワハラ、モラハラ、セクハラとは?
-
辞めさせてくれない!そんな時こそ「退職代行サービス」
テーマ
- 転職サイト
- 不支給
- 引っ越し
- 雇用契約
- 退職代行
- 職務経歴書
- 等級
- 社宅
- 内定
- 退職代行サービス
- 人間関係
- 離職票
- 障害者手帳
- 就労移行支援
- ブラック企業
- スタートアップ
- 労務不能
- 精神保険福祉手帳
- 業務委託
- ハラスメント
- 転職
- 傷病手当金
- 労災
- 社会保険
- 引き継ぎ
- 違法派遣
- 障害者控除
- 産休
- 福利厚生
- 給与
- 派遣契約
- 退職届
- 解雇
- 就職困難者
- 残業代
- 障害厚生年金
- 面接
- 中小企業
- 再就職手当
- 退職金
- 失業保険
- 障害手当金
- ベンチャー企業
- 社会保険給付金
- 会社都合退職
- 資格取得
- 新型コロナウイルス
- 退職勧奨
- 職業訓練受講給付金
- 自己都合退職
- うつ病
- 有給消化
- 自己PR
- 退職給付金
- クレジットカード
- 統合失調症
- 休職
- 確定申告
- ハローワーク
- アルバイト
- 契約社員
- 免除申請
- 保険料
- 傷病手当
- 雇用保険
- 弁護士
- 適応障害
- 社会保障
- 退職コンシェルジュ
- 健康保険
- 公的貸付制度
- 住宅確保給付
- 就職
- ストレス
- 年金
- 生活福祉資金貸付制度
- 職業訓練
- 労働基準法
新着記事
-
2025.12.08
産休・育休後そのまま退職はマナー違反?退職時のポイントと注意点
-
2025.12.07
会社を辞めさせられた場合は失業保険は受け取れる?条件や注意点を解説
-
2025.12.04
傷病手当金は退職後もらえない?受給できる条件と不支給になる理由を徹底解説
-
2025.12.01
休職でも傷病手当金はもらえる?休職手当との違いや支給額を解説
-
2025.12.01
うつ病は傷病手当がもらえない?活用できる制度も併せて紹介
-
2025.12.01
適応障害で傷病手当金はもらえる?受給するメリット・デメリットと申請方法
-
2025.12.01
退職後も傷病手当金はもらえる?受給できる条件と注意点を解説
-
2025.12.01
傷病手当金の支給日はいつになる?振込が遅れる原因と早く受給するコツ
-
2025.12.01
傷病手当金の計算方法は?早見表と調整されるケースも紹介
-
2025.12.01
傷病手当金をもらえない9つのケースとは?申請前に確認すべき条件と対処法を解説





 サービス詳細
サービス詳細