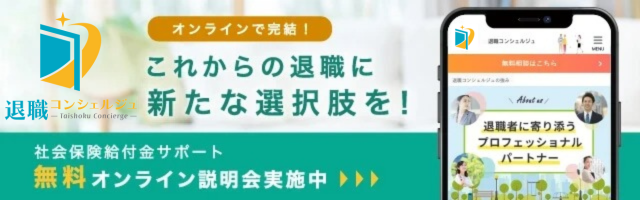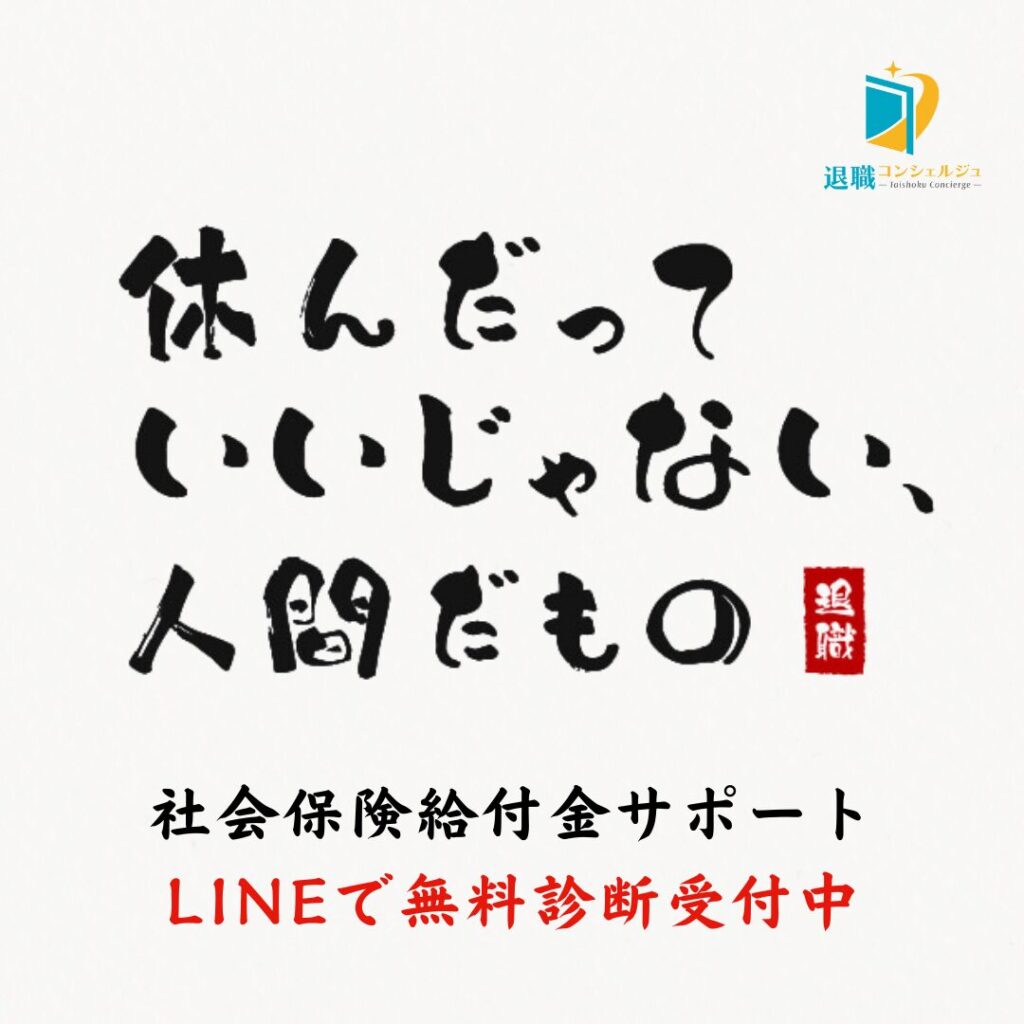労災保険とは?

労災保険(労働者災害補償保険)は、仕事中や通勤中に起きたケガや病気を補償する制度です。
厚生労働省が管轄し、労働基準監督署を通じて申請・給付が行われます。
参考:厚生労働省「労災保険制度について」
対象になるケース
- 仕事中にケガをした(工場・建設現場など)
- 通勤途中に交通事故に遭った
- 長時間労働が原因で体調を崩した(過労・うつ病など)
- 医療職で感染症にかかった
つまり、「仕事や通勤に関係するケガ・病気」なら労災の対象になります。
主な給付内容
労災保険にはいくつかの補償があり、代表的なものが次のとおりです。
| 給付の種類 | 内容 |
|---|---|
| 療養補償給付 | 医療費を全額補償(自己負担なし) |
| 休業補償給付 | 休業4日目以降、平均賃金の約60%支給 |
| 休業特別支給金 | さらに平均賃金の20%を上乗せ |
| 障害補償給付 | 障害が残った場合に支給 |
| 遺族補償給付 | 労災で死亡した場合の遺族補償 |
一方の傷病手当金は、業務外の理由で病気やケガをして働けないときに支給される健康保険の制度です。
たとえば「私生活中のケガ」「うつ病」「病気の治療で長期休職」などが対象になります。
参考:全国健康保険協会「傷病手当金」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/
支給条件
次の4つをすべて満たすと、傷病手当金を受け取れます。
- 業務外のケガや病気で働けない
- 医師が「労務不能」と診断している
- 3日間連続で休み(4日目から支給)
- 給与が出ていない、または減っている
支給額の目安
支給額は「標準報酬日額 × 3分の2」。
| 例:標準報酬月額が30万円なら
→ 30万円 ÷ 30 × 2/3 = 約6,667円/日 |
支給期間は「最長1年6か月」。
2022年(令和4年)からは途中で復職しても通算1年6か月まで支給OKになっています。
参考:厚生労働省「傷病手当金の支給期間が通算化されました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html
労災と傷病手当金の違いまとめ
| 比較項目 | 労災保険 | 傷病手当金 |
|---|---|---|
| 管轄 | 労働基準監督署(厚生労働省) | 健康保険組合・協会けんぽ |
| 対象 | 仕事中・通勤中のケガや病気 | 私生活中のケガや病気 |
| 支給額 | 平均賃金の約80% | 標準報酬日額の2/3 |
| 支給期間 | 治癒まで(制限なし) | 通算1年6か月 |
| 医療費 | 全額補償(自己負担なし) | 3割負担 |
よく似ているようですが、「仕事が原因かどうか」が最大の違いです。
労災と傷病手当金、どっちを使えばいい?
仕事中にケガをしたり、体調を崩したりすると、まず気になるのが「これって労災?それとも傷病手当金?」という点ですよね。
実は、この2つを見分けるポイントはとてもシンプルです。
| 発生した状況 | 使う制度 | 手続き先 |
|---|---|---|
| 仕事中にケガ・病気をした | 労災保険 | 労働基準監督署 |
| 通勤途中で事故に遭った | 労災保険(通勤災害) | 労働基準監督署 |
| プライベート中のケガ・病気 | 傷病手当金(健康保険) | 健康保険組合 |
つまり、「仕事や通勤が関係しているかどうか」がポイントです。
労災かどうかは「業務との関係性」で判断
厚生労働省では、労災かどうかを判断する際に
- 業務遂行性(仕事中だったか)
- 業務起因性(仕事が原因だったか)
という2つの観点を見ています。
たとえば、
- 会社で作業中にケガをした → 労災
- 取引先に向かう途中で事故に遭った → 労災(業務中)
- 退勤後に私用で寄り道中に事故 → 労災ではなく傷病手当金
といった具合です。
労災と傷病手当金、両方もらえる?
よくある質問が「両方申請すれば2倍もらえるのでは?」というものですが、残念ながら同じケガや病気では併用できません。
どちらも「働けない期間の生活を補う」ことが目的なので、二重でもらうことはできない仕組みになっています。
参考:全国健康保険協会「傷病手当金と労災保険給付の関係」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
「あとから労災認定された」場合は?
最初は「業務外のケガ」として傷病手当金を受け取っていたけれど、後から「やっぱり労災だった」と認められるケースもあります。
この場合、健康保険側に返金が必要になることがあります。
(同じ期間で両方受け取るのは二重給付になるため)
特に「うつ病」や「腰痛」「過労による体調不良」などは、仕事との関係が分かりづらく、あとから変更になるパターンが少なくありません。
迷ったときの進め方
「どっちかわからない」というときは、焦らず次の流れで進めましょう。
① 状況を整理する
- いつ・どこで発生したか
- 何をしている最中だったか
- 誰の指示で動いていたか
をしっかりメモに残しておきましょう。後で申請時に役立ちます。
② 労災の可能性があればまず監督署に相談
会社を通じて、労働基準監督署に労災保険給付請求書(様式第8号)を提出します。
医師の証明や会社の署名が必要なので、個人では難しい手続きですが、会社に拒否権はありません。
参考:厚生労働省「労災保険の請求手続」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148874.html
③ 労災が不支給になったら傷病手当金に切り替え
万が一、労災が認められなかった場合は、健康保険の「傷病手当金」に切り替えて申請します。
このとき、過去分をさかのぼって支給されることもあります(ただし時効は2年)。
「例外的に併用できる」こともある
原則はどちらか一方ですが、別の原因で新しい病気やケガが発生した場合は、両方の制度を使えることもあります。
たとえば、
- 仕事中の事故(労災)で療養中に、私生活で風邪をひいた(傷病手当金対象)
- 労災治療中に、別の病気が発症し、医師が「業務とは無関係」と判断
このように、病名や発生原因が明確に別なら、併用も可能です。
ただし、医師の診断書と書類の整合性が重要なので、必ず会社や保険組合に確認しましょう。
会社・人事担当者が注意すべきこと
企業側も、従業員から相談を受けたときに誤った案内をしてしまうとトラブルになりかねません。
- 「労災隠し」(労災をわざと健康保険扱いにする)は法律違反(労働基準法第100条)
- 申請を拒否したり、圧力をかけるのはNG
- 曖昧なケースは“労災の可能性あり”として報告するのが安全
上記の基準や情報を確認してもそれでももし判断に迷うときは、労働基準監督署か社会保険労務士に相談するのが確実です。
傷病手当金を受け取るための条件
「傷病手当金」は、健康保険に入っている人が業務外の病気やケガで働けなくなったときに支給される手当です。
ここでは、実際に受け取るための条件を詳しく見ていきましょう。
支給されるための4つの条件
- 業務外のケガ・病気であること(プライベート中の事故や病気など)
- 医師が“働けない”と診断していること(労務不能の証明)
- 連続して3日休んでいること(4日目から支給対象)
- 給与が出ていない、または減っていること
この「3日間」は、会社の休日も含めてカウントされます。
つまり、金曜に倒れて休んだ場合でも、金・土・日で3日とカウントされ、月曜からが支給対象になるということです。
参考:全国健康保険協会「傷病手当金」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/
支給される期間は「通算で1年6か月」
以前は「連続して1年6か月」が限度でしたが、2022年1月の改正で、途中で復職しても「通算で1年6か月」まで支給されるようになりました。
たとえば、
| 3か月休職 → 復職 → 再発で6か月休職 → 再復職 |
というケースなら、合計9か月分の支給が可能です。
長期的な療養や再発のリスクがある人にとって、安心できる制度になりました。
参考:厚生労働省「傷病手当金の支給期間が通算化されました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html
支給金額の計算方法
支給額は、ざっくりいうと「お給料の約3分の2」です。
具体的には次の計算式で出します。
| 支給額(日額)= 過去12か月の平均標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3
例)標準報酬月額が30万円の場合 30万円 ÷ 30日 × 2/3 = 約6,667円/日 |
この金額が、働けなかった日数分だけ支給されます。
参考:厚生労働省「健康保険法に基づく傷病手当金の計算方法」
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000619554.pdf
支給開始日は「4日目から」
傷病手当金は、休業初日からもらえるわけではありません。
最初の3日間(待期期間)は対象外で、4日目から支給となります。
| 期間 | 扱い | 支給 |
|---|---|---|
| 休業1〜3日目 | 待期期間(支給なし) | ✕ |
| 休業4日目以降 | 支給対象 | ○ |
例:会社から一部給与が出ている場合
給与が少しでも出ている場合は、差額分だけ支給されます。
例)
- 標準報酬日額:10,000円
- 傷病手当金:10,000円 × 2/3 = 6,667円
- 会社からの支給:5,000円
→ 差額の1,667円/日が健康保険から支給されます。
退職後でももらえるケース
「退職したあとでも、傷病手当金はもらえるの?」という質問もよくあります。
結論から言うと、退職時点で要件を満たしていれば受け取り可能です。
退職後でも支給される条件
- 退職前にすでに傷病手当金の支給を受けている、または支給要件を満たしている
- 退職日も引き続き“働けない状態”である
- 退職日に健康保険の資格がある(社会保険加入中)
- 退職後に別の健康保険に加入していない
この条件を満たしていれば、最長1年6か月まで支給が続くことになります。
参考:全国健康保険協会「退職後の傷病手当金」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat510/sb5120/sbb51210/2263-278/
任意継続した場合は注意
退職後に「任意継続被保険者」として健康保険に残っても、新たに傷病手当金はもらえません。
任意継続で受けられるのは“医療費の給付”のみで、“収入の補償”は対象外です。
申請に必要な書類
実際に申請する際には、次の書類を用意します。
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 傷病手当金支給申請書 | 本人が作成。休業期間などを記入 |
| 医師の意見書 | 「労務不能」の診断証明欄 |
| 事業主記入欄 | 会社が勤務実績や給与支払いを記入 |
| 添付資料 | 給与明細・休業証明など(必要に応じて) |
申請は会社経由で健康保険組合に提出します。
申請のタイミング
基本的には1か月分ごとにまとめて申請します。
たとえば4月に休んだ分は、5月初旬にまとめて提出するイメージです。
注意点として、2年を過ぎると時効で支給されなくなるため、早めの申請を心がけましょう。
労災保険の「休業補償給付」ってなに?
労災保険のなかで、休業中の収入を補う制度が「休業補償給付」です。
仕事中や通勤途中の事故・ケガなどで働けなくなったときに、お給料の約8割が補償されます。
この「8割」は、実は2つの支給で構成されています。
- 休業補償給付:平均賃金の60%
- 休業特別支給金:さらに20%を上乗せ
つまり、合計で約80%の収入がカバーされる仕組みです。
参考:厚生労働省「労災保険制度について」
対象になる人
労災の休業補償を受けられるのは、次の条件を満たす人です。
- 仕事中または通勤途中のケガ・病気で働けなくなった
- 実際に仕事を休んでいる
- 休業期間中の給与が支払われていない(または一部のみ)
- 労災保険に入っている労働者である
ここでいう“労働者”は、正社員だけでなく、アルバイト・パート・派遣社員も含まれます。
雇用形態に関係なく、労災が認められれば対象です。
支給のタイミングと仕組み
休業初日からすぐに労災給付が出るわけではありません。
- 休業初日〜3日目:会社(事業主)が「休業補償(労働基準法第76条)」として平均賃金の60%を支払う
- 4日目以降:労災保険から「休業補償給付(60%)」+「特別支給金(20%)」が支給される
つまり、最初の3日間は会社負担、4日目からは国(労災保険)が補償する形です。
| 期間 | 支給者 | 支給内容 | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 1〜3日目 | 会社(事業主) | 休業補償(労働基準法) | 平均賃金の60% |
| 4日目以降 | 労災保険 | 休業補償給付+特別支給金 | 平均賃金の80%程度 |
支給金額のイメージ
支給額の計算はシンプルです。
| 休業補償給付:平均賃金 × 0.6
休業特別支給金:平均賃金 × 0.2 例)平均賃金が12,000円の場合 休業補償給付:12,000円 × 0.6 = 7,200円 休業特別支給金:12,000円 × 0.2 = 2,400円 合計:9,600円/日(約80%) |
つまり、生活費の大部分をカバーできる計算になります。
支給期間と「治癒」の考え方
労災の休業補償は、治療が続く限り支給されるのが特徴です。
健康保険の傷病手当金のように「1年6か月の上限」はありません。
ただし、ケガや病気が「治癒」と判断された時点で終了します。
ここでいう“治癒”とは、「仕事に復帰できる状態になった」または「症状が固定され、障害補償に切り替わる」ことを指します。
申請の流れ
実際の申請は、会社経由で労働基準監督署に行います。
以下の流れを押さえておきましょう。
労災(休業補償給付)申請の流れ
業務上・通勤途上のケガや病気で働けない場合の手順。1〜3日目は事業主の休業補償(平均賃金の60%)、4日目以降は労災から給付(60%+特別20%)。
1
・「仕事/通勤中の事故」と伝える。労災指定医療機関なら窓口負担なし。
・医師に就労不能(労務不能)の証明を書いてもらう(労災様式の診断欄)。
2
・休業補償給付支給請求書(様式第8号)に、本人・医師・事業主が記入/証明。
・勤務実績、賃金、事故状況などの証明資料を添付。
3
・業務遂行性/起因性(仕事や通勤との関係)を中心に確認。
・必要に応じて追加資料の提出を求められることあり。
4
・決定通知後、指定口座へ振込。
・4日目以降は「60%+特別20%」相当で支給。継続分は期間ごとに申請。
- 休業補償給付支給請求書(様式第8号)…本人・医師・事業主の各記入欄
- 医師の診断・就労不能の証明
- 賃金台帳・出勤簿などの写し
- 事故状況のわかる資料(労災発生報告、通勤経路など)
・1〜3日目は事業主の休業補償(平均賃金60%)。
・4日目以降は労災から60%+特別20%。
・認定に時間がかかる場合あり。勤務記録・指示記録・事故メモを残す。
・会社が協力しない場合でも、労働者本人の請求は可能(事後の会社証明は必要)。
よくある注意点
① 労災隠しは絶対NG
「会社のイメージが悪くなるから」といって、労災を隠して健康保険で処理するのは違法です。
見つかれば、会社に罰金(50万円以下)などの行政処分が下されることもあります。
② 労災認定まで時間がかかることも
特に「うつ病」「過労死」など、業務との因果関係が複雑なケースは、審査に時間がかかる傾向があります。
勤務記録や上司の指示メールなど、客観的な証拠を残しておくことが大切です。
③ 会社の協力が不可欠
申請書には会社の証明欄が必要なため、本人だけでは手続きができません。
会社は労働者からの申請を拒むことはできません。
労災と傷病手当金の比較まとめ
| 項目 | 労災保険(休業補償給付) | 健康保険(傷病手当金) |
|---|---|---|
| 対象 | 仕事・通勤中のケガ・病気 | 私生活中のケガ・病気 |
| 管轄 | 労働基準監督署 | 健康保険組合・協会けんぽ |
| 支給開始 | 休業4日目から(最初の3日は会社) | 待期3日後の4日目から |
| 支給額 | 平均賃金の約80% | 標準報酬日額の2/3 |
| 支給期間 | 治るまで(制限なし) | 通算1年6か月まで |
ケース別で見る「労災」と「傷病手当金」の使い分け

制度の違いを理解していても、実際にどちらを使えばいいか迷う場面は多いですよね。
ここでは、よくある4つのケースで整理してみましょう。
ケース①:勤務中のケガ
製造現場で作業中に手を切って2週間休むことになった。
→ 業務中の事故なので「労災保険」が対象。
医療費は全額補償、休業4日目以降は平均賃金の約80%が支給されます。
ケース②:通勤途中の交通事故
自転車で通勤中に転倒し、1か月の休業が必要になった。
→ 通勤途上の事故も「労災(通勤災害)」として扱われます。
会社を通して監督署に申請すればOKです。
ケース③:プライベート中のケガや病気
休日にスポーツで足を骨折して休職。
→ 業務外のため、「健康保険の傷病手当金」が対象。
給与が出ていない期間に、標準報酬日額の3分の2が支給されます。
ケース④:うつ病や過労による体調不良
長時間労働や職場ストレスで心身の不調を訴えた場合。
→ 業務との関連性があるかどうかで判断が分かれます。
業務が原因と認められた → 労災保険
私生活やプライベート要因が中心 → 傷病手当金
精神疾患や過労系のケースは、判断が難しいため、早めに医師・会社・監督署に相談しておくのが安心です。
よくある質問(Q&A)
Q1. 労災と傷病手当金、両方申請してもいい?
A. 同じケガ・病気で両方をもらうことはできません。
どちらか一方を選ぶ形になります。
ただし、別の病気やケガが原因なら併用OKです。
Q2. 労災が認められなかったらどうすれば?
A. その場合は健康保険の「傷病手当金」に切り替えましょう。
労災の不支給通知を添付すれば、健康保険側で改めて審査されます。
Q3. 退職したあとでも労災給付は受けられる?
A. 受けられます。
労災は「在職中に発生したケガ・病気」であれば、退職後でも継続して支給対象になります。
Q4. 会社が「労災扱いにしない」と言ってきたら?
A. 労災申請は本人でも可能です。
会社が協力しない場合でも、本人が直接労働基準監督署に申請できます。
拒否されたり「うちは労災は出せない」と言われても、あきらめる必要はありません。
参考:厚生労働省「労災保険の請求手続」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148874.html
「労災」と「傷病手当金」— どっちの方がが得?比較表
| 比較軸 | 労災保険(休業補償給付+特別支給金) | 健康保険(傷病手当金) |
|---|---|---|
| 1日当たりの手取り目安 | 平均賃金の約80%(60%+特別20%) (厚生労働省) | 標準報酬日額の2/3(=過去12か月平均の標準報酬月額÷30×2/3) (厚生労働省) |
| 医療費の自己負担 | 0円(原則全額補償) (厚生労働省) | 3割負担(通常の健康保険) |
| 受給できる期間 | 治癒・症状固定まで(上限なし) | 通算1年6か月(2022年改正) (厚生労働省) |
| 申請先・審査の重さ | 労基署。業務との因果関係の立証が必要(重め) | 健保組合・協会けんぽ(比較的スムーズ) |
| 併用可否(同一傷病・同期間) | 同時併用不可(どちらか一方に整理) | 同時併用不可/ただし制度間で差額調整・返還ありの運用がある (協会けんぽ) |
期間や金額等で考えると労災の方が得に見えますが、大前提まずはしっかり自分はどちらが対象なのかをこれまでの内容を踏まえて判断することが大切です。
まとめ:迷ったら「どこで・なぜ起きたか」で判断しよう
ここまで見てきたとおり、労災と傷病手当金はどちらも大切な制度ですが、使い方を間違えると受け取れないこともあります。
判断のコツはシンプルです。
- 仕事や通勤が原因 → 労災保険
- 私生活が原因 → 傷病手当金
もし「どっちかわからない…」と思ったら、
「社会保険給付金サポート」にも相談してみましょう。
LINEから気軽に10秒で問い合わせ可能です。
早めに正しい手続きをすれば、きっと安心して治療に専念できるでしょう。

 給付金がいくらもらえるか
知りたい方
給付金がいくらもらえるか
知りたい方 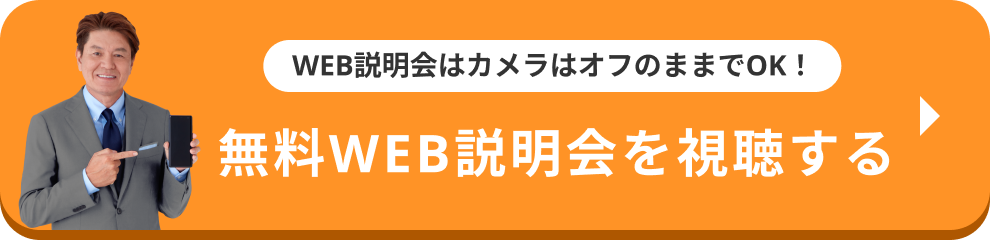
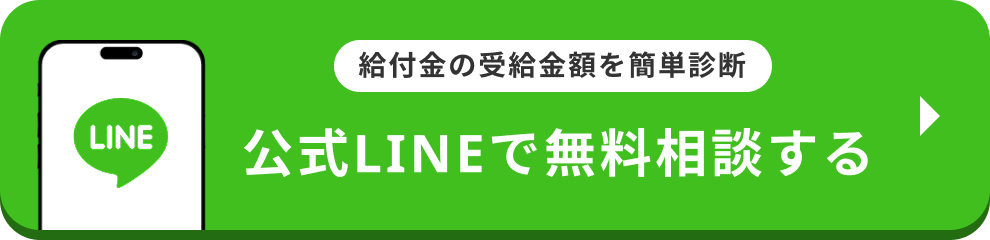
 給付金サポートを
ご検討中の方
給付金サポートを
ご検討中の方  評判・口コミ
評判・口コミ  給付金がもらえる
転職支援を活用する方
給付金がもらえる
転職支援を活用する方  その他退職について
ご不安がある方
その他退職について
ご不安がある方  もらえる給付金ラボ
もらえる給付金ラボ  退職コンシェルジュについて
退職コンシェルジュについて