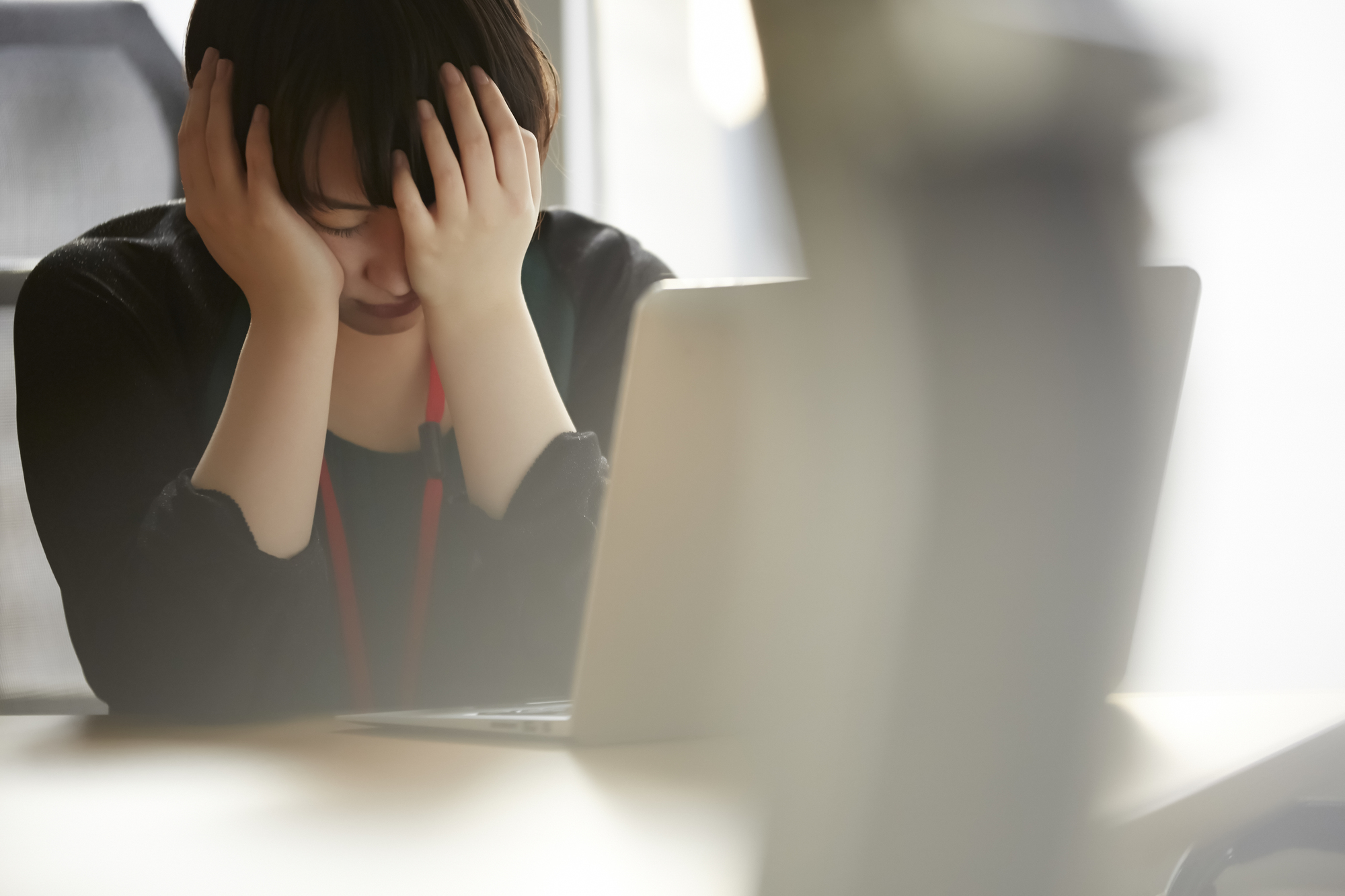2025.08.01
精神疾患について
うつで退職を決める前にやっておくべきことは?退職の流れや活用できる制度を解説
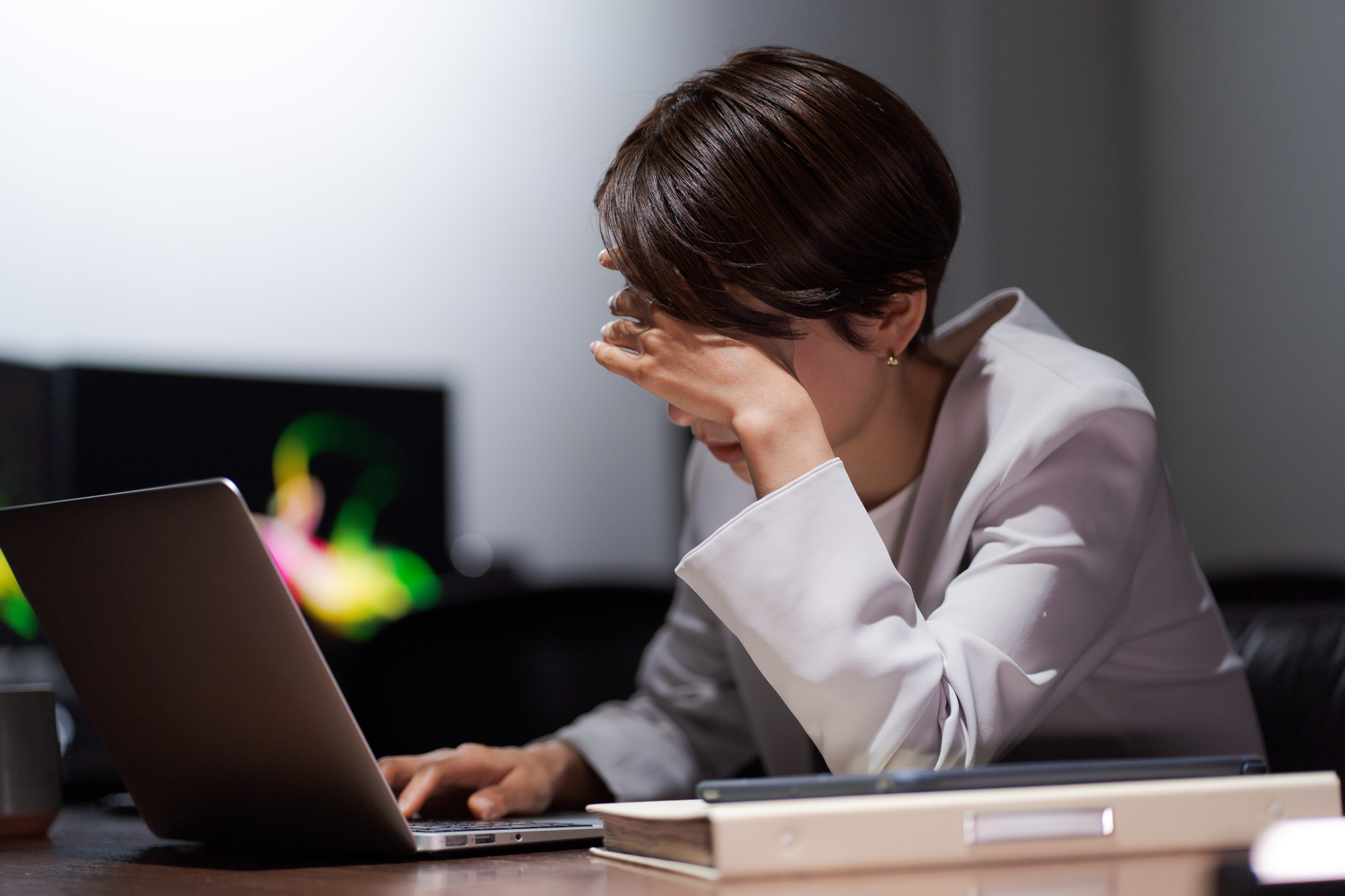 うつ病による退職を考えているものの、「何を準備すればいいのか分からない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。退職にあたっては、医師の診断や会社とのやりとり、公的制度の申請など、多くの手続きが発生します。状況に応じた支援制度を活用しないと、生活の不安が増したり、損をしたりする可能性があります。
うつ病による退職を考えているものの、「何を準備すればいいのか分からない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。退職にあたっては、医師の診断や会社とのやりとり、公的制度の申請など、多くの手続きが発生します。状況に応じた支援制度を活用しないと、生活の不安が増したり、損をしたりする可能性があります。
本記事では、うつで退職する前にやっておきたいことや、実際の手続きの流れ、退職後に受け取れる可能性のある給付制度、再就職に向けた支援までをわかりやすく解説します。
うつで退職を決める前にやっておくべきこと

うつ病による退職は、心身の負担を軽減する一つの選択肢ですが、勢いだけで決断すると後悔することもあります。退職の前にできることを整理し、将来の不安やトラブルを減らしましょう。
医師への相談や休職の検討、職場との調整方法など、退職を決める前に考えておきたいポイントを解説します。
医師に相談して病状を客観的に把握する
うつ病かどうかを自分で判断することは難しく、他の病気が隠れている場合もあります。まずは心療内科や精神科を受診し、専門医の診断を受けることが重要です。病状の把握には継続的な通院が効果的で、診断書の取得にもつながります。
診断書は、休職や退職時に会社へ説明する際や、傷病手当金の申請などにも活用可能です。症状がつらく受診が難しい場合は、オンライン診療なども選択肢に入れましょう。
判断を急がずにまずは休職を検討する
うつ病の症状があるときは、思考力や判断力が低下していることが多く、冷静に退職を決めるのは難しいものです。まずは心身を休めることを優先し、休職制度の利用を検討しましょう。
休職の期間や給与の支給条件は企業によって異なるため、就業規則を確認することが大切です。休職中に治療を進め、症状が落ち着いてから今後の働き方や退職の可否を考えることが、後悔の少ない選択につながります。
家族や身近な人に状況を共有・相談する
うつ病は、心の不調だけでなく日常生活にも影響を及ぼします。病気の一種であり、恥ずかしいと思う必要はありません。一人で抱え込まず、信頼できる家族や友人に早めに相談することが大切です。精神的な支えになるだけでなく、通院の付き添いや家計の見直しなど、生活面でも協力を得やすくなります。
また、退職後の生活設計や収入面についても、第三者と話すことで冷静に考えられるようになります。事後報告ではなく、早めに共有しておくことでトラブルの回避にもつながります。
配置転換・短時間勤務などの職場の選択肢を模索する
退職の前に、職場内でできる対策を検討してみるのもひとつの方法です。たとえば、業務量の調整や職種の変更、時短勤務などによって、無理なく働き続けられる可能性があります。
企業によっては短時間勤務制度が設けられていることもあるため、労務担当者に制度の有無や利用条件を確認してみましょう。必要に応じて産業医に相談し、会社との橋渡しをしてもらうことで、より現実的な対応も可能です。
就業規則や雇用契約を再確認しておく
退職や配置転換、休職などを検討する前に、自分の働き方が契約や規則に沿った内容になっているかを確認しておくことが重要です。たとえば、労働時間や業務内容が契約と違っていれば、改善を求めたり、円満に退職しやすくなったりする場合もあります。
また、就業規則の中には、休職制度や異動の条件が書かれていることがあるため、制度を利用する際の判断材料になります。規則や契約内容を読み返すことは、自分を守る選択肢の拡大に広がります。
経済面と退職後の支援制度を調べて備える
退職後の生活を安定させるためには、経済的な備えが欠かせません。たとえば、うつ病で働けない期間には「傷病手当金」や「失業手当」「労災保険」などの制度を活用できる場合があります。
それぞれ受給条件や申請手続きは異なるため、自分に該当する制度を調べ、準備しておきましょう。併せて、家族と一緒に家計の見直しや貯金額の確認もしておくと安心です。制度を知ることは、将来への不安を和らげる手助けにもなります。
ストレスの原因と職場環境を記録して整理する
うつ病の背景に職場のストレスがある場合、その内容を記録しておくことは大切です。たとえば、長時間労働やパワハラなどがあれば、日時や状況を具体的にメモしておきましょう。これらの記録は、退職理由を説明する際や、公的制度の申請時の裏付け資料になります。
自分にとって負担となる働き方や環境を客観的に整理することで、今後の再発予防や転職時の希望条件を明確にする手がかりにもなります。
うつで退職する際の流れや手続き
うつ病による退職は、心身の状態を守るための大切な選択肢のひとつですが、スムーズに進めるには事前の準備が欠かせません。医療機関の受診から退職の意思表示、各種手続きまで、流れを理解しておくことで余計な負担を減らすことができます。
うつで退職する際に必要となる基本的な手順や注意点を順を追って紹介します。
1. 医療機関を受診して診断書を取得する
退職前に、まず心療内科や精神科を受診し、現在の状態を正しく診断してもらいましょう。医師から「うつ病」と診断されることで、今後の対応がより明確になります。診断書は、職場への説明や傷病手当金などの制度を利用する際にも必要となる重要な書類です。
即日発行が難しい場合や費用がかかるケースもあるため、余裕をもって依頼しておくと安心です。継続的に通院しておくことで、今後の手続きに役立ちます。
2. 退職の意思を会社へ伝える
退職を決めたら、まずは会社に意思を伝えましょう。上司や人事担当者に、メール・電話・対面など、自分の負担にならない方法で伝えるのがおすすめです。就業規則で定められた退職の申出期限(たとえば「2週間前までに申告」など)も事前に確認しておきましょう。
うつ病であることを必ずしも詳しく説明する必要はなく、「一身上の都合」と伝えるだけでも問題ありません。無理のない方法と適切なタイミングを選ぶことが大切です。
3. 退職届を作成・提出し、有給休暇を消化する
退職の意思が受理されたら、会社の規定に従って退職届を作成・提出します。企業によってはフォーマットが指定されている場合もあるため、確認してから準備しましょう。提出後は、可能な範囲で有給休暇を使い、体調を整える時間にあてるのがおすすめです。
退職後に必要となる書類の受け取りやスムーズな連絡のやりとりに備えて、人事担当者などの連絡先を控えておくと安心です。
4. 社会保険・年金の切り替え手続きを行う
退職後は、健康保険と年金の切り替えが必要になります。健康保険は「国民健康保険」「任意継続」「家族の扶養に入る」のいずれかから選ぶ形になります。年金については、会社員として加入していた厚生年金から、退職後は国民年金への切り替えが基本です。
いずれも市区町村の窓口で手続きが必要となるため、必要書類を確認し、退職後できるだけ早めに行いましょう。
5. 離職票の交付を依頼する
離職票は、退職後に会社から発行される書類で、雇用保険(失業手当)を申請する際に必要です。ただし、会社によっては本人からの申し出がないと発行してもらえない場合もあります。退職時に「離職票が必要」と伝えておき、後日郵送してもらうよう依頼しておくと安心です。
離職票が届いたら、ハローワークでの手続きに進みましょう。退職から10日以内を目安に準備を始めると、支給開始までの流れがスムーズになります。
うつで退職した人がもらえる可能性のある制度や手当
うつ病で退職し、すぐに働けない場合に役立つのが、公的な制度や手当の活用です。経済的な不安を和らげながら、治療や生活を安定させるための支援を受けられる可能性があります。
うつ病で退職した人が利用できる主な制度と、それぞれの概要や申請条件について解説します。
失業保険(基本手当)
失業保険(基本手当)は、離職後の生活を支えるために支給される給付金です。自己都合退職の場合でも、うつ病などやむを得ない理由があれば「特定理由離職者」として扱われ、給付制限なしで早期に受給を開始できる可能性があります。
支給額は退職前6ヶ月の給与をもとに算出され、おおよそ50~80%が目安です。受給にはハローワークでの求職申込みと、離職票の提出が必要になります。
傷病手当金
傷病手当金は、会社を休職・退職したあとも、病気やケガで働けない場合に支給される制度です。連続して会社を3日間休んだ場合、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。健康保険に加入していた人が対象で、在職中にうつ病の診断を受けていれば、退職後も一定の条件を満たすことで受給できます。
支給期間は最長1年6ヶ月で、金額は退職前の給与のおおよそ3分の2が目安です。受給には、医師の診断と会社の証明、申請書の提出が必要になります。働けない期間の生活を支える重要な制度です。
障害年金
障害年金には「障害基礎年金(国民年金加入者)」と「障害厚生年金(厚生年金加入者)」があり、受給には初診日や保険加入状況、症状の重さなどが関係します。うつ病などの精神疾患も、一定の条件を満たせば障害年金の対象になります。
障害者手帳がなくても申請できることが特徴で、支給額は年額83万円〜104万円以上が目安です。等級や扶養家族によって異なるものの、長期的な支援として活用できる可能性があり、心強い制度と言えるでしょう。
雇用保険の傷病手当
雇用保険の傷病手当は、うつ病などで15日以上働けないときに、失業保険の代わりとして受け取れる制度です。支給額は失業保険(基本手当)と同じで、医師による就労不能の証明が必要になります。
申請により、最大4年間まで受給期間を延長できる点も特徴のひとつです。体調が回復してから失業保険に切り替えることも可能なため、療養を優先したい方にとって心強い制度といえます。
自立支援医療制度
自立支援医療制度は、精神疾患で通院治療をしている人の医療費を軽減する制度です。対象者は原則として医療費の自己負担が1割になり、所得に応じて月額の上限も設定されます。継続的に治療を受ける場合の経済的な負担が大きく軽減されるため、通院を続けやすくなるメリットがあります。申請には市区町村の福祉窓口での手続きと、医師による診断書が必要です。
労災保険
うつ病の原因が職場にあると考えられる場合は、労災保険の対象となることがあります。たとえば、パワハラや長時間労働などの職場環境が原因で発症したケースです。労災と認定されれば、治療費の全額補償や休業補償、障害補償などの給付が受けられます。
ただし、因果関係を証明する必要があり、具体的な記録や証拠が求められます。手続きには時間がかかることもあるため、早めの準備と専門機関への相談が重要です。
うつ病で退職した人が再就職するために活用したい制度とサービス

うつ病で退職した後、「また働きたい」と思っても、ブランクや体調への不安から、すぐには踏み出せないこともあります。そんなときに頼りになるのが、就労支援の制度や公的サービスです。制度やサービスの活用により、精神的なケアを受けながら、自分のペースで働く準備を整えていきましょう。
うつ病からの回復を経て再就職を目指す方に向けて、活用できる主な支援制度を紹介します。
就労移行支援や就労継続支援
「就労移行支援」は、一般企業への就職を目指す人向けのサービスです。ビジネスマナーやパソコンスキルの習得、職場実習などを通じて、再就職に向けた力を身につけられます。原則2年間の利用が可能です。
「就労継続支援」にはA型とB型があり、A型は雇用契約を結んで働くスタイル、B型は体調にあわせて、より柔軟な支援が受けられるなど無理のない作業が中心です。どちらも福祉サービスの一環として提供されており、自分の体調や状況に応じた働き方を模索するうえで役立つ支援制度です。
ハローワーク
ハローワークでは、うつ病など精神疾患のある方に向けた支援体制が整えられています。専門の相談員が在籍しており、一般求人だけでなく障害者雇用枠の求人紹介や、面接対策、応募書類の添削など、再就職に必要な支援を一貫して受けられます。ときには企業実習や職場見学の機会が設けられる場合もあります。
また、障害者手帳を持っていなくても利用できるため、「今は手帳の申請までは考えていない」と迷っている段階でも相談が可能です。まずは最寄りのハローワークに問い合わせ、今の状況を伝えることから始めましょう。
障害者就業・生活支援センター
「障害者就業・生活支援センター」は、仕事と日常生活の両面からサポートしてくれる公的機関です。就職活動のアドバイスだけでなく、生活リズムの整え方、金銭管理、健康面のフォローなど、就労を継続するために必要な支援を包括的に受けられます。
相談は無料で、障害者手帳を持っていなくても利用できる場合があります。再就職後も定期的な面談や職場との連携を通じて支援を続けてくれるため、「働き続けられるか不安」という人にとって、心強い存在となるでしょう。退職前の段階でも相談可能です。
まとめ
うつ病による退職は、決して特別なことではありません。退職は、自分自身を守るための大切な選択肢のひとつです。
退職を決める前にやっておきたい準備には、医師への相談や休職の検討、職場との調整方法、経済面の備えなどがあります。傷病手当金や失業保険、障害年金、自立支援医療制度といった支援制度や、再就職を支えるサービスなどの制度を知り、備えておくことで、退職後の不安を減らし、安心して次のステップに進むことができます。
「制度が複雑」「給付金の対象者かどうかよくわからない」と感じた方は社会保険給付金サポートの利用もおすすめです。専門家のサポートにより、申請や手続きに不安がある方でも、状況に応じたアドバイスやサポートが受けられます。
この記事の監修者

杉山 雅浩
東京弁護士会所属。
池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。
NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、
詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。
YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!
おすすめの関連記事
ピックアップ
- CATEGORY
- 給付金について
- 転職・再就職について
- 就労について
- 社会保険について
- 精神疾患について
- サービスについて
- 傷病手当金について
- 失業保険について
- 退職について
- 障害年金について
- ピックアップ
- 人気記事
-
退職代行サービスの利用方法、実際の流れと体験談を紹介
-
今の会社に3年後もいる自信はありますか?
-
退職代行を利用した時の有給消化の仕組みとその対応方法
-
退職代行サービスを使うメリット・デメリットは?
-
ブラック企業を判定する方法と実際のチェックポイント
-
障害年金を知ろう
-
会社を“円満に退職する”方法は?
-
退職時の引き継ぎは義務?スムーズな業務引き継ぎの必須ポイント
-
パワハラ、モラハラ、セクハラとは?
-
辞めさせてくれない!そんな時こそ「退職代行サービス」
テーマ
- 転職サイト
- 不支給
- 引っ越し
- 雇用契約
- 退職代行
- 職務経歴書
- 等級
- 社宅
- 内定
- 退職代行サービス
- 人間関係
- 離職票
- 障害者手帳
- 就労移行支援
- ブラック企業
- スタートアップ
- 労務不能
- 精神保険福祉手帳
- 業務委託
- ハラスメント
- 転職
- 傷病手当金
- 労災
- 社会保険
- 引き継ぎ
- 違法派遣
- 障害者控除
- 産休
- 福利厚生
- 給与
- 派遣契約
- 退職届
- 解雇
- 就職困難者
- 残業代
- 障害厚生年金
- 面接
- 中小企業
- 再就職手当
- 退職金
- 失業保険
- 障害手当金
- ベンチャー企業
- 社会保険給付金
- 会社都合退職
- 資格取得
- 新型コロナウイルス
- 退職勧奨
- 職業訓練受講給付金
- 自己都合退職
- うつ病
- 有給消化
- 自己PR
- 退職給付金
- クレジットカード
- 統合失調症
- 休職
- 確定申告
- ハローワーク
- アルバイト
- 契約社員
- 免除申請
- 保険料
- 傷病手当
- 雇用保険
- 弁護士
- 適応障害
- 社会保障
- 退職コンシェルジュ
- 健康保険
- 公的貸付制度
- 住宅確保給付
- 就職
- ストレス
- 年金
- 生活福祉資金貸付制度
- 職業訓練
- 労働基準法
新着記事
-
2025.12.08
産休・育休後そのまま退職はマナー違反?退職時のポイントと注意点
-
2025.12.07
会社を辞めさせられた場合は失業保険は受け取れる?条件や注意点を解説
-
2025.12.04
傷病手当金は退職後もらえない?受給できる条件と不支給になる理由を徹底解説
-
2025.12.01
休職でも傷病手当金はもらえる?休職手当との違いや支給額を解説
-
2025.12.01
うつ病は傷病手当がもらえない?活用できる制度も併せて紹介
-
2025.12.01
適応障害で傷病手当金はもらえる?受給するメリット・デメリットと申請方法
-
2025.12.01
退職後も傷病手当金はもらえる?受給できる条件と注意点を解説
-
2025.12.01
傷病手当金の支給日はいつになる?振込が遅れる原因と早く受給するコツ
-
2025.12.01
傷病手当金の計算方法は?早見表と調整されるケースも紹介
-
2025.12.01
傷病手当金をもらえない9つのケースとは?申請前に確認すべき条件と対処法を解説





 サービス詳細
サービス詳細