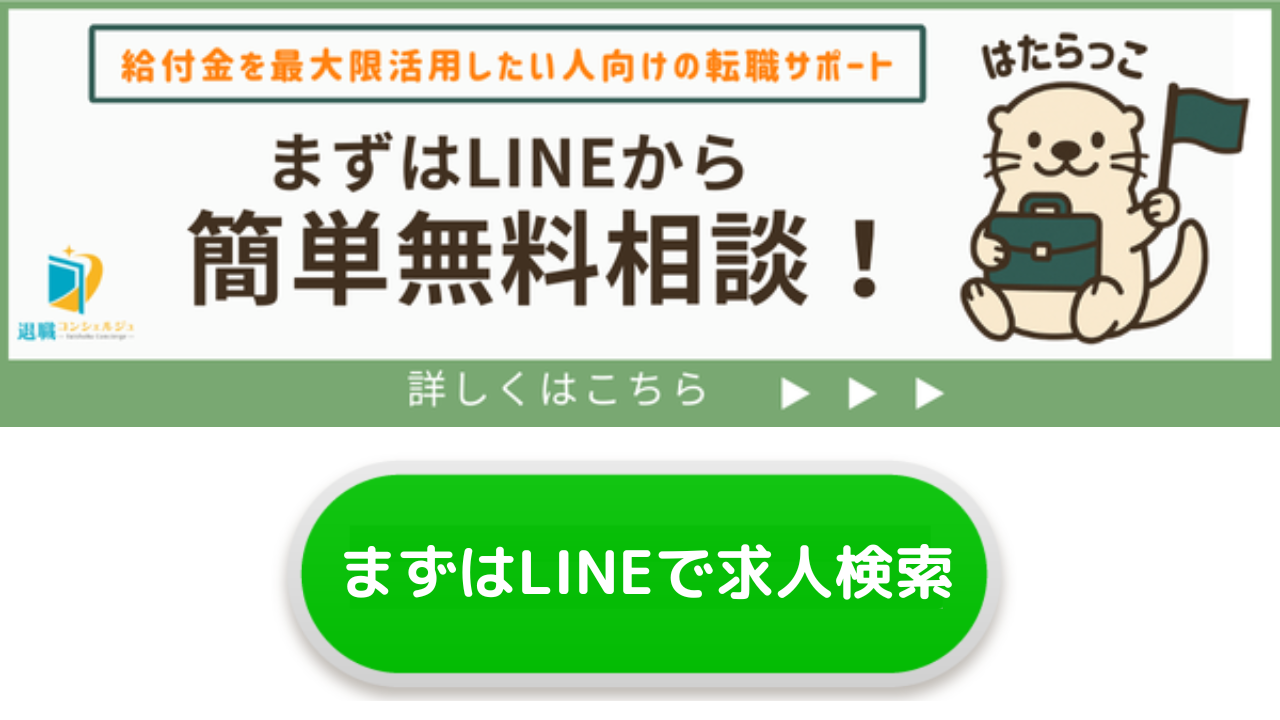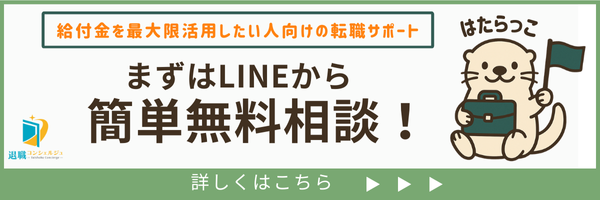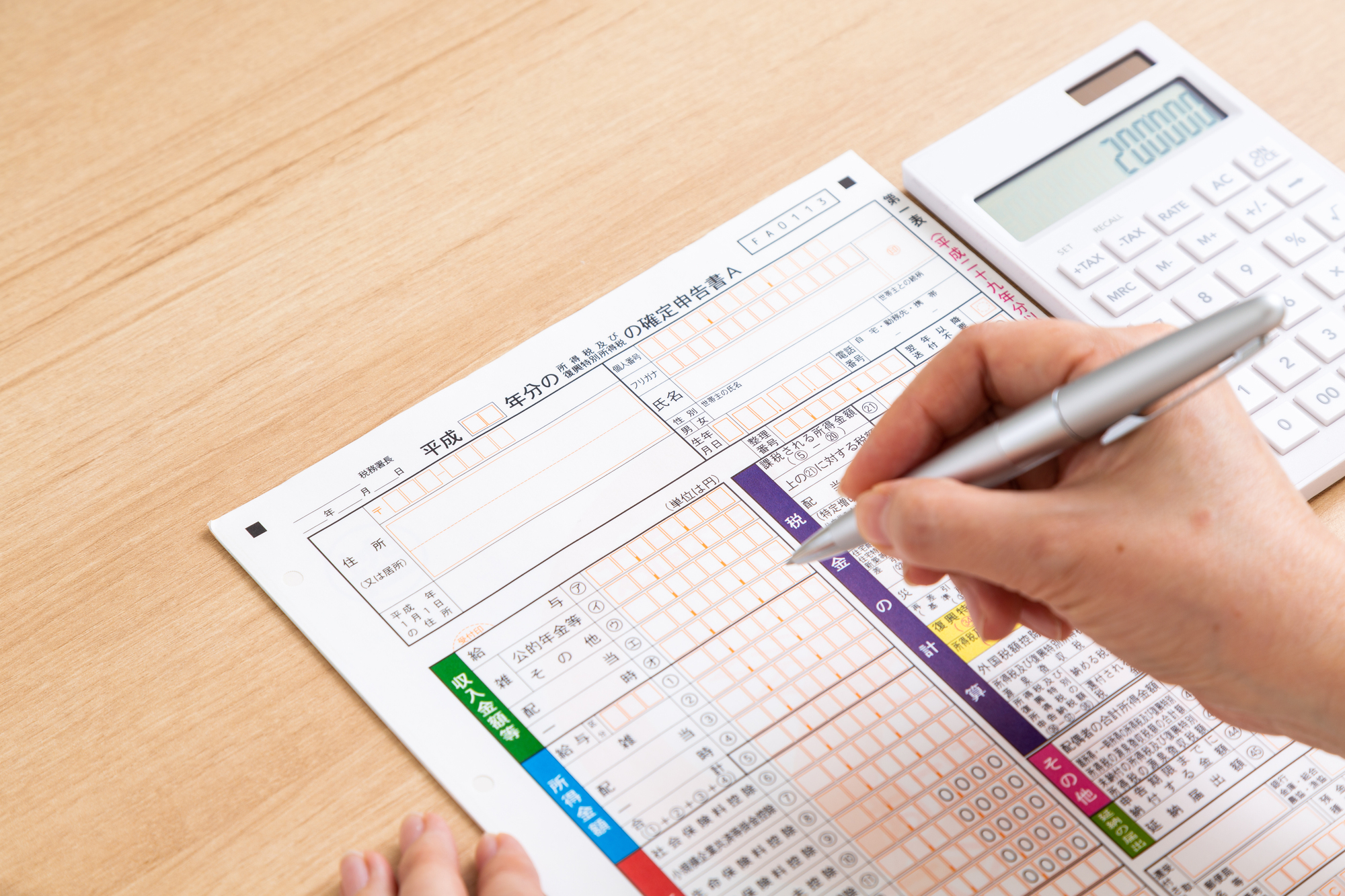2025.05.20
給付金について
妊娠で退職しても失業保険はもらえる?受給できる条件を紹介

妊娠を理由に退職した場合、すぐに失業保険をもらえない決まりがあるため、生活の不安を感じる方もいるのではないでしょうか。確かに、妊娠中で就業が難しい場合は失業保険を受給できませんが、受給期間を延長して出産後に受給することはできます。
そこで今回は、妊娠中に失業保険を受給できない理由や、受給期間を延長するための申請方法と必要書類、出産後に失業保険を受給する際の受給金額や申請方法、気をつけたいポイントなどを解説します。退職しない場合に受け取れるお金やよくある質問もご紹介しますので、妊娠中で退職を悩まれている方は参考にしてください。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
妊娠中は失業保険を受給できない

結論からお伝えすると、妊娠中で直ちに就業ができない場合には、失業保険を受給できません。そもそも、失業保険(基本手当)は雇用保険法に定められた保険制度で、受給には、就職の意思と能力、求職活動が必要であるためです。
しかし、妊娠して働けない状態でも受給資格を失うわけではありません。妊娠や出産、育児などで30日以上就業できない状態が続く場合は、受給期間の延長を申請することが可能です。
なお、受給期間の延長手続きは、離職日の翌日から30日を経過した後、1カ月以内に行う必要があります。
失業給付の受給期間延長の申請方法
妊娠が理由で失業給付の受給期間を延長するには、ハローワークへの来所、郵送が可能です。それぞれの申請方法を解説します。
直接ハローワークに来所する場合
ハローワークに直接来所して手続きをする場合の手順は以下のとおりです。なお、必要書類は、次の章で解説します。
- 受給期間延長申請書をハローワークで受け取る(ハローワーク窓口もしくは郵送)
- 必要書類と印鑑を用意する
- 必要書類を管轄のハローワークへ持参して提出する
ハローワークに郵送する場合
ハローワークに必要書類を郵送して申請する場合は、以下の手順で進めます。
- 受給期間延長申請書を受け取る(ハローワーク窓口もしくは郵送)
- 居住地を管轄するハローワークの「雇用保険給付・教育訓練給付窓口」へ電話し、郵送で受給期間延長を申請する旨を事前に伝える
- 必要書類に必要事項を記入し、郵送で提出する
定年などが理由の場合
なお、妊娠で離職するケースとは異なりますが、60歳以上での定年退職や、勤務延長の期間終了後に退職する場合は、退職日の翌日から2カ月以内に申請すれば、受給期間を延長することが可能です。
延長が可能な期間は、元々の受給期間の1年に加え、最長1年間までの休養したい期間を申請できます。
原則として、本人が「受給期間延長等申請書」と「雇用保険被保険者離職票-2」、「本人の印鑑(認印・スタンプ印以外)」をハローワークに直接提出して申請します。
失業給付の受給期間延長に必要な書類
失業保険の受給期間延長に必要な書類は、受給手続きが済んでいる場合と済んでいない場合とで異なります。それぞれのケースでの必要書類を解説します。
受給手続きが済んでいる場合
受給手続きが済んでいる場合は、以下の書類が必要です。
- 雇用保険受給資格者証(もしくは雇用保険受給資格通知)
- 受給期間延長申請書
- 延長の理由を証明する書類(例:医師の証明書等)
受給手続きが済んでいない場合
受給手続きが済んでいない場合は、以下の書類が必要です。
- 雇用保険被保険者離職票-2
- 受給期間延長申請書
- 延長の理由を証明する書類
出産後に失業保険を利用する場合にいくら受給できる?
失業手当の受給額は「給付日数 × 基本手当日額」で決まるため、出産後に失業保険を利用する場合にいくら受給できるかは、ケースによって異なります。一般的には、受給額は離職前の賃金の5〜8割程度になります。
具体的な受給金額は、以下の手順で計算します。
- 賃金日額を計算する
- 基本手当日額を計算する
- 基本手当総額を計算する
賃金日額を計算する
「賃金日額」とは、離職前の直近6カ月間に支払われた賃金の総額を180で割った金額を指します。「賃金」には、基本給、残業代、通勤手当や住宅手当などの各種手当が含まれる。賞与や退職金、祝い金などの臨時的な賃金は含まれませんので留意が必要です。
基本手当日額を計算する
続いて基本手当日額を計算します。基本手当日額とは、前の工程で計算した賃金日額に、50%〜80%の給付率を掛け合わせたものです。
なお、給付率は、賃金日額が低いほど高く設定されており、具体的な給付率は厚生労働省の基準に基づいて決定されます。
基本手当総額を計算する
最後に、基本手当日額に所定給付日数を掛け合わせて、基本手当総受給額を計算します。
「所定給付日数」は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢などによって異なります。例えば、自己都合で退職した場合で、被保険者期間が1年以上5年未満のケースにおける所定給付日数は90日です。
<具体例>
離職前6カ月間の賃金総額が180万円の場合、賃金日額は180万円÷180日=1万円になります。
仮に、給付率が60%のケースでは、基本手当日額は1万円×60%=6,000円です。さらに、所定給付日数が90日の場合、総受給額は6,000円×90日=54万円となります。
なお、基本手当日額には上限額と下限額が設定されています。
出産後、失業保険を利用する際に気をつけたいポイント
出産後に失業保険を受給する場合は、いくつか気をつけたいポイントがあります。ここでは、4つの留意点を解説します。
配偶者の健康保険の扶養から外れる可能性がある
失業保険の基本手当を受給している期間中は、配偶者の健康保険の扶養から外れる可能性があります。扶養に入るための条件には年間所得の規定があり、受給額がその規定を超えると扶養資格を喪失するためです。
具体的に、どのような条件で不要資格を喪失するかは加入している健康保険組合によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
受給できる期間が短くなることもある
出産後に失業保険を受給する場合、受給可能な期間が短くなることがあります。
一般に、妊娠・出産・育児などで30日以上働くことができない場合は、失業保険の受給期間を延長することが可能です。しかし、延長の申請は離職日の翌日から30日を経過した日以降、1カ月以内に行う必要があり、この期間内に申請を行わないと、受給期間の延長が認められません。その結果、受給できる期間が短くなる可能性がある点に注意しましょう。
前述のとおり、延長手続きは郵送や代理人による申請も可能ですが、配達日数なども考慮して早めに対応することが重要です。
受給開始までに時間がかかる
退職理由によっては、申請後から受給開始までに時間がかかるため、すぐに失業保険を受け取れない可能性があることにも注意が必要です。
まず、会社都合、自己都合であっても、失業保険の受給手続きを行った後は、原則として7日間の待期期間が設けられます。さらに、自己都合退職の場合は、1カ月間の給付制限期間が追加されることがあります。
待期期間と給付制限期間の期間中は基本手当が支給されないため、受給開始までに時間がかかることを理解しておきましょう。
産前6週間・産後8週間は就業が禁止されている
労働基準法では、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)および産後8週間は、女性労働者の就業が禁止されています。
この期間中は就業だけでなく求職活動も制限されてしまうため、失業保険の受給条件である「就職の意思と能力」を満たさないとハローワークから判断される可能性があります。
失業保険の申請方法
失業保険の申請方法は、以下の流れで進めます。必要書類などを準備しておき、スムーズに手続きを進めましょう。
- 必要書類をそろえる
- ハローワークで求職を申し込む
- 待期期間を過ごす
- 雇用保険説明会に参加する
- 失業認定日にハローワークを訪れる
必要書類を揃える
求職申込自体はハローワークで行いますが、その際は必要書類を提出する必要があるため、あらかじめ準備しておきましょう。
必要書類は次のとおりです。
- 雇用保険被保険者離職票-1・2
- 雇用保険被保険者証
- 証明写真(たて3cm×よこ2.4cm、正面上半身)×2
- 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
- 住所・氏名・年齢が確認できる本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1つ)
また、印鑑(認印は可、スタンプ印は不可)を持参しておくと良いでしょう。
ハローワークで求職を申し込む
必要書類がそろえば、ハローワークで求職の申し込みを行います。
具体的な流れは、次の通りです。
- 求職申込書に記入する
- 必要書類の提出、職業相談を行う
- 申請のタイミングで雇用保険説明会の日時が決定する
求職の意思と能力があり失業保険を受けたい場合は、離職票の提出と求職の申し込みを行いましょう。窓口での申し込み後に、受給資格が決定すると「失業等給付受給資格者のしおり」が渡されます。
また、後日、失業保険の受給の流れや求職の方法が説明される「雇用保険説明会」に原則として参加する必要があります。具体的な参加日時は申請日から7日後以降になるため、忘れずにメモをしておきましょう。
待機期間を過ごす
ハローワークでの求職申請を経て受給資格を得ると、7日間の待機期間が設けられます。求職申し込みをした日から失業期間が7日に満たない場合は、失業保険は給付されません。
待機期間となる7日間は、ハローワークが申請者の失業状況を調査する期間です。この期間中において短時間の勤務やアルバイトをした場合は就労とみなされるため、一切の就労をしないことが大切です。
また、失業保険の受給中に再就職が決まると、残りの給付期間に応じて再就職手当を受けられるケースもあります。ただし、待期期間中に入社日を迎えると、再就職手当を受け取ることはできません。再就職手当の受給を目指している場合は、待期期間経過後に入社日を調整するなど、注意する必要があります。
また、確実な再就職手当の受給を目指すなら、転職エージェントの活用もおすすめです。
退職コンシェルジュの転職エージェントは、国の認可を受けているため、待期期間の終了からすぐ再就職手当の申請が可能です。
雇用保険説明会に参加する
失業保険の受給には、求職の申し込み時に案内された雇用保険受給説明会に原則として参加する必要があります。雇用保険説明会では、失業保険の仕組み、受給の手順、求職方法などが詳しく説明されるので、必ず参加して理解を深めましょう。
雇用保険説明会への参加時は、以下のものが必要です。
- 雇用保険受給資格者のしおり(求職の申し込み時に受け取る)
- 印鑑
- 筆記用具
説明会の終了後に、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が渡されます。さらに、初回の「失業認定日」が案内されます。
失業認定日にハローワークを訪れる
「失業認定日」とは、ハローワークが受給者における失業の事実を認定する日です。失業認定日には、ハローワークに来所したうえで、失業認定申告書を提出し、就職活動の実績を報告しなければなりません。
初回の失業認定日は、離職票を提出した日から約3週間後に設定されます。その後は、年末年始を除き、通常は4週間ごとに1日、指定された平日が失業認定日となります。
退職しない場合に受け取れるお金

妊娠、出産を機に退職する人もいれば、在籍のまま産前・産後休業や育児休業を取る方もいるでしょう。このような場合、失業保険は受け取れませんがその他の手当金や給付金を受け取ることが可能です。
出産手当金
出産手当金は、健康保険の被保険者である女性が出産のために仕事を休み、その期間中に給与の支払いを受けなかった場合に支給される手当です。
具体的には、出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前の42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲のうち、仕事を休んで給与の支払いがなかった期間を対象に支給されます。
支給額は、標準報酬日額の3分の2相当額となります。なお、産休中に給与の支払いがある場合や、その給与の日額が出産手当金の日額よりも少ない場合は、給与と手当金の差額が支給される仕組みです。
出産手当金の申請手続きは、所属する健康保険組合や協会けんぽに対して行います。健康保険出産手当金支給申請書を作成して、医師または助産師の証明および事業主の証明を受けた上で、所属する健康保険組合や協会けんぽに提出しましょう。
育児休業給付金
育児休業給付金は、働いている人が出産後に育児のために休業する場合に、経済的な負担を軽減するために支給されるお金です。
育児休業給付金を受給するには、以下の1〜5の件を満たす必要があります。
- 雇用保険に加入していること
- 育児休業開始前の2年間に、11日以上働いた月が12カ月以上あること
- 育休中の給与が、休業前の月収の8割未満であること
- 育休中の労働日数が月10日以下(または80時間以下)であること
- 1歳(最大2歳)までの子どもの育児のために休業していること
また、支給額は育休開始からの経過日数で以下のように異なります。
- 180日目まで:休業前の給与の 67%
- 181日目以降:休業前の給与の 50%
育児休業給付金の受給手続きは、勤務先を通じて行います。以下の手順で進めましょう。
- 勤務先に申請を依頼する(通常は会社が手続きを行う)
- 必要書類(育児休業給付金支給申請書や雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書など、雇用主が準備する書類、および母子手帳のコピーや振込先口座の通帳のコピ
- ーなど)をハローワークに提出
2カ月ごとに給付される
妊娠中の失業保険にまつわるよくある質問
ここからは、妊娠中の失業保険受給や失業保険受給中の妊娠に関してよくある質問と回答をご紹介します。
Q1. 求職活動をしても就職できない場合には、妊娠中でも失業保険が受け取れる?
求職活動をしても就職できない場合、それが妊娠に由来するものであれば失業保険は受け取れない可能性が高いでしょう。
失業保険(基本手当)の受給には、就職の意思と能力、さらに、積極的な求職活動が必要とされています。そのため、求職活動自体ができない場合には要件を満たしません。
ただし、妊娠中であっても、これらの要件を満たしたうえで、実際に求職活動を行っている場合は、失業保険を受給することが可能です。
Q2. 妊娠中に会社都合での退職が発生した場合、失業保険はどうなる?
会社の倒産や解雇など、会社都合での退職(特定受給資格者)に該当する場合は、失業保険の受給資格を得ることができます。
しかし、妊娠中で直ちに就職できない場合は失業保険受給の要件を満たさず受給できません。ただし、受給期間の延長を申請することで出産後に受け取ることが可能です。
Q3. 失業保険申請中に妊娠したらどうなる?
失業保険の受給手続き中に妊娠が判明した場合は、就職の意思と能力があり、積極的に求職活動を行っている限り、受給を継続することが可能です。
しかし、出産が近くなるなど妊娠によって求職活動が困難になった場合や、出産・育児のために30日以上就業できない状態が続く場合は、受給期間の延長を申請ができます。
Q4. 妊娠を隠して失業保険を受給したらどうなる?
妊娠を隠して失業保険を受給した場合、不正受給とみなされる可能性があります。
失業保険(基本手当)を受給するには、就職の意思と能力、積極的な求職活動が求められますが、妊娠を隠して受給した場合に、これらの条件を満たしていないと判断されると、不正受給になる可能性があるためです。
不正受給が発覚した場合は、すでに受給した金額の返還だけでなく、追加の制裁金が科されるため、正しく申請しましょう。
まとめ
失業保険を受給するには、就職の意思と能力を持ち、積極的に求職活動を行う必要があります。妊娠を機に就業が難しいために退職した場合は、就職の能力が欠けるため、失業保険をすぐには受給できないことに注意が必要です。ただし、受給期間を延長することができ、出産後に就業可能になれば失業保険を受け取ることができます。
そのため、妊娠の前後や出産後に就職を検討している場合は、失業手当の申請を行うことをおすすめします。ただし、ご紹介したとおり申請期間には期限が設けられており受給要件を満たす必要があるため、制度を理解して手続きを進めましょう。
失業保険の申請に不安をお持ちの方は、退職コンシェルジュが提供する「社会保険給付金サポート」をご活用ください。サポート実績が豊富な専任スタッフが申請手続きをサポートいたします。安心してご利用いただけるよう、個別相談会も実施しておりますので、ぜひご参加ください。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
この記事の監修者

杉山雅浩
スピネル法律事務所 弁護士
東京弁護士会所属。
池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。
NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、
詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。
YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、テ日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!
おすすめの関連記事
ピックアップ
- CATEGORY
- 給付金について
- 転職・再就職について
- 就労について
- 社会保険について
- 精神疾患について
- サービスについて
- 失業保険について
- 再就職手当
- 雇用保険について
- 退職について
- 障害年金について
- ピックアップ
- 人気記事
-
退職代行サービスの利用方法、実際の流れと体験談を紹介
-
今の会社に3年後もいる自信はありますか?
-
退職代行を利用した時の有給消化の仕組みとその対応方法
-
退職代行サービスを使うメリット・デメリットは?
-
障害年金を知ろう
-
ブラック企業を判定する方法と実際のチェックポイント
-
会社を“円満に退職する”方法は?
-
退職時の引き継ぎは義務?スムーズな業務引き継ぎの必須ポイント
-
辞めさせてくれない!そんな時こそ「退職代行サービス」
-
パワハラ、モラハラ、セクハラとは?
テーマ
- クレジットカード
- 資格取得
- 退職届
- 引っ越し
- 労働基準法
- 退職コンシェルジュ
- 退職代行
- アルバイト
- 精神疾患
- 面接
- 社宅
- 雇用契約
- ストレス
- 退職代行サービス
- 雇用保険
- うつ病
- 障害手当金
- 障害者手帳
- 内定
- ブラック企業
- 健康保険
- 統合失調症
- 自己都合
- 精神保険福祉手帳
- 就労移行支援
- ハラスメント
- 年金
- 契約社員
- 会社都合
- 労災
- 業務委託
- パワハラ
- 転職活動
- 弁護士
- 失業給付
- 産休
- 社会保険
- モラハラ
- 転職サイト
- 公的貸付制度
- 新型コロナウイルス
- 解雇
- 福利厚生
- セクハラ
- 職務経歴書
- 生活福祉資金貸付制度
- 有給消化
- 中小企業
- 失業手当
- 障害年金
- 人間関係
- 不支給
- 休職
- ベンチャー企業
- 就職困難者
- 引き継ぎ
- スタートアップ
- 等級
- 免除申請
- 会社倒産
- 再就職手当
- 給与
- 転職
- 離職票
- 適応障害
- 退職勧奨
- 社会保険給付金
- 残業代
- 違法派遣
- 労務不能
- 住宅確保給付
- 自己PR
- 職業訓練受講給付金
- 退職金
- 派遣契約
- 傷病手当金
- 給付金
- 確定申告
- 退職給付金
- 会社都合退職
- 障害厚生年金
- 年末調整
- 職業訓練
- 保険料
- ハローワーク
- 自己都合退職
- 失業保険
- 障害者控除
- 再就職
- 社会保障
- 就業手当
- 退職
- ブランク期間
- 退職願
- 職業訓練受講手当
- 就職
- 傷病手当
新着記事
-
2025.10.09
失業手当の手続きで提出する必要書類は?離職票再発行や延長申請の流れも解説
-
2025.10.08
個人事業主が再就職手当をもらえるケースと手続き方法、注意点を解説
-
2025.10.08
アルバイトを4時間ピッタリすると失業手当はどうなる?支給条件や注意点も解説
-
2025.10.08
いつが得?損しない退職日の決め方とパターン別おすすめの退職日
-
2025.10.08
失業認定日までに就職が決まったらどうする?必要な手続きの手順を解説
-
2025.10.08
確実に退職できる理由はある?退職理由で嘘をつくメリット・デメリット
-
2025.10.08
引き止められない退職理由の具体例|円満退社するコツと引き止められたときの対策
-
2025.10.07
年金と失業保険を同時にもらう方法はある?年齢別の受給方法を解説
-
2025.10.07
ハローワークの認定日の時間に遅刻したら失業保険は受けられない?欠席した場合も解説
-
2025.10.03
失業保険はいつ振り込まれる?支給日の目安と早くもらう方法を解説





 サービス詳細
サービス詳細