2025.05.17
税金について
国民健康保険は失業保険を受け取りながら減額できる?条件やタイミングとは

失業保険の受給中は収入が限られており、国民健康保険料を納める余裕がない方も多いのではないでしょうか。国民健康保険には免除や減額できる制度があり、条件を満たせば失業保険を受け取りながら減額してもらうことも可能です。
本記事では、失業保険を受け取りながらでも保険料を減額できる条件と、社会保険から切り替えるタイミングを詳しく解説します。切り替える際の手続き方法や注意点も紹介しますので、国民健康保険の減額を希望する方はぜひ参考にしてみてください。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
失業保険を受け取りながら国民健康保険を減額する条件
国民健康保険料は、失業保険を受け取りながらでも減額できます。しかし、誰もが減額できるものではなく、一定の条件を満たす人が対象です。
まずは、減額できる人の条件と軽減期間、申請方法について詳しく見ていきましょう。
対象条件
失業保険を受給中に国民健康保険料を減額してもらうためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 倒産や解雇などで失業し、離職時点で65歳未満の方
- 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に当てはまる方
- 離職理由が特定の条件(コード)に該当する方
- 雇用保険受給資格者証または受給資格通知を持っている方
ただし、季節雇用などの特例受給資格者や高齢受給資格者は対象外です。
離職理由の特定条件(コード)は、11・12・21・22・23・31・32・33・34が該当します。雇用保険受給資格者証、または受給資格通知書に記載されている離職理由コードで確認できます。
保険料の軽減期間
国民健康保険料の減額期間は、離職日の翌日から離職した月が属する年度の翌年度末までです。例えば、2025年3月15日に離職した場合は、2025年3月16日から2026年3月31日までの保険料が減額対象です。2025年3月31日に離職した場合は、2025年4月1日から2027年3月31日までが軽減期間となり、24ヶ月間減額されます。ただし、再就職が決まって他の健康保険に加入すると、その時点で減額措置は終了です。
申請が遅れた場合でも遡って減額してもらうことは可能ですが、2年以上遡って手続きする際は保険料の軽減が適用されないケースがあります。
軽減される内容
倒産や解雇により非自発的失業者となり国民健康保険料の減額を受ける場合、保険料は前年の給与所得を30%として算出します。例えば、前年の給与所得が300万円だとすると、30%の90万円に対する保険料が支払い対象となります。
ただし、減額対象は給与所得のみであり、不動産所得や株の譲渡所得は30%減額されません。
申請方法
国民健康保険料の減額措置を受けるには、住民票を置いている市区町村役所の担当課に、申請書と以下の書類を提出する必要があります。
- 雇用保険受給資格者証または受給資格通知
- 国民健康保険証
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
マイナ保険証を取得しており、紙タイプの保険証を発行されていない人はマイナンバーカードの提示が必要です。
一部の自治体では、郵送やマイナンバーカードによるオンライン申請も可能です。申請方法や申請書類の詳細は、各自治体の公式サイトで確認しましょう。
社会保険から国民健康保険に切り替えるタイミング
会社を退職して社会保険(健康保険)の資格を喪失した場合は、退職日の翌日から14日以内に、住民票を置いている市区町村役場で手続きすることが法律で定められています。期間内に手続きしなかった場合は無保険状態となり、医療費が全額自己負担になります。
手続きが遅れてしまったとしても、最長2年分の国民健康保険料が退職日の翌日まで遡って請求される点に注意が必要です。また、手続きの遅延理由によっては、自己負担した医療費が払い戻されない可能性もあるため、退職後は速やかに対応しましょう。
なお、退職後も一定の条件を満たせば、社会保険を最長2年間延長できる「任意継続被保険者制度」も利用できます。しかし、この制度は保険料が全額自己負担となるため、場合によっては国民健康保険料のほうが安くなることがあります。
社会保険と国民健康保険の違い
社会保険から国民健康保険へ切り替わることで、何が変わるのでしょうか。ここでは、切り替える際に知っておきたい加入条件と保険料、扶養制度の違いを解説します。
加入条件
社会保険(健康保険)とは、企業などの適用事業所に雇用されている正社員や、一定の条件を満たすアルバイトやパートなどの短時間労働者が加入する保険制度です。社会保険に加入できる条件は、週に所定労働時間が20時間以上で、かつ1年以上の雇用見込みがある場合などが該当します。
一方、国民健康保険は、社会保険に加入しておらず、生活保護制度を受けていない74歳以下のすべての人が対象になる保険制度です。主に、社会保険の加入条件を満たしていない自営業者やフリーランス、失業中の人、年金受給者などが加入します。
保険料・計算方法
社会保険の健康保険料は、被保険者の給与額に応じて決まる「標準報酬月額」に基づき算出されます。算出された健康保険料は事業主と折半で負担するため、実際に従業員が支払うのは算出された保険料の50%です。例えば、健康保険料が4万円と算出された場合、事業主と従業員で2万円ずつ支払う仕組みです。
国民健康保険料は、前年の1月1日から12月31日までの所得に応じて市区町村が計算し、全額を本人が負担します。具体的な計算方法や保険料率は各自治体によって異なるため、同じ所得の人でも住んでいる地域によって保険料が異なる場合があります。
扶養の有無
社会保険には扶養制度があり、一定の条件下で配偶者や子どもなどの家族を被扶養者として会社の保険に加入させることが可能です。被扶養者と認められると、その家族は保険料の負担なしで保険給付を受けられるようになります。
一方で、国民健康保険には扶養というシステムはなく、世帯の加入者数などで保険料が決まる制度で、社会保険に加入していない家族分の保険料の支払いが必要です。例えば、本人と配偶者、子ども1人の世帯では、3人分の保険料を支払います。ただし、子どもの年齢によっては、均等割減額措置を受けられることもあります。
社会保険から国民健康保険に切り替えるには
退職に伴い社会保険から国民健康保険に切り替える際は、会社側が健康保険組合や年金事務所に「被保険者資格喪失届」を提出する必要があります。その後、各役所で切り替え手続きをする流れです。ここでは、切り替えのときに必要な書類と手続きについて詳しく解説します。
必要書類
事業主が健康保険組合に「被保険者資格喪失届」を提出する際は、以下の書類を添付する必要があるため、扶養家族の分も併せて会社に返却します。ただし、交付されていない書類は提出する必要はありません。
- 本人および被扶養者の健康保険被保険者証
- 高齢受給者証
- 健康保険特定疾病療養受給者証
- 健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
会社が「被保険者資格喪失届」を提出すると、「健康保険等資格喪失証明書」が発行され、従業員へ渡されます。従業員本人が行う手続きに必要な書類は、以下のとおりです。
- 健康保険等資格喪失証明書
- 本人確認書類
- マイナンバーがわかる書類
保険料を口座引き落としにする際は、上記のほかにキャッシュカードや通帳、印鑑が必要です。
手続き
会社の健康保険を脱退した後、市区町村役所の健康保険業務の担当窓口にて、国民健康保険への加入手続きを行います。
繰り返しになりますが、健康保険の脱退後14日以内の手続きが基本です。すでに国民健康保険に加入している世帯で、追加で加入する場合は世帯主の保険証が必要になることがあります。
【退職理由別】失業保険を受け取れる条件
退職後、失業保険を受け取りながら国民健康保険料を減額することは可能です。では、そもそも失業保険は誰でも受け取れるのでしょうか。
ここでは、。退職理由別に失業保険の受給条件を紹介します。
自己都合退職
自己都合退職とは、個人的な都合や希望により退職することです。例えば、キャリアアップや転職活動、家庭の事情などで退職する場合が該当します。自己都合退職で失業保険を受給するには、離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上必要です。
また、失業保険の給付開始までに7日間の待機期間と1ヶ月の給付制限期間が設けられています。
特定理由離職者
特定理由離職者とは、以下のようにやむを得ない事情で退職した人を指します。
- 労働契約の更新がなかった場合
- 健康上の理由で離職した場合
- 家庭の事情で離職した場合
- 通勤困難な状況になった場合
上記の理由に当てはまる場合、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば、失業保険を受給できます。自己都合退職とは異なり、給付制限期間はありません。 なお、労働契約の更新がなかった場合は所定給付日数の延長も可能です。
特定受給資格者
特定受給資格者とは、会社側の都合で退職した人を指します。主に、以下のような例が挙げられます。
- 倒産や事業所の廃止
- 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)
特定理由離職者と同じく、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば、失業保険を受給できます。また、給付制限期間は設けられておらず、所定給付日数も延長されます。
国民健康保険を手続きする前に確認すること
会社を退職後、社会保険から国民健康保険へ切り替える必要がありますが、任意継続制度を利用したり、家族の扶養に入ったりすることも可能です。ここでは、国民健康保険への加入手続きの前に確認したいことを紹介します。
任意継続制度を利用するかどうか
任意継続被保険者制度は、退職前に加入していた健康保険を最長2年間継続できる制度です。制度を利用するには、退職日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があり、退職後20日以内に所定の手続きを行う必要があります。
制度を利用した場合の保険料は、退職時の標準報酬月額に基づいて算定され、全額自己負担となります。扶養家族がいる場合でも追加の保険料負担はありませんが、制度の利用中は新たに家族を扶養に入れることはできません。
任意継続の保険料は、在職中の自己負担分と会社負担分を合わせた金額となるため、在職中より高額になることがあります。
扶養に入るかどうか
国民健康保険へ切り替えない場合のもう一つの選択肢は、家族の社会保険に加入して、扶養家族となる方法です。主に配偶者の扶養に入るのが一般的ですが、条件によっては被保険者の父母や子、祖父母、兄弟姉妹など第三親等までの人も扶養家族と認定されることがあります。
扶養に入るための条件は、以下のとおりです。
- 年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)
- 被保険者の収入によって生計を維持している
- 同一世帯の場合は被保険者の年間収入の2分の1未満
- 同一世帯に属していない場合は、年間収入が被保険者からの援助による収入より少ない
扶養家族として認定されると、保険料の追加負担なしで健康保険の給付を受けられます。ただし、年間収入が上記の扶養認定基準を超えると、その時点で扶養から外れます。
社会保険から国民健康保険に切り替える際の注意点
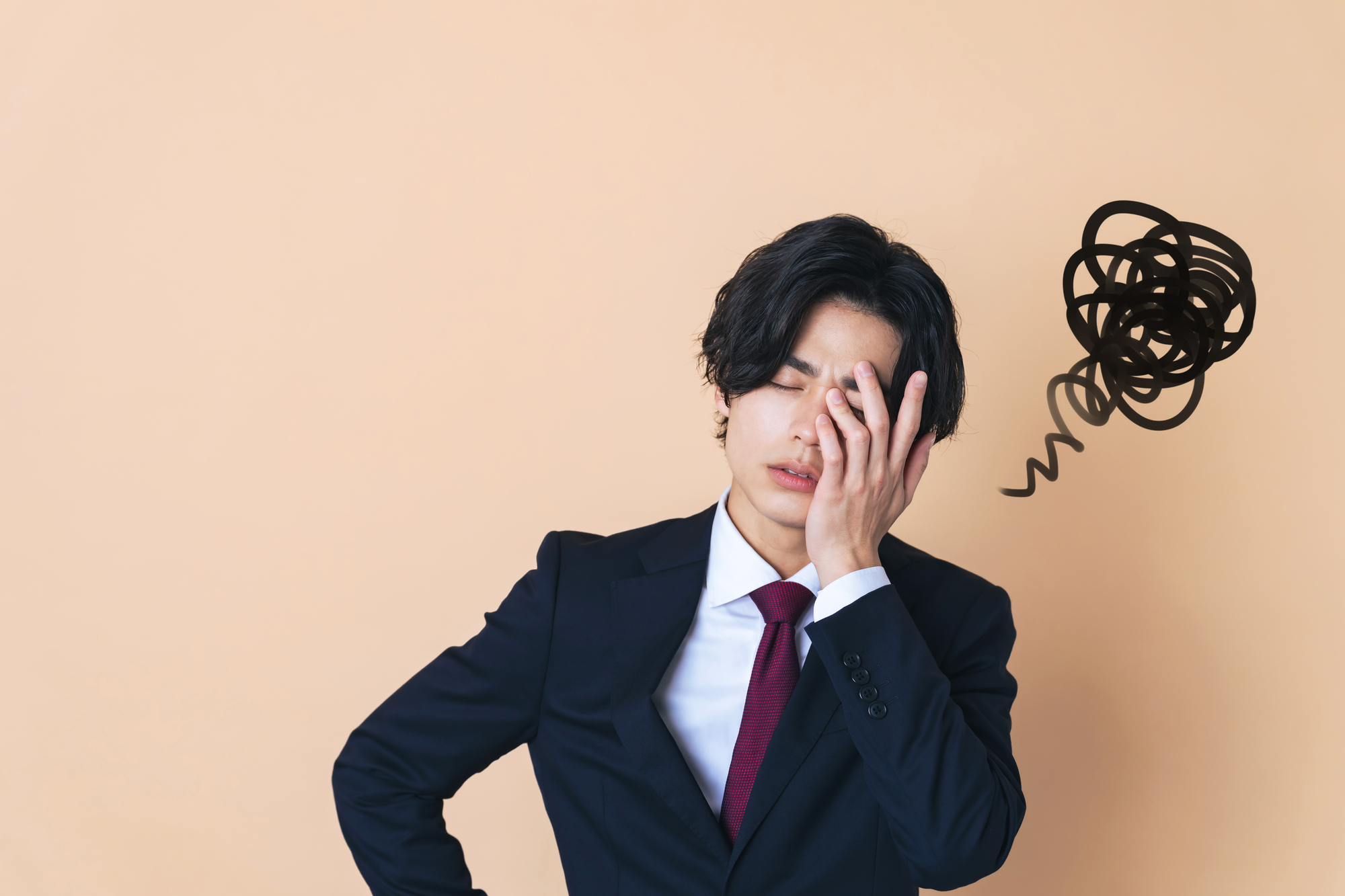
社会保険から国民健康保険に切り替えるときは、以下の点に注意が必要です。
- 速やかに手続きを行う
- 切り替えを行わずに放置することにはリスクがある
- 健康保険証を速やかに会社へ返却する
それぞれの注意点を詳しく見ていきましょう。
速やかに手続きを行う
繰り返しになりますが、退職後の国民健康保険への加入手続きは、原則14日以内に行う必要があります。定められた期間をすぎてしまった場合でも、速やかに手続きすることが重要です。
手続きが遅れた場合、保険料は退職日の翌日まで遡って請求されます。また、手続きが遅延すると、医療費の給付が届出日からしか適用されない可能性もあります。
切り替えを行わず放置することにはリスクがある
国民健康保険への切り替えが必要なのにもかかわらず、手続きをせず放置して無保険状態になると、医療費を全額自己負担しなくてはなりません。
また、国民皆保険制度により健康保険への加入義務があるため、届出せず未加入の状態が続く場合は、10万円以下の過料を科せられる可能性があります。
健康保険証を速やかに会社に返却する
退職時は、健康保険証を速やかに会社に返却しましょう。健康保険の資格喪失日以降に失効した保険証を使用すると、後日、医療費の返還を求められることがあります。
また、国民健康保険へ切り替える際に必要な「健康保険等資格喪失証明書」の発行には、保険証が必要です。そのため、保険証を会社に返却しないまま放置すると、会社側の手続きが滞り、新たな保険への加入手続きに支障をきたす可能性があります。
古い保険証を郵送で返却する場合は追跡可能な方法で送付し、確実に会社に届いたことを確認することが望ましいでしょう。
まとめ
失業保険を受け取りながら、国民健康保険を減額してもらうことは可能です。保険料が軽減される期間は、離職日の翌日からその年度の翌年度末までで、前年の給与所得の30%を基に保険料が減額されます。ただし、減額を受けるには雇用保険への加入や離職理由に条件があります。
会社の社会保険から国民健康保険へ切り替える際は、自分で手続きする必要があり、手間と時間がかかります。特に、扶養家族がいる場合は、それぞれの状況に応じた書類が必要になるため、手続きがスムーズに進まないこともあるかもしれません。もし、手続きが遅れてしまうと、過去に遡って保険料を支払う必要があるだけでなく、最悪の場合は過料を科される可能性があるため注意が必要です。
しかし、求職活動中に情報を集め、必要書類を確認して手続きするのは難しいことがあります。忙しくて手続きできない方や手続き方法が難しいと感じる方は、ぜひ「社会保険給付金サポート」をご活用ください。まずは、LINEからお気軽にお問い合わせください。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
この記事の監修者

杉山雅浩
スピネル法律事務所 弁護士
東京弁護士会所属。
池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。
NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、
詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。
YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、テ日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!
おすすめの関連記事
ピックアップ
- CATEGORY
- 給付金について
- 転職・再就職について
- 就労について
- 新型コロナウイルスについて
- 社会保険について
- 退職代行について
- 税金について
- 精神疾患について
- サービスについて
- 失業保険について
- 退職について
- 障害年金について
- ピックアップ
- 人気記事
-
退職代行サービスの利用方法、実際の流れと体験談を紹介
-
今の会社に3年後もいる自信はありますか?
-
退職代行を利用した時の有給消化の仕組みとその対応方法
-
退職代行サービスを使うメリット・デメリットは?
-
ブラック企業を判定する方法と実際のチェックポイント
-
障害年金を知ろう
-
会社を“円満に退職する”方法は?
-
退職時の引き継ぎは義務?スムーズな業務引き継ぎの必須ポイント
-
パワハラ、モラハラ、セクハラとは?
-
辞めさせてくれない!そんな時こそ「退職代行サービス」
テーマ
- クレジットカード
- 資格取得
- 退職願
- 職業訓練受講手当
- 自己PR
- 社会保険給付金
- 退職代行
- アルバイト
- 精神疾患
- 退職届
- インフルエンザ
- 確定申告
- 職業訓練受講給付金
- 退職代行サービス
- 雇用保険
- うつ病
- 面接
- 感染症
- 保険料
- 退職給付金
- ブラック企業
- 健康保険
- 統合失調症
- 障害手当金
- 引っ越し
- 社会保障
- ハローワーク
- ハラスメント
- 年金
- 契約社員
- 自己都合
- 社宅
- 就職
- 就業手当
- パワハラ
- 転職活動
- 弁護士
- 会社都合
- 障害者手帳
- 労働基準法
- 傷病手当
- モラハラ
- 転職サイト
- 公的貸付制度
- 失業給付
- 精神保険福祉手帳
- 雇用契約
- 退職コンシェルジュ
- セクハラ
- 職務経歴書
- 生活福祉資金貸付制度
- 新型コロナウイルス
- 労災
- 内定
- 社会保険給付金サポート
- 障害年金
- 人間関係
- 通勤定期券
- 有給消化
- 産休
- 就労移行支援
- 雇用保険サポート
- 引き継ぎ
- スタートアップ
- 不支給
- 休職
- 育児休暇
- 業務委託
- 退職手当
- 給与
- 転職
- 等級
- 免除申請
- 解雇
- 社会保険
- ストレス
- 残業代
- 違法派遣
- 離職票
- 適応障害
- 大企業
- 福利厚生
- 診断書
- 退職金
- 派遣契約
- 労務不能
- 住宅確保給付
- 中小企業
- 失業手当
- 会社都合退職
- 障害厚生年金
- 傷病手当金
- 給付金
- ベンチャー企業
- 就職困難者
- 自己都合退職
- 失業保険
- 年末調整
- 職業訓練
- 会社倒産
- 再就職手当
- 退職
- ブランク期間
- 障害者控除
- 再就職
- 退職勧奨
- 転職エージェント
新着記事
-
2025.08.19
仕事を辞める前にするべきこと10選|辞める際の流れや手続きを解説
-
2025.08.12
失業保険で損をしないためのポイントは?概要や受給する際の注意点も解説
-
2025.08.07
退職(離職)したらやることは?5つの手続きや知っておくべきことを解説
-
2025.08.05
解雇通知書とは?会社都合で解雇された際の手当についても解説
-
2025.08.01
うつで退職を決める前にやっておくべきことは?退職の流れや活用できる制度を解説
-
2025.07.25
会社を辞めさせられた場合は失業保険は受け取れる?条件や注意点を解説
-
2025.07.18
ストレスで仕事を辞める場合は診断書が必要?活用できる制度も解説
-
2025.07.10
潰瘍性大腸炎で退職したら失業保険はもらえる?その他の支援制度も解説
-
2025.07.10
退職したいけどお金がない場合の対処法7選!対処法や制度について解説
-
2025.07.09
4月退職は迷惑がかかる?メリット・デメリットや退職するポイントを解説





 サービス詳細
サービス詳細










