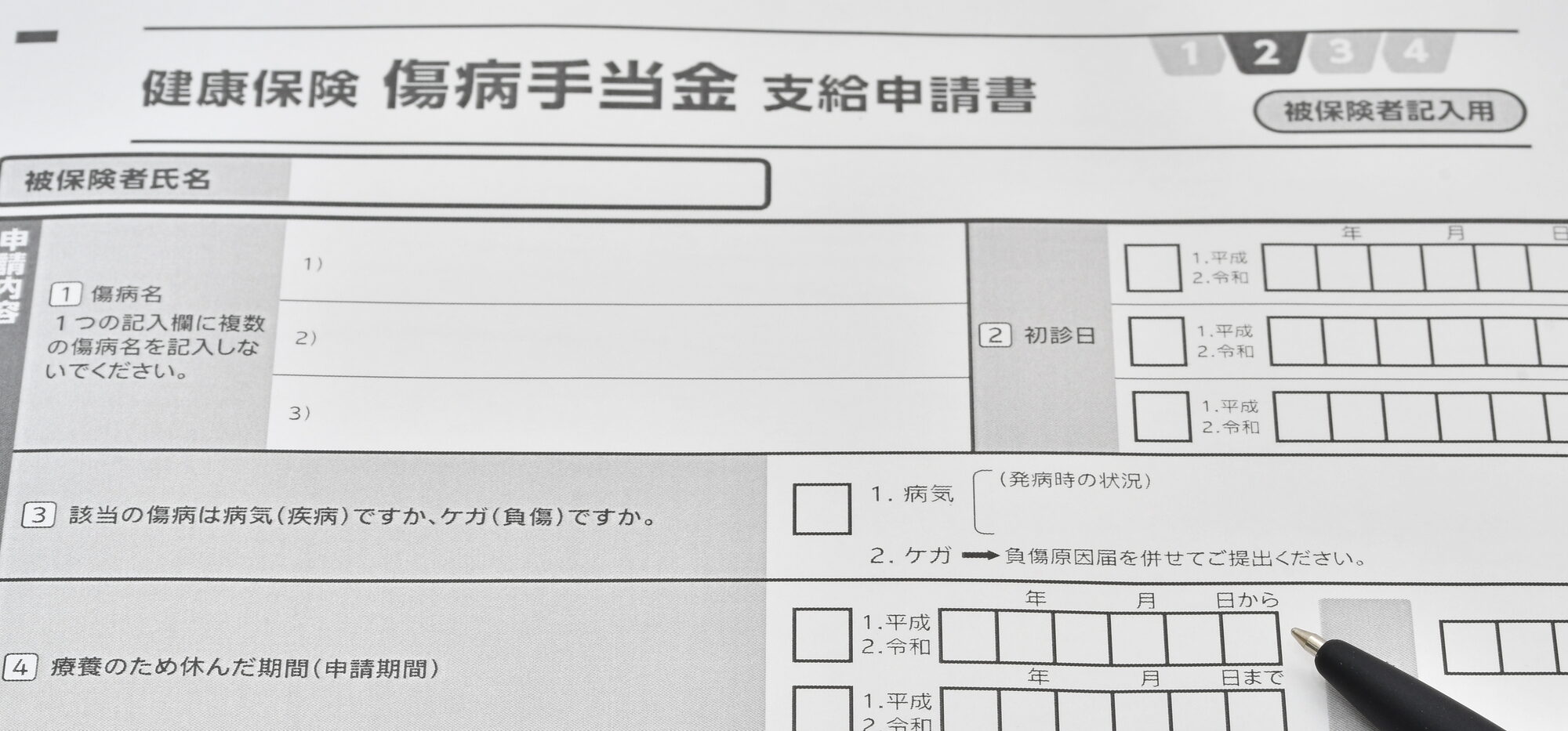2025.11.12
社会保険について
テーマ:
傷病手当金と税金の関係を完全解説!確定申告・扶養・住民税の扱いとは

「傷病手当金って税金がかかるの?」「確定申告は必要?」
休職や退職のタイミングで支給を受ける人が多い制度だけに、税金の扱いを不安に思う方は少なくありません。
結論から言えば──
傷病手当金は所得税・住民税ともに非課税です。
ただし、自治体によっては「申告書への記入」を求められる場合があり、ここを誤解すると「申告=課税」と勘違いしてしまう人も多いところ。
この記事では、2025年時点の最新ルールに基づき、傷病手当金がなぜ非課税なのか、その根拠と実務上の注意点をわかりやすく解説します。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
傷病手当金は非課税所得|法律上の根拠を確認

国税庁も明示する「非課税所得」
傷病手当金は、所得税法上「非課税所得」に分類されます。
国税庁の公式サイトでは、健康保険から支給される傷病手当金や出産手当金などは、所得税・住民税の課税対象外であると明記されています。
「傷病手当金」や「育児休業手当金」などの保険給付は、非課税所得に該当します。
参考:国税庁『給与所得Q&A』
この「保険給付」というのは、健康保険法(大正11年法律第70号)で定められた給付制度のこと。
e-Govで確認できる同法第99条にも、傷病手当金が健康保険の保険給付のひとつとして明確に規定されています。
参考:健康保険法(e-Gov法令検索)
つまり、健康保険法に基づいて支給される傷病手当金は、そもそも課税の対象にならないのです。
たとえ月20万円や30万円といった高額な支給を受けても、所得税・住民税はいっさいかかりません。
確定申告は原則不要|他の所得がある場合だけ注意
傷病手当金だけの人は確定申告不要
確定申告が必要になるのは、課税対象となる所得が一定額を超える場合です。
しかし、傷病手当金は非課税所得なので、たとえ受給額が多くても確定申告を行う必要はありません。
よって、「会社を休んでいて給料は止まり、傷病手当金だけを受け取っていた」という人は、確定申告不要です。
給与・副業など課税所得がある人は例外
一方、休職中に給与の一部が支給されていたり、副業収入がある場合は、課税対象となる所得が発生します。
この場合は、給与所得や雑所得として確定申告を行う必要があります。
ただしこのときも、傷病手当金そのものは申告対象に含めません。
あくまで課税対象となる所得(給与・事業・雑所得など)だけを記入します。
医療費控除などを受けたい場合も注意
医療費控除や生命保険料控除などを申請したい場合は、所得の多少にかかわらず確定申告書を提出できます。
この場合も、傷病手当金は「収入」には含めず、申告書の金額欄には記載不要です。
医療費控除の対象からも除外されます。
住民税も非課税|ただし申告を求められることがある
非課税でも申告書が届く理由
「非課税なのに、なぜ市役所から住民税の申告書が届いた?」
と驚く人も多いですが、これは税金を徴収するためではありません。
自治体は、国民健康保険料や児童手当・保育料の算定、非課税証明書の発行などのために、住民全員の前年所得を把握する必要があります。
会社員や年金受給者は自動的に報告されますが、収入がない人や非課税所得のみの人(=傷病手当金受給者)は、自治体が確認できません。
そのため、「前年の所得を申告してください」という案内が届くのです。
これはいわば「税金を取らないことを証明する」ための申告です。
例:千代田区「所得がなかった方でも、非課税証明書や国民健康保険料の算定のために申告をお願いする場合があります。」
申告書に金額を記載しても課税されない
自治体の所得申告書には、「非課税所得」や「備考」欄があり、
「健康保険法による傷病手当金 ○円」と記載を求められる場合があります。
しかし、これは行政上の所得確認にすぎず、実際の課税計算には反映されません。
つまり、金額を記載しても税金がかかることはありません。
まとめ:税金はかからないが書類は無視しない
- 傷病手当金は所得税・住民税ともに非課税
- 確定申告は原則不要
- 自治体から住民税申告書が届いた場合は「所得確認のため」提出
- 記載しても課税対象にはならない
扶養への影響|税法上は外れないが社会保険上は「収入」とみなされる
税法上の扶養(配偶者控除・扶養控除)には影響なし
まず、税金面での扶養(配偶者控除や扶養控除)については、傷病手当金の受給が直接影響することはありません。
理由はシンプルで、傷病手当金は所得税法上の非課税所得であり、「合計所得金額」に含める必要がないからです。
そのため、
- 配偶者控除(年収103万円以下)
- 配偶者特別控除(最大201万円以下)
といった税法上の扶養条件を満たしている限りは、傷病手当金の受給によって外れることはありません。
社会保険上の扶養は“収入扱い”で判定される
一方、健康保険・社会保険における「扶養」は、税法とは異なる判断基準です。
ここでは「課税か非課税か」ではなく、実際に得ている収入の金額で判定されます。
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、被扶養者認定の要件について以下のように定めています。
「被扶養者とは、主として被保険者の収入によって生計を維持している者であって、
年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)であること」
この「年間収入」には、給与・事業所得・年金などのほか、傷病手当金・失業給付・出産手当金などの給付金も含まれます。
つまり、たとえ非課税であっても、生活の糧となる定期的な収入である以上、「収入」として見なされるのです。
原則として基準を下回らない限り扶養には入れない
社会保険の扶養に入るための基準は次のとおりです。
| 年齢区分 | 年間収入基準 | 月額換算 | 扶養認定可否の目安 |
|---|---|---|---|
| 60歳未満 | 130万円未満 | 約108,334円未満 | 収入がこの範囲内なら扶養可能 |
| 60歳以上または一定の障害者 | 180万円未満 | 約150,000円未満 | 同上 |
傷病手当金の支給額がこの基準を超える場合、
「収入によって生計を維持している」とは見なされないため、被扶養者にはなれません。
つまり、扶養中の配偶者や家族が傷病手当金を受給しており、その額が年間130万円を上回る見込みがある場合、
社会保険上の扶養から外れる(または加入できない)のが原則です。
実際の運用例:被扶養者から外れるケース
例えば次のようなケースです。
- 配偶者が傷病手当金を月12万円受給(年間144万円)
- 他に給与収入なし
この場合、収入見込みが130万円を超えるため、協会けんぽや健康保険組合では
「被扶養者の要件を満たさない」と判断され、扶養から外れるのが一般的です。
外れた場合は、本人が国民健康保険へ加入することになります。
(傷病手当金自体は支給継続されますが、保険証が切り替わるため手続きが必要です)
基準を下回る場合でも個別確認が必要
一方、受給額が月10万円前後などで基準をわずかに下回る場合は、
支給期間・将来見込み・世帯の扶養状況なども含めて総合判断されます。
とくに支給が長期に続く場合は、
「恒常的な収入」と見なされ、被扶養者として認められないケースもあります。
したがって、
| “非課税=扶養に入れる”ではなく、“実際の収入金額が基準を超えないか”で判断される |
というのが正確な考え方です。
退職後に受け取る傷病手当金の税金・住民税
退職後も、在職中に発症・申請していれば、最長1年6か月間の支給を受けることができます。
この場合も、課税上の扱いは変わらず非課税所得です。
所得税・住民税は一切かかりません。
ただし、退職によって社会保険の扶養関係が変わるため、
配偶者の健康保険に入れない場合(=被扶養者要件を満たさない場合)は、
自分自身で国民健康保険への加入手続きが必要です。
また、翌年に自治体から住民税の「所得申告書」が届く場合があります。
これは前述のとおり課税目的ではなく、「前年の所得状況(非課税であること)」を確認するためのものです。
非課税であっても提出しておくと、非課税証明書の発行などがスムーズになります。
給与・失業手当・労災との違いを比較
| 給付・収入 | 税金の扱い | 社会保険上の収入扱い | 備考 |
|---|---|---|---|
| 給与 | 課税対象(源泉徴収あり) | 収入として扱う | 税金・保険とも課税対象 |
| 傷病手当金 | 非課税所得 | 収入に含める | 扶養判定では基準超過に注意 |
| 失業手当 | 非課税所得 | 収入に含める | 受給中は扶養不可 |
| 労災補償給付 | 非課税所得 | 原則収入に含めない(短期給付) | 給与性がないため除外される場合も |
まとめ|税金は非課税でも「扶養」は外れることがある
- 傷病手当金は所得税・住民税ともに非課税所得
- ただし、社会保険上は「収入」として扱われるため、扶養基準を超えると加入不可
- 年間130万円(月108,334円)を超える見込みがある場合は、扶養から外れる
- 退職後も非課税扱いは変わらないが、国民健康保険への加入が必要な場合がある
- 自治体から申告書が届いた場合は「所得確認目的」で提出しておくと安心
ケース別に見る|傷病手当金の税金・扶養・申告の取り扱い
ケース①:給与がなく傷病手当金のみを受給している場合

- 所得税:課税対象外(確定申告不要)
- 住民税:非課税だが、所得申告を求められる可能性あり扶養:
・税法上の扶養 → 維持される(非課税所得のため)
・社会保険上の扶養 → 月108,334円(年130万円)を超えなければ維持可能だが、超える場合は扶養から外れる
税金面では安心だが、社会保険の扶養基準に注意。
受給が長期化・高額化する場合は、早めに扶養の見直しを行うのが安全です。
ケース②:給与と傷病手当金を併給している場合
- 傷病手当金と給与が同時に支給される場合、給与額に応じて手当金が減額されますが、給与部分は課税所得として扱われるため、確定申告が必要になることがあります。
- ただし、傷病手当金そのものは非課税なので、申告対象には含めません。
例:
給与所得が年間80万円、傷病手当金が年間100万円の場合 →
課税対象は給与80万円のみ。
所得税は発生しない可能性が高く、住民税は非課税限度額を下回ることもあります。
ケース③:退職後に傷病手当金を受給している場合
退職後も、在職中に発症していれば支給期間(最長1年6か月)内で継続受給が可能です。
この場合も課税されません。
ただし、
- 扶養に入る場合 → 収入見込み130万円未満である必要
- 扶養に入れない場合 → 国民健康保険に加入する
翌年に自治体から「所得申告書」が届いたら、
「健康保険法による傷病手当金(非課税)」として記載しておきましょう。
申告しないと「未申告扱い」で非課税証明書が発行できないことがあります。
よくある質問(Q&A)
Q1. 傷病手当金をもらうと確定申告が必要ですか?
A. いいえ。傷病手当金は非課税所得なので確定申告は不要です。
ただし、給与や副業収入など課税所得がある場合は、その分のみ申告が必要です。
Q2. 傷病手当金を受け取ったら扶養から外れますか?
A. 税法上の扶養は外れませんが、社会保険上の扶養は収入扱いとなります。
年間130万円(月108,334円)を超える見込みがある場合は、原則として扶養から外れます。
Q3. 住民税の申告書に金額を記載したら課税されますか?
A. 課税されません。
自治体は所得確認のために「非課税所得欄」に記載を求めますが、税額計算には反映されません。
Q4. 傷病手当金を受けている間に他の給付金をもらった場合は?
A. 失業手当(雇用保険)や労災補償給付などもすべて非課税です。
ただし、重複して受け取れない制度(併給調整)があるため、申請前に制度を確認しましょう。
実務上のポイント|誤解しやすい3つの落とし穴
| よくある誤解 | 正しい理解 |
|---|---|
| 非課税だから確定申告も住民税申告も一切不要 | 非課税でも住民税の「所得申告」を求められる場合がある |
| 傷病手当金をもらっても扶養に影響しない | 社会保険上は収入扱い。130万円を超えると扶養から外れる |
| 給与の代わりでも税金がかかる | 健康保険法に基づく保険給付なので課税対象外 |
まとめ|非課税でも社会保険・申告には注意が必要
- 傷病手当金は所得税・住民税の課税対象外(非課税所得
- ただし、社会保険上は収入として扱われるため、基準(年間130万円)を超えると扶養から外れる
- 退職後に受給しても非課税扱いは変わらない
- 自治体から住民税申告書が届いた場合は「所得確認」のため提出しておく
税金面では安心でも、扶養・保険加入手続きには注意
傷病手当金は安心して受け取れる制度ですが、
「非課税=影響なし」ではなく、税金・扶養・社会保険それぞれのルールが異なる点を押さえておくことが重要です。
不明点がある場合は、勤務先の健康保険組合や「社会保険給付金サポート」への問い合わせも有効です。
お気軽にご連絡ください。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
この記事の監修者

萩原 伸一郎
ファイナンシャルプランナー(FP)資格を持ち、東証一部上場企業に入社。資産形成、資産運用、個人のライフプランニングなどを経験。これまでに10,000名以上の退職後のお金や退職代行に関する相談などを対応した経験から、社会保険や失業保険についてわかりやすく解説。
おすすめの関連記事
ピックアップ
- CATEGORY
- 給付金について
- 転職・再就職について
- 就労について
- 社会保険について
- 精神疾患について
- サービスについて
- 傷病手当金について
- 失業保険について
- 退職について
- 障害年金について
- ピックアップ
- 人気記事
-
退職代行サービスの利用方法、実際の流れと体験談を紹介
-
今の会社に3年後もいる自信はありますか?
-
退職代行を利用した時の有給消化の仕組みとその対応方法
-
退職代行サービスを使うメリット・デメリットは?
-
ブラック企業を判定する方法と実際のチェックポイント
-
障害年金を知ろう
-
会社を“円満に退職する”方法は?
-
退職時の引き継ぎは義務?スムーズな業務引き継ぎの必須ポイント
-
パワハラ、モラハラ、セクハラとは?
-
辞めさせてくれない!そんな時こそ「退職代行サービス」
テーマ
- 転職サイト
- 不支給
- 引っ越し
- 雇用契約
- 退職代行
- 職務経歴書
- 等級
- 社宅
- 内定
- 退職代行サービス
- 人間関係
- 離職票
- 障害者手帳
- 就労移行支援
- ブラック企業
- スタートアップ
- 労務不能
- 精神保険福祉手帳
- 業務委託
- ハラスメント
- 転職
- 傷病手当金
- 労災
- 社会保険
- 引き継ぎ
- 違法派遣
- 障害者控除
- 産休
- 福利厚生
- 給与
- 派遣契約
- 退職届
- 解雇
- 就職困難者
- 残業代
- 障害厚生年金
- 面接
- 中小企業
- 再就職手当
- 退職金
- 失業保険
- 障害手当金
- ベンチャー企業
- 社会保険給付金
- 会社都合退職
- 資格取得
- 新型コロナウイルス
- 退職勧奨
- 職業訓練受講給付金
- 自己都合退職
- うつ病
- 有給消化
- 自己PR
- 退職給付金
- クレジットカード
- 統合失調症
- 休職
- 確定申告
- ハローワーク
- アルバイト
- 契約社員
- 免除申請
- 保険料
- 傷病手当
- 雇用保険
- 弁護士
- 適応障害
- 社会保障
- 退職コンシェルジュ
- 健康保険
- 公的貸付制度
- 住宅確保給付
- 就職
- インフルエンザ
- 年金
- 生活福祉資金貸付制度
- 職業訓練
- 労働基準法
- ストレス
新着記事
-
2025.12.27
インフルエンザで仕事を休むと「傷病手当金」はもらえる?条件・日数・申請方法まで解説
-
2025.12.26
傷病手当金と副業の関係をわかりやすく解説
-
2025.12.17
傷病手当金の不正と調査|どこからがNG?就労・外出・求職活動の正しい判断基準を解説
-
2025.12.16
【徹底比較】退職給付金サポート おすすめランキング
-
2025.12.09
傷病手当金をもらいながら働く方法はある?アルバイトならOK?収入を得る方法や注意点を解説
-
2025.12.09
社会保険給付金と失業保険の違いは?受給要件やメリット・デメリット解説
-
2025.12.08
産休・育休後そのまま退職はマナー違反?退職時のポイントと注意点
-
2025.12.07
会社を辞めさせられた場合は失業保険は受け取れる?条件や注意点を解説
-
2025.12.04
傷病手当金は退職後もらえない?受給できる条件と不支給になる理由を徹底解説
-
2025.12.01
休職でも傷病手当金はもらえる?休職手当との違いや支給額を解説





 サービス詳細
サービス詳細