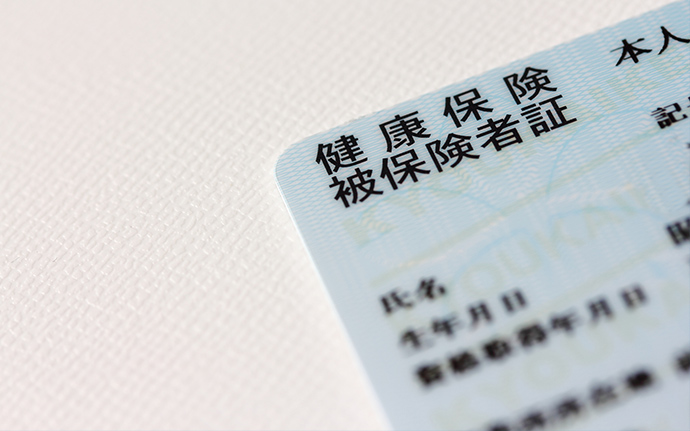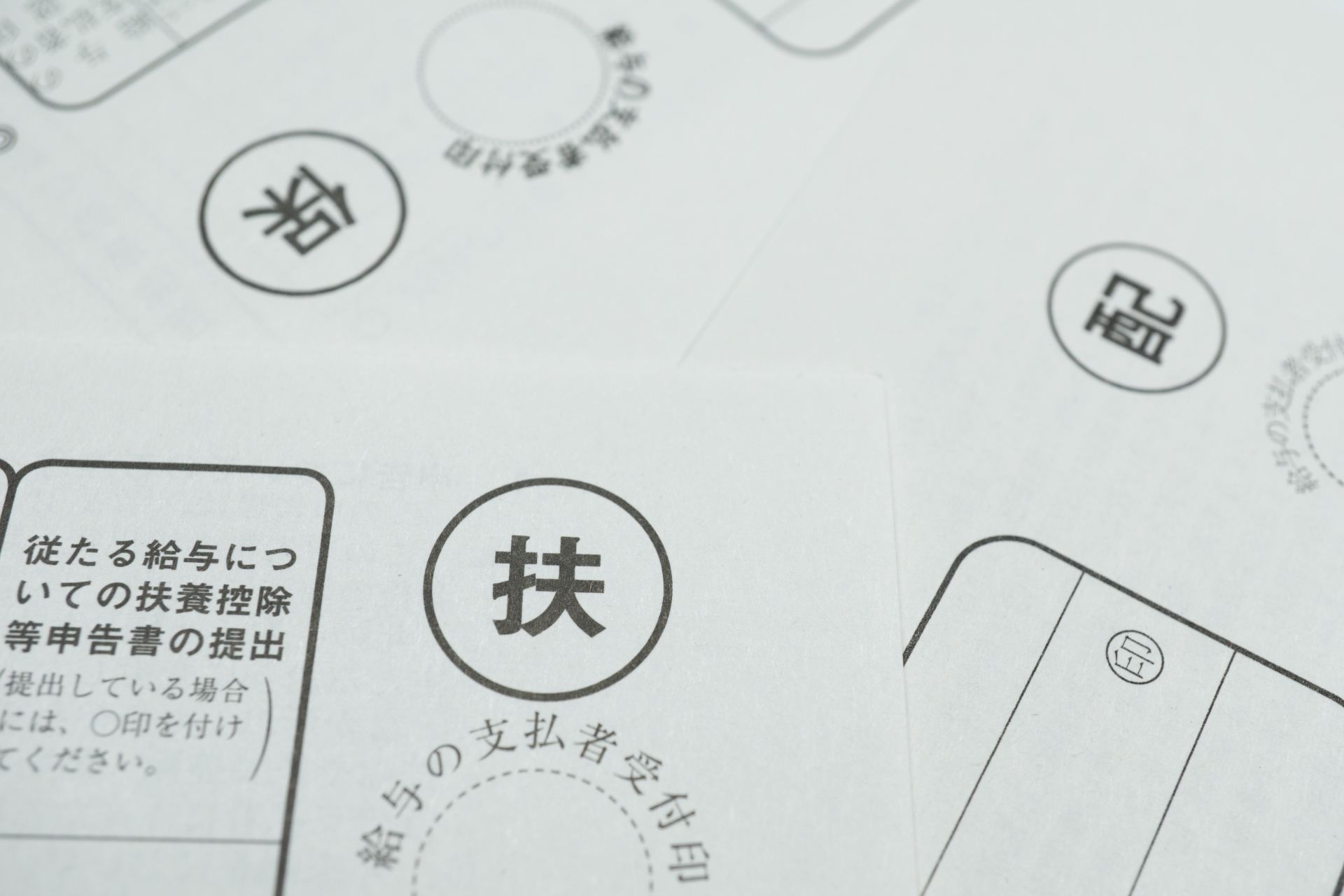2025.11.11
社会保険について
傷病手当金はいくらもらえる?計算方法と手取り額の目安

病気やケガで長期間働けなくなったとき、「会社を休んでも収入が途絶えないように支えてくれる制度」が傷病手当金です。
ただし実際にいくらもらえるのか、そして「手取りベース」でどの程度の生活費になるのかは分かりづらいですよね。
この記事では、最新(2025年時点)の制度をもとに、傷病手当金の計算方法と手取り額の目安をわかりやすく解説します。
厚生労働省や協会けんぽなどの公的資料を根拠にしながら、具体例・早見表つきで紹介します。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
傷病手当金とは?まずは制度の概要を確認

制度の目的
傷病手当金は、業務外のケガや病気で働けないときに、給与の一部を補うための給付です。
健康保険(社会保険)に加入している人が対象で、休業中に所得がゼロにならないよう支える制度として設けられています。
支給の条件
傷病手当金を受け取るには、次の4つの条件をすべて満たす必要があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ① 被保険者であること | 社会保険に加入していること |
| ② 業務外の理由で病気やケガをした | 労災は対象外(労災保険の対象) |
| ③ 労務不能であること | 医師の証明が必要 |
| ④ 給与の支払いがない、または減額されている | 無給または一部減額時に支給対象 |
これらの条件を満たしていれば、最長1年6カ月間、日額ベースで手当を受け取ることができます。
退職後でも受給できる場合がある
退職してからも、一定の条件を満たすと傷病手当金を継続して受給できます。
ただし、退職日までにすでに傷病手当金の受給が始まっていることが必要です。
この「退職後継続給付」は多くの人が見落とすポイントで、会社を辞めるタイミング次第で受給の可否が変わることもあります。
支給額の計算方法を理解しよう
次に、実際にいくらもらえるかの計算をしていきましょう。
基本の計算式
傷病手当金は、「給与の約3分の2」が支給されると聞いたことがあるかもしれません。
これは次のような計算式で算出されます。
|
支給額(日額) =(支給開始日以前の12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30)× 2/3 |
参考:全国健康保険協会|健康保険給付金支給額の計算方法について(PDF)
つまり、「過去1年間の標準報酬月額の平均」をもとに日額を出し、さらにその3分の2が支給される仕組みです。
「標準報酬月額」とは?
標準報酬月額とは、社会保険料を計算するために設定された、給与の等級表上の金額です。
たとえば毎月の給与が28万円なら、「標準報酬月額28万円」として計算されます。
標準報酬月額はあくまで“保険上の基準額”であり、実際の手取り額とは異なります。
したがって、傷病手当金の「3分の2」といっても、実際に口座に振り込まれる金額(手取り)とは少し差があります。
支給額の目安(例)
| 月収(標準報酬月額) | 傷病手当金の日額(約) | 1か月(30日換算)の支給額(約) |
|---|---|---|
| 20万円 | 約4,440円 | 約13万3,200円 |
| 30万円 | 約6,660円 | 約19万9,800円 |
| 40万円 | 約8,880円 | 約26万6,400円 |
「手取り」との違いを整理
傷病手当金は所得税がかかりません(非課税所得)ですが、社会保険料や住民税の支払いは別途必要です。
そのため、実際の生活で使える金額(手取り)は、上記表の金額より1〜2万円程度少ないケースが多いです。
たとえば、月収30万円の人の場合:
- 傷病手当金支給額:約19万9,800円
- 手取りの目安:約18万円前後
このように「非課税」とはいえ、給与時代の手取りより少なくなるため、休業中の家計をシミュレーションしておくことが大切です。
手取り額を左右するポイントと注意点
給与が一部支払われる場合の扱い
傷病手当金は「給与が支払われない期間」を対象としていますが、一部でも給与が支払われた場合は、その分が差し引かれます。
具体的には、次のように調整されます。
| 支給される金額 = 傷病手当金の基本額 − 給与支給分 |
たとえば、1日あたりの傷病手当金が6,000円で、会社から3,000円分の給与が出た場合は、差額の3,000円が支給されます。
つまり「給与+傷病手当金」が、もとの給与の約3分の2になるように調整される仕組みです。
税金の取り扱い(非課税)
傷病手当金は、所得税・住民税の課税対象外です。
給与のように源泉徴収されることもありません。
ただし、支給期間中も「社会保険料」や「住民税の納付義務」は残るため、次の点には注意が必要です。
- 社会保険料は、給与天引きがない分を自分で納付(退職後は任意継続や国保に切替)
- 住民税は前年の所得に基づくため、休業中でも支払い義務が発生
このため、手取り=支給額そのままではなく、実際には月1〜2万円ほど少なく感じる人が多いです。
退職後も受給できるケース
退職しても、一定条件を満たせば傷病手当金を受け続けることが可能です。
これを「退職後継続給付」と呼びます。
退職後に継続して受け取るには、以下すべてを満たしている必要があります。
- 退職日までに傷病手当金の支給を受けていること
- 退職日に引き続き労務不能であること
- 健康保険の被保険者期間が1年以上あること
この場合も、退職日以降の「無給期間」に対して支給が続きます。
ただし、健康保険組合ごとに細かい条件が異なるため、必ず加入先への確認、申請書類についてなどのサポートも検討の場合は給付金サポートサービスへも相談してみましょう
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
受給できない・減額される主なケース
以下のような場合は支給対象外または減額となります。
| ケース | 理由 |
|---|---|
| 労災事故での休業 | 労災保険が優先されるため |
| 出産手当金と重複 | 出産手当金が優先される |
| 年金受給(障害・老齢) | 一部減額・支給調整される |
| アルバイト・副業などで収入あり | 就労可能とみなされると支給停止も |
これらの制度間調整は複雑なため、複数の給付を受ける場合は健康保険組合への事前相談が安心です。
手取りの実際をイメージする計算例
ケース①:月収30万円、完全休職(給与ゼロ)
- 標準報酬月額:30万円
- 1日あたりの支給額:(30万円 ÷ 30)× 2/3 = 6,666円
- 1か月(30日)で:6,666円 × 30 = 約20万円
→ 支給額20万円、住民税・任意継続保険料などを自己負担となるため手取りの目安は約18万円前後
ケース②:月収30万円、給与の一部(10万円)が支払われた場合
- 傷病手当金支給額:20万円(基本額) − 10万円(給与分) = 10万円
→ 「給与10万円+手当10万円=合計20万円」となり、
おおむね給与の約3分の2程度を確保できる。
ケース③:月収20万円、退職後に継続給付
標準報酬月額:20万円
日額:(20万円 ÷ 30)× 2/3 = 約4,444円
1か月で:4,444円 × 30 = 約13万3,000円
→ 手取りは約12万円前後が目安。
この金額で家計を組み立てるため、生活費の見直しが重要です。
モデル別の早見表(2025年版)
| 標準報酬月額 | 支給額(月30日換算) | 手取りの目安 |
|---|---|---|
| 18万円 | 約12万円 | 約11万円 |
| 25万円 | 約16万6,000円 | 約15万円 |
| 30万円 | 約19万9,800円 | 約18万円 |
| 35万円 | 約23万3,100円 | 約21万円 |
| 40万円 | 約26万6,400円 | 約24万円 |
「社会保険料の支払い」に要注意
休職中でも、健康保険や厚生年金の保険料は発生します。
とくに退職後に任意継続を選ぶ場合、会社負担分を含めた全額自己負担となるため、
保険料は在職時の約2倍近くになることがあります。
そのため、傷病手当金が支給されても、実際の手取りでは
「在職時より月5〜7万円ほど減る」ケースも少なくありません。
申請の流れと実務上のポイント
申請に必要な書類
傷病手当金を受け取るためには、所定の申請書を提出する必要があります。
一般的に、以下の4つの欄を関係者がそれぞれ記入します。
| 記入者 | 内容 |
|---|---|
| ① 被保険者(本人) | 氏名・住所・休業期間など |
| ② 事業主(勤務先) | 給与支払い状況・在職証明 |
| ③ 医師 | 労務不能の証明・診断内容 |
| ④ 保険者(協会けんぽ・組合) | 内容確認と審査 |
申請書は健康保険組合の公式サイトからダウンロード可能な場合もあります。
申請から支給までの流れ(図解)
↓
② 会社(事業主)へ提出し、「事業主記入欄」に給与情報を記入してもらう
↓
③ 自身が「被保険者記入欄」を記入し、全ての欄が揃ったら提出
↓
④ 協会けんぽ(または健康保険組合)に郵送または事業所経由で提出
↓
⑤ 書類審査後、通常2〜4週間で支給決定・振込
※初回申請時は確認に時間がかかる場合があります。
※2回目以降は「続柄記入欄」のみ更新で申請がスムーズです。
提出期限と注意点
傷病手当金の申請には、明確な時効(期限)があります。
支給対象期間の翌日から2年以内
つまり、休職開始から2年以上経つと、その期間分の申請はできません。
後からまとめて請求する場合も、過去2年分までが限度となります。
よくある質問(Q&A)

Q1:パートやアルバイトでも受給できる?
社会保険(健康保険)に加入していれば、雇用形態に関係なく受給可能です。
ただし、勤務先が「健康保険未加入」の場合は対象外です。
※2024年10月から社会保険適用拡大により、週20時間以上勤務・月収8.8万円以上などの条件を満たすと加入対象になります。
参考:厚生労働省|社会保険適用拡大特設サイト
Q2:休職中に少しだけ働いた場合はどうなる?
「労務不能」とは、本来の仕事ができない状態を指します。
たとえば在宅で軽作業をしたり、副業で一時的に収入を得た場合でも、
本業の勤務ができない状態なら支給対象になる場合があります。
ただし、収入があるとその分が減額されるため、事前に必ず保険者へ確認しましょう。
Q3:退職してから申請することはできる?
可能です。退職時に傷病手当金を受給していた、または受給要件を満たしていた場合、
「退職後継続給付」として支給を続けられます。
ただし、退職後に新たに発症した病気は対象外となります。
Q4:扶養に入っている場合は?
扶養関係は健康保険の加入条件とは別に判断されます。
たとえば配偶者の扶養に入っていても、自分が社会保険に加入していれば
傷病手当金の対象となります。
反対に、扶養のみで健康保険に加入していない場合は受給できません。
Q5:他の給付金(出産手当金・労災・失業手当など)との併給は?
同時には受け取れません。
優先順位があり、以下のように調整されます。
| 他制度 | 優先される給付 | 備考 |
|---|---|---|
| 出産手当金 | 出産手当金が優先 | 同時支給不可 |
| 労災保険(休業補償) | 労災が優先 | 傷病手当金は支給対象外 |
| 失業手当 | どちらか一方 | 傷病手当金受給中は失業給付の受給不可 |
まとめ:手取り額を把握して、休業中も安心を
傷病手当金は、「給与の約3分の2」と言われますが、
実際の手取り額は生活費に直結する大事なポイントです。
最後に、改めてこの記事のポイントを整理すると以下の通りです。
- 計算式は「標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3」
- 所得税は非課税だが、社会保険料・住民税の支払いは継続
- 給与や他給付がある場合は減額調整
- 退職後でも条件を満たせば継続受給可能
- 申請は医師・会社・本人がそれぞれ記入、2年以内が期限
休職期間中の家計を安定させるためにも、
早めに「標準報酬月額」や「支給額の目安」を把握し、加入している健康保険の窓口へ確認しておくと安心です。
退職後より複雑になる傷病手当金の申請について不安な場合は「社会保険給付金サポート」の利用もおすすめです。
まずは気軽に問い合わせてみましょう。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
この記事の監修者

萩原 伸一郎
ファイナンシャルプランナー(FP)資格を持ち、東証一部上場企業に入社。資産形成、資産運用、個人のライフプランニングなどを経験。これまでに10,000名以上の退職後のお金や退職代行に関する相談などを対応した経験から、社会保険や失業保険についてわかりやすく解説。
おすすめの関連記事
ピックアップ
- CATEGORY
- 給付金について
- 転職・再就職について
- 就労について
- 社会保険について
- 精神疾患について
- サービスについて
- 傷病手当金について
- 失業保険について
- 退職について
- 障害年金について
- ピックアップ
- 人気記事
-
退職代行サービスの利用方法、実際の流れと体験談を紹介
-
今の会社に3年後もいる自信はありますか?
-
退職代行を利用した時の有給消化の仕組みとその対応方法
-
退職代行サービスを使うメリット・デメリットは?
-
ブラック企業を判定する方法と実際のチェックポイント
-
障害年金を知ろう
-
会社を“円満に退職する”方法は?
-
退職時の引き継ぎは義務?スムーズな業務引き継ぎの必須ポイント
-
パワハラ、モラハラ、セクハラとは?
-
辞めさせてくれない!そんな時こそ「退職代行サービス」
テーマ
- 転職サイト
- 不支給
- 引っ越し
- 雇用契約
- 退職代行
- 職務経歴書
- 等級
- 社宅
- 内定
- 退職代行サービス
- 人間関係
- 離職票
- 障害者手帳
- 就労移行支援
- ブラック企業
- スタートアップ
- 労務不能
- 精神保険福祉手帳
- 業務委託
- ハラスメント
- 転職
- 傷病手当金
- 労災
- 社会保険
- 引き継ぎ
- 違法派遣
- 障害者控除
- 産休
- 福利厚生
- 給与
- 派遣契約
- 退職届
- 解雇
- 就職困難者
- 残業代
- 障害厚生年金
- 面接
- 中小企業
- 再就職手当
- 退職金
- 失業保険
- 障害手当金
- ベンチャー企業
- 社会保険給付金
- 会社都合退職
- 資格取得
- 新型コロナウイルス
- 退職勧奨
- 職業訓練受講給付金
- 自己都合退職
- うつ病
- 有給消化
- 自己PR
- 退職給付金
- クレジットカード
- 統合失調症
- 休職
- 確定申告
- ハローワーク
- アルバイト
- 契約社員
- 免除申請
- 保険料
- 傷病手当
- 雇用保険
- 弁護士
- 適応障害
- 社会保障
- 退職コンシェルジュ
- 健康保険
- 公的貸付制度
- 住宅確保給付
- 就職
- インフルエンザ
- 年金
- 生活福祉資金貸付制度
- 職業訓練
- 労働基準法
- ストレス
新着記事
-
2025.12.27
インフルエンザで仕事を休むと「傷病手当金」はもらえる?条件・日数・申請方法まで解説
-
2025.12.26
傷病手当金と副業の関係をわかりやすく解説
-
2025.12.17
傷病手当金の不正と調査|どこからがNG?就労・外出・求職活動の正しい判断基準を解説
-
2025.12.16
【徹底比較】退職給付金サポート おすすめランキング
-
2025.12.09
傷病手当金をもらいながら働く方法はある?アルバイトならOK?収入を得る方法や注意点を解説
-
2025.12.09
社会保険給付金と失業保険の違いは?受給要件やメリット・デメリット解説
-
2025.12.08
産休・育休後そのまま退職はマナー違反?退職時のポイントと注意点
-
2025.12.07
会社を辞めさせられた場合は失業保険は受け取れる?条件や注意点を解説
-
2025.12.04
傷病手当金は退職後もらえない?受給できる条件と不支給になる理由を徹底解説
-
2025.12.01
休職でも傷病手当金はもらえる?休職手当との違いや支給額を解説





 サービス詳細
サービス詳細