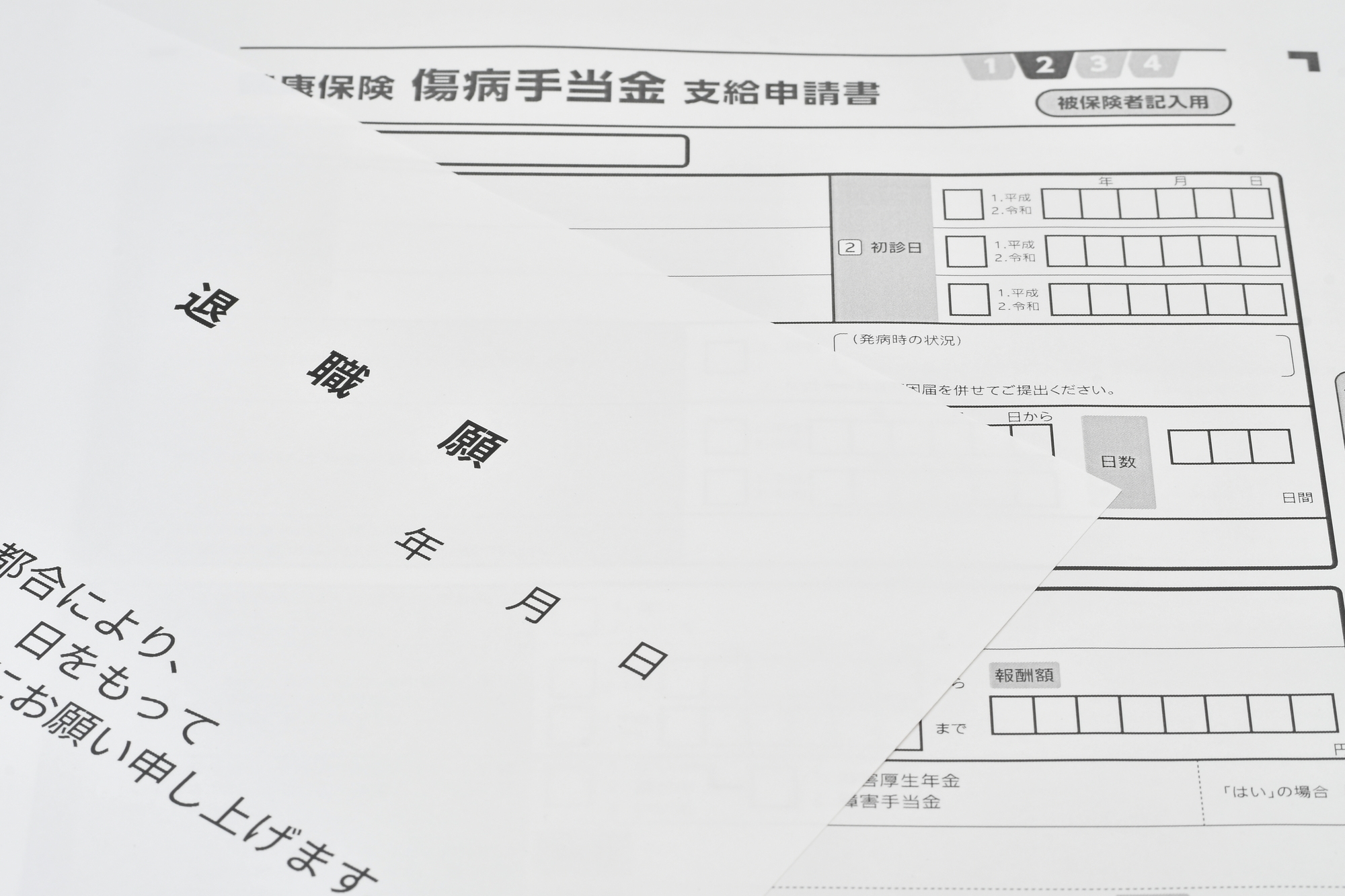2025.11.11
社会保険について
傷病手当金申請書は誰が書く?本人・会社・医師の役割と注意点

「傷病手当金を申請したいけど、書類って自分で全部書くの?」
そう疑問に思う方は多いのではないでしょうか。
実は、傷病手当金の申請書は「本人・会社・医師」の3人がそれぞれ記入して完成する仕組みになっています。
つまり、あなた一人で完結できるものではありません。
しかも退職後になると、会社の協力を得にくかったり、医師の証明を毎月もらう必要があったりと、
自力で申請を進めるのは想像以上に大変です。
この記事では、
- 申請書は誰がどの部分を書くのか
- 書類の入手・提出の流れ
- 退職後に申請する際の注意点やつまずきポイント
といった内容を、わかりやすく順を追って解説していきます。
初めての方でも「ここを押さえれば迷わない!」と思えるようにまとめていますので、
ぜひ最後までチェックしてみてください。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
傷病手当金申請書ってそもそも何?

仕事を休んでいる間にお給料が出ないとき、健康保険から支給されるのが「傷病手当金」です。
病気やケガで働けなくなったときの生活をサポートしてくれる制度で、健康保険法第99条に基づいています。
ただし、このお金を受け取るには「傷病手当金支給申請書」を提出する必要があります。
この書類は、本人・会社・医師の3者がそれぞれの欄を記入して、そろって初めて提出できる仕組みです。
つまり、「自分だけでパッと書いて出せる書類」ではありません。
医師の証明や会社の記入が必要になるため、調整や確認に時間がかかりやすいのが実情です。
傷病手当金申請書は誰が書く?3人の役割を整理しよう
申請書を完成させるには、3人の協力が欠かせません。
それぞれの担当を順番に見ていきましょう。
① 本人(自分)が書くところ
最初に、自分で書くのが「被保険者記入欄」です。
ここには、氏名・住所・生年月日などの基本情報のほか、休んだ期間や振込先の口座情報などを記入します。
- 健康保険証の記号・番号
- 勤務先
- 休業開始日・療養期間
- 振込先の金融機関名・口座番号
押印欄がある場合は自筆で署名し、印鑑を忘れずに。
提出後に修正できないことも多いので、控えを取っておくと安心です。
② 会社(事業主)が書くところ
2枚目の「事業主記入欄」は、勤務先(人事・総務など)が記入します。
ここでは、あなたがどの期間働いていたか、休職中に給与が出ていたかなどを証明します。
- 出勤・欠勤・有給の状況
- 給与や手当の支払い有無
- 標準報酬月額
- 会社代表者名・押印
この部分は「事業主証明」にあたるため、本人が代筆することはできません。
もし退職後に申請する場合は、退職前に会社に記入してもらう準備が超重要です。
③ 医師が書くところ
3枚目の「療養担当者意見書」は、主治医が書く部分です。
ここには、病気やケガの内容、働けない期間、回復の見込みなどが書かれます。
医師が記入することで、健康保険が「この人は実際に働けない状態なんだな」と判断できるわけです。
この部分は本人が書けないので、必ず医師に依頼します。
病院によっては、申請書記入料(診断書料のようなもの)がかかる場合もあるので、受付で確認しておくと安心です。
退職後に申請するのはハードルが高い
在職中なら、会社が書類の取りまとめをしてくれるケースが多いのですが、
退職後に「継続して傷病手当金を申請する」となると、ここが一気に難しくなります。
理由は主に3つです。
- 会社の協力が得にくくなる(担当者が変わったり、書類のやり取りに時間がかかる)
- 医師の証明書を毎月もらう必要がある(1回で終わらない)
- 自分で健康保険組合に郵送・問い合わせをする必要がある
つまり、在職中のように「会社が間に入ってくれる」サポートがないため、
すべての管理・記入依頼・提出を自分でやる必要があるんです。
特に、申請書の書き方や提出先の判断ミスで支給が遅れたり、書類が差し戻されるケースも珍しくありません。
「自力だとかなり難しい」と言われるのは、まさにこのためです。
もし退職後も申請を続ける予定がある場合は、退職前に会社・医師・保険組合に確認して段取りを整えておくのがベストです。
3人の流れを図で見てみよう
申請書ができあがるまでの流れを、ざっくり図にするとこんな感じです。
↓
② 医師:病院で意見書欄を記入してもらう
↓
③ 会社:勤務・報酬欄を記入して証明押印
↓
④ 健康保険へ提出(協会けんぽ or 健康保険組合)
3者のタイミングがそろわないと提出できないため、
「誰がいつ書けるか」をあらかじめ調整しておくのが大切です。
傷病手当金申請書の入手方法と提出先
ここからは、「申請書ってどこで手に入るの?」「どこに出せばいいの?」という実務的な部分を整理していきましょう。
実はこの部分でも、健康保険の種類によって少し違いがあるんです。
申請書の入手方法
申請書は、あなたが加入している健康保険によって入手先が異なります。
多くの人が加入している「協会けんぽ」の場合は、公式サイトからPDFでダウンロードできます。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金支給申請書」
印刷して使う形式なので、プリンターがなければコンビニ印刷などを利用しましょう。
会社独自の「健康保険組合」に入っている場合は、各組合ごとに書式が異なることがあります。
そのため、勤務先の人事担当や健保組合のホームページで「傷病手当金申請書」を探すのが確実です。
例:トヨタ健康保険組合・関東ITソフトウェア健康保険組合などは独自書式です。
提出先と提出方法
申請書を提出するのは、あなたが加入している健康保険の「保険者」(運営元)です。
勤務先ではなく、健康保険そのものに提出する点を間違えないようにしましょう。
| 加入先 | 提出先 | 提出方法の例 |
|---|---|---|
| 協会けんぽ | 各都道府県の支部(管轄) | 郵送 or 窓口提出 |
| 健康保険組合 | 所属する組合本部 | 郵送 or 会社経由提出 |
提出時は、記入済みの原本(コピー不可)を送付します。
封筒には「傷病手当金支給申請書在中」と書いておくと安心です。
提出期限の目安
傷病手当金は、支給対象になった日(労務不能になった日)から2年以内に申請しないと時効になります。
あまり知られていませんが、2年を過ぎると受け取れなくなるので要注意です。
また、申請書は月ごとに必要になります。
「1ヶ月分書いて提出 → 次の月も同じ手順を繰り返す」というイメージです。
つまり、医師の証明も毎回もらう必要があります。
退職後に申請する場合の注意点
ここからが、実は一番つまずきやすいポイントです。
退職してからも傷病手当金をもらえるケースはありますが、申請手続きは一気に難しくなるんです。
退職後ももらえる人の条件
退職後でも、次の条件をすべて満たせば支給が続く可能性があります(健康保険法第104条)。
- 退職日までに継続して1年以上、健康保険に加入していた
- 退職時点で傷病手当金を受給中、または受給資格がある状態だった
- 退職後も引き続き同じ傷病で働けない状態が続いている
- この条件を満たしていれば「継続給付」として申請できます。
でも実際は自力申請がかなり大変
前述の通り退職後に自力での申請はかなりハードルが高い作業です。
退職後は、会社が書類を取りまとめてくれることがないため、完全に自分で進める必要があります。
たとえば、こんな壁があります。
- 医師に毎月「療養担当者意見書」を書いてもらわなければいけない
- 元の会社に「事業主証明」を頼まなければいけない
- 健康保険の提出先を自分で調べて郵送・管理しなければいけない
- 書き方や記載ミスによる差し戻しリスク
特に「会社記入欄」を退職後に依頼するのは、連絡が取りづらかったり、担当が変わっていたりして苦労するケースが多いです。
また、健康保険組合によっては「在職時の証明がなければ受け付けられない」とされることもあります。
こうした理由から、退職後の継続申請を完全に自力でやるのは、正直かなりハードルが高いです。
スムーズに進めるためのコツ
退職後も申請予定がある場合は、退職前から次の準備をしておくのがおすすめです。
1.会社に記入を依頼しておく
退職直前に「事業主記入欄」を埋めてもらいましょう。
後で連絡を取るよりもずっとスムーズです。
2.健康保険の提出先を確認しておく
自分がどの健康保険組合かをあらかじめチェック。
提出先の住所もメモしておくと安心です。
3.医師に継続証明を依頼するタイミングを決める
毎月どのタイミングで書いてもらうかを事前に相談しておくと、抜け漏れが防げます。
これをやっておくだけでも、退職後の手続きがかなりスムーズになります。
もしどうしても難しいときは
傷病手当金の継続申請は、書類を集めて提出するだけでも労力がかかります。
特に体調が安定していない時期は、自分で全てやるのは大きな負担です。
最近では、給付金サポートサービスに依頼して手続きをサポートしてもらうのも手です。
費用はかかりますが、「提出ミスや書類の遅れで支給が止まるリスク」を防げるというメリットもあります。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
退職後の申請フローを整理
↓
② 医師:療養担当者意見書を毎月記入
↓
③ 本人:自分の欄を記入し、保険者へ郵送
↓
④ 健康保険:審査 → 支給決定
このように、退職後はすべて自分で動かす必要があります。
体調が不安定な中で進めるのは大変なので、「誰にどの書類を頼むか」をあらかじめ整理しておくと安心です。
傷病手当金申請でよくある質問とトラブル例

申請書の仕組みや提出方法がわかっても、実際に手続きを進めると「ここどうすればいいの?」という場面が出てきます。
ここでは、よくある質問とつまずきやすいポイントをQ&A形式でまとめました。
Q1. 医師の証明が遅れて提出期限を過ぎたらどうなる?
提出期限(2年以内)を過ぎると、原則としてその期間分の傷病手当金は時効で受け取れません。
ただ、2年以内であれば「医師の証明が後になった」場合でも受理されることが多いです。
つまり、「証明書がまだ出ていないから」と放置せず、とりあえず本人欄と会社欄だけ先に提出しておくのも有効です。
医師の証明が整い次第、追って提出するようにしましょう。
Q2. 会社が協力してくれない場合はどうすれば?
会社が事業主記入欄を書いてくれない場合でも、支給をあきらめる必要はありません。
健康保険によっては、本人が会社の報酬明細などを添付して代替資料として扱ってくれるケースもあります。
まずは、加入している健康保険(協会けんぽや健保組合)の支部に相談しましょう。
状況を説明すれば、必要書類や対応方法を案内してもらえます。
ただし、退職後は会社との連絡が取りづらくなるため、在職中にできる限り書類をそろえておくのが理想です。
Q3. 医師に「この期間は働ける」と言われて書いてもらえないときは?
医師が「もう働ける状態」と判断すれば、当然ながら傷病手当金の対象外になります。
これは本人の希望ではなく、医師の医学的な判断に基づいて決まります。
もし「体調的にまだ厳しいのに…」という場合は、セカンドオピニオンとして他の医師に相談する方法もあります。
また、復職後に体調を崩して再び働けなくなった場合は、再支給申請も可能です。
Q4. 健康保険組合ごとに申請書は違う?
それぞれ微妙に違います。
基本的な内容は同じな場合でも、フォーマットや提出先、記入欄の順番が異なる場合があります。
特に企業の健康保険組合では、
「会社のシステム上から申請する」「電子申請が必要」といったルールを設けている場合も。
自分の保険証に書かれている「保険者名」を確認して、該当するHPから最新の申請書をダウンロードするのが確実です。
Q5. 申請書をなくしたら再発行できる?
提出前なら、再度ダウンロードして書き直せばOKです。
すでに会社や医師に依頼していた場合は、それぞれにもう一度お願いする必要があります。
提出後に「控えを取っていなかった」というケースも多いので、
今後はコピーを1部残しておくのが鉄則です。
(スマホで写真を撮っておくだけでも十分役立ちます。)
退職後の継続給付でつまずかないためのポイント
改めて整理すると、退職後に傷病手当金を申請・継続するのは、
「会社」「医師」「保険者」すべてと個別にやり取りする必要があるため、かなりの労力がかかります。
体調が安定していない中で、
- 申請書の記入ミス
- 医師の証明忘れ
- 会社への依頼漏れ
などが起きやすく、支給がストップする原因にもなりがちです。
自分で進めるのが不安なら専門サポートも検討を
最近では、給付金サポートの専門サービスが、
「申請書の作成」「医師への依頼文書のサポート」「提出先確認」までサポートしてくれるケースもあります。
特に退職後に一人で進めるのが難しい方や、体調が安定しない方には、
ミスを防ぎながら確実に受け取れる手段として利用価値があります。
(制度の仕組みを理解しておくだけでも、トラブルをかなり減らせます。)
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼

まとめ|申請書は3人で完成、退職前の準備がカギ
傷病手当金の申請書は、本人・会社・医師の3者がそろって初めて提出できる書類です。
それぞれの欄が欠けていると、支給が遅れたり不支給になることもあります。
とくに退職後に継続して申請する場合は、
会社の協力が得にくかったり、提出先の確認が複雑だったりと、自力で進めるにはかなりの根気が必要です。
そのため、
- 退職前に会社欄を埋めてもらっておく
- 医師への依頼タイミングを決めておく
- 提出先の住所や書式を確認しておく
この3点を早めに準備しておくと、あとで大きなトラブルを防げます。
「とりあえず大丈夫でしょ」と思っていると、実際の申請時に慌ててしまう人が多いので、
余裕のあるうちに手を打っておきましょう。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼

この記事の監修者

萩原 伸一郎
ファイナンシャルプランナー(FP)資格を持ち、東証一部上場企業に入社。資産形成、資産運用、個人のライフプランニングなどを経験。これまでに10,000名以上の退職後のお金や退職代行に関する相談などを対応した経験から、社会保険や失業保険についてわかりやすく解説。
おすすめの関連記事
ピックアップ
- CATEGORY
- 給付金について
- 転職・再就職について
- 就労について
- 社会保険について
- 精神疾患について
- サービスについて
- 傷病手当金について
- 失業保険について
- 退職について
- 障害年金について
- ピックアップ
- 人気記事
-
退職代行サービスの利用方法、実際の流れと体験談を紹介
-
今の会社に3年後もいる自信はありますか?
-
退職代行を利用した時の有給消化の仕組みとその対応方法
-
退職代行サービスを使うメリット・デメリットは?
-
ブラック企業を判定する方法と実際のチェックポイント
-
障害年金を知ろう
-
会社を“円満に退職する”方法は?
-
退職時の引き継ぎは義務?スムーズな業務引き継ぎの必須ポイント
-
パワハラ、モラハラ、セクハラとは?
-
辞めさせてくれない!そんな時こそ「退職代行サービス」
テーマ
- 転職サイト
- 不支給
- 引っ越し
- 雇用契約
- 退職代行
- 職務経歴書
- 等級
- 社宅
- 内定
- 退職代行サービス
- 人間関係
- 離職票
- 障害者手帳
- 就労移行支援
- ブラック企業
- スタートアップ
- 労務不能
- 精神保険福祉手帳
- 業務委託
- ハラスメント
- 転職
- 傷病手当金
- 労災
- 社会保険
- 引き継ぎ
- 違法派遣
- 障害者控除
- 産休
- 福利厚生
- 給与
- 派遣契約
- 退職届
- 解雇
- 就職困難者
- 残業代
- 障害厚生年金
- 面接
- 中小企業
- 再就職手当
- 退職金
- 失業保険
- 障害手当金
- ベンチャー企業
- 社会保険給付金
- 会社都合退職
- 資格取得
- 新型コロナウイルス
- 退職勧奨
- 職業訓練受講給付金
- 自己都合退職
- うつ病
- 有給消化
- 自己PR
- 退職給付金
- クレジットカード
- 統合失調症
- 休職
- 確定申告
- ハローワーク
- アルバイト
- 契約社員
- 免除申請
- 保険料
- 傷病手当
- 雇用保険
- 弁護士
- 適応障害
- 社会保障
- 退職コンシェルジュ
- 健康保険
- 公的貸付制度
- 住宅確保給付
- 就職
- インフルエンザ
- 年金
- 生活福祉資金貸付制度
- 職業訓練
- 労働基準法
- ストレス
新着記事
-
2025.12.27
インフルエンザで仕事を休むと「傷病手当金」はもらえる?条件・日数・申請方法まで解説
-
2025.12.26
傷病手当金と副業の関係をわかりやすく解説
-
2025.12.17
傷病手当金の不正と調査|どこからがNG?就労・外出・求職活動の正しい判断基準を解説
-
2025.12.16
【徹底比較】退職給付金サポート おすすめランキング
-
2025.12.09
傷病手当金をもらいながら働く方法はある?アルバイトならOK?収入を得る方法や注意点を解説
-
2025.12.09
社会保険給付金と失業保険の違いは?受給要件やメリット・デメリット解説
-
2025.12.08
産休・育休後そのまま退職はマナー違反?退職時のポイントと注意点
-
2025.12.07
会社を辞めさせられた場合は失業保険は受け取れる?条件や注意点を解説
-
2025.12.04
傷病手当金は退職後もらえない?受給できる条件と不支給になる理由を徹底解説
-
2025.12.01
休職でも傷病手当金はもらえる?休職手当との違いや支給額を解説





 サービス詳細
サービス詳細