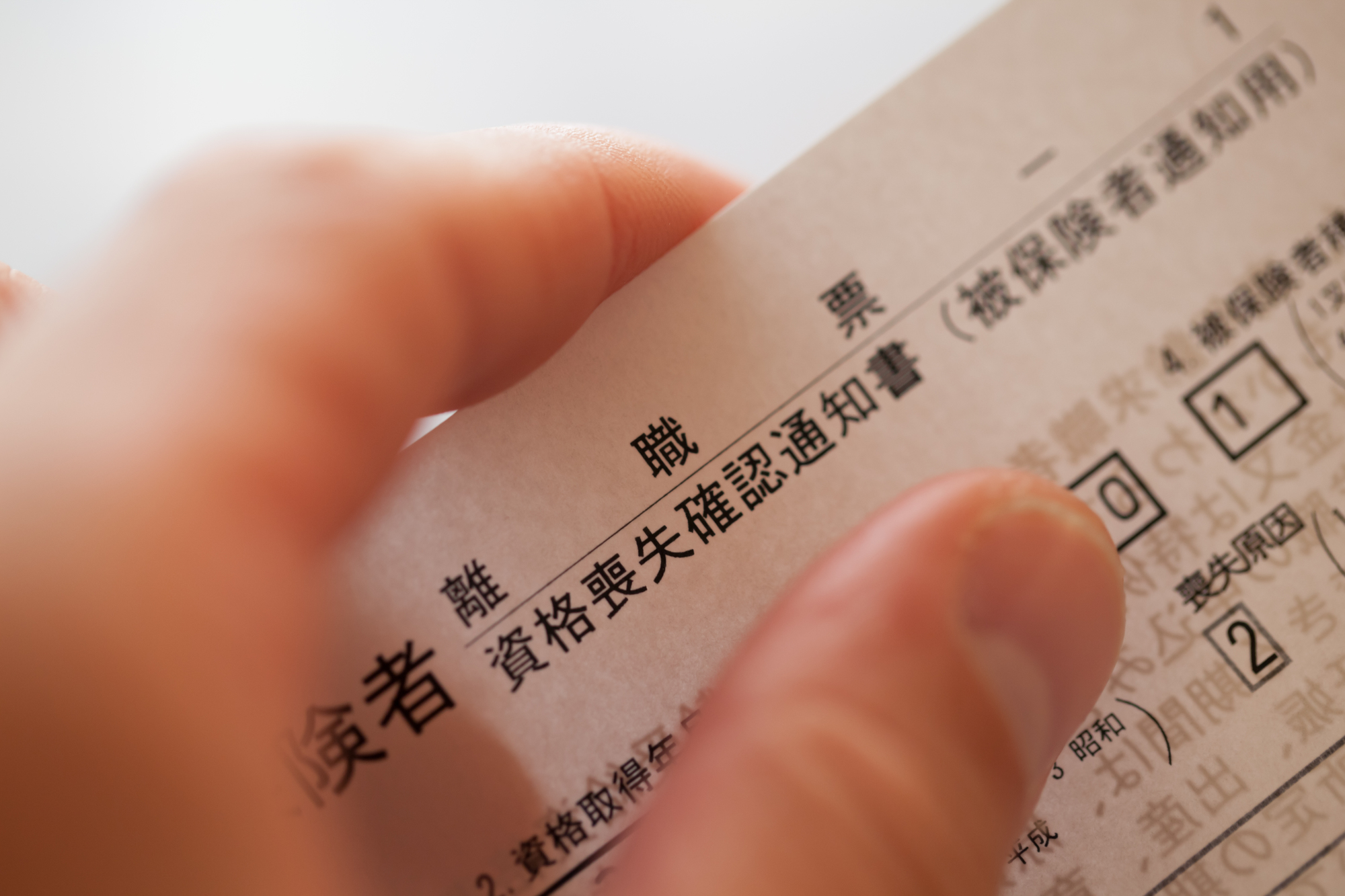2025.11.28
失業保険について
失業保険の申請方法は?離職票の発行手続きや延長申請の手順も解説

失業保険の給付金を受け取るためには、必要書類を準備した上でハローワークでの申請手続きが必要です。しかし、どのような書類が必要なのか、どのように手続きを進めればいいのか、疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、失業保険の申請に必要な書類の種類や入手方法、受給までの具体的な流れ、スムーズに手続きを進めるためのポイントを解説します。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
失業保険の手続きに必要な申請書類
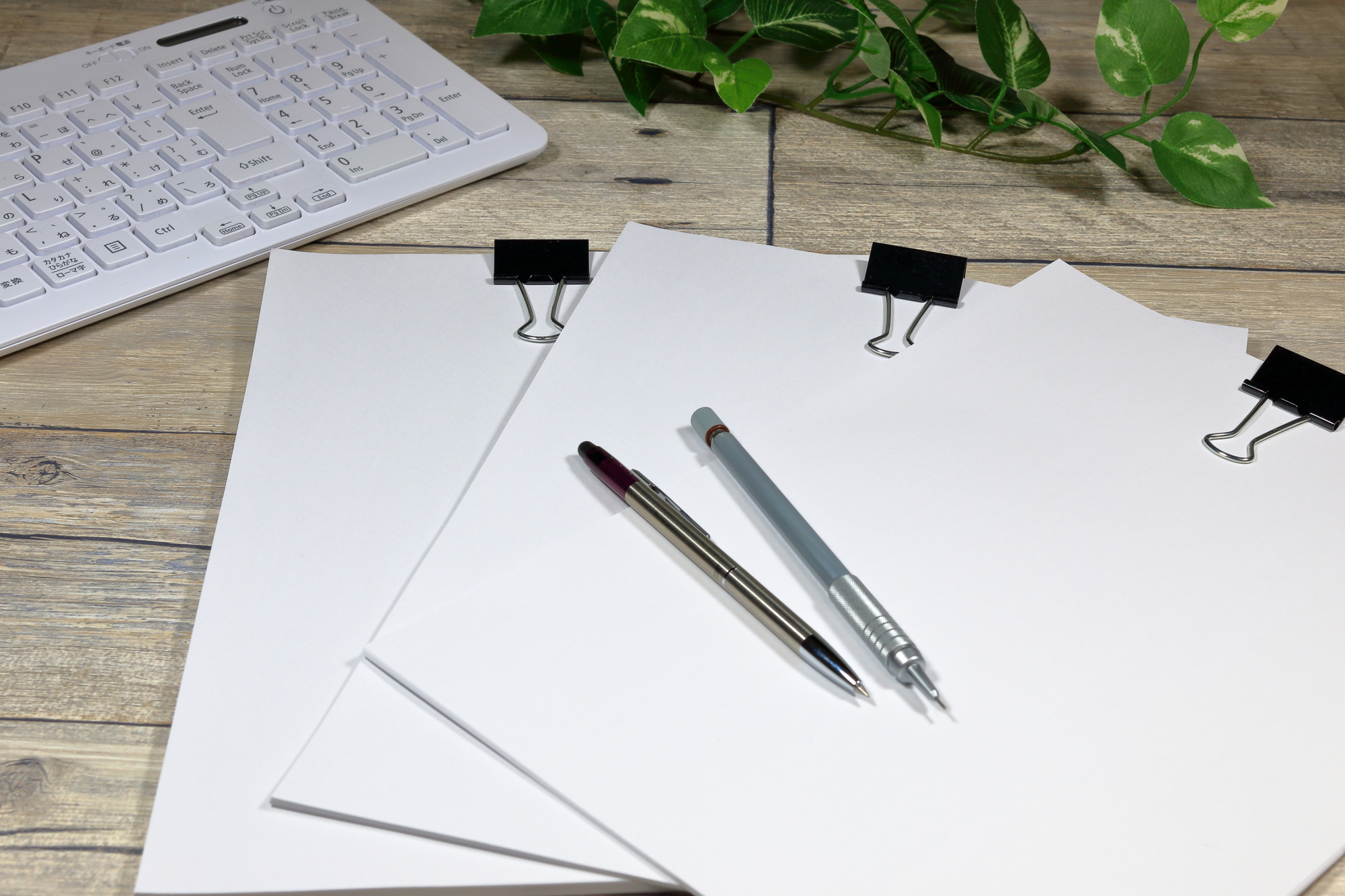
失業保険の手続きに必要な申請書類と入手先、入手できる時期を以下の表にまとめました。
|
必要書類の種類 |
入手先 |
入手できる時期 |
|
雇用保険被保険者証 |
会社または労働者自身が保管 |
会社保管の場合は退職時 |
|
雇用保険被保険者離職票-1、-2 |
会社から郵送または手渡し |
退職後約1週間〜2週間 |
上記以外に、以下の書類も必要です。
- 個人番号確認書類
- 本人確認書類
- 顔写真2枚
- 本人名義の預金通帳やキャッシュカード
まずは、手続きで必要になる書類について、一つずつ詳しくみていきましょう。
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証とは、雇用保険に加入している人に発行される書類です。雇用保険の被保険者であることを証明する書類で、雇用保険被保険者番号や被保険者氏名、生年月日が記載されています。
また、雇用保険被保険者証に添付されている「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」には、事業所名や雇用保険の資格取得年月日などが書かれています。
この書類は、雇用保険に加入すると発行され、原則は会社から受け取って労働者本人が管理します。会社が保管している場合は、退職時に返却されるのが一般的です。
雇用保険被保険者離職票-1、-2
雇用保険被保険者離職票とは、会社を退職したことを証明する公的書類です。退職後に会社が手続きすることでハローワークが発行して会社に郵送され、最終的に退職者に渡されます。
離職票がないと失業保険を受給できないため、手元に届いたら手続きまで大切に保管しておきましょう。以下のような退職後に会社から渡される書類や、手元にある似たような書類と間違えないように注意が必要です。
- 雇用保険被保険者証
- 健康保険資格喪失証明書
- 基礎年金番号通知書・年金手帳
- 源泉徴収票
- 退職証明書
- 離職証明書
個人番号確認書類
個人番号確認書類とは、個人番号(マイナンバー)を確認できる以下のような書類です。
- マイナンバーカード
- 通知カード
- 個人番号の記載された住民票の写し
住民票の写しは、住所地の市区町村役場で交付申請できます。通常の住民票の写しに個人番号は記載されないため、「個人番号入りの住民票の写し」が必要なことを伝えて交付してもらう必要があります。
本人確認書類
身分確認できる書類として、以下のうちいずれか1種類を準備しましょう
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- マイナンバーカード
- 官公署発行の写真付き運証明書や資格証明書
上記を準備できない場合は、以下のうち2種類の原本でも問題ありません。
- 公的医療保険の被保険者証
- 児童扶養手当証書
顔写真2枚
手続きごとに毎回マイナンバーカードを持参しない場合は、正面上三分身・縦3.0cm×横2.4cmの顔写真を2枚準備します。厳密に写真を撮った時期は定められていませんが、より最近のものが望ましいとされています。
本人名義の預金通帳やキャッシュカード
失業保険の給付金は銀行振込されるため、本人名義の預金通帳やキャッシュカードが必要です。
インターネット銀行など、一部の金融機関は指定口座にできないことがあるので注意しましょう。また、本人ではない家族の口座を指定することはできません。
失業保険の受給に必要な離職票を発行してもらう方法
失業保険の受給には、離職票の提出が必要です。離職票は退職後、自動的に受け取れるものではなく、発行は任意となっています。
そのため、退職前に会社に発行依頼しておく必要があります。離職票を発行してもらう手順を詳しくみていきましょう。
会社に離職票の発行を依頼する
退職が決まり、失業保険を受給する可能性がある場合は、会社の担当者に離職票の発行を依頼します。
退職前は失業保険を受け取らない予定でも、後から受給することになる可能性があります。そのため、退職後の転職先が決まっていない場合は、念の為に発行依頼して受け取っておくと安心です。
退職後、すぐに失業保険を申請したい場合は、スムーズに受給するためにも、退職前に発行依頼するのを忘れないようにしましょう。
会社がハローワークに離職証明書を提出する
退職者から離職票の発行を求められた会社は、雇用保険被保険者資格喪失届と一緒に雇用保険被保険者離職証明書をハローワークに提出します。
離職証明書の提出期限は、退職日翌日から10日以内です。そのため、会社が期限の間際に発行手続きをした場合は、退職者の手元に離職票が届くのは退職してから2週間後になることがあります。
ハローワークが離職票を発行し会社が受け取る
離職証明書を受け取ったハローワークは、離職票を発行して会社に送付します。
2025年1月から、一定の条件を満たすと電子申請が可能になりました。条件を満たした上で会社が電子申請した場合は、会社を通さず退職者のマイナポータルに直接離職票が送信される仕組みです。
退職者が特別に希望しない場合は、通常通りハローワークから会社に離職票が郵送されます。
会社から退職者に渡される
一般的には退職から1週間〜2週間程度で、会社が受け取った離職票は直接手渡し、または郵送で退職者に渡されます。手渡しの場合は、会社に受け取りに行かなければならないため、郵送や電子申請を依頼しておくと会社に行く手間が省けます。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
離職票が届かないときの対処法
失業保険の申請には離職票の提出が必須のため、届くまでは手続きを進められません。離職票が届かないときは、発行手続きが行われているかの確認や再発行の依頼、仮手続きなどの対処法が必要です。
ここでは、離職票がなかなか手元に届かないときにできる4つの対処法を解説します。
会社の担当者に確認する
まずは、会社の担当者に発行手続きが進んでいるか確認しましょう。担当者が手続きを忘れてしまっていたり、書類の不備で申請が滞っていたりすることがあるためです。
また、タイミング悪く担当者が変わったことで離職票発行の申し送りがされていないケースや、手続きに不慣れで申請できていないケースなども考えられます。
前述のとおり、会社がハローワークに必要書類を送付する期限は、退職日の翌日から10日以内です。期限ぎりぎりに提出していた場合は、離職票の発行が退職から2週間以上かかることもあるため、どこまで手続きが進んでいるか確認しておくと安心です。
再発行を依頼する
離職票が発行されたにもかかわらず会社が紛失したり、渡してくれなかったりする場合は、ハローワークに再発行を依頼できます。
会社を通じて、再発行を申請することも可能です。ハローワークで直接再発行を依頼する場合は、「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」の提出が必要になります。
ハローワークに相談する
そもそも会社が離職票の発行手続きをしてくれない場合は、速やかにハローワークに相談しましょう。
雇用保険法第76条3項には、「失業保険の支給を受けるために必要な書類の交付を請求された場合、事業主(会社)はその請求にかかる証明書を交付しなくてはいけない」と記載されています。
請求を無視すると会社は罰則を受ける可能性があるため、ハローワークに相談することで発行手続きをしてもらいやすくなります。
失業保険の仮手続きを進めておく
失業保険の手続きには離職票が必要なため、手元に届かないと受給開始が遅れてしまいます。しかし、実は離職票が手元になくても「仮手続き」は可能です。
仮手続きとは、離職票が届くまでの間に失業保険の申請を進めておける手続きです。最終的に離職票がないと支給は開始されませんが、仮手続きしておくことで離職票が届いたら速やかに受給できるようになります。
仮手続きは、退職日の翌日から数えて12日目以降にできるようになります。
失業保険の申請方法と受給までの流れ
失業保険の申請から給付金の支給までの流れは、以下のとおりです。
- 必要書類を準備する
- 申請手続きを行う
- 待期期間を過ごす
- 雇用保険受給者初回説明会に参加する
- 求職活動をする
- 失業認定を受ける
- 銀行口座に給付金が振り込まれる
- それぞれのステップを詳しくみていきましょう。
申請手順①必要書類を準備する
まずは、失業保険の申請に必要な書類を準備します。
離職理由によっては、前述の書類に加えて他の証明書類が必要になることもあります。例えば、会社の倒産で離職した場合は「業務停止命令の事実が分かる資料」、雇い止めによる離職では「動労契約書」「雇入通知書」「就業規則」などです。
申請手順②申請手続きを行う
次の手順では、必要書類を持って、住所地を管轄するハローワークの窓口で失業保険の申請手続きを行います。
ハローワークは原則として土日祝日は開庁していないため、開庁日時を確認して来所しましょう。申請手続きが遅れると、失業保険の受給開始も遅くなるため、申請書類が準備できたら速やかに手続きを進めることが重要です。
申請当日は、求職申込みをすることで受給資格が決定されます。受給資格が決まると、雇用保険受給者初回説明会の日時が案内され、「雇用保険受給資格者のしおり」をもらえます。しおりは今後も使用するため、無くさないように保管しておきましょう。
申請手順③待期期間を過ごす
離職理由に限らず、求職申込みした日から7日間の待期期間が設けられています。
待期期間は、求職申込みした人が失業状態にあるかをハローワークが確認する期間です。そのため、この期間中にアルバイトなどの労働をしてしまうと働いた日だけ待期期間が延長されるので注意しましょう。
申請手順④雇用保険受給者初回説明会に参加する
待期期間を過ごした後、受給資格決定のときに案内された「雇用保険受給資格者初回説明会」に参加します。
失業保険の受給に必要な説明があるため、受給にはこの説明会への参加は必須です。参加の際は、以下の持ち物を持参します。
- 雇用保険受給資格者のしおり
- 筆記用具
説明会に参加すると、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取れます。このとき、初回の失業認定日の日時も伝えられるため、忘れないようにメモしておきましょう。
申請手順⑤求職活動をする
失業認定日の前日までに、決められた回数以上の求職活動を行います。受給で求められる求職活動とは、具体的に以下のような活動です。
- 求人への応募
- ハローワークの職業相談・各種講習・セミナー受講
- 公的機関や国から許可を得た民間期機関の職業相談・各種講習・セミナー受講
- 再就職のための各種国家試験や検定などの受験
実績として申請するためには、証明書類が必要になる活動もあるため、事前に確認しておくと安心です。
申請手順⑥失業認定を受ける
決められた日時にハローワークに来所し、失業認定を受けます。
失業認定の手続きでは、雇用保険受給資格者証と求職活動実績を記入した「失業認定申告書」を提出します。期間中にアルバイトなどをした場合は、申告書に日付と賃金を記入して忘れずに申告しましょう。
申請手順⑦銀行口座に給付金が振り込まれる
失業認定を受け、支給が決定されると申請時に指定した銀行口座に給付金が振り込まれます。
求職活動実績が足りないなど不支給となった場合は、今回は支給されません。不支給となった分は持ち越されるため、次回以降に支給決定となれば先送りになった分を受給できます。
口座に振り込まれるのは、失業認定日から約1週間後です。失業保険の給付日数がなくなるか、再就職するまで求職活動と失業認定を繰り返します。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
失業保険の申請期限を延長する方法
失業保険の申請期限は、退職日翌日から1年間です。期限を過ぎると、支給日数が残っていても受給できなくなります。
ただし、病気や妊娠・出産などすぐに働ける状況にない場合は、受給期間を延長できます。
延長申請の条件
失業保険の受給期間を延長できる条件は、以下のとおりです。
すぐには働けない正当な理由がある
受給期間中に連続30日以上職業に就くことができない
延長可能な正当な理由とは、本人の病気やケガ、妊娠・出産・育児(3歳未満)、親族の看護などです。
延長できる期間
延長申請で延長できる受給期間は、退職翌日から最長4年間です。
例えば、2025年12月1日に退職し、病気ですぐに再就職できない場合は、最長2029年12月2月まで延長できます。病気から回復し、2026年6月から働ける状態になった場合は、本来2026年12月2日に受給期間が終わるところが、2027年6月になり約6か月間延長される仕組みです。
受給期間中に失業保険の申請をすると、受給開始となります。
延長申請の必要書類
失業保険の延長申請をする場合は、以下の書類をハローワークに提出する必要があります。
- 受給期間延長等申請書
- 雇用保険被保険者離職票-2
- 延長理由を証明する書類(医師の診断書など)
延長申請の手順
延長申請は、基本的に以下の手順で行います。
必要書類を準備する
退職日の翌日から30日間が過ぎた後、速やかに書類をハローワークに提出する
本人が来所できない場合は、郵送や代理人による提出も可能です。ただし、代理人に提出してもらうときは、委任状が必要になります。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
失業保険をスムーズに申請するポイント

失業保険を受給するためには、必要書類を揃えたり煩雑な手順で手続きしたりする必要があります。そのため、退職後できるだけ早く受給を開始できるよう、スムーズに申請することが重要です。
申請書類を事前に準備しておく
失業保険の受給は任意のため、自ら申請しないと受け取れません。申請するのが遅くなると、退職から受給開始までの期間が空いてしまいます。
退職後、できるだけ早く失業保険を受給したい場合は、退職後に受け取る必要書類以外は事前に準備しておくことが重要です。
待期期間中にアルバイトはしない
失業保険の申請後に設けられている待期期間中のアルバイトなどの労働は、期間が延長されて受給開始が遅くなる原因です。
離職理由が「正当な理由がない自己都合退職」の場合、待期期間後からさらに原則1か月の給付制限が設けられています。給付制限中も失業保険は支給されないため、待期期間が延びると全体のスケジュールがずれて受給開始まで時間がかかってしまいます。そのため、期間中はアルバイトしない方が無難です。
給付制限期間のアルバイトは禁止されていませんが、働く時間や賃金によって不支給や減額になることがある点に留意しましょう。
離職票が届かないときは仮手続きを進めておく
離職票は、退職後に会社が発行手続きをしないと発行されません。申請書類の不備などで手続きが遅れていたり、そもそも会社が手続きしてくれなかったりすると受給が遅れてしまいます。
離職票が手元に届くのが遅れている場合は、仮手続きをしておくと、書類が準備次第すぐに受給開始の手続きができます。
まとめ
失業保険は、退職後の生活を安定させる上で重要な給付金ですが、申請には定められた期間内に、多くの書類準備と煩雑な手続きを正確に行う必要があります。離職票の発行遅延への対処や、待期期間中の過ごし方など注意すべき点も多く、すべてを自分一人で進めることに負担を感じる方も少なくありません。
「複雑な失業保険の手続きをスムーズに進めたい」「書類の不備なく確実に受給を開始したい」という方は、「社会保険給付金サポート」の利用を検討してみましょう。失業保険の申請に必要な書類の準備や手続きを専任スタッフが丁寧にサポートします。公式LINEでも無料相談を受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
この記事の監修者

杉山 雅浩
東京弁護士会所属。
池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。
NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、
詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。
YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!
おすすめの関連記事
ピックアップ
- CATEGORY
- 給付金について
- 転職・再就職について
- 就労について
- 社会保険について
- 精神疾患について
- サービスについて
- 傷病手当金について
- 失業保険について
- 退職について
- 障害年金について
- ピックアップ
- 人気記事
-
退職代行サービスの利用方法、実際の流れと体験談を紹介
-
今の会社に3年後もいる自信はありますか?
-
退職代行を利用した時の有給消化の仕組みとその対応方法
-
退職代行サービスを使うメリット・デメリットは?
-
ブラック企業を判定する方法と実際のチェックポイント
-
障害年金を知ろう
-
会社を“円満に退職する”方法は?
-
退職時の引き継ぎは義務?スムーズな業務引き継ぎの必須ポイント
-
パワハラ、モラハラ、セクハラとは?
-
辞めさせてくれない!そんな時こそ「退職代行サービス」
テーマ
- 転職サイト
- 不支給
- 引っ越し
- 雇用契約
- 退職代行
- 職務経歴書
- 等級
- 社宅
- 内定
- 退職代行サービス
- 人間関係
- 離職票
- 障害者手帳
- 就労移行支援
- ブラック企業
- スタートアップ
- 労務不能
- 精神保険福祉手帳
- 業務委託
- ハラスメント
- 転職
- 傷病手当金
- 労災
- 社会保険
- 引き継ぎ
- 違法派遣
- 障害者控除
- 産休
- 福利厚生
- 給与
- 派遣契約
- 退職届
- 解雇
- 就職困難者
- 残業代
- 障害厚生年金
- 面接
- 中小企業
- 再就職手当
- 退職金
- 失業保険
- 障害手当金
- ベンチャー企業
- 社会保険給付金
- 会社都合退職
- 資格取得
- 新型コロナウイルス
- 退職勧奨
- 職業訓練受講給付金
- 自己都合退職
- うつ病
- 有給消化
- 自己PR
- 退職給付金
- クレジットカード
- 統合失調症
- 休職
- 確定申告
- ハローワーク
- アルバイト
- 契約社員
- 免除申請
- 保険料
- 傷病手当
- 雇用保険
- 弁護士
- 適応障害
- 社会保障
- 退職コンシェルジュ
- 健康保険
- 公的貸付制度
- 住宅確保給付
- 就職
- インフルエンザ
- 年金
- 生活福祉資金貸付制度
- 職業訓練
- 労働基準法
- ストレス
新着記事
-
2026.01.06
退職して国民健康保険に切り替えたあとも傷病手当金はもらえる?注意点も解説
-
2025.12.27
インフルエンザで仕事を休むと「傷病手当金」はもらえる?条件・日数・申請方法まで解説
-
2025.12.26
傷病手当金と副業の関係をわかりやすく解説
-
2025.12.17
傷病手当金の不正と調査|どこからがNG?就労・外出・求職活動の正しい判断基準を解説
-
2025.12.16
【徹底比較】退職給付金サポート おすすめランキング
-
2025.12.09
傷病手当金をもらいながら働く方法はある?アルバイトならOK?収入を得る方法や注意点を解説
-
2025.12.09
社会保険給付金と失業保険の違いは?受給要件やメリット・デメリット解説
-
2025.12.08
産休・育休後そのまま退職はマナー違反?退職時のポイントと注意点
-
2025.12.07
会社を辞めさせられた場合は失業保険は受け取れる?条件や注意点を解説
-
2025.12.04
傷病手当金は退職後もらえない?受給できる条件と不支給になる理由を徹底解説





 サービス詳細
サービス詳細