2025.10.09
失業保険について
テーマ:
失業手当の手続きで提出する必要書類は?離職票再発行や延長申請の流れも解説

失業手当を受け取るには、ハローワークで必要書類を揃えて提出し、所定の手続きを行う必要があります。
しかし、いざ申請しようとしたときに「何を準備すればいいのかわからない」「書類が足りずに申請できなかった」というケースは珍しくありません。特に退職直後は他の手続きや再就職に向けた情報収集で慌ただしい時期でもあるため、失業手当の申請に時間を避けない方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、失業手当の申請に必要な書類をわかりやすく整理し、さらにスムーズに手続きを進めるためのポイントも解説します。これから失業手当の申請を控えている方や、退職後の流れを確認したい方にとって役立つ内容になっていますので、ぜひ参考にしてみてください。
失業手当の手続きで提出する必要書類
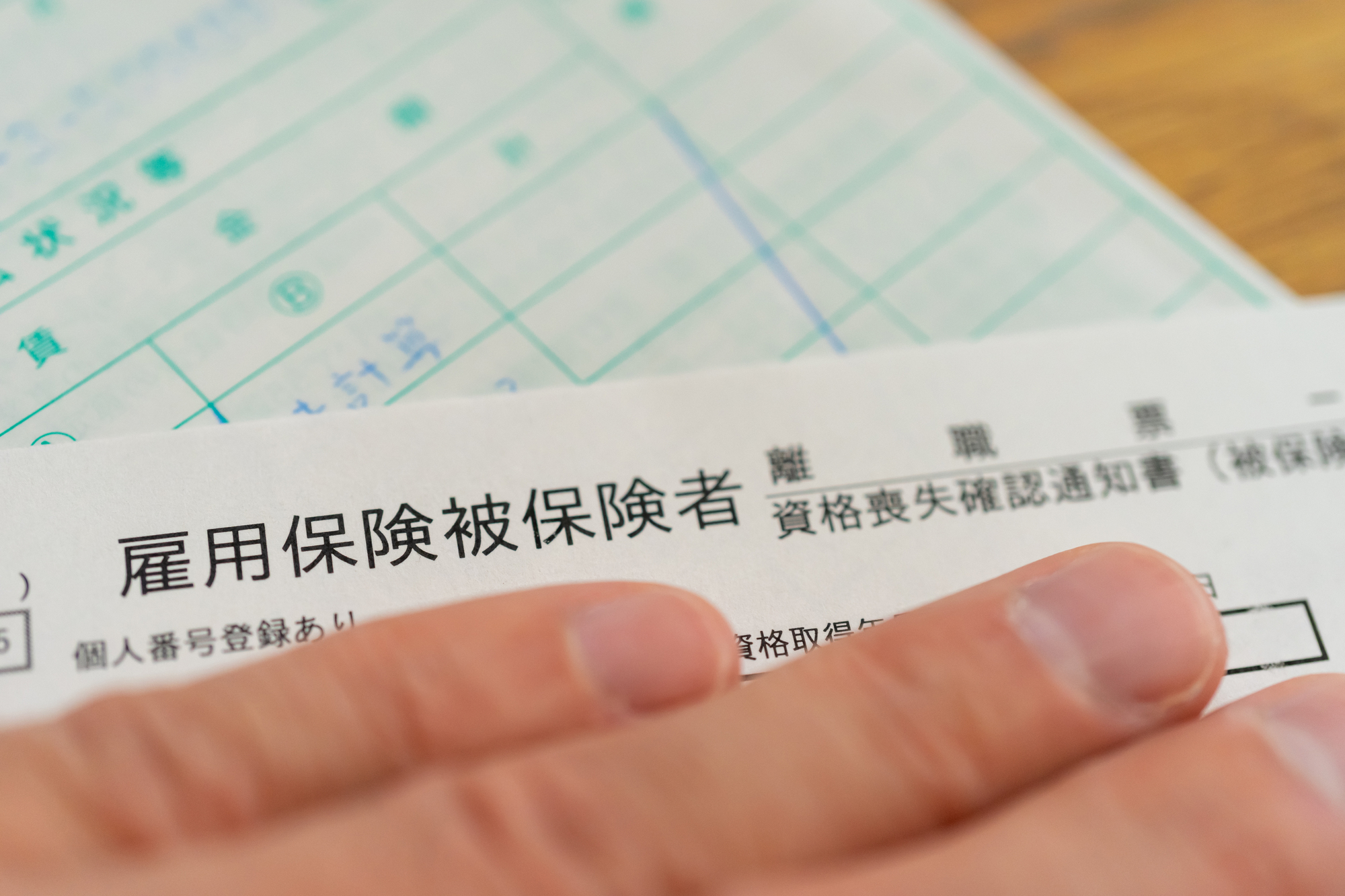
失業手当の手続きで提出を求められる必要書類は、以下の6種類です。
- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険被保険者離職票
- 個人番号確認書類
- 本人確認書類
- 本人名義の預金通帳やキャッシュカード
- 顔写真2枚
間違った書類を持っていくと手続きできないケースもあるため、それぞれ入手方法や条件などを確認しましょう。ここでは、各書類の詳細や注意点を解説します。
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証とは、雇用保険に加入していることを証明する書類です。主に雇用保険の加入番号や被保険者氏名、被保険者の生年月日が記載されています。
「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」とセットになっており、通知書には資格取得年月日や事業所名などの情報が書かれています。
雇用保険被保険者証は、会社が雇用保険加入の手続きをして被保険者本人に渡される書類です。基本的には加入者本人が保管するものですが、会社が保管しているケースも多々あるため、手元にない場合は退職時に会社から受け取る必要があります。
雇用保険被保険者離職票
離職票とは、離職したことを証明する公的文書で、「雇用保険被保険者離職票ー1」と「雇用保険被保険者離職票ー2」の2種類があります。失業手当の受給申請には両方とも必要です。
退職後に発行される書類のため、退職日から1週間〜2週間程度で会社から郵送または手渡しで受け取れます。書類には、離職した日や離職理由、離職日までの賃金支払い状況などが記載されています。
離職票に似ている書類として挙げられるのは、以下の書類です。失業手当の受給に必要な離職票と間違えないように注意しましょう。
- 源泉徴収票:当年1月から退職までの収入や所得税額が記載された書類
- 退職証明書:退職した事実や退職日、雇用期間などを証明するために会社が発行する書類
- 健康保険資格喪失証明書:退職により健康保険の被保険者資格を喪失したことを証明する書類
個人番号確認書類
個人番号確認書類とは、個人番号(マイナンバー)がわかる書類のことです。マイナンバーカードや通知カードが該当します。
マイナンバーカードや通知カードが手元にない場合は、個人番号が記載された住民票の写し(住民票記載事項証明書)でも問題ありません。ただし、通常の住民票の写しには個人番号の記載がないので、「個人番号あり」で請求する必要があります。
住民票の写しの請求は住所地の市区町村役場のほか、郵送でも可能です。請求の際は、本人確認できる身分証明書と手数料が必要になります。
本人確認書類
失業手当の手続きで必要な本人確認書類は、次のとおりです。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 顔写真付きの官公署が発行した身分証明書・資格証明書
上記の本人確認書類はいずれか1点のみの提出ですが、健康保険証や児童扶養手当証書、年金手帳など顔写真がないものは2点必要です。コピーしたものは本人確認書類と認められないため、原本を持参しましょう。
本人名義の預金通帳やキャッシュカード
失業手当の受け取り方法は銀行口座への振込みのため、退職した本人名義の預金通帳やキャッシュカードが必要です。家族名義の口座は指定できないため、本人名義の口座を準備しましょう。また、ネット銀行や外資系金融機関など、一部の金融機関は振込先に指定できないことがあります。
一度振込先を指定した場合でも、手続き後に振込先を変更することも可能です。変更したいときは、ハローワークで「払渡希望金融機関変更届」を提出します。
顔写真2枚
失業手当の手続きには、原則として本人の顔写真を持参する必要があります。ただし、失業認定などの手続きごとに、毎回マイナンバーカードを提示する場合であれば顔写真は不要です。
提出する顔写真のサイズは、縦3.0cm、横2.4cmです。履歴書やパスポート用の証明写真より、若干サイズが小さいので注意しましょう。
写真を撮った時期について具体的な決まりはなく、最近撮ったものであれば問題ありません。一般的な証明写真と同様に、正面上半身の写真を準備しましょう。
会社から離職票をもらえないときの対処法
失業手当の申請には、原則として離職票の提出が必須です。離職票は退職後、1週間から2週間程度で会社から郵送されるのが一般的ですが、会社やハローワークの手続きが滞っていたり、意図的に離職票を渡してもらえなかったりすると手元に届かないことがあります。
ここでは、会社から離職票をもらえないときの対処法を4つ紹介します。
会社に問い合わせる
離職票は、退職日の翌日から10日以内に会社がハローワークに離職証明書を提出すると発行される書類です。基本的には、会社を通して退職者の手元に届きます。退職者が依頼し、会社が手続きを進めないと発行されないため、事前に手続きを依頼しておく必要があります。
万が一、依頼したのに届かない場合は手続きの遅延や、離職票の送り忘れなども考えられるため、まずは会社に問い合わせてみましょう。
離職票は退職者の住所地に郵送されるのが一般的ですが、会社に取りに行くケースもあります。どのように受け取るのか、退職前に会社に確認しておきましょう。
また、退職後に引っ越しで住所が変わっている場合、離職票の発送先が旧住所宛になっていて届かない可能性もあるので住所の確認も必要です。
ハローワークに相談する
会社側が離職証明書を提出したのに、ハローワークからの発行が遅れている場合や、会社が離職票の発行手続きをしてくれない場合は、直接ハローワークに問い合わせましょう。問い合わせ先は、住んでいる地域のハローワークでも問題ありませんが、会社の住所地を管轄するハローワークにすると話がスムーズです。
退職者が離職票の発行を希望する場合、会社は手続きする義務があります。ハローワークに問い合わせることで、会社が手続きしてくれない場合に書類の提出を促してくれることが期待できます。
また、離職票が届かない場合の対応を教えてくれるので、離職票が届かず会社に頼れないときの相談先として利用しましょう。
失業手当の仮手続きを進める
失業手当は離職票がないと受給できませんが、離職票が届かないときは仮手続きも可能です。
仮手続きとは、離職票が手元にない状態で失業手当の申請手続きを進める方法です。退職日の翌日から12日目以降に手続きを開始できます。離職票以外の必要書類と「退職証明書」など退職を証明する書類を持って、ハローワークの窓口に行きましょう。
仮手続きしておくと、離職票の到着を待つ間に失業手当の受給に向けて手続きを進められますが、最終的に離職票を提出しないと給付金は振り込まれません。離職票が届き次第、提出して手続きする必要があります。
ハローワークで再発行してもらう
離職票は1度発行されていれば、退職者本人が直接ハローワークで再発行申請を行えます。もちろん、会社を通じて再発行を依頼することも可能です。
また、汚れや破損で離職票が使えなくなってしまった場合でも再発行できます。汚れや破損の場合は、再発行手続きで手元の離職票を提出する必要があるため、大切に保管しておきましょう。
離職票を再発行するときの必要書類
離職票を再発行する方法には、窓口申請・電子申請・郵送申請の3パターンがあります。例えば、窓口申請の必要書類は以下のとおりです。
- 雇用保険被保険者離職票再交付申請書
- 写真付きの本人確認書類
上記以外に、雇用保険被保険者証があれば持っていくと手続きがスムーズに進みます。
また、郵送の場合は切手を貼った返信用封筒を同封する必要があります。
雇用保険被保険者証を紛失・破損したときの対処法
離職票と同様に、失業手当の手続きには雇用保険被保険者証も必須です。会社が保管している場合は退職時に返還してもらえますが、自分で管理していて紛失したときは、ハローワークの窓口申請・郵送申請・電子申請で再発行の手続きを行いましょう。
ここでは、被保険者証を紛失・破損したときの手続きの必要書類や再交付までにかかる時間を解説します。
再交付手続きの必要書類
失業手当の再交付手続きを進める場合は、以下の必要書類を準備します。手続き方法ごとに書類が異なるため、どのように申請するかを決めてから準備を始めるとよいでしょう。
手続きの必要書類を申請方法ごとに次の表にまとめました。
|
必要書類 |
窓口申請 |
郵送申請 |
電子申請 |
|
雇用保険被保険者証再交付申請書 |
◯ (当日窓口で入手可) |
◯ |
◯ |
|
本人確認書類 |
◯ |
◯ (コピーしたもの) |
◯ (電子証明書で本人確認できる場合は不要) |
|
返信用封筒 |
× |
◯ |
× |
被保険者証の再発行に必要な本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証、官公庁が発行した写真付き身分証明書は1点、住民票や個人番号通知カード、健康保険証などは2点必要です。
再交付にかかる時間
雇用保険被保険者証の再交付にかかる時間は、申請方法によって異なります。
例えば窓口申請の場合、原則として当日受け取れます。ハローワークの閉庁時間まで余裕があれば、再交付後そのまま失業手当の手続きを進めることも可能です。失業手当の必要書類も併せて持っていくと、再び来所する手間が省けます。
一方、郵送申請の場合は1週間程度かかるため、失業手当の受給手続きを急ぐときは窓口申請がおすすめです。
失業手当とは
失業手当とは、雇用保険に加入していた人が退職し、一定の条件を満たすと申請できる給付金で、正式には「基本手当」と呼ばれます。倒産や解雇など会社都合による離職のほか、転職など自己都合で退職した場合も、雇用保険に加入していて条件を満たせば受け取れる給付金です。
ここでは、失業保険の受給条件や受け取れる期間について解説します。
失業手当の受給条件
受給には、雇用保険に一定以上の期間加入していたことが条件の一つです。受給可能な雇用保険の被保険者期間は、退職理由によって異なります。
一般離職者の場合、離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることが原則の条件です。
一方、特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合では、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算6か月以上あることが求められます。特定受給資格者は会社都合で、特定理由離職者はやむを得ない事情があり退職した人が該当します。
雇用保険の被保険者期間以外には、以下の条件をすべて満たす人が受給対象者です。
- ハローワークに来所して求職申込みを行う
- 就職しようとする積極的な意思がある
- いつでも就職できる能力がある
- 失業の状態にある
失業手当の受給期間
失業手当は受け取れる期間が決まっており、原則として離職日の翌日から1年間です。例外として、失業手当が支給される日数が330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日に設定されています。
受給期間を過ぎると失業手当の手続きができなくなり、受給条件を満たしていても受け取れません。
また、受給期間内に支給額をすべて受け取れない場合でも、支給停止となります。つまり、受給開始が遅れると満額受け取れなくなることがあるため、対処口語はできるだけ早く手続きすることが重要です。
万が一、受給期間中に受給開始できない特別な理由がある人は、受給期間の延長もできます。
【退職理由別】追加で必要になる提出書類
失業手当の受給に必要な書類は前述のとおりですが、退職理由によっては別途書類の提出を求められることがあります。
ここでは、退職理由から特定受給資格者と特定理由離職者に分けて、提出書類を紹介します。
特定受給資格者に該当する場合
特定受給資格者とは、倒産や解雇など会社都合により離職した人のことです。特定受給資格者として失業手当を受給するためには、基本の必要書類のほかに離職理由に応じた添付書類が必要です。
主な離職理由と添付書類を以下の表にまとめました。
|
離職理由 |
添付書類 |
|
倒産 |
業務停止命令の事実がわかる資料など |
|
事業所の廃止 |
解散の議決が行われた議事録の写しなど |
|
事務所の移転 |
事業所移転の通知、移転先がわかる資料、通勤経路の時刻表など |
|
解雇 |
解雇予告通知書、退職証明書、就業規則など |
|
労働条件と事実の著しい相違 |
労働条件がわかる労働契約書、労働協約や就業規則の変更内容がわかる書類など |
|
賃金の未払い・低下 |
労働契約書、就業規則、賃金規定、給与明細書、賃金低下に関する通知書など |
参考:厚生労働省|特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
特定理由離職者に該当する場合
特定理由離職者とは、主に以下の理由で離職した人のことです。
- 期間の定めがある労働契約の期間満了時に、契約の更新がなかった
- 正当な理由により自己都合退職した
特定理由離職者に該当する場合も、基本の必要書類に追加して理由を証明する書類が必要です。主な離職理由と必要書類を以下の表にまとめました。
|
離職理由 |
添付書類 |
|
有期雇用の契約期間が終了後、契約が更新されなかった |
労働契約書、雇入通知書、就業規則など |
|
本人の健康状態 |
医師の診断書など |
|
妊娠・出産・育児 (受給期間延長措置を受けた場合) |
受給期間延長通知書など |
|
家族の事情の急変(死亡・病気など) |
扶養控除等申告書、健康保険証、医師の診断書など |
|
家族との別居生活が困難になった |
転勤辞令、住民票の写し、扶養控除等申告書、健康保険証 |
|
通勤不可能・困難 |
通勤経路の時刻表、住民票の写し、事業所移転の通知、交通機関の運行時間変更に関する書類など |
参考:厚生労働省|特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
失業手当を受給する流れ
失業手当を受給するには、所定の手続きを行う必要があります。基本的な流れは、以下のとおりです。
- 必要書類をハローワークの窓口に提出する
- 雇用保険初回説明会に参加する
- 求職活動を行う
- 失業認定日にハローワークに行く
ここでは、上記の手順を詳しくみていきます。
ステップ1:必要書類をハローワークの窓口で提出する
まずは、必要書類を準備し、住所地を管轄するハローワークの窓口に行って「求職の申込み」を行います。離職理由によっては追加の書類を提出することになるため、事前に問い合わせておくとスムーズに手続きできるでしょう。
提出した書類に不備がなければ受給資格が決定し、7日間の待期期間を過ごすことになります。待期期間中に就労すると、期間が延長されて受給開始が遅れるため注意が必要です。
ステップ2:雇用保険初回説明会に参加する
受給資格が決定すると渡される「受給資格者のしおり」と筆記用具を持って、指定された日時の雇用保険初回説明会を受けます。
失業手当の受給には、説明会への参加が必須です。雇用保険の制度や失業手当の受給手続きに関して説明されるので、聞き漏らすことのないようにしましょう。
また、説明会で「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡され、初回の失業認定日の日時が通知されます。どちらも失業手当の受給に必要な書類のため、なくさないように大切に保管しましょう。
ステップ3:求職活動する
失業手当を受け取るには、「積極的に就職する意思がある」「失業状態にある」ことが条件です。条件を満たすことを証明するため、失業認定日までに一定回数以上の求職活動実績を提示する必要があります。
具体的には、初回の失業認定日の前日までに「原則2回以上の求職活動」が必要な実績です。雇用保険初回説明会も1回の求職活動に加算されるため、最低でも残り1回の実績を作りましょう。
自己都合で退職した一般の離職者など、7日間の待期期間後に給付制限が設けられている人もいますが、給付制限がない人と同様に求職活動を開始できます。求職活動の実績は、説明会でもらった「失業認定申告書」に記入します。
ステップ4:失業認定日にハローワークへ行く
雇用保険初回説明会で知らされた失業認定日の日時に、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を持参してハローワークへ行き、失業認定を受けます。
失業認定申告書に記入した求職活動の種類によっては、以下の必要書類も一緒に提出します。
- 講習・セミナーの受講証明書
- 各種国家試験、検定などの受験票
すぐに失業手当を受け取れない場合は延長申請が可能
退職後、すぐに失業手当を受け取れない状況にある場合、受給期間の延長申請が可能なケースもあります。
延長申請しておくと、後から受給可能になったときに手続きを再開できることがメリットです。失業手当の受給条件に当てはまらない人は、延長申請が可能か確認することが重要です。
受給期間を延長できる人の条件
失業手当の受給期間を延長できるのは、主に以下の理由で30日以上引き続き働けなくなった人です。
- 病気やケガ
- 妊娠・出産・育児(3歳未満の子に限る)
- 親族(6親等以内の血族・配偶者・3親等以内の姻族)の介護・看護
- 配偶者の海外勤務への同行
- 公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
延長申請の期限・延長される期間
受給期間の延長申請は、働けない状態が30日続いた日の翌日から延長後の受給期間の最後の日まで可能です。
上記の期間中に手続きした場合でも、申請が遅れると失業手当を満額受給できないケースもあるので、速やかに申請するのが原則と覚えておきましょう。
受給期間の延長申請により延長される期間は、最大で離職日の翌日から4年です。働けるようになった日の翌日以降、できるだけ速やかに失業手当の受給申請を行いましょう。
失業手当の受給期間を延長する際の必要書類
すぐに働ける状態になく、失業手当の受給期間を延長するときは、通常の手続きで必要な書類のほかに、働けない状態を証明する書類の提出が必要です。
例えば、本人や家族の病気やケガは医師の診断書、妊娠・出産・育児は母子手帳など、延長理由を説明できる書類が求められます。ハローワークの窓口だけでなく、郵送でも延長申請が可能です。
失業手当の手続き開始前に延長申請する場合
失業手当の手続き前に受給期間の延長申請を行う場合は、以下の書類を準備します。
- 雇用保険被保険者離職票-2
- 受給期間延長申請書
- 延長の理由を証明する書類
延長申請時に離職票-1は不要ですが、延長が必要なくなり失業手当を受け取るときに必要なので大切に保管しましょう。
また、延長申請後に失業手当の手続きを開始するときは、通常の手続きで求められる必要書類のほかに以下の書類が必要です。
- 受給期間延長通知書
- 延長理由が解消されたことを確認できる書類
失業手当の受給中に延長申請する場合
すでに失業手当を受給している途中で延長申請するときは、以下の書類が必要です。
- 雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知
- 受給期間延長申請書
- 延長の理由を証明する書類
延長後に失業手当の受給を再開するときは、以下の必要書類を提出します。
- 雇用保険受給資格者証
- 受給期間延長通知書
- 延長理由が解消されたことを確認できる書類
失業手当の受給中に再就職したときにもらえる給付金

失業手当の受給中、あるいは受給手続き中に再就職したときは、「再就職手当」を受け取れる可能性があります。再就職手当とは、失業者の再就職を促進するために支給される給付金で、一定の条件を満たすと受け取れます。
再就職手当の受給条件
再就職手当を受け取るためには、失業手当の支給日数の3分の1以上残して再就職する必要があります。さらに、次の条件をすべて満たすことで、ハローワークで申請が可能です。
- 再就職先で1年を超えての勤務が決まっている
- 待期期間後の就職、かつ給付制限があるとき期間中はハローワークなど許可・届出のある職業紹介事業者により紹介されて就職している
- 退職前の会社やその関連企業への再就職ではない
- 離職日前3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を支給されていない
- 失業手当の申し込み前から採用が決定していた会社への就職でない
- 原則、再就職先で雇用保険に加入できる雇用である
再就職手当の必要書類
再就職手当の申請の必要書類について、以下の表にまとめました。
|
必要書類 |
入手先 |
|
再就職手当支給申請書 |
ハローワークの窓口、厚生労働省のホームページからダウンロード |
|
雇用保険受給資格者証 |
ハローワークが開催する雇用保険初回説明会への参加時に受取 |
|
失業認定申告書 |
ハローワークが開催する雇用保険受給説明会への参加時、または失業認定日に受取 |
|
採用証明書 |
ハローワークで受取 |
上記の書類以外に、勤務実績の証明書類や前職の会社と関連がないことを証明する書類などを求められることもあります。
再就職手当の手続き手順
再就職手当の申請は、主に以下の手順で行います。
- 再就職先に採用証明書を書いてもらう
- ハローワークに「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」「採用証明書」を提出し、「再就職手当支給申請書」をもらう
- 再就職先に「再就職手当支給申請書」の事業主欄を記入してもらう
- 本人欄を埋め、ハローワークに提出する
- 再就職手当支給決定通知が届き、指定した口座に再就職手当が振り込まれる
まとめ
失業手当の申請には、雇用保険被保険者証や離職票、本人確認書類、顔写真、印鑑など多くの必要書類が求められます。
しかし、どれか一つでも不足していると、ハローワークでの手続きが進まず、失業手当の給付開始が遅れてしまうことも少なくありません。特に初めて失業手当をもらう場合は、「どの書類をどのタイミングで提出すればいいのか」「手続きに不備がないか」と不安を感じる方も多いでしょう。
そんなときに頼れるのが、「社会保険給付金サポート」です。専門スタッフが必要書類の準備から申請までを丁寧にサポートしてくれるため、スムーズに失業手当の受給へとつなげられます。一人で悩まず、専門家のサポートを活用して安心して次のキャリアへ進む準備を整えましょう。
この記事の監修者

杉山 雅浩
東京弁護士会所属。
池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。
NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、
詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。
YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!
おすすめの関連記事
ピックアップ
- CATEGORY
- 給付金について
- 転職・再就職について
- 就労について
- 社会保険について
- 精神疾患について
- サービスについて
- 傷病手当金について
- 失業保険について
- 退職について
- 障害年金について
- ピックアップ
- 人気記事
-
退職代行サービスの利用方法、実際の流れと体験談を紹介
-
今の会社に3年後もいる自信はありますか?
-
退職代行を利用した時の有給消化の仕組みとその対応方法
-
退職代行サービスを使うメリット・デメリットは?
-
ブラック企業を判定する方法と実際のチェックポイント
-
障害年金を知ろう
-
会社を“円満に退職する”方法は?
-
退職時の引き継ぎは義務?スムーズな業務引き継ぎの必須ポイント
-
パワハラ、モラハラ、セクハラとは?
-
辞めさせてくれない!そんな時こそ「退職代行サービス」
テーマ
- 転職サイト
- 不支給
- 引っ越し
- 雇用契約
- 退職代行
- 職務経歴書
- 等級
- 社宅
- 内定
- 退職代行サービス
- 人間関係
- 離職票
- 障害者手帳
- 就労移行支援
- ブラック企業
- スタートアップ
- 労務不能
- 精神保険福祉手帳
- 業務委託
- ハラスメント
- 転職
- 傷病手当金
- 労災
- 社会保険
- 引き継ぎ
- 違法派遣
- 障害者控除
- 産休
- 福利厚生
- 給与
- 派遣契約
- 退職届
- 解雇
- 就職困難者
- 残業代
- 障害厚生年金
- 面接
- 中小企業
- 再就職手当
- 退職金
- 失業保険
- 障害手当金
- ベンチャー企業
- 社会保険給付金
- 会社都合退職
- 資格取得
- 新型コロナウイルス
- 退職勧奨
- 職業訓練受講給付金
- 自己都合退職
- うつ病
- 有給消化
- 自己PR
- 退職給付金
- クレジットカード
- 統合失調症
- 休職
- 確定申告
- ハローワーク
- アルバイト
- 契約社員
- 免除申請
- 保険料
- 傷病手当
- 雇用保険
- 弁護士
- 適応障害
- 社会保障
- 退職コンシェルジュ
- 健康保険
- 公的貸付制度
- 住宅確保給付
- 就職
- インフルエンザ
- 年金
- 生活福祉資金貸付制度
- 職業訓練
- 労働基準法
- ストレス
新着記事
-
2026.01.06
退職して国民健康保険に切り替えたあとも傷病手当金はもらえる?注意点も解説
-
2025.12.27
インフルエンザで仕事を休むと「傷病手当金」はもらえる?条件・日数・申請方法まで解説
-
2025.12.26
傷病手当金と副業の関係をわかりやすく解説
-
2025.12.17
傷病手当金の不正と調査|どこからがNG?就労・外出・求職活動の正しい判断基準を解説
-
2025.12.16
【徹底比較】退職給付金サポート おすすめランキング
-
2025.12.09
傷病手当金をもらいながら働く方法はある?アルバイトならOK?収入を得る方法や注意点を解説
-
2025.12.09
社会保険給付金と失業保険の違いは?受給要件やメリット・デメリット解説
-
2025.12.08
産休・育休後そのまま退職はマナー違反?退職時のポイントと注意点
-
2025.12.07
会社を辞めさせられた場合は失業保険は受け取れる?条件や注意点を解説
-
2025.12.04
傷病手当金は退職後もらえない?受給できる条件と不支給になる理由を徹底解説





 サービス詳細
サービス詳細














