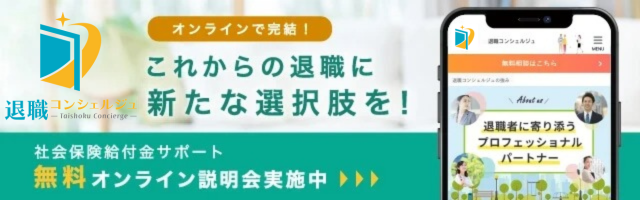特定理由離職者になるにはどうすればいい?

特定理由離職者は、なりたいからといって誰でも認定されるものではありません。認められるのは、以下の離職理由に当てはまる人です。
労働契約の期間満了後、契約更新されずに離職した者
正当な理由があり離職した者
認定はハローワークが行うため、退職理由を証明できる書類の提出を求められることがあります。
特定理由離職者とは
特定理由離職者とは、失業保険の給付にかかる離職理由の分類の一つです。働く意思はあるものの、主に雇止めなどやむを得ない理由で離職した人が分類されます。
失業保険は、求職活動に集中できるよう生活を安定させることを目的に給付金が支給される制度です。
やむを得ない理由による退職と認められると、失業保険の受給条件が緩和されたり、給付日数が増えたりといった優遇措置を受けられます。一定の条件を満たす場合は、単なる自己都合の退職ではなく、特定理由離職者として失業保険をもらうほうが生活を安定させやすくなります。
給付日数の延長については下記の記事も併せてご確認ください。
参考:社会保険給付金を最大28か月もらう方法とは?失業保険とは違う?条件や流れ、申請サポートも紹介
離職理由による所定給付日数の違い
同じ特定理由離職者でも、退職した理由によって所定給付日数が異なります。所定給付日数とは、失業保険が支給される最大日数のことです。退職の理由や年齢、雇用保険の被保険者期間によって日数が決められています。
労働契約の満了後、契約の更新がなく離職した人の所定給付日数を表にまとめました。
| 雇用保険の被保険者期間 | |||||
| 離職時の年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
| 30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
| 35歳以上45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | ||
| 45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
| 60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
参考:ハローワークインターネットサービス|基本手当の所定給付日数
一方、正当な理由があり離職した人の所定給付日数は年齢による違いはありません。
| 雇用保険の被保険者期間 | 所定給付日数 |
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
参考:ハローワークインターネットサービス|基本手当の所定給付日数
特定受給資格者・一般離職者との違い
離職理由の区分には、特定理由離職者のほかに「特定受給資格者」と「一般の離職者」があります。
特定受給資格者とは、倒産や解雇など会社都合によって離職を余儀なくされた人のことです。在職中に再就職の準備をする時間もなく、急に職を失ったようなケースが該当します。
具体的には、以下のような人が挙げられます。
- 倒産:事業所の倒産・廃止・移転により離職した人、大量雇用変動の届出により離職した人など
- 解雇:自分に非のない会社都合の解雇で離職した人、賃金の未払いや予見できない減額により離職した人など
一方、一般の離職者とは、転職や独立など個人的な事情があり本人の意思で退職した人を指します。特定理由離職者とは異なり、「やむを得ない事情」が認められないケースです。
特定理由離職者になる判断基準①雇止めによる離職
労働契約期間の満了後、本人が希望したのに契約が更新されずにそのまま離職した人など、いわゆる「雇止め」が判断基準の一つです。具体的には、次の条件を満たす場合に認定されます。
期間の定めのある労働契約が満了した
満了する労働契約の更新・延長が明示されているが、確約はされていない
契約期間満了日までに労働者が契約の更新・延長を申し出た
労働契約の更新・延長がされずに離職した
「更新・延長が確約されていない」とは、「更新する場合がある」など断定を避けた表現が使われている場合を指します。一方で、「更新なし」と書かれているときは、そもそも「更新・延長が明示されている」と言えないため、雇止めと判断されません。
特定理由離職者になる判断基準②正当な理由による離職
雇止め以外に、正当な理由があって退職したケースも判断基準です。「正当」と認められる理由は、以下の6つが挙げられます。
- 健康上の理由
- 妊娠・出産・育児
- 父母や親族の扶養・介護
- 配偶者や扶養親族と別居が困難
- 通勤不可能または困難
- 人員整理による希望退職
上記の理由を詳しく解説します。
労働者本人の健康上の理由による離職
以下のように、労働者本人の健康上の理由で離職せざるを得なかった場合は、特定理由離職者と認定されることがあります。
- 体力の低下
- 心身の障害
- 疾病
- 負傷
- 視力の低下
- 聴力の低下
- 触覚の低下
特定理由離職者の範囲に当たるのは、上記の理由で退職した人のうち次の条件を満たす場合です。
- 業務を続けることが不可能または困難になった場合
- 新たに割り当てられた業務の遂行が不可能または困難な場合
ただし、業務だけでなく、勤務場所への通勤が不可能または困難になった場合も含まれます。
妊娠・出産・育児による離職
妊娠・出産・育児で離職し、以下の条件を満たす場合は特定理由離職者になります。
- 雇用保険法第20条第1項の受給期間の延長事由に該当する
- 離職日の翌日から引き続き30日以上職業に就けず、受給期間の延長措置が決定された
雇用保険法第20条では、失業保険の支給期間や日数について定めています。その中でも第1項には、妊娠・出産・育児などの理由ですぐに働ける状況にない人を対象とした受給期間の延長について記載されています。
家族の事情の急変による離職
父母の死亡・疾病・負傷などによる扶養や、常に介護が必要な親族の疾病・負傷などが「家族の事情による離職」です。
家族の事情の急変と認めてもらうためには、事実の証明が求められます。例えば、「常に介護が必要な親族の疾病・負傷を理由に離職した」と証明するためには、会社に退職を申し出たときに、看護期間が30日を超えると見込まれていた事実の提示が必要です。
家族の看護や介護以外にも、自宅の火事や水害によって勤務の継続が不可能または困難になったときも、「家族の事情の急変による離職」の範囲に含まれます。
配偶者や扶養親族との別居が困難になったときの離職
就業のために配偶者や扶養親族と別居中、家庭生活や経済的な事情などで同居することになり、会社への通勤ができなくなったことで離職した人が該当します。
具体的には、本人が単身赴任中に家族の介護が必要になり、同居するために引越して通勤できなくなったケースなどが挙げられます。
通勤困難になったときの離職
通勤困難と判断される基準は、通勤にかかる時間がおおむね往復4時間以上のときです。具体的には、以下のようなやむを得ない事情が挙げられます。
- 結婚に伴う引越し
- 子どもの保育所等施設の利用や親族への保育の依頼
- 事業所の移転
- 自己の意思に反した自宅の引越し
- 鉄道・バスなど運輸機関の廃止や運行時間の変更
- 異動辞令による転勤・出向に伴う別居の回避
- 配偶者の事業主の異動辞令による転勤・出向
- 配偶者の再就職による別居の回避
「自己の意思に反した自宅の引越し」とは、自宅の強制立退きや天災による移転などが挙げられます。
労働者本人の会社に起因するものだけでなく、配偶者の転勤・出向も特定理由離職者に含まれる範囲です。
人員整理のための希望退職による離職
企業整備による人員整理などで、希望退職者の募集によって退職した人も特定理由離職者に当たります。
ただし、該当するのはあくまで自ら希望退職した場合に限り、事業主から直接もしくは間接的に退職するように促されて退職した人は「特定受給資格者」と認定されます。
特定理由離職者になるために必要な書類
失業保険の受給に必要な書類以外に、特定理由離職者の範囲に当たると証明する書類も必要です。
失業保険の受給に必要な書類
離職理由に限らず、失業保険を受給するためには以下の書類を準備します。
- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険被保険者離職票
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カードなど)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 写真(縦3.0cm×横2.4cm)2枚
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
雇用保険被保険者証は、入社するときに会社がハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出後に発行され、従業員に渡される書類です。
会社で管理していることもあり、その場合は退職後に会社から受け取るか、郵送してもらう必要があります。紛失した場合は、ハローワークの窓口で手続きすると再交付してもらえます。
離職票とは、退職日の翌々日から10日以内に、会社がハローワークに「離職証明書」と「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出すると発行される書類です。一般的には退職日から約2週間で手渡しまたは郵送で受け取れます。
離職票は労働者が希望しないと発行手続きをしてもらえないこともあるため、必要な場合は退職前に担当者に伝えておく必要があります。
特定理由離職者の認定に必要な証明書類
特定理由離職者になるには、離職理由を客観的に証明するための書類が必要です。証明書類は離職理由により異なります。
主な離職理由に求められる書類の種類を、以下の表にまとめました。
| 離職理由 | 証明書類 |
| 雇止め | 労働契約書、雇入通知書、就業規則など |
| 妊娠・出産・育児 | 受給期間延長通知書など |
| 家庭の事情の急変 | 扶養控除等申告書、健康保険証、医師の診断書など |
| 配偶者や扶養親族との別居困難 | 転勤辞令、住民票の写し、扶養控除等申告書、健康保険証など |
| 通勤困難 | 住民票の写し、保育園の入園許可証、事業所移転の通知、転勤辞令など |
参考:ハローワーク|特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
表で示した書類以外にも、必要に応じて客観的に証明可能な書類を求められることがあります。離職理由や労働者の状況によって証明書類が異なることがあるため、準備する書類がわからないときはハローワークに問い合わせましょう。
特定理由離職者として失業保険を受給する手順
特定理由離職者と認定され、失業保険を受給するまでの一般的な手順は以下のとおりです。
- 受給申請の必要書類と証明書類を準備する
- ハローワークの窓口で求職申込みをする
- 7日間の待期期間を過ごす
- 雇用保険説明会に参加する
- 失業認定申告書を提出する
- 失業保険が振り込まれる
ハローワークで必要書類を提出すると、担当者との面談で失業保険の受給資格が認定されます。特定理由離職者として申請した場合、離職理由を証明する書類と面談内容で審査されるため、不備がないように準備することが重要です。
無事に認定されると、特定理由離職者であることや所定給付日数が記載された「雇用保険受給資格者証」を雇用保険説明会後に受け取れます。
特定理由離職者が失業保険を受給するメリット

特定理由離職者になることで、主に以下のようなメリットがあります。
- 受給条件が緩和される
- 早く受給できるようになる
- 離職理由によっては受給額が増える
- 国民健康保険料や住民税が軽減される
それぞれのメリットを詳しく解説します。
受給条件が緩和される
特定理由離職者の場合、失業保険の受給要件が一部緩和されます。
一般の離職者は、離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要です。一方、特定理由離職者は離職日以前の1年間に被保険者期間が通算6か月以上必要となり、一般の離職者より短い被保険者期間で受給できます。
早く受給できるようになる
特定理由離職者になると、1か月の給付制限期間が免除されることもメリットです。給付制限期間とは、失業保険を受給できない期間で、一般の離職者は7日間の待期期間に加えて1か月の給付制限後に支給開始されます。
特定理由離職者も7日間の待期期間は設けられているものの、給付制限を受けないため、一般の離職者より早く受給できます。
ただし、待期期間後すぐに失業保険を受け取れるわけではなく、振込完了まで1週間程度かかることがある点に注意が必要です。
離職理由によっては受給額が増える
特定理由離職者のうち、雇止めで離職した場合は特定受給資格者と同等の所定給付日数がもらえるため、その他の離職者より受給総額が増えることがあります。
例えば、雇用保険の被保険者期間が20年以上の45歳労働者が雇止めで離職した場合、所定給付日数は330日です。一方、一般の離職者や正当な理由で離職した特定理由離職者は、離職理由以外の条件が同じでも所定給付日数は150日と、雇止めによる離職の半分以下になります。
ただし、雇用保険の被保険者期間によっては、雇止めでも自己都合で退職した場合と所定給付日数が変わらないケースもあります。
国民健康保険料や住民税が軽減される
特定理由離職者は、国民健康保険料や住民税が減額・免除される可能性があります。離職によって収入が減り、保険料や税金の支払いが困難な場合はメリットになります。
特定理由離職者に該当する場合、前年の給与所得を30%に換算した金額で国民健康保険料や高額療養費を算出するため、負担額が軽減される仕組みです。軽減対象は給与所得のみで、事業所得や利子所得、配当所得などは軽減されません。
国民健康保険料の軽減措置は、自動的に軽減されるわけではなく、市区町村役場で届出の手続きが必要です。
また、失業した人のうち一定条件を満たす場合は、住民税が減免される可能性もあります。特定理由離職者の範囲に当たる「雇止め」や「正当な理由による離職」は、住民税の減額・免除の対象です。具体的な軽減措置の内容は自治体によって異なるため、制度を利用する場合は市区町村役場に問い合わせましょう。
特定理由離職者のデメリット
特定理由離職者にはメリットがある一方で、以下のようなデメリットも存在する点に注意が必要です。
- 手続きに時間がかかることがある
- 離職理由によっては再就職に影響を与える
手続きに時間がかかることがある
特定理由離職者になるためには、客観的事実を証明する書類をハローワークに提出することが求められます。人によって証明書類が異なるため、必要な書類を把握して準備するのに時間がかかり、失業保険の受給開始が遅くなる可能性があります。
場合によっては、会社から書類をもらう必要があったり、離職理由について会社と対立して事実確認に時間がかかったりと、精神的な負担になる可能性があることもデメリットです。
また、書類に不備があると審査に時間がかかり、受給時期が遅れる原因になります。
離職理由によっては再就職に影響を与える
労働者本人や家族の健康上の理由による退職など、再就職の際にネガティブな印象を与えてしまう可能性は否定できません。
マイナスイメージを与えやすい離職理由だったとしても、ポジティブな印象に変えられるような説明を準備しておき、再就職への影響を軽減することが重要です。
まとめ
離職理由が「雇止め」や「正当な理由での離職」に該当する場合、特定理由離職者に認定されます。正当な理由とは労働者本人の傷病や家族の介護などで、認定の際は理由を客観的に証明できる書類の提出が必要です。
特定理由離職者には、失業保険の優遇措置が受けられるなどのメリットがある一方で、手続きに時間がかかると受給が遅れてしまう点に注意しましょう。
スムーズに受給するためには、「社会保険給付金サポート」の活用がおすすめです。必要書類の準備や申請手続きをプロの担当者が丁寧にサポートします。無料相談も受け付けているので、「自分が特定理由離職者になれるか知りたい」「どの書類が必要かわからない」といったお悩みもお気軽にご相談ください。

 給付金がいくらもらえるか
知りたい方
給付金がいくらもらえるか
知りたい方 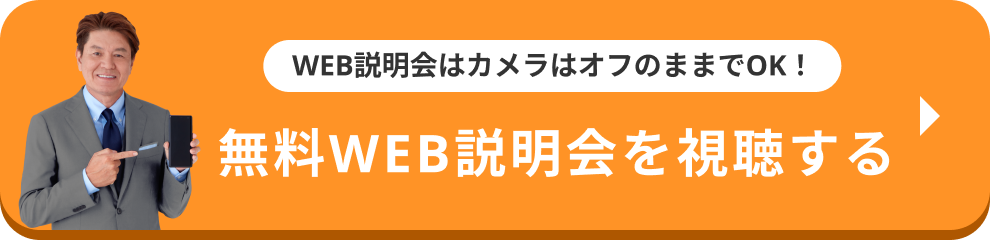
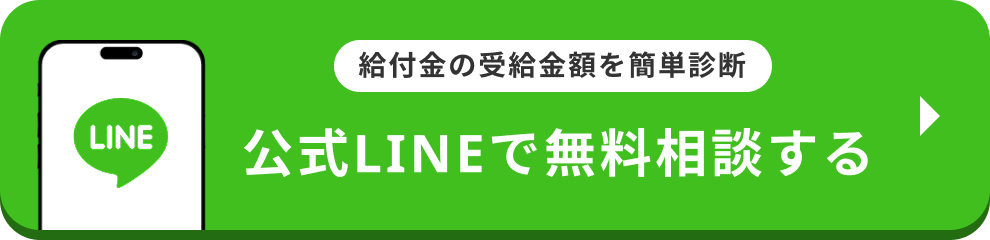
 給付金サポートを
ご検討中の方
給付金サポートを
ご検討中の方  評判・口コミ
評判・口コミ  給付金がもらえる
転職支援を活用する方
給付金がもらえる
転職支援を活用する方  その他退職について
ご不安がある方
その他退職について
ご不安がある方  もらえる給付金ラボ
もらえる給付金ラボ  退職コンシェルジュについて
退職コンシェルジュについて