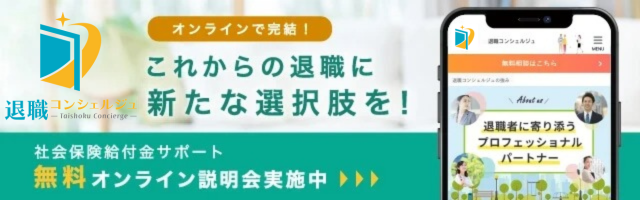失業保険の受給額の計算方法

失業保険の1日分の金額(基本手当日額)は「賃金日額×給付率」で、総額は「基本手当日額×基本手当の所定給付日数」で計算できます。
ただし、離職前の賃金や年齢、雇用保険の被保険者期間によって計算の条件などが異なるため、受給額を計算する際は個々の条件を調べる必要があります。
STEP1:賃金日額の計算
6か月間(180日間)の賃金総額を1日分に換算したものを「賃金日額」と呼び、この金額をもとに失業保険の受給額が決まります。賃金日額は、「退職前6か月間の賃金総額÷180日」で計算します。
受給額を計算する際の「賃金総額」とは、離職した日の直前6か月で毎月決まって支払われた賃金の総額です。基本的にボーナス(賞与)や各種祝金、退職金は対象外ですが、3か月毎に支給されるボーナスや毎月支払われる通勤手当、住宅手当、夜勤手当などの各種手当は賃金総額に含まれます。
賃金日額には上限額と下限額が設定されており、算出した金額が上限を上回っている場合は上限額で受給額を計算します。一方、下限を下回るときは、下限額をもとに受給額を計算するため注意が必要です。
令和7年8月以降の賃金日額の上限額と下限額は、以下のとおりです。
| 上限額 | 下限額 | |
| 29歳以下 | 14,510円 | 3,014円 |
| 30歳〜44歳 | 16,110円 | |
| 45歳〜59歳 | 17,740円 | |
| 60歳〜64歳 | 16,940円 |
参考:ハローワーク|雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和7年8月1日から〜
ただし、上限額・下限額は原則として毎年変更されるため、受給のタイミングによっては上記の金額が変更されていることがあります。
STEP2:基本手当日額の計算
賃金日額を算出後、「賃金日額×給付率」で基本手当日額を計算します。
基本手当日額とは、失業保険でもらえる1日当たりの受給額のことです。給付率は、離職時の年齢と賃金日額によって変わり、基本的には賃金日額が低いほど高く設定されています。
計算した賃金日額からおおよその基本手当日額は、以下の表のとおりです。ただし、表の金額は変更されることがあります。
・離職時の年齢が29歳以下、または65歳以上(高年齢職者給付金)の場合
| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
| 3,014円以上5,340円未満 | 80% | 2,411円〜4,271円 |
| 5,340円以上13,140円以下 | 80%〜50% | 4,272円〜6,570円 |
| 13,140円超14,510円以下 | 50% | 6,570円〜7,255円 |
| 14,510円超 | ー | 7,255円 |
参考:ハローワーク|雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和7年8月1日から〜
・離職時の年齢が30歳〜44歳
| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
| 3,014円以上5,340円未満 | 80% | 2,411円〜4,271円 |
| 5,340円以上13,140円以下 | 80%〜50% | 4,272円〜6,570円 |
| 13,140円超16,110円以下 | 50% | 6,570円〜8,055円 |
| 16,110円超 | ー | 8,055円 |
参考:ハローワーク|雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和7年8月1日から〜
・離職時の年齢が45歳〜59歳
| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
| 3,014円以上5,340円未満 | 80% | 2,411円〜4,271円 |
| 5,340円以上13,140円以下 | 80%〜50% | 4,272円〜6,570円 |
| 13,140円超17,740円以下 | 50% | 6,570円〜8,870円 |
| 17,740円超 | ー | 8,870円 |
参考:ハローワーク|雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和7年8月1日から〜
・離職時の年齢が60歳〜64歳
| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
| 3,014円以上5,340円未満 | 80% | 2,411円〜4,271円 |
| 5,340円以上11,800円以下 | 80%〜45% | 4,272円〜5,310円 |
| 11,880円超16,940円以下 | 45% | 5,310円〜7,623円 |
| 16,940円超 | ー | 7,623円 |
参考:ハローワーク|雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和7年8月1日から〜
基本手当日額にも上限があり、賃金日額が上限額となった場合は基本手当日額も上限額となります。また、全年齢とも基本手当日額の下限額は2,411円です(2025年8月時点)。
給付率に「80%〜50%」と記載されている場合は、「0.8×賃金日額-0.3{(賃金日額-5,340円)÷7,800円}×賃金日額」で基本手当日額を計算します。
ただし、60歳〜64歳の離職者は、「0.8×賃金日額-0.35{(賃金日額-5,340円)÷6,460円}×賃金日額」か「0.05×賃金日額+4,720円」のいずれか低い方が基本手当日額として支給されます。
STEP3:基本手当の受給総額を計算
失業保険は4週間ごとに実施される失業認定で支給が決定されるため、原則として28日分ずつ受け取ることになります。1回で受け取れる金額は、「基本手当日額×28日」で計算できます。
ただし、待期期間や給付制限期間、祝日などにより毎回28日分が支給されるわけではありません。
失業保険の総額を知りたいときは、「基本手当日額×所定給付日数」で計算します。
所定給付日数とは、失業保険が支給される日数のことです。失業保険は無期限に受け取れるものではなく、離職理由や雇用保険の加入期間、年齢などによって異なる所定給付日数が設定されています。
失業保険の所定給付日数を離職理由ごとに、以下の表にまとめました。
・特定受給資格者及び一部の特定理由離職者の場合
| 雇用保険の被保険者期間 | |||||
| 離職時の年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
| 30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
| 35歳以上45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | ||
| 45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
| 60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
参考:ハローワークインターネットサービス|基本手当の所定給付日数
・就職困難者の場合
| 雇用保険の被保険者期間 | ||
| 離職時の年齢 | 1年未満 | 1年以上 |
| 45歳未満 | 150日 | 300日 |
| 45歳以上65歳未満 | 360日 | |
参考:ハローワークインターネットサービス|基本手当の所定給付日数
・上記以外の離職者の場合(全年齢)
| 雇用保険の被保険者期間 | 所定給付日数 |
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
参考:ハローワークインターネットサービス|基本手当の所定給付日数
就職困難者とは、身体・知的・精神障害のある人や保護観察処分を受けた人、社会的事情で就職が著しく困難な状況にある人が該当します。離職理由について、詳しくは後述します。
失業保険の計算で把握しておきたい離職理由とは?
失業保険の受給総額を計算するときは、自分の所定給付日数を把握する必要があります。所定給付日数は離職理由、年齢、雇用保険の被保険者期間によって設定されており、特に離職理由によって大きく異なります。
離職理由から「特定受給資格者及び一部の特定理由離職者」と認定されると最大330日分が給付され、それ以外の離職者の最大150日と比較して、2倍以上多く受給することも可能です。そのため、失業保険の受給額を計算する際は、離職した理由を把握しておくことが重要です。
失業保険の受給額を決める要因となる離職理由には、以下の3つがあります。
- 特定受給資格者
- 特定理由離職者
- 一般の離職者
それぞれに該当する人の例を出しながら、詳しく解説します。
特定受給資格者
特定受給資格者とは、倒産や解雇など会社都合で離職せざるを得なかった人のことです。具体的には、「倒産等による該当事由」や「解雇等による該当事由」に当てはまる人が対象となります。
| 離職理由 | 具体例 |
| 倒産等による該当事由 | ・会社の倒産や事務所の廃止により離職した者
・大量雇用変動の届出により離職した者 ・事業所の移転で通勤困難となり離職した者 |
| 解雇等による該当事由 | ・会社都合で解雇されて離職した者(自己が原因の重大な理由による解雇を除く)
・一定以上の賃金低下や未払いにより離職した者 ・直接もしくは間接的に退職するよう勧奨を受けて離職した者 ・一定期間の時間外労働時間を超えたことで離職した者 ・ハラスメントを受けたことで離職した者 ・労働契約で示された労働条件と事実が著しく相違したことで離職した者 |
特定理由離職者
特定理由離職者とは、特定受給資格者には該当しないが、雇い止めや正当な理由があり離職せざるを得なかった人のことです。
所定給付日数が決まる条件となる「一部の特定理由離職者」に該当するのは、期間の定めがある労働契約の期間が満了し、希望したのに更新されずに離職した場合に限ります。
以下のような正当な理由があり、自己都合で退職した人も「特定理由離職者」に含まれますが、所定給付日数は一般の離職者と同等の条件となります。
- 体力不足や心身の障害など、本人の健康状態が理由で退職した人
- 妊娠・出産・育児などにより離職し、受給期間の延長措置を受けた人
- 父母の死亡・疾病・負傷などにより、離職を余儀なくされた人
- 家族と別居生活を続けることが困難になり離職した人
- 結婚や事業所の移転、交通機関の運行時間変更などで、通勤が困難になり離職した人
- 希望退職者の募集に応じて離職した人
一般の離職者
一般の離職者とは、特定受給資格者や特定理由離職者に該当しない離職者のことです。例えば、転職や独立など、自己都合で退職した人は一般の離職者になります。
職場環境や労働契約に不備がなかったにもかかわらず、個人の都合で退職したと判断されるため、特定受給資格者や一部の特定理由離職者と比べて、失業保険の所定給付日数が少なく設定されています。
【パターン別】失業保険の計算例
失業保険の受給額は一律ではなく、個々の状況によって大きく異なります。そのため、自分の場合はいくら受け取れるのかを把握するには、個々の条件をもとに計算することが必要です。
ここでは、年齢や手取り月収など具体的なパターンに分けて、実際の計算例を紹介します。
20代・手取り17万円の受給額
以下の条件で受給すると仮定し、支給総額と1回で受給できる金額を計算します。
| 年齢 | 20代 |
| 離職理由 | 転職のための自己都合退職(一般の離職者) |
| 前職の月収 | 総支給額約22万円(手取り17万円程度) |
| 被保険者期間 | 3年 |
まずは、賃金日額を計算します。賃金日額を計算する際の賃金総額は手取りではなく、総支給額を使います。総支給額とは、所得税などの税金や社会保険料が天引きされる前の金額のことです。
賃金日額=退職前6か月間の賃金総額÷180日=22万円×6か月÷180日=約7,333円
計算した賃金日額からこのケースの給付率は50%〜80%となり、以下の計算式で基本手当日額を算出できます。
基本手当日額=0.8×7,333円-0.3{(7,333円-5,340円)÷7,800円}×7,333円=約5,304円
転職による自己都合退職で雇用保険の被保険者期間は3年なので、所定給付日数は90日です。つまり、総支給額は、5,304円×90日=約47万7,360円となります。
失業保険は原則28日ごとに支給されるため、1回分の支給額は5,304円×28日=約14万8,512円です。
35歳・手取り40万円の受給額
年齢や離職理由、雇用保険の加入期間などの条件が違う場合、受給額はどれくらい変わるのでしょうか。次は以下の条件で計算してみます。
| 年齢 | 35歳 |
| 離職理由 | 会社の倒産による離職 |
| 前職の月収 | 総支給額約50万円(手取り40万円程度) |
| 被保険者期間 | 10年 |
賃金日額=50万円×6か月÷180日=約16,666円
賃金日額の上限額を超えているため、基本手当日額が上限の8,055円となります。
また、離職理由が会社の倒産で特定受給資格者に該当するため、年齢と雇用保険の被保険者期間から所定給付日数は240日です。
支給総額=8,055円×240日=193万3,200円
28日分の支給額を計算すると、8,055円×28日=22万5,540円が1回分の支給額です。
45歳・手取り30万円の受給額
計算に必要な条件に注意して、以下の受給額を計算します。
| 年齢 | 45歳 |
| 離職理由 | 独立のため自己都合による退職 |
| 前職の月収 | 総支給額約40万円(手取り30万円程度) |
| 被保険者期間 | 12年 |
賃金日額=40万円×6か月÷180日=約13,333円
45歳で賃金日額が13,333円の場合は給付率が50%となり、基本手当日額を計算します。
基本手当日額=賃金日額×給付率=13,333円×50%=約6,666円
離職理由は独立のための自己都合退職で、特定受給資格者や特定理由離職者に該当しないため、雇用保険の被保険者期間12年から所定給付日数は120日です。
支給総額=6,666円×120日=約79万9,920円
1回分を28日で計算すると、1回の支給額は6,666円×28日=約18万6,648円となります。
62歳・手取り20万円の受給額
特定理由離職者に該当するケースとして、次の条件で受給額を計算します。
| 年齢 | 62歳 |
| 離職理由 | 雇用の定めがある労働契約が満了し、更新がなかったため離職 |
| 前職の月収 | 総支給額約25万円(手取り20万円程度) |
| 被保険者期間 | 2年 |
賃金日額=25万円×6か月÷180日=約8,333円
60歳から64歳の場合、賃金日額が5,340円以上11,800円以下の範囲にあるときは、給付率は45%〜80%です。以下の2つのパターンで計算し、いずれか低いほうの金額が基本手当日額になります。
- 「0.8×賃金日額-0.35{(賃金日額-5,340円)÷6,460円}×賃金日額」=0.8×8,333円-0.35{(8,333円-5,340円)÷6,460円}×8,333円=約5,315円
- 「0.05×賃金日額+4,720円」=0.05×8,333円+4,720円=約5,136円
算出額が①>②のため、基本手当日額は約5,136円となります。
離職理由が一部の特定理由離職者に当てはまり、被保険者期間が2年であることから、所定給付日数は150日です。
支給総額=5,136円×150日=約77万400円
よって、1回分(28日分)の支給額は5,136円×28日=約14万3,808円となります。
65歳以上で離職したときの受給額
65歳以上で退職した場合は、「高年齢求職者給付金」の条件を満たすと給付金を受給できます。高年齢求職者給付金は、離職日以前の1年間に雇用保険の被保険者期間が通算6か月以上あり、失業状態ですぐに働ける状態にあり、積極的な就職の意思があることが受給条件です。
以下の条件で、高年齢求職者給付金を受け取る時の受給額を計算します。
| 年齢 | 65歳以上 |
| 離職理由 | 体調不良が続いたため離職 |
| 前職の月収 | 総支給額約13万円(手取り10万円程度) |
| 被保険者期間 | 2年 |
基本手当日額を計算するところまでは、64歳以下のパターンと同様に進めていきます。
賃金日額=13万円×6か月÷180日=約4,333円
65歳以上の給付率は29歳以下の場合と同等で、この場合は80%で計算します。
基本手当日額=賃金日額×給付率=4,333円×80%=約3,466円
高年齢求職者給付金の支給日数も、以下のように被保険者期間で変わります。
| 雇用保険の被保険者期間 | 給付日数 |
| 1年未満 | 30日 |
| 1年以上 | 50日 |
参考:厚生労働省|離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>
上記の表から、支給総額は3,466円×50日=約17万3,300円です。高年齢求職者給付金は一括で支給されるため、この金額が一度に振り込まれます。
失業保険を受給するときに知っておきたい基礎知識
そもそも失業保険とは、何らかの理由で退職後、再就職を希望する際の求職期間中に給付金を受給できる制度です。正式には「雇用保険の基本手当」のことを指し、「失業保険」「失業手当」と呼ばれることもあります。
失業保険は失業した人なら誰でももらえるものではなく、一定の条件を満たしたうえで、受給期間中に手続きが必要です。
失業保険の受給条件
失業保険をもらうための条件を以下にまとめました。
- 離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12か月以上ある
- ハローワークに来所して求職の申込みを行う
- 就職しようとする積極的な意思がある
- いつでも就職できる能力がある
- 失業状態にある
特定受給資格者または特定理由離職者に該当する場合は、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば受給条件を満たします。以下の条件に当てはまる月を、被保険者期間として計算します。
- 雇用保険の被保険者期間のうち、賃金支払いの対象となった日数が11日以上ある月
- 賃金支払いの対象となった時間数が80時間以上ある月
被保険者期間は通算として計算するため、途中で未加入の時期があったとしても、合計で12か月以上または6か月以上加入時期があれば支給対象です。
また、失業保険は就職を目指す人を支援する制度のため、以下のように、すぐに就職できない場合や就職の意思がない場合は支給対象外となります。
- 病気やケガですぐに就職できないとき
- 妊娠・出産・育児・介護によりすぐに就職できないとき
- 定年などで退職し、しばらく休養する予定のとき
失業保険の受給期間
失業保険を申請できる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。ただし、所定給付日数が330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日が過ぎる日まで手続きできます。
もし受給期間中に病気やケガ、妊娠、出産などで連続して30日以上働けない場合は、働けない日数分の受給期間を最高4年延長できます。働けない日が30日を超えた日の翌日から、延長後の受給期間内であれば申請可能です。期限ギリギリで申請すると満額受給できなくなるため、できるだけ早く手続きすることが望ましいでしょう。
また、定年退職などで一定期間求職申込みをしないときは、離職日の翌日から2か月以内に手続きすることで、受給期間を最高2年延長できます。
万が一、手続きを忘れてしまって受給期間が過ぎた場合でも受給できる可能性があるため、できるだけ迅速にハローワークで相談しましょう。
失業保険の申請で準備する必要書類
失業保険を受給するためには、ハローワークの窓口で求職申込みをして、受給資格を得る必要があります。求職申込みに必要な書類は、以下のとおりです。
- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険被保険者離職票
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 証明写真(縦3.0cm×横2.4cm)2枚
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
雇用保険被保険者証と離職票は、前職の会社から退職後に受け取ります。雇用保険被保険者証は労働者が管理しているケースもあるため、渡されない場合は自分で持っていないか確認が必要です。会社が離職票の発行手続きをしてくれない場合は、ハローワークへ相談すると対応してもらえることがあります。
上記の提出書類のうち、失業認定など手続きごとにマイナンバーカードを提示する場合は、証明写真は省略できます。
失業保険の申請手順
失業保険は、退職すると自動的に振り込まれる給付金ではないため、自分で受給申請する必要があります。申請後も説明会への参加や失業認定などの手続きが複雑なため、スムーズに受給するにはあらかじめ手順を把握しておくことが重要です。
基本的な受給の流れは、以下のとおりです。
- ハローワークで求職申込の手続きを行う
- 7日間の待期期間を過ごす
- 雇用保険説明会に参加する
- 初回の失業認定を受ける
- 受給が開始される
- 失業認定と受給を繰り返す
それぞれの手順を詳しく解説します。
1.ハローワークの窓口で求職申込みを行う
退職後、前述の必要書類を揃えて、ハローワークの窓口で求職申込みを行います。求職活動の際は全国どこのハローワークでも利用できますが、受給申請の手続きは住所地を管轄するハローワークでしかできません。
求職申込み後、担当者と面談で受給資格が決定すると、「失業等給付受給資格者のしおり」を受け取れます。同時に雇用保険説明会の日時が決定するので、忘れないように日程をメモしておきましょう。一般的に、説明会は申請日から7日後以降に設定されます。
2.7日間の待期期間を過ごす
受給資格の決定後に、7日間の待期期間が設けられています。
失業状態であることを審査する期間のため、待期期間中の就労は避けましょう。短時間のアルバイトだとしても、働いてしまうと収入の大小に関わらず、働いた日数分だけ待期期間が延長されてしまいます。
また、失業保険の受給中に再就職するともらえる再就職手当は、待期期間中の再就職ではもらえないので注意が必要です。
3.雇用保険説明会に参加する
指定された日時にハローワークへ行き、雇用保険説明会に参加します。説明会では、失業保険の仕組みや受給の流れ、求職活動の方法など受給に必要な説明があるので、聞き漏らすことのないようにしましょう。
基本的な持ち物は以下のとおりですが、その他に指定された持ち物がある場合は忘れず持参します。
- 雇用保険受給資格者のしおり
- 筆記用具
説明会後に、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡されます。初回の失業認定日の案内もあるため、日程をメモしておくと安心です。認定日は原則4週間(28日)ごとに設定されますが、初回認定日は求職申込みの日から換算するため、待期期間が明けて約3週間後に指定されます。
4.初回の失業認定を受ける
雇用保険説明会で指定された初回認定日にハローワークを訪れ、失業認定申告書を提出して失業認定を受けます。
失業認定申告書は、求職活動の実績を申告するための書類です。前回の失業認定日から、今回の認定日の前日までに行った求職実績の内容を記入して提出します。実績が不十分と判断されると不支給となるため、一定以上の求職活動を行う必要があることに注意しましょう。
実績や労働の有無を虚偽申告すると、不正受給と判断されることがあるため、正しい内容を記載します。
5.受給が開始される
求職活動の実績申告に不備がなければ、失業認定日から1週間程度で指定した口座に失業保険が振り込まれます。
ただし、「特定受給資格者及び一部の特定理由離職者」に該当しない離職者は、1か月の給付制限期間が設けられており、期間中の認定日には支給されません。給付制限期間後、最初の失業認定日から支給が開始されます。
6.失業認定と受給を繰り返す
初回認定日から約4週間後に2回目の認定日が指定され、初回と同様に求職活動の実績を記載した失業認定申告書を提出します。受給に必要な求職活動の実績は、期間中に2回以上です。
以降、所定給付日数が終わるまで、または再就職するまで求職活動と失業認定、受給を繰り返します。
失業保険の受給で注意したいポイント
失業保険は受給申請したら終わりではなく、給付金を受け取るためにはいくつかの条件を満たす必要があります。受給の際の注意点は、主に以下のとおりです。
- 受給資格の決定後も求職活動の実績が求められる
- 失業保険の支給開始日や給付日数は条件によって異なる
- 受給中の労働は減額や支給停止になる可能性がある
- 不正受給しないように注意する
もし条件を満たさない場合、受給中でも支給停止になる可能性があるため、注意点を守ることが重要です。
受給資格の決定後も求職活動の実績が求められる
求職申込み後、失業保険の受給資格が決定したからといって、その後自動的に給付金が振り込まれるわけではありません。受給するためには、決められた失業認定日にハローワークへ行って、失業認定を受ける必要があります。
失業認定では、求職活動中であることを証明するために、一定以上の求職活動実績が求められます。具体的には、求人への応募やハローワークが実施する職業相談や職業紹介、各種講習・セミナーの参加などです。
ハローワークが主催するもの以外でも、許可のある民間事業者や公的機関が実施する職業相談や講習会・セミナーの受講も実績の対象です。その他には、再就職のための国家試験や検定の受験なども実績として認められています。
職業相談や講習・セミナーに参加する際は、雇用保険受給資格者証にハンコを押してもらう必要があります。ハローワーク以外での活動実績は、失業認定申告書に記載するだけで証明書は不要ですが、調査を行うケースもあるため虚偽の報告はしないように注意しましょう。
支給開始日や給付日数は条件によって異なる
失業保険の支給開始日や給付日数は離職理由によって異なるため、自分の条件を把握しておくことが重要です。
例えば、倒産や解雇など会社都合で退職した場合、求職申込み後7日間の待期期間を経て受給が始まります。一方、自己都合による退職では、待期期間後1か月の給付日数がかかるため、会社都合より支給開始日が遅くなることを理解しておきましょう。
また、一般の離職者より特定受給資格者のほうが、年齢や雇用保険の加入期間次第で給付日数が多くなることがあります。自分の場合はいつからいつまで受給できるのか、いくらもらえるのか把握することで、求職活動中の生活を具体的にイメージしやすくなります。
受給中の労働は就職と判断されることがある
受給には「失業状態であること」が一つの条件のため、原則として週20時間以上の労働はアルバイトでも「就職している」と判断され、受給が終了となることがあります。受給中の労働は制限されますが、週20時間未満であれば、週20時間以上の仕事を探す意思と能力がある場合は、受給しながら働くことも可能です。
ただし、受給中に働く際は、失業認定申告書で報告が必要です。事業主に雇用されている場合だけでなく、自営業の準備や家業の従事、内職、ボランティア活動なども労働の範囲とみなされるため、漏れのないよう申告しましょう。
週20時間未満の労働であっても、1日4時間以上働いた日は不支給となり繰り越しとなり、1日4時間未満の場合は賃金によって減額されることがある点に注意が必要です。短時間労働による減額幅は、「(4時間未満の賃金÷4時間未満の労働日数-内職控除額+基本手当日額)-賃金日額×0.8」で計算されます。
不支給による繰り越しがあると支給終了日が遅くなり、失業期間が長くなって就職で不利になることがあります。早期の再就職を目指すなら、受給中の労働は控えたほうが無難です。
不正受給しないように注意する
受給中に就職や就労の申告をしなかったり、求職活動の実績を偽って申請したりすると、不正受給になる点に注意が必要です。不正受給と判断されると、主に以下のペナルティが与えられることがあります。
- 支給停止
- 不正に受給した分の金額の返還
- 不正受給した金額の最大2倍額の納付
より悪質と判断された場合は、刑事事件として告発され、遅滞金などを加えた金額の返還を求められることもあります。具体的な不正受給の例は、主に以下のようなケースが挙げられます。
- 受給中のアルバイトを失業認定申告書に記載しなかった
- 就職日を偽って多く受給した
- 実際には行っていない求職活動を申告した
故意に不正受給しないことはもちろん、申告漏れや記入ミスにも注意が必要です。
失業保険以外の給付金

失業保険の受給額は離職理由や雇用保険の加入期間によって決まるため、受け取れる金額が少ないと感じることがあるかもしれません。実は、失業保険以外にも退職後に条件を満たすともらえる給付金があります。
求職活動を支援する制度
失業中の求職活動を支援する制度や給付金には、主に以下の種類があります。
| 給付金の種類 | 内容 | 失業保険との併用 |
| 技能就職手当 | 公共職業訓練等を受講する場合に、受講手当日額500円(上限額20,000円)と通所手当を受給できる | 可能 |
| 教育訓練給付金 | 教育訓練の修了後に、受講費用が最大80%支給される | 可能 |
| 短期訓練受講費 | 1か月未満の教育訓練を修了後、受講費用の20%(上限10万円)が支給される | 可能 |
| 広域求職活動費 | ハローワークの紹介で遠方の事業所へ面接に行った際に、運賃や宿泊料が支給される | 可能 |
早期に再就職するともらえる給付金
失業保険の受給している途中で早期に再就職し、条件を満たすと以下のような給付金をもらえることがあります。
| 給付金の種類 | 内容 | 支給額 |
| 再就職手当 | 失業保険の受給期間がある人が安定した職業に就いた際、残りの給付日数に応じた給付金が支給される | 支給残日数×60〜70%×基本手当日額 |
| 就業促進定着手当 | 再就職手当をもらった人が、再就職先の6か月の賃金が離職前より低い場合に支給される | (離職前の賃金日額-再就職先の賃金日額)×再就職した日から6か月以内の給与支払い日数 |
| 常用就職支度手当 | 失業保険の受給資格があり、就職が困難な人が安定した職業に就いたときに支給される | 90×40%×基本手当日額 |
まとめ
失業保険の受給額は、離職理由や雇用保険の加入状況、年齢などの条件によって異なります。そのため、受給額を調べるときは自分の条件を把握しておくことが必要です。
計算してみると、意外ともらえる金額が少ないと感じた方もいるかもしれません。実は、退職後に支給されるお金は失業保険だけでなく、さまざまな給付金があります。
しかし、給付金の種類は多く、一つずつ受給条件を調べるのは時間と労力がかかります。退職後にもらえる給付金を申請したい場合におすすめなのが、「社会保険給付金サポート」です。相談は無料ですので、自分がもらえる給付金はあるか、いくらもらえるのかを知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 給付金がいくらもらえるか
知りたい方
給付金がいくらもらえるか
知りたい方 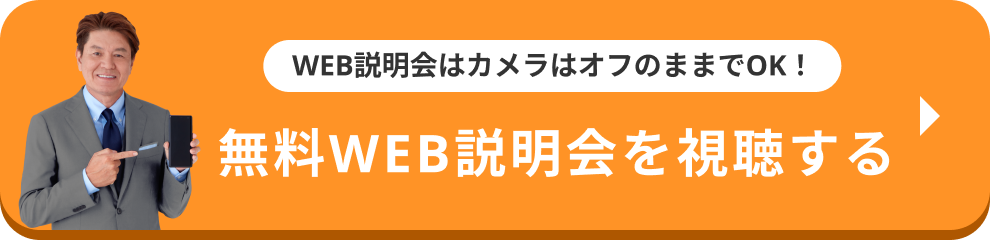
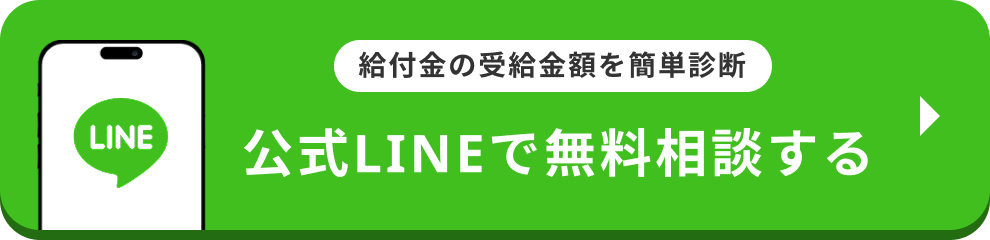
 給付金サポートを
ご検討中の方
給付金サポートを
ご検討中の方  評判・口コミ
評判・口コミ  給付金がもらえる
転職支援を活用する方
給付金がもらえる
転職支援を活用する方  その他退職について
ご不安がある方
その他退職について
ご不安がある方  もらえる給付金ラボ
もらえる給付金ラボ  退職コンシェルジュについて
退職コンシェルジュについて