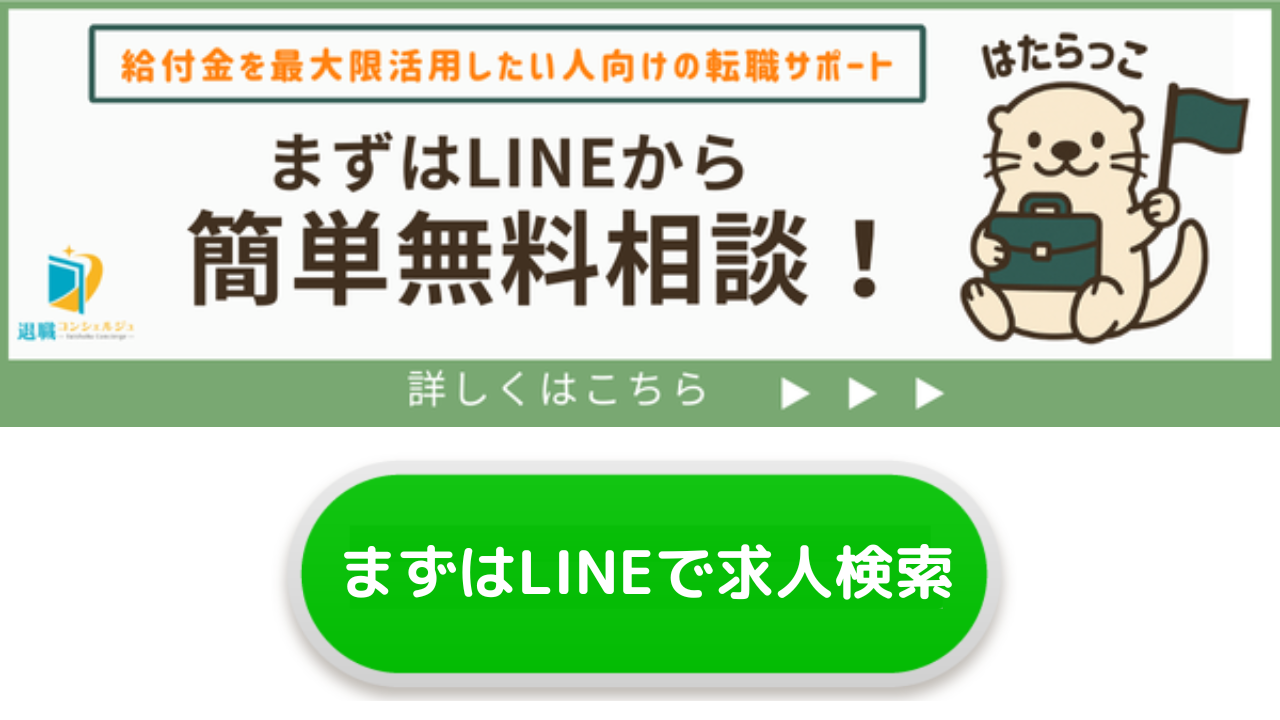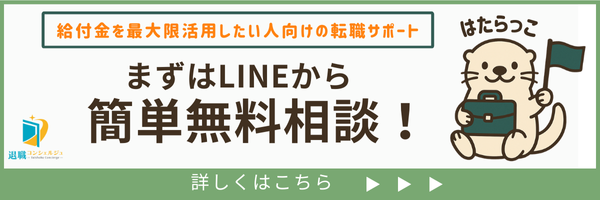2025.05.16
転職・再就職について
失業保険は週20時間以内なら働きながら受け取ることができる?

「働きながら失業保険は受給できるのか」このように疑問に思う方は少なくありません。実際には、週20時間以内・短期契約など一定の条件を満たせば、アルバイトやパートなどで収入を得ながら失業保険の受給が可能です。
しかし、条件を正しく理解しないまま働いてしまうと支給が止まったり減額されたりするリスクもあります。本記事では、働きながら失業保険をもらう際の条件・メリット・注意点を具体的に解説します。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
働きながら失業保険をもらう条件

失業保険を受給中でも、一定の条件を満たせば働くことが可能です。ただし、働き方によっては「就職した」とみなされ、支給が停止される恐れがあります。失業状態を保ちつつ働くには、法律や制度のルールを正確に理解する必要があります。
ここでは、働きながら失業保険をもらう条件を3つ解説します。
7日間の待期期間を完了する
失業保険の支給を受けるには、まず7日間の待期期間を終える必要があります。待期期間とは、ハローワークで求職の申込みを行い、受給資格が決定したあとに設けられる7日間の確認期間のことです。待機期間中は失業状態であることが前提となるため、原則として労働は禁止されています。
なお、待期期間は、自己都合退職・会社都合退職のいずれでも適用されます。ただし、自己都合退職の場合はこの7日間に加えて、通常1ヵ月間の給付制限期間を経ないと実際の支給は始まりません。
週20時間未満、契約期間31日未満
失業保険をもらいながら働くには、働き方の条件にも注意が必要です。労働時間や契約内容によっては雇用保険への加入対象と判断され、「就職した」とみなされる可能性があります。
以下のいずれかに該当する場合は、原則として雇用保険への加入義務が発生します。
- 週20時間以上働く場合
- 31日以上の雇用契約がある場合
失業保険を受け取りながら働き続けたい場合は、週の所定労働時間が20時間未満で、かつ雇用契約期間が31日未満という条件を満たす必要があります。
なお、契約書に「契約更新の可能性がある」と明記されている場合や、同じ事業所で過去に31日以上の雇用実績がある場合は、実質的に長期雇用と見なされる可能性があります。形式的に短期の契約であっても、ハローワークが総合的に判断して「再就職」と認定するケースもあるため、雇用条件を事前に確認しておくことが重要です。
ハローワークへ申告
失業保険を受けながら働く際は、労働の有無をハローワークに正確に申告しなければなりません。申告漏れや虚偽の報告があると不正受給と判断され、給付停止や返還命令といった重い処分を受ける可能性があります。
申告は、失業認定日に提出する「失業認定申告書」に記入して行います。申告対象期間内に働いた日があれば、該当する日付に○や×をつけて内容を説明してください。働いた時間が短い、また収入がなかった場合でも働いた事実そのものを報告しなければなりません。
例えば、家族の事業を手伝った場合や、単発の作業を行った場合も「労働」に該当するケースがあります。「少しだけだから」と申告を省略すると、不正と見なされることもあるため注意が必要です。
週20時間以内で働きながら失業保険をもらうメリット
働きながら失業保険をもらうことは、単に生活費を補う手段にとどまりません。実際には、再就職の準備やキャリア形成においても多くのメリットがあります。ここでは、週20時間以内で働きながら失業保険をもらうメリットを3つ解説します。
再就職に向けた実践的な訓練の場になる
失業保険を受給しながら短時間の仕事に取り組むことは、再就職に向けた準備として効果的です。業務の進め方や職場の雰囲気に少しずつ慣れていくことで、復職に対する不安を軽減しやすくなります。
例えば、接客業であれば言葉遣いや対応の仕方など、対人スキルを実践的に学べます。事務職であれば、パソコン操作や業務連絡の進め方など、基本的なビジネススキルを身につけられるでしょう。
働く環境に身を置いて経験を積んでおくと、再就職後もスムーズに職場に適応しやすくなります。また、実際の業務で得た経験は面接でのアピール材料にもなるはずです。
将来的にやりたい仕事を見つける可能性が高まる
複数の職種や業種で働いた経験は、自分に向いている仕事を見極めるきっかけになります。短時間労働は柔軟に職場を選べるため、将来のキャリア選択に役立ちます。
飲食業の現場に入って接客の楽しさに気づく人もいれば、軽作業を経験して黙々と取り組む業務が合っていると感じる方もいるでしょう。実際に働いてみると、求人票や面接だけではわからない自分の適性が見えてくることも多いのです。
また、仕事を通じて新たな人間関係が生まれ、情報や選択肢が広がることもあるでしょう。アルバイト先で得たつながりが将来的な就職に結びつくかもしれません。
新しいスキルや知識を習得する機会がある
短時間の勤務でも、業務内容によってはスキルや知識の習得が可能です。未経験の分野への挑戦により、これまでにない知識や技術を身につけられるかもしれません。
例えば、接客や販売の仕事では、対人対応やその場の判断力が鍛えられます。事務系の業務では、パソコン操作や書類の整理など、基本的な事務スキルを実務の中で身につけられるでしょう。
また、日々の業務を通じて、時間の使い方や優先順位のつけ方など、汎用性の高い力も自然と養われていきます。再就職を目指すうえで、汎用性の高いスキルは職種を問わず強みになるでしょう。
週20時間以内で働きながら失業保険をもらうデメリット
失業保険を受給しながら短時間の仕事に取り組むことにはメリットも多くありますが、一方で注意すべきデメリットも存在します。ここでは、週20時間以内で働きながら失業保険をもらうデメリットを3つ解説します。
失業手当が減額される
失業保険の受給中に収入を得ると、条件によっては失業手当が減額される場合があります。働いたこと自体では受給資格を失いませんが、収入の金額によって調整が行われる仕組みです。
基本手当日額とアルバイト収入の合計額が前職の賃金日額の80%を超えると、その超過分が差し引かれるかたちで支給額が減ります。賃金日額は、退職前6か月間の賃金総額(通勤手当などを含む)を180で割った金額で、基本手当日額はそれに基づき算出される1日あたりの支給額です。
厚生労働省では、以下のような具体例が示されています。
|
賃金日額7,000円、基本手当の日額4,797円の者(60歳未満)が、失業の認定に係る期間 (28日間)中に2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の認定期間(28日分)の 基本手当の支給額 1日当たりの減額分は、 〔(6,000円/2-1,334円)+(4,797円)〕-7,000円×80% = 863円 基本手当の支給額は、 4,797円×(28日-2日)+(4,797円-863円)×2日 =132,590円 |
アルバイトの収入が賃金日額の80%を超えると、その日の基本手当が支給されないこともあります。収入が一時的に増えても結果として手取りが減ることもあるため、就労と受給のバランスには注意が必要です。
参照:厚生労働省|失業期間中に自己の労働による収入がある場合の減額の算定
ハローワークに申告しなければならない
失業保険の受給中に働いた場合、働いた内容を正確にハローワークへ申告しなければなりません。働いた事実を報告しない、あるいは内容が不正確であると、不正受給と判断される可能性があります。
申告は4週間ごとの失業認定日に提出する「失業認定申告書」で行います。失業認定申告書には、労働日や労働時間、収入の有無などの記載が必要です。仮に報酬が発生していなくても、労働行為があれば申告対象となります。
手続きには確認書類が求められる場合もあり、内容の整理や準備に時間がかかることもあります。作業を後回しにすると申告の抜け漏れが発生しやすくなるため、日々の労働内容を記録しておくことが大切です。
失業手当の支給最終日が遅れることもある
1日に4時間以上働いた場合、その日は「就労日」として扱われ、失業手当の対象日数から除外されます。支給予定だった期間が延長され、支給最終日が後ろにずれることがあります。
失業手当の総支給額そのものは変わりませんが、支給が長引くとブランク期間が延び、再就職のタイミングに影響を及ぼすこともあるでしょう。短時間の仕事であっても、労働時間が4時間を超えないよう意識しておくことが重要です。
そもそも失業保険とは
失業保険は、雇用保険に加入していた人が離職した後、一定の条件を満たすと受け取れる給付制度です。正式には「雇用保険の基本手当」と呼ばれ、再就職までの生活を支えるとともに、安定した雇用環境への復帰を後押しする役割を持っています。
ここからは、失業保険の受給条件や金額、受給期間について詳しく見ていきましょう。
失業保険の受給条件
失業保険を受け取るには、いくつかの条件を満たす必要があります。最も基本的な要件は、雇用保険に加入しており、かつ一定の期間、保険料を支払っていることです。
一般的には、離職前の2年間に通算12ヵ月以上、雇用保険の被保険者であったことが必要です。ただし、会社都合の退職や特定の事情による離職(特定受給資格者・特定理由離職者)の場合は、過去1年間に6ヵ月以上の加入でも受給対象になります。
さらに、「働く意思」と「働ける能力」があることが求められます。就職する意志がなく、求職活動を行っていない場合は対象外です。
一方、以下のようなケースでは受給条件を満たしません。
- 妊娠・出産・育児のためにすぐに働けない場合
- 病気やケガで就労が困難な状態にある場合
- 自営業や家業を継いでおり、雇用保険に未加入だった場合
- 家事や学業に専念している場合
- 会社の役員などに就任している場合
失業手当は就職の意思を持つ方を支援する制度であるため、働ける状態にあることが前提となります。
失業給付金の受給金額
失業保険の支給額は、「基本手当日額」に「給付日数」を掛けて算出されます。基本手当日額は退職前の収入を基に決まるため、人によって金額が異なります。目安としては、退職前の賃金のおおよそ50%〜80%程度が支給されると考えてよいでしょう。
支給額の算出は、次のような手順で進められます。
- 賃金日額の算出:退職前6ヵ月間に支払われた総賃金額を180で割った金額
- 基本手当日額の算出:賃金日額に所定の給付率(50〜80%)を乗じて計算
- 総受給額の算出:基本手当日額 × 所定の給付日数
例えば、退職前6ヵ月間の給与総額が150万円だった場合、賃金日額は150万円 ÷ 180日 = 約8,333円となります。給付率が60%であれば、基本手当日額は8,333円 × 0.6 = 約5,000円です。給付日数が90日であれば、支給される総額は5,000円 × 90日 = 450,000円となります。
給付率は離職前の賃金や年齢に応じて決定され、収入が低かった人ほど高くなる傾向があります。一方で、賃金が高い場合は給付率が下がり、支給額も相対的に抑えられる仕組みです。
また、基本手当日額には年齢ごとに上限が設けられており、支給額が高くなりすぎないよう調整されています。反対に、極端に低い賃金であった場合には最低額が適用されます。
|
賃金日額の上限額(円) |
基本手当日額の上限額(円) |
|
|
29歳以下 |
14,130 |
7,065 |
|
30〜44歳 |
15,690 |
7,845 |
|
45〜59歳 |
17,270 |
8,635 |
|
60〜64歳 |
16,490 |
7,420 |
|
賃金日額の下限額(円) |
基本手当日額の下限額(円) |
|
|
全年齢 |
2,869 |
2,295 |
失業給付金の受給期間
失業給付金の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間と定められています。この期間内であれば、所定の給付日数を上限として手当を受け取ることが可能です。
実際に支給されるのは、「失業していた日」に限られます。給付日数が90日であっても、認定日に「働いていた」と見なされた日や就職した日は支給対象外です。
また、離職後すぐに手続きを行わず1年が経過してしまった場合、所定日数分をすべて受け取る前に受給資格が失効してしまいます。支給されるべき日数が残っていたとしても期間を過ぎると受け取れなくなるため、早めに手続きを進めることが大切です。
失業保険の申請方法
失業保険を受け取るには、ハローワークで所定の手続きを進める必要があります。申請は書類を提出すれば完了するものではなく、求職の申し込みや雇用保険説明会への参加、失業認定日での活動報告など、複数のステップを段階的に進めていく必要があります。
ここからは、失業保険の申請方法について見ていきましょう。
必要書類を揃える
失業保険の手続きを始めるには、まず必要な書類をすべて揃えておきます。書類が不足していると申請の受付自体が後回しになる可能性があるため、退職後すぐに準備を進めておくと安心です。
提出書類として求められるものは以下のとおりです。
- 雇用保険被保険者離職票-1・2
- 雇用保険被保険者証
- 証明写真(縦3cm×横2.4cm、正面・上半身)2枚
- 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
- 氏名・住所・年齢が確認できる本人確認書類(運転免許証、
- パスポート、マイナンバーカードなど)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号入り住民票のいずれか1点)
上記の書類は求職の申し込み時に提出が求められるため、あらかじめ一覧をチェックして忘れ物がないよう準備しておきましょう。
ハローワークで求職を申し込む
必要書類がそろったら、ハローワークで求職の申し込みを行います。失業保険を受け取るには、単に退職した事実だけでなく、「就職の意思があること」を示す必要があります。
手続きの流れは以下のとおりです。
- 求職申込書に必要事項を記入
- 書類の提出と職業相談
- 雇用保険説明会の案内を受ける
申し込みの段階で受給資格の有無が判断され、「失業等給付受給資格者のしおり」が手渡されます。説明会の開催日は申請から7日以上後になるのが一般的です。日時はその場で案内されるため、忘れないようメモしておきましょう。
待機期間を過ごす
求職の申し込みを終えると、7日間の「待機期間」に入ります。待機期間は、ハローワークが申請者の就労状況を確認するために設けられており、失業状態であることが必須です。
待機期間中にアルバイトやパートなどの就労行為があると失業状態とはみなされず、給付開始が延期される場合があります。また、待機期間に再就職が決まった場合は、再就職手当の受給資格を失う可能性もあるため就労開始日には注意が必要です。
待機期間中は原則として収入を伴う労働を控え、再就職活動の準備に専念しましょう。
雇用保険説明会に参加する
待機期間中、またはその後に実施されるのが雇用保険説明会です。説明会では、失業保険の制度内容や受給までの流れ、再就職に向けた求職活動の進め方などについて具体的な説明が行われます。
説明会当日は、以下の持ち物が必要です。
- 雇用保険受給資格者のしおり
- 印鑑
- 筆記用具
説明会終了後には、実際に給付を受けるために必要な書類として「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が配布されます。最初の失業認定日についての案内もあるため、必ず内容を確認しておきましょう。
失業認定日にハローワークを訪れる
失業保険を継続して受け取るには、4週間に1度の「失業認定日」にハローワークを訪れる必要があります。失業認定日は、申請者が失業中であること、そして就職活動を行っていることを確認する日です。
初回の認定日は、離職票の提出日から約3週間後に設定されます。指定された日に「失業認定申告書」を提出し、期間中の就職活動実績や就労の有無などを正確に報告します。
虚偽の申告があると不正受給とみなされる可能性があるため、事実に基づいた記載を心がけましょう。手当の支給は失業認定日を経て行われるため、忘れずに出向く必要があります。
失業保険が先延ばし・減額されなくなるケース
失業保険は一定の条件を満たした場合に支給される制度ですが、支給が遅れたり減額されたりするケースも少なくありません。以下では、失業保険が先送りされたり、支給額が減らされたりする具体的な状況について解説します。
待機期間中に働いてしまう
失業保険の申請後には、まず7日間の「待機期間」が設けられます。待機期間中は失業状態にあるかどうかを確認するため、労働を一切行わないことが原則です。短時間のアルバイトや内職であっても収入の有無にかかわらず労働行為が確認された場合は、働いた日数分、待期期間が延長されます。
待機期間は自己都合退職・会社都合退職にかかわらず全員に設けられるため、申請後は7日間の就労を控えることが重要です。
1日4時間以上の労働を行う
失業保険の受給中に1日あたり4時間以上働くと、その日は失業状態とは見なされず、「就労日」として扱われます。就労日と判断された日は手当の支給対象から外れるため、支給日数が1日分先送りにされます。
支給額の合計は変わりませんが、受給期間が延びると再就職手当の申請タイミングに影響を及ぼす可能性があります。日数のズレが後々の制度利用に響くこともあるため、失業保険を受けながら働く際は1日あたりの労働時間を正確に管理しておくことが大切です。
一定以上の金額を稼ぐ
1日の労働時間が4時間未満であっても、収入額が高くなると失業保険の給付が減額される可能性があります。アルバイトなどの収入と基本手当日額の合計が、前職の賃金日額の80%を超えた場合に適用されるルールです。
例えば、賃金日額が9,000円である方がその80%にあたる7,200円を超える収入を得た場合、その超過分に応じて手当が差し引かれます。金額によっては当日の給付がゼロになることもあります。収入と給付額のバランスを把握し、慎重に働き方を選ぶことが大切です。
定職に就いたとみなされる
失業保険の受給中に、週あたり20時間以上働いたり、31日以上の雇用契約が見込まれる仕事に就いたりした場合、「就職した」とみなされます。就職の判断が下されると、失業保険の受給資格はその時点で失効します。
たとえ契約期間が31日未満であっても、以下のような条件に該当する場合は長期雇用が見込まれると判断される可能性があります。
- 契約書に「契約更新の可能性がある」と明記されている場合
- 同じ条件で雇用された他の労働者が31日以上継続して勤務している実績がある場合
上記のケースでは、形式上の短期契約であっても実質的には就職したと見なされる可能性が高まります。短時間・短期間のつもりで始めた仕事でも条件次第では失業保険の支給対象外になるため、勤務条件や契約内容を確認したうえで就業することが大切です。
働きながら失業保険をもらう際の注意点
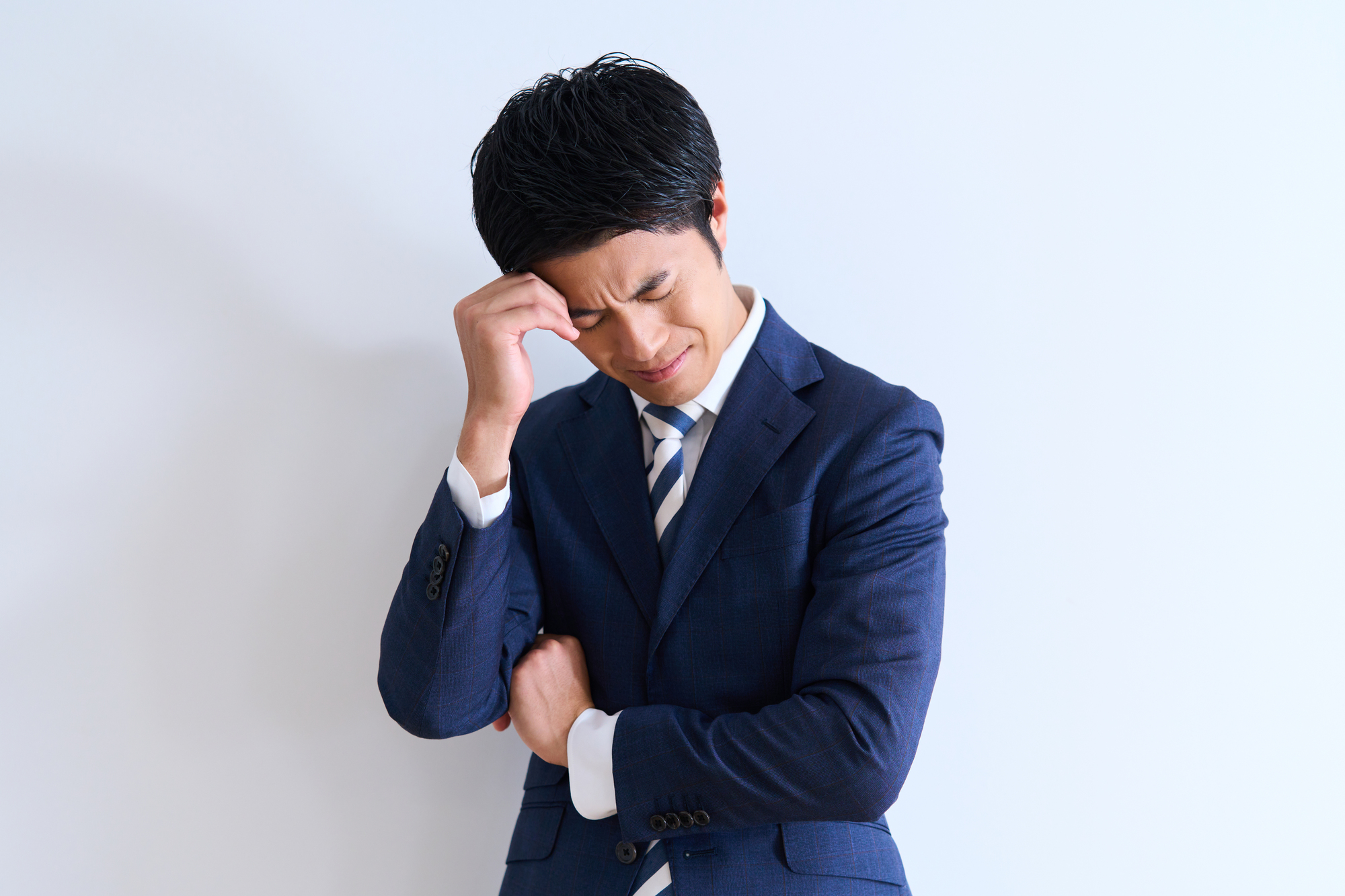
失業保険を受け取りながら働くことは可能ですが、守るべき義務を怠ると不正受給とみなされ厳しい処分を受ける可能性があります。ここでは、働きながら失業保険をもらう際の注意点を3つ解説します。
必ずハローワークへ申告する
失業保険を受給している間にアルバイトやパートなどで働いた場合は、その事実を必ずハローワークに申告しなければなりません。収入の有無にかかわらず、働いた日や時間数、仕事内容などを正確に報告する義務があります。
申告は、4週間ごとの「失業認定日」に提出する「失業認定申告書」で行います。申告書には、認定対象期間中に就労した日を記入し、対応する収入がある場合はその金額も明記しましょう。
少しの作業だからと報告を怠ってしまうと、結果として不正受給と見なされるリスクがあります。働いた事実がある場合は、漏れなく申告することが重要です。
不正受給は絶対に避ける
失業保険の受給中に働いていたにもかかわらず、その事実を申告せずに給付を受け取った場合、不正受給と判断されます。不正受給が発覚すると、受け取った金額の全額返還に加え、最大で2倍に相当する額の納付を求められることがあります。
たとえ短時間の就労であっても、申告を怠ると重大なトラブルに発展しかねません。安心して受給を続けるためには、制度の趣旨を守り、正直に申告しましょう。
求職活動も忘れずにおこなう
失業保険は、再就職を目指す方の生活と就職活動を支えるための制度です。そのため、受給中は求職活動を継続し、その実績をハローワークに報告する必要があります。求職活動として認められる具体的な行動には、次のようなものが当てはまります。
- 求人への応募
- 企業との面接
- 職業相談の利用
- 各種セミナーの受講
上記のうち、失業認定期間内に原則として2回以上の活動実績が必要です。活動の実績は失業認定申告書に記入し、ハローワークの担当者に提出します。実績が不足していた場合はその期間の手当が支給されないこともあるため、計画的に取り組むことが大切です。
また、国の認可を受けた転職エージェントへの職業相談も立派な求職実績となります。
退職コンシェルジュの運営するエージェントでは、給付金のプロ相手に再就職手当などの相談も可能です。まずはLINEで気軽にご相談ください!
まとめ
失業保険をもらいながら働くためには、労働時間や契約期間、ハローワークへの申告義務など、いくつかの重要なルールを守る必要があります。短時間の仕事であっても制度の仕組みを理解しないまま進めてしまうと、減額や支給停止といった不利益を被る恐れがあります。そのため、正しい知識を持ち、慎重に行動することが重要です。
契約終了後の生活費や手続きに不安を感じている方は、「社会保険給付金サポート」の活用をご検討ください。制度に詳しい専門スタッフが申請書類の準備から提出まで丁寧にサポートし、給付金の受け取りをスムーズに進められるようお手伝いします。一人で悩まず、まずは気軽にご相談ください。
社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼
この記事の監修者

杉山 雅浩
スピネル法律事務所 弁護士
東京弁護士会所属。
池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。
NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、
詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。
YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!
おすすめの関連記事
ピックアップ
- CATEGORY
- 給付金について
- 転職・再就職について
- 就労について
- 社会保険について
- 精神疾患について
- サービスについて
- 失業保険について
- 再就職手当
- 雇用保険について
- 退職について
- 障害年金について
- ピックアップ
- 人気記事
-
退職代行サービスの利用方法、実際の流れと体験談を紹介
-
今の会社に3年後もいる自信はありますか?
-
退職代行を利用した時の有給消化の仕組みとその対応方法
-
退職代行サービスを使うメリット・デメリットは?
-
障害年金を知ろう
-
ブラック企業を判定する方法と実際のチェックポイント
-
会社を“円満に退職する”方法は?
-
退職時の引き継ぎは義務?スムーズな業務引き継ぎの必須ポイント
-
辞めさせてくれない!そんな時こそ「退職代行サービス」
-
パワハラ、モラハラ、セクハラとは?
テーマ
- クレジットカード
- 資格取得
- 退職届
- 引っ越し
- 労働基準法
- 退職コンシェルジュ
- 退職代行
- アルバイト
- 精神疾患
- 面接
- 社宅
- 雇用契約
- ストレス
- 退職代行サービス
- 雇用保険
- うつ病
- 障害手当金
- 障害者手帳
- 内定
- ブラック企業
- 健康保険
- 統合失調症
- 自己都合
- 精神保険福祉手帳
- 就労移行支援
- ハラスメント
- 年金
- 契約社員
- 会社都合
- 労災
- 業務委託
- パワハラ
- 転職活動
- 弁護士
- 失業給付
- 産休
- 社会保険
- モラハラ
- 転職サイト
- 公的貸付制度
- 新型コロナウイルス
- 解雇
- 福利厚生
- セクハラ
- 職務経歴書
- 生活福祉資金貸付制度
- 有給消化
- 中小企業
- 失業手当
- 障害年金
- 人間関係
- 不支給
- 休職
- ベンチャー企業
- 就職困難者
- 引き継ぎ
- スタートアップ
- 等級
- 免除申請
- 会社倒産
- 再就職手当
- 給与
- 転職
- 離職票
- 適応障害
- 退職勧奨
- 社会保険給付金
- 残業代
- 違法派遣
- 労務不能
- 住宅確保給付
- 自己PR
- 職業訓練受講給付金
- 退職金
- 派遣契約
- 傷病手当金
- 給付金
- 確定申告
- 退職給付金
- 会社都合退職
- 障害厚生年金
- 年末調整
- 職業訓練
- 保険料
- ハローワーク
- 自己都合退職
- 失業保険
- 障害者控除
- 再就職
- 社会保障
- 就業手当
- 退職
- ブランク期間
- 退職願
- 職業訓練受講手当
- 就職
- 傷病手当
新着記事
-
2025.10.17
退職バンクにはどんな口コミ・評判がある?怪しいと言われてしまう理由も解説!
-
2025.10.17
失業保険の初回支給はいくら?【2025年最新版】支給額と計算方法・少ない理由を徹底解説
-
2025.10.17
勤続1年未満でも失業保険はもらえる?勘違いしやすい条件を整理
-
2025.10.17
失業手当と扶養の関係を徹底解説(2025年版)|受給中に扶養に入れる?外れる?
-
2025.10.15
仕事を辞めるタイミングとは?適切な伝え方や注意点を解説
-
2025.10.09
失業手当の手続きで提出する必要書類は?離職票再発行や延長申請の流れも解説
-
2025.10.08
個人事業主が再就職手当をもらえるケースと手続き方法、注意点を解説
-
2025.10.08
アルバイトを4時間ピッタリすると失業手当はどうなる?支給条件や注意点も解説
-
2025.10.08
いつが得?損しない退職日の決め方とパターン別おすすめの退職日
-
2025.10.08
失業認定日までに就職が決まったらどうする?必要な手続きの手順を解説





 サービス詳細
サービス詳細